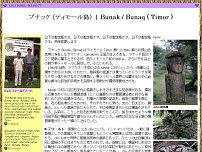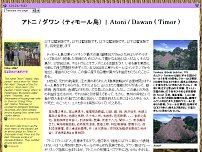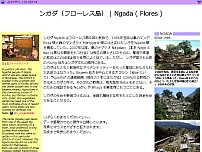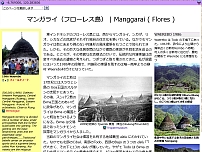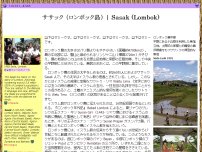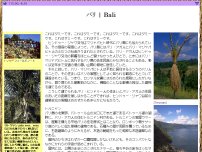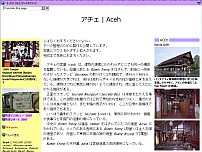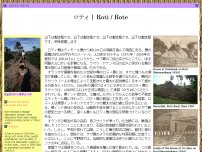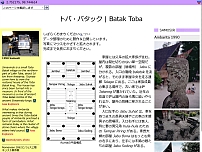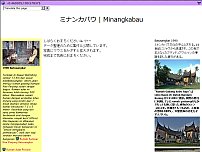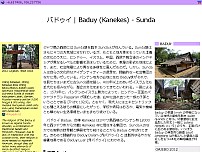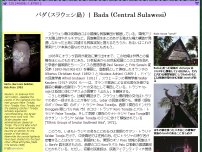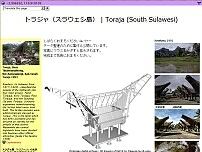屋根 | ATAP roof
この地域の建築の魅力でもある独特の屋根形態について、類似する話題の多い技術的側面をまとめておこう。
家づくりは周囲の環境との対話があってはじめて成立する。なかでも、屋根葺きにはおなじ種類の材料が大量に必要とされるから、環境に依存する度合いもそれだけ大きいことになる。
たとえば、ボルネオの狩猟採集民プナンが移動中のキャンプの場所として考慮するのは、食料や水の確保とならんで、屋根葺きに相応しい植物の群生があるかどうかだった。
定住民の集落では、定期的に屋根の補修や葺き替えもおこなわねばならない。どんなにすぐれた素材があっても、取り尽くしてしまって再生できなければ屋根には使えない。長い間には維持管理するノウハウも必要になる。かくして歴史的に積み重ねられてきた試行錯誤の結果、屋根葺き材はだいたいどこでも一定している。
また、屋根工事に大工のような専門職がいることはまれで、一般には社会成員の共同作業によって屋根葺きはおこなわれている。慣習的な社会の約束事は得てして大きな変化を受けにくい。屋根葺きのような単純作業ではなおさらである。屋根形態に共同体的性格がきわめてよく発揮される理由の一端はそんなところにある。屋根に注目してみるだけで、その社会がどのようなものであるかが朧気にみえてくるわけである。
この地域で伝統的に屋根にもちいられてきた材料を大別するとつぎの4つになる。
(1)イネ科の植物で葺くもの、
(2)ヤシ科の植物を利用するもの、
(3)その他の植物材料、そして
(4)瓦、
であり、さらに現代では(もっともその利用は20世紀はじめにまで遡るようだが)家屋の共同体的性格が薄れるのにあわせて、
(5)波板トタン
がひろまっている。
イネ科植物のなかでは、東南アジア全域でチガヤが利用されている。とくに農村集落の多い山岳、高原地帯では、ヤシ科の植物が乏しいこともあって、チガヤは屋根の代名詞といえるほど普遍的な屋根葺き材料である。
反対に、海岸地帯や小さな島嶼では、ヤシ以外の屋根葺き材は見あたらない。ヤシ科の植物では、サゴヤシ、ニッパヤシ、ロンタルヤシ(オウギヤシ)などの葉がよく利用される。比較的まとまって生育し、材料が入手しやすいことにくわえて、小葉の形状がある程度大きいことがその理由である。この点、どこにでもありそうなココヤシはあまり屋根に適した材料といえない。
屋根の素材という点では、チガヤとヤシのふたつが両横綱といってよいが、そのほかにも、竹、木板、樹皮、木の葉など、それぞれ地域の生態環境に応じた固有の材料がある。もっとも、材料はおなじでも、それをどのような仕方で屋根に葺くかは地域や民族ごとに工夫がある。チガヤの葺き方ひとつとってもじつに多様な技術があるもので、日本の茅葺き屋根をイメージしていると、その発想の豊かさに驚かされることになる。
トタン

Minangkabau
1990 West Sumatra

Toba Batak
1990 North Sumatra

Sa'dan Toraja
1991 South Sulawesi

Sumba
1985 West Sumba

Jarai ??
1997 Kontum (Vietnam)


日本の屋根葺き:白川郷 1983
ヨシやススキをもちいる日本の茅葺き屋根では、葺き草の根先を下にむけて葺くのが普通である。葉先よりも丈夫な根先を雨のあたる外側にさらすのは合理的でもあるが、それを実現するためには若干のテクニックがいる。これに対して、日本の周辺地域の草葺き屋根はほとんどが葉先を下にむけて葺く。日本ではこうした葺き方を逆葺きと呼んで、大嘗宮のような仮設的建物の葺き方とされている。本当は、日本の茅葺きのほうが逆をいっている。
▽Luzon島Bontoc族の屋根葺き
▽1981
チガヤは、日本の茅葺き屋根でよくもちいられるススキやアシなどとおなじイネ科の多年草だが、草丈はススキとくらべてもずっと低く、か細い。チガヤの穂先を下に向けて葺く(逆葺き)ことで、日本の茅葺き屋根のような防寒性や重厚さは得られないかわりに、この地域独特の軽やかな屋根の造形美を実現している。


チガヤの屋根葺き
Lombok 島 Sasak
チガヤを屋根に固定するには、作業の工程から二通りのアプローチがある。
ひとつは、出来上がった屋根の構造体にチガヤの束を順次固定してゆく方法で、日本の茅葺き屋根もおよそこのようにしてつくられる。草葺き屋根本来の作業手順ではないかとおもう。
もうひとつは、あらかじめチガヤのパネルをこしらえておいてから、パネルごと屋根に載せて固定する方法で、これはヤシの葉を葺く際の常套手段でもある。チガヤ屋根のほとんどがいまではこの第二の方法で葺かれている。

Lombok 島 Sasak
まえもって定型の屋根パネルをつくっておく利点は、屋根葺き作業が短時間ですむことにある。チガヤの場合には、チガヤの刈り取りそのものがたいてい村全体の共同作業になるから、パネルの製作も屋根葺き当日の作業であることが多い。いっぽう、ヤシの葉では、各家が事前にパネルをつくりためておくのが普通である。そうすれば屋根葺き当日はあまり多くの人手がいらない。
「結」のような相互扶助の組織がうまく機能しているあいだはよいが、コスト計算がはじまるとチガヤの屋根は急速になくなる。この点、サゴヤシの屋根はパネルになったものを市場でも売っている。商品経済のなかでもトタンに代わる安価な屋根材としてヤシ葺きの屋根はまだ生きのびている。
ちなみにトタン屋根は職人の仕事と決まったわけではない。トタンの波板を一枚一枚市場で購入してかついで村まで運び、まとまったところで一人で屋根を葺きかえてしまう。あとは何十年も手間いらず。けっして快適ではないトタン屋根が急速に普及した大きな理由である。屋根の材料は、社会のまとまり具合をはかる物差しでもあるのだ。
パネルをつくらない方法


串刺しにしたチガヤを葺く
Sumba 島
スンバ島では、あらかじめチガヤを60mmほどの太さに束ねて、根元の部分をロンタルヤシの葉脈を利用した紐で縛っておく。1棟の屋根葺きにこうしたチガヤ束がおよそ12000束いる。
先端を尖らせた長さ40cm~1m程度の串(ハマカズラ属のフイリソシンカ [Bauhinia variegata] などの枝や堅い灌木、割竹を利用する)を用意しておき、チガヤの束を串刺しにしながら、屋根にわたした横木(小舞:木、竹、ビンロウの幹などを利用する)に串ごとつぎつぎと括りつけてゆく。この結縛には蔓植物の表皮を裂いて利用する。即席のパネルをつくって屋根を葺くわけである。
屋根と同様の仕方で、壁をチガヤで覆う地域もある。穂先が下を向くので箒のような案配だが、もともとか細い材質だからじきにしっくりとなじんでしまう。


屋根裏の仕上げ Timor島Atoni族
下は王族クラスの穀倉
ティモール島でも、屋根にはもっぱらチガヤが利用される。チガヤの束を直接屋根に固定する点はスンバ島と一緒だが、穀倉の屋根裏は外から見えることもあって、ずっと繊細な仕事をしている。
アトニ Atoni 族ではもともと王族クラスが穀倉を所有した。領内の諸侯が協力してその建設にあたったという。穀倉の下は集会所にもなる公共性の高い空間だったから、屋根裏の仕上げにこだわるのにももっともな理由がある。
円錐状に配置された垂木にとりつける小舞には靱性の高いモクマオウ(一般にcemaraと呼ばれる)やビンロウ(一般にpinang、檳榔樹のこと)の幹を割って使う。小舞の結縛にもちいるのはグバンヤシの若葉を編んだ紐で、ロンタルヤシやグバンヤシの葉柄の皮を剥いでつくった紐をもちいてチガヤの束を括りつけてゆく。ただし、王族クラスの穀倉ではすべてトウで固定するのがよいとされる。こうした結縛の仕方にもいちいち名前があるほどで、屋根裏の格好のデザインモチーフになっている。最後にトウを編んだ飾りで全体を補強する。
チガヤは生長しても高さ1~2メートルしかない。スンバ島やティモール島のように、刈り取った長さそのままを屋根葺きに使用するのは理にかなった方法でもあるが、これだとチガヤの切断面が屋内にむき出しになってしまう。チガヤの長さによっては、割竹などの心材をはさんで折り返してもちいる地域も多い。パネルをつくる場合にはよくやる方法だが、フローレス島中部ではパネルを作らずにこれをやってしまう。

慣習家屋の屋根裏
Flores 島 Lio
リオ Lio 族の慣習家屋の葺き替えでは、垂木(竹をもちいる)のうえから12cm程度の間隔で割竹の小舞をはりめぐらしておく。この横材にチガヤの束を引っかけ、根先を外に向けてチガヤをつぎつぎと折り返してゆくだけで巨大な屋根を葺きあげてしまう。屋根の勾配が急なことと、小舞が比較的密に配置されているため、チガヤを特に固定しなくても大丈夫なのである。
葺き替えに要したチガヤ(太さ10cm程度)は約1000束、竹(垂木と小舞は種類のことなる竹)が約100本、ビンロウ(屋根下地構造用のモヤとサス)4本、ijuk縄(麻縄のようなもの)50巻。100人が7日がかりで作業し、葺き替えの日には300人もの協力者があつまったという。かかった費用(といっても、ほとんどが儀式のさいに供犠した豚や馬、それに手伝った者たちへの食事のふるまい)は1986年当時の値段で100万RP。日本円で約25万円、ただし食費が500RPで可能な時代の話だ。

毛羽立つ屋根裏(上)
Flores 島 Ngada

軒先と棟付近は丁寧な仕上げ(上)
あとはチガヤを葺くばかり(下)
Flores 島 Nage

リオに隣接するンガダ Ngada やナゲケオ Nagekeo も同様にしてチガヤを葺くが、こちらは折り返したチガヤの根先を下層のチガヤの上に敷きこまない。垂木をはさんで2本の横木を対にむすび、チガヤの先をその間に差し込むだけといういたって簡単な作業である。つまり、屋根裏ではチガヤの根先が垂直に突き出したまま、まるで総毛立ってみえる。年月を経た屋根裏はこの毛羽先いっぱいに煤が堆積して近寄りがたい状態になっている。調査どころではない。それでも外側はつぎつぎと上層のチガヤが積み重なってゆくから、チガヤの重みだけできれいな屋根になる。リオほど屋根勾配が急でないため、これでもチガヤが抜け落ちないのである。草丈の短いチガヤを効率的に使う工夫ともいえるだろう。
こんな仕事でいったいどのくらいの期間もつのだろうか?
屋根の耐久性は、屋根の勾配や葺き厚(葺き重ねる間隔)によっても変わるが、一般にスンバ島のような葺き方なら(リオでもかつてはそうしていたという)チガヤの屋根は15~20年もつといわれる。ティモール島では、むかしはいまより小舞の間隔がせまく、チガヤの束を3重になるように葺いた(現在は2重)そうだ。当時は40年ちかくもったという。
屋根葺き材の世評からいうと、ヤシ(なかではサゴヤシが最上位)、チガヤ、ijuk の順に耐久性はたかくなるといわれる。古い立派な慣習家屋の屋根が得てしてチガヤや ijuk で葺かれているのは、集落の立地(多くは山間部にある)とならんで屋根葺きの効率からも納得できる。ただし、リオでも現状(現在の葺き方)は3~8年ごとに葺き替えているようだ。もちろん、経済的な余裕がなければできない話である。
パネルをつくる方法

屋根パネルの部分:Lombok 島

棟の納まり:(上) Lombok 島
(下) Bali 島

ロンボック島では、長さ2メートルほどの小竹2本でチガヤのパネルをつくりあげてしまう。それには、小竹の節元一カ所をのこして3つに割り、割った先を三つ編みの要領でチガヤの束(もちろん根先側)を編み込んでゆくのである。最後に、3つの竹片を結びあわせると、チガヤの抜け落ちない丈夫なパネルができあがる。こうしてできたパネルを、グバンヤシの小葉の葉脈部分をもちいて屋根の垂木にじかに固定する。
雨のあたる屋根の棟をどう納めるかはそれぞれの土地で工夫のみられるところだが、ロンボック島では、チガヤの代わりに稲藁を束ねて棟をまたぐように重ねる。稲藁が手に入らないときは、稲刈りの時期までチガヤで代用しておくという。チガヤより稲藁のほうが丈夫というのがその理由である。
隣りのバリ島では、屋根の棟をチガヤで覆ったあと、さらに補強に ijuk(サトウヤシの樹皮の繊維)を載せてから、棟の周囲で竹の枠をつくって固定する。
チガヤをそのままの長さで使うのではなく、割竹などの心材のまわりに折り返してパネルにすることはロンボック島やバリ島でもおこなわれている。ヤシの葉の一般的な利用法とおなじだから、あるいはパネル化の原形はヤシ葺き屋根にあるのではないかとおもう。

ロール状の屋根パネル
Flores島Manggarai
このなかですこしばかり変わり種なのはフローレス島西部のマンガライ Manggarai である。
マンガライの家屋は10数家族が共同で生活する蜂窩状の大きな高床建築で、丸い屋根を葺きやすくするように長さ10メートルにも達するチガヤのパネル(屋根ロール?)をこしらえる。心材にするのは半割にしたトウで、この心材のまわりにチガヤの根先側3分の1ほどを折り返し、トウの紐で縫ってパネルに仕上げてゆく。根気のいる仕事だが、サゴヤシのパネルをつくるときと作業の形態は変わらない。
こうしてできた屋根パネルを反時計回りにぐるぐると屋根の骨組みにまきつけて屋根葺きをおこなうわけである。一棟まるまる葺くのにおよそ130ロールの屋根パネルが必要だという。


Luzon島Bontoc族
屋根パネルと呼ぶべきかどうかは疑問だが、屋根面全体を地上で葺いて一気に屋根上にもちあげてしまう例がフィリピン、ルソン島にはある。日本の茅葺き屋根ではまずありえない発想である。
ボントック Bontocでは、寄棟屋根を6等分(妻側はそれぞれ一面、平側は2分割する)して、屋根上にlono(トキワススキ [Miscanthus floridulus]?)を組んで仮枠をつくる。これをいったんはずして地上に降ろし、全体に lono を敷きつめ、その上にチガヤを結びつけて大きな屋根パネルをこしらえる。これをふたたび全員総掛かりで屋根にもちあげ固定する。チガヤのように軽く葺ける材料でなければとてもできない芸当だが、屋根葺きのもつダイナミズム(盛大なお祭りにちかい)はいかんなく発揮されている。


パネルを利用した屋根

パネルをつくらない屋根
Sedang (Vietnam)
最後に、ベトナム中部高原の例を紹介しておこう。
ベトナム中部のコントゥム、ジャライ(プレイク)、ダックラックの3省には、バナ Bana 族などのモンクメール系の民族とジャライ Jarai などのオーストロネシア系の民族がモザイクのように混住している。そうした言語系統にかかわらず、居住様式はどこもだいたい同一で、高床のロングハウスに住み、集落内には長大な屋根をもつ男性集会場がある。
屋根に葺くのは草丈1.5mほどに生長したチガヤ(?詳細不明)で、縦横90~100cm程度のパネルをつくる。まず、心材になる割竹をはさんで、チガヤの根元側1/3を折り返す。つぎに半割にした竹2本で、折り返したチガヤの根先付近を表裏からはさみ、竹同士を結びつけて固定する。これでちょうどパネルの中央付近を竹でとめたパネルができあがる。
このパネルを屋根に葺くには、パネル中央の割り竹が、下に葺いたパネル上端にある心材の割竹と重なるようにして垂木に固定してゆく。こうすることで葺き間隔50cm、葉先を下にむけた逆葺きの屋根になる。
また、こうしたパネルをつくらないで、屋根にわたした横木に直接チガヤの根先を引っかけて折り返すだけの方法もある。フローレス島のンガダ地方とおなじやり方だが、ここでは仮設建物の屋根などに使われる。






棟の納まり:Timor島Atoni族
とんがり帽子、だんご、ボサボサ、編んでもよし、木彫があれば、洗面器もある
チガヤ

Yami house
1983 Lanyu (Taiwan)

Ifugao house
1982 Luzon (Philippines)

Atoni / Dawan house
1987 West Timor

Bima granary
1985 Sumbawa

Dompu house
1986 Sumbawa

Wawo (Bima) house
1986 Sumbawa

Sasak house & granary
1986 Lombok

Wongaya Gede granary
1986 Bali

Tenganan house
1991 Bali

Ede longhouse
1994 Dak Lak (Vietnam)

Jarai/Gialai longhouse
1997 Kontum (Vietnam)

Bana communal house
1997 Kontum (Vietnam)

Lawa house
1995 Mae Hong Son (Thailand)

Akha house
1995 Chiang Rai (Thailand)

チガヤ:ススキより小型(高さは2mに満たない)のイネ科の多年草。東南アジアで広く屋根葺き材として利用されている。マレー語のalang-alangがこの地域での通称。 [Imperata cylindrica]
NAMA DAERAH: Naleueng lakoe (Aceh); Jih (Gayo); Rih, Ri (Batak); Oo (Nias); Alalang, Hilalang, Ilalang (Minang kabau); Lioh (Lampung); Halalang, Tingen, Padang, Tingan, Puang, Buhang, Belalang, Bolalang (Dayak); Eurih (Sunda); Alang-alang kambengan (Jawa); Kebut, Lalang (Madura); Ambengan, Lalang (BaIi); Kii, Rii (FIores); Padengo, Padanga (Gorontalo); Deya (Bugis); Erer, Muis, Wen (Seram); Weli, Welia, Wed (Ambon).
NAMA ASING: Cogon grass, satintail (En). Paillotte (Fr). Malaysia: lalang, alang-alang. Papua New Guinea: kunai (Pidgin), kurukuru (Barakau, Central Province). Philippines: kogon (Tagalog), gogon (Bikol), bulum (Ifugao). Burma (Myanmar): kyet-mei. Cambodia: sbo’:w. Laos: hnha:z kh’a:. Thailand: ya-kha, laa laeng, koe hee (Karen, Mae Hong Son). Vietnam: c [or] tranh.
 Banyu Bening
Banyu Bening
 PIER
PIER

ベトナム中部高地では la-lang (Jarai)、jia/gia (Bana)、dia (Jolong) などと呼ばれる。草丈は高く2mちかくに生長する。
(2007.11.07/12.17追補/2008.1.22/5.25追補/11.13スンバ島情報訂正/2011.08.24カロ・バタック情報追加訂正)
 本ページ中に間違いを発見された方はどうかご連絡ください。誤った情報は改めていきます
本ページ中に間違いを発見された方はどうかご連絡ください。誤った情報は改めていきます
 ボントック ( ルソン島 ) | Bontoc ( Luzon )
ボントック ( ルソン島 ) | Bontoc ( Luzon )