アトニ / ダワン (ティモール島) | Atoni / Dawan ( Timor )
東インドネシア最大の島ティモール。私がはじめてこの島を訪れたのは1986年、モルッカ諸島南西の小島キサール島から島の産物を運ぶ帆船に便乗し、快適とは言い難い3日間の航海を経て東ティモールのディリに上陸したのだった  。
。
当時の東ティモールはインドネシアに併合され、外国人が立ち入ることのできない土地になっていた。小さな帆船で到着してしまったことはいわば抜け道である。好景気にわくディリの町はあかるく活気にみちていた。内戦など存在しないかのように。私は市内に一日滞在をゆるされただけで、翌日には西ティモールのクパンに向けてバスに乗った。クパンまではおよそ400km、東ティモールを出るまでに6回の検問をパスし、まる一日かけてクパンに到着した。
ティモール島の面積は30,777km2(日本の九州よりやや小さい)、人口3,182,693(2014年:九州の人口のおよそ1/4)、東西に長い島内には少なくとも14種類の相異なる言語集団がいる。それらは大別して東ティモールに居住するパプア語族 ― Makasae, Kemak (Ema), Bunak (Marae), Fataluku (Dagada) ― と残りの多数をしめるオーストロネシア語族 ― Atoni (Dawan), Belu (Tetun) ― に分類される。もっとも、人種構成は語族の分類と一致せずに、西ティモールの主要な民族であるAtoni族(*) は形質的にパプア人にちかいと言われる。
(*) atoni は「人(男)」を意味する Dawan (Uab Meto ともいうが方言も多い) 語であり、現地には Atoni 族という呼称はない。ここでは民族学の慣例に従って Atoni族と表記する。
一説によると、この島の先住民は Atoni族で、彼らを山岳地帯に追いやり、穀物栽培文化を島にもたらした民族が遅れてやってきた Belu (Tetun) 族である。この侵略者の集団はマラッカを原郷とし、スラウェシ島南部のマカッサル、さらにフローレス島のララントゥカを経て、14世紀頃ティモール島の中部に至り、Benain 平野に拠って Waihale 王国を建国したという。
乾燥した気候のためにけっして豊かな土地とはいえない島が、外部世界に注目された理由のひとつは、この島に産する白檀が莫大な利益をもたらしたことにある。その結果、17世紀以来、ティモール島はポルトガルとオランダの支配に翻弄され、島を東西に分断して21世紀にいたるまで独立問題を引きずってきた。ポルトガルが東ティモールから手を引いた1976年以降、島を実効支配していたインドネシア政府は独立派住民を弾圧すると同時に東ティモールへの外国人の来訪をきびしく制限していた。東ティモールがようやく独立国となったのは2002年のことである。

19世紀 Amarasi 王国の農村景観 [MÜLLER 1844]
"Inlandsche schans bij het dorp Toeboeropo (landschap Amarassie)", 1839-1844
Natuurkundige commissie in Indië
 Memory of the Netherlands
Memory of the Netherlands
ティモール島簡史
ティモールの名は遅くとも13世紀初頭から中国文献に登場し、福建や広東からの商人が定期的にこの島を訪れていたらしい。
宋代にまとめられた『諸蕃志』(趙汝活 1225)は、檀香の産地として「底勿」(ティモール)をあげ、「渤泥」(ブルネイ??)に隣接し、「闍婆」(ジャワ)の属国であったと報じている。
14世紀、元末の航海家、汪大淵が自ら見聞するところを記した『島夷誌略』(汪大淵 1349)によれば、「古里地悶」(「古里」は「吉里」の誤記。Gili Timor = ティモール島)では、山にただ檀樹ばかりが繁っていて、銀鉄碗、西洋絲布、色絹などをもちいて交易したという。ただし、この島との交易は万倍の利益を生むものの、それは命と引き替えであって、むかし、泉州の呉宅という者が百人あまりの船でこの島に向かい、交易を終えたときには10人中8、9人が死亡、残った1、2人も多くは病気になっていたというのである。
明代にはいると、さらに具体的な情報がもたらされるようになる。明初の航海書とされる『順風相送』(著者不詳 1403?)は「池汶」の12の港の名をあげ、なかでも美膋 Mena と啞媽魯班 Amanuban? が白檀の集散地であるとしている。また、『東西洋考』(張燮 1617)は「遲悶」の産物として白檀のほか、蓽撥(ヒハツ)と豆蔲(ニクヅク)をくわえている。
鄭和の遠征に同行した費信は、「吉里地悶」に死者が多いのは土地の甚だしい瘴気のせいだと記したが(『星槎勝覽』1436)、マゼランの航海に随行したピガフェッタも、ティモール島は聖ヨブの病(天然痘?癩病?)の蔓延が他のどの島よりいっそう激しいと報告している。そのためか否か、白檀の自生地として知られていたにもかかわらず、ヨーロッパ諸国による植民は周辺の島々より遅れたのである。
「神はティモールを白檀のために、バンダを豆蔲花(メース)のために、モルッカを丁字のために創られたので、これらの島々を別にすると世界のどこにもない」
そんな話を、マラッカのポルトガル商館官吏トメ・ピレスはマラヨ人商人からの聞き伝えとして記録している。
アジア航路の発見に成功したポルトガルは、こうした香料諸島の情報にかんして厳重な秘密主義を貫いていた。ティモール島へは1520年頃、オエクシ Oecussi(Lifau 王国)に来航して交易をはじめ、後にクパン Kupang に要塞を築いた。この頃の小スンダ列島における活動の中心はソロール島にあり(ティモール島とならぶ白檀の産地だったという)、ドミニコ教団の熱心な布教活動によって、現地人のあいだに多くの改宗者を生みだしていた。これらドミニコ教徒と現地人との混血の子孫は黒いポルトガル人 Toepassen と呼ばれて、その後この地域の支配に腐心したオランダ人たちを大いに悩ますことになった。
オランダは、1613年、Apollonius Schotte 率いる艦隊がソロール島のポルトガル要塞 Fort Henricus を攻撃の帰途、はじめてティモール島に来港し、クパンに商館をひらくことに成功した(Fort Concordia の建設は1653年)。
続く50年間は小スンダ列島やモルッカ諸島の覇権をめぐるポルトガル、オランダ両国間の抗争の連続である。1641年、マラッカはオランダに征服され、その結果、ポルトガル人の多くがスラウェシ島のマカッサルに逃れた。そのマカッサルも1660年に陥落する。これはフローレス島のララントゥカやティモール島のポルトガル勢力を増強する結果になったらしい。マカッサルの王室に隠然たる力をもった Francisco Vieira de Figueiredo のようなポルトガル人の豪商も、マカッサルを追放されてララントゥカに居をかまえ、ティモール島の Toepassen にも影響を及ぼしたといわれる。[Boxer 1947 "The Topasses of Timor"]
かくてオランダは、ティモール島から Toepassen を駆逐することに失敗し、1859年のリスボン条約で、ポルトガルとティモール島の分割統治を決めるのである。
Atoni族の建築
ティモール島の西部、即ち旧オランダ領に対する学術調査は、1821年の Reinwardt(ボゴール植物園の創設者)調査隊にはじまる。しかし、この調査隊は内陸部への探検を試みながら、わずか2日後にはクパンへの撤退を余儀なくされている。したがって、この島の家屋にかんして、はじめて満足のゆく報告をもたらしたのはドイツの博物学者 Salomon Müller であった。

丸い家と四角い家 [MÜLLER 1844]
"Het dorp Nasikoo, in het landschap Amarassie", 1839-1844
Natuurkundige commissie in Indië
 Memory of the Netherlands
Memory of the NetherlandsMüller の調査は1828年10月から13か月間におよぶが、Atoni族の家屋について2種類の形式を指摘している。屋根の先端の尖った蜂の巣のような丸い家と、大きな屋根を架した四角い家のふたつである。前者は真に原住民の家と呼ぶにふさわしく、内陸部でも普遍的に見られるのに対して、後者は主に王侯貴族やすでに文明化した住民たちが利用していた。ただし、一般のマレー家屋のような高床ではなく、みな土間床のうえで暮らしていたという。[Müller 1844]


Müller の報告する丸い家 ume bubu とその構造 [Müller 1844]
"Woningen der inlanders, uit het westelijke gedeelte van Timor", 1839-1844
 Memory of the Netherlands
Memory of the NetherlandsAtoni族の建築事情は、1987年の私の調査時でも Müller の報告と基本的にかわらない。唯一例外は、Müller の紹介する丸い家 Ume Bubu のなかに、円板型の部材(鼠返し)を柱頭にのせているものがある点だ。構造的には穀倉 Lopo そのものと言ってよい。もしこれが本当に人の住まいだったとすれば、穀倉の周囲を壁で囲って、その床下に住んでいたことになる。スンバ島などでいまも見られる通り、高床構造の転用を物語る貴重な証拠になるだろう。
20世紀後半、Atoni族の現代風住宅のもっとも一般的なスタイルは、木造フレームの上に波板鉄板の屋根を被せ、壁にはグバンヤシの葉柄 pepe-tune をならべるといったものだった。しかし、こうした現代風の住宅に併設して伝統的な建物がそのまま維持されているところをみかける。昔のモロ Mollo 王国やニキニキ Niki-Niki 王国の領内なら、現代住宅の背後に蟻塚のような円錐屋根の丸い家 Ume Bubu(Ume Kbubu と表記されることもある)が残されているし、さらに東のインサナ Insana 王国やビボキ Biboki 王国の領内なら現代住宅の前にきまって傘のような穀倉 Lopo が建ちならんでいる。家屋や穀倉の寿命が一般には20年から30年しかないことを考えるなら、伝統の根強さに驚かされるほかない。
家屋 Ume
家屋 Ume の所有は核家族単位でなされる。男は結婚後、自分の村に新しい家屋を建設するまでのあいだ妻の両親と暮らすのである。
丸い家 Ume Kbubu は直径3~5メートルほどの円錐形の建物で、地上まで屋根が葺きおろされているため、屋根を伏せただけの小屋のようにみえる。人間の住まいのもっとも原初的な姿をとどめていると言ってもよい。建築形態だけをみれば、オーストロネシア的というよりはパプア的(イリアンの高地民にちかい)なのである。
実際には、1メートルほどの高さの壁が周囲をめぐり、屋根組を支えるために、家のなかには4本柱の柱梁構造が組まれている。屋内の設備も土間の上に日常生活に最低限必要な物しか置かれていない。4本柱の中央に三つ石の炉 tunaf、柱によせて水甕 nai oel、奥の壁にそって調理道具や食器をならべる棚 tetu / pana があり、左右の壁際には寝所に使う低いベッド hala があるだけだ。
人間の暮らす土間の生活領域 Nanan (Nonot, Nesat など他の表現多し) に対して、天井裏 Po にはトウモロコシを保管する。

Ume Kbubu の平面
Tobu, Kec.Mollo Utara, TTS
間取りと方位観:こうした間取りは Atoni の家屋全般に共通している。ところが、象徴的な空間の意味合いは地域や地形によっても異なるのである。
入口 nesu / eno は東 Neon Saet(Naon は太陽、Saet は昇る)を向くか、あるいは土間床の雨仕舞を考慮して、土地の低い側にとられることが多い。この場合、オーストロネシア語族の通例にしたがって、南北の方位のかわりに Fafon (上) / Pinan (下)、Nakaf (頭) / Haef (足) などの言葉で家の向きをあらわしている。入口は Pinan や Haef の側にあるわけだ。
いっぽうで、Dawan 語には北をさす Knaben Amonot、南をさす Knaben Ahinat という言葉がある。Amonot は左、Ahinat は右を意味する。つまり、東を向いたときにこの方位観は矛盾なく人の身体に投影される。家屋が東向きに建てられるのは人の認知行動の上からも理にもかなっている。
Atoni 家屋の象徴論的な分析で家屋研究に画期をもたらした Cunningham [1964] によれば、入口の向きは右手、すなわち南にあるのが理想という。ただし、現実には東西の軸線上に乗ることを避ける(太陽が家のなかを通過することのないよう)だけであまり厳密な規則はなかったようだ。私の調査でも西に向く家屋こそなかったものの、地域によってまちまちの方向を向いていた。
また、南/北、あるいは、右/左を示す Ahinat/Amonot は同時に「賢い」「愚か」といった使い方もされる。Dawan語の新訳聖書「コリント人への第一の手紙」(1:25)のなかにこんな一節がある。
Fun lasi amonot neu Uisneno*, nane lasi ahinet le nesin mansian in lasi ahinet. (神の愚かさは人の叡智よりも賢い)
* Uisneno は本来 Atoni の民間信仰の対象である太陽(天上)神のこと
象徴論的な双分観を持ち出すまでもなく、こうしたDawan語の使い方を知れば、「右手の優越」[Robert Hertz] が Atoni の建築空間を律する基本概念になっていることがわかるだろう。丸い家 Ume Kbubu は間仕切りのない単一空間にすぎない。そのなかで、家財道具もほぼ左右対称に配置されているけれども、右と左を対比させる観念の連鎖は、家屋の空間に異なる意味と機能をあたえるのである。
Insana や Amanuban では入口に向かって右側のベッドを Hal' Atoni (男のhala)、左側のベッドを Hal' Bife (女のhala) と呼んで男女が使い分けている。Bikomi の村では右のベッドに主人夫婦が、左のベッドには子どもたちが寝る。Miomaffo にある儀礼家屋では右のベッドを Hala Nono (神聖なhala) と呼び、トウモロコシの初収穫を食べる儀式 Tahfeo に際して、聖水のはいった水甕をこのベッドに置き、二人の女が火の番をした。通常の起居には左のベッドしか使わないという。
建築構造:まず、4本の主柱 ni を掘立てにする。主柱は、頂部がY字形に枝分かれした材をもちいることが多く、そのうえに大梁 suif をのせて柱間をつなぐ。つぎに、大梁 suif と直行して4~6本の小梁 nonof をわたして軸組を固定する。さらに、nonof の上に suif と同じ向きに6~8本の小梁 tunis をのせて屋根裏の床根太を構成する(用語は地方によって若干相違する)。tunis の中央には横木 がわたされ、その上に棟束の足元を柄差しにして立て、屋根の棟を支えている。
部材同士の接合には、面倒な継手や仕口をつくらず、mausak と呼ばれる蔦の一種で縛る。単純明快にして原初的な構造原理である。こうした構造は家屋 Ume にかぎらず高床の穀倉 Lopo にも見られるし、さらにティモール島をこえて、スンバ島のような穀倉由来の構造をもつ建築全般に通底している。
建築構造の基本は Atoni 全体で共通するが、建物の向きと軸組との位置関係は地方によって異なっている。旧 Amanuban王国の領内では、入口に平行して大梁 suif があるのに対し、Mollo や Miomaffo王国では、suif は入口と直交し、小梁 nonof が入口と平行に配置される。

Supul, Amanuban Barat

Oenenu, Miomaffo Timur
棟の納まりにも相違がある。棟束の頂部が枝分かれして先端に短い棟木 lael (あるいは nete bifo 鼠の橋の意)をもつ場合、棟木はつねに入口と直交する向きにある。また、棟木をまったくもたずに、屋根の垂木を棟束のまわりに寄せ集めるだけの形式もある。こうした違いは各出自集団に固有のものとされる。棟木をもたないのは原住民であるNis Metan(黒い歯)の子孫、一方の棟木を持つ形式は征服民 Nis Muti(白い歯)の子孫とも言われている。

Oeleu, Amanuban Tengah

Oenenu, Miomaffo Timur

Oeleu, Amanuban Tengah

Nimasi, Miomaffo Timur
壁:軸組ができあがると、外周に沿って高さ1メートル程度の柱 ni ana (小柱といった意味) を立てならべる。この外周柱の上をぐるりと軒桁 nono (小屋組のモヤと同じ呼称) でつなぎ、屋根のタルキ suaf を受けるのである。同時に、軒桁にそって縦板を隙間なくならべて外周壁とする。
唯一ある戸口 nesu / eno には、平行にならべた方立のあいだに何枚かの横板をすべり落として建具とする。もっとも、閂はかからないから、これには動物の侵入をふせぐ程度の意味しかない。より高度な仕口では、戸枠の楣と框に軸吊用の穴を穿ち、扉板をつりこむ形式も見られるが、おそらく他からもたらされたものだろう。

Tobu, Mollo Utara

Nimasi, Miomaffo Timur
屋根:屋根には一般にチガヤ hun [Imperata cylindrica] をもちいる。海岸地帯では手間のかからないグバンヤシ tune [Corypha utan] やロンタルヤシ noe [Borassus flabellifer L.] の葉で屋根を覆うこともあるが、近隣の Belu地方や Roti島などからの影響ではないかとおもう。
まず、チガヤの下地をこしらえる。タルキ suaf の上に平行に小舞(横桟)takpani をめぐらして屋根全体を鳥かご状に形づくる。小舞をタルキに固定するには、グバンヤシの若葉(展開前の若葉から葉軸を取り除いたもの)を編んだ紐 tain tune やロンタルヤシの葉柄の表皮を裂いてできる紐 pepe、あるいは manbani という蔓植物などを利用する。このとき、小舞の間隔が屋根の葺厚を左右する。丁寧な仕事なら、その間隔は人差指と親指を広げた巾 lakat がよいとされる。
こうして屋根の下地が出来あがると、直径10cm程度の束にまとめたチガヤの葉先を下に向け、小舞2列ごとに pepe やトウ uwe をもちいて縫うように結びつけてゆくのである。






屋根頂部の雨仕舞
とんがり帽子、だんご、洗面器、棟があれば編んでもよし、半割丸太、木彫
建築材料:市場経済が発達する以前には、どこでもその土地固有の木材のなかから用途にふさわしい木を選択して利用してきた。木材の価値が市場原理ではかられ、チークが商業材として高い評価を受けるようになると、全国津々浦々にチークが植林され、材木として優先的に取引されるようになる。家造りは森の木を活用することから材木店で建材を買ってくることに変化した。1980年代にはまだそこまで地域文化の独自性は失われていなかった。
Atoni の建築は hau matani と hau aijao (hau は木) があれば済むほど、この二材がよく使われる。matani はマメ科シタン属の広葉樹インドカリン [Pterocarpus indicus] のことで、インドネシアでは angsana という。木部が赤いことから赤い木 kayu merah と通称される。堅く重い木で、地面に掘立てる柱にはこの木を使う。いっぽうの aijao はインドネシア名 cemara、一見、松と間違う外観をしているがモクマオウ科の樹木 [Casuarina eqnisetifolia]。柱以外の構造材全般に利用する。とくに丸い家屋の屋根裏を円環状にめぐるモヤ nono や小舞 takpani には靭性の高い素材が必要で、aijao の小枝や檳榔樹 pua [Areca catechu] の幹を割いたもの、トウ uwe などを束ねて使う。
ココマデ済み
穀倉 ロポ Lopo
アトニではロポとウメはハレとケの好一対をなす。高床のロポは収穫物や家宝の貯蔵庫であったが、同時に、床下を集会場や特別な来客の接待場に使った。しかし、現在の主食であるトーモロコシは穀倉での保存には適さない。たいていは虫がつかないように、炉の煙りでいつも燻し出される家屋の屋根裏に吊すか、灰と混ぜてドラムカンに保存する。米はインドネシア全体で品種改良が進み、穂刈りできなくなったため、収穫時に脱穀してそのまま米俵に入れてしまう。アトニだけの問題ではないが、穀倉はどこでも中はからっぽで機能を失い、維持されることも稀だ。
かってニキニキ王国には高さ8.5メートル、直径8メートルの巨大な吊鐘型のロポがあったと報告されている。それも修復されぬまま1980年代初頭に柱を残して倒壊してしまった。柱にささった石板の鼠返しには蜥蜴、鰐、馬、鳥などの彩色画が残されていて、ロポ建設に費やされたエネルギーの大きさを感じることができる。
ロポは本来王(ロロ、オランダ時代以後はスワプ・ラジャ)や貴族(ウシフやフェトル。儀礼を司る王に対して、実際の統治をおこなう)だけしか所有できなかった。その建設には彼らの支配する親族集団の首長(アマフ)たちがたずさわった。このような王族のロポでは垂木の数は支配下にあるアマフの数を、また、彫刻と彩色を施された特別な垂木はフェトルの数を表わしたという。王の偉大さはロポに使われた垂木の本数、つまり建物の規模で示されるのである。儀礼的な集会がもたれる場合には、ロポの基壇上にラジャとフェトルたちが、基壇下のそれぞれ垂木に対応する位置にアマフたちが腰をおろすのである。
高床建築であるロポの構造は、主柱の頭部に鼠返しを持つ点をのぞけば、地床の家屋ウメの構造と基本的に変わらない。
儀礼家屋 ウメ・レウ Ume Leu
戦闘儀礼や穀物儀礼の舞台となるウメ・レウ(神聖な家)は、また、親族集団の中心家屋とか戦闘の家ともよばれる。外観は一般の家屋とかわらないが、屋内に入るとその様子はまったく違う。四本柱のかわりに屋根を支えるのは家屋中央に立つ一本の中心柱であり、天井はつくられていない。この神聖な柱ニ・アイナフ(母柱)には祖先伝来の様々な神器の類、剣、槍、火打銃、ゴング、シリー(ビンロウジを噛む時にこの葉や実を一緒に口に含む)入れ、薬草、赤い布(戦いの際に頭に巻く)やトーモロコシの初穂などがかけられ、柱の足元には円形に石積みの祭壇が築かれている。
大規模なウメ・レウのなかには、中心柱の他に四本柱の軸組構造をもつ家屋ウメとの折衷形式もある。一般にこのようなウメ・レウの前には、アトニの天上神ウイス・ネノを象徴するハウ・モネフ(男の木)が立てられている。これは、祖霊ニトゥ(同時に地霊)を象徴する中心柱ニ・アイナフ(母柱)とともにアトニ社会における信仰の三位一体をなすといわれる。供犠儀礼はこのそれぞれに捧げられるのである。
王宮 ソナフ Sonaf
ウメ・レウのうちでも巨大なもの(多くはフェトル以上が所有する)はソナフの名でよばれる。建物を拡張するために、円形平面は失われ楕円形の平面構成をとる例が多い。こうなると中心柱だけではもはや屋根をささえられず、二本の棟持柱を立てて棟木をのせている。そのため、ニ・アイナフ(母柱)がになっていた柱のシンボリズムは内奥側の棟持柱が担うことになる。
穀倉と王宮
LOPO




1918年。Nikiniki 王国の Lopo は高さ8.5m、直径8mの巨大な吊鐘型をしていたと報告されている [Nieuwenkamp 1923]
本来は王族や貴族だけが所有した蜂窩状の穀倉建築。石積みの基壇上に建つ長大な屋根の建物は、所有者の権威を象徴する村の中心的な施設だった。配下の土侯が共同で建設し、彫刻された垂木の数が協力した土侯をあらわしたという。鼠返しの円板や柱などの部材は装飾され、儀礼で供犠したブタの顎骨が飾られた。床下は集会場として使われた
SONAF
王族の所有する儀礼家屋。王宮とも訳される。円形をした本来の儀礼家屋を拡張するため、多くは2本の棟持柱をもち、楕円形平面になる
男の木と母の柱
HAU MONEF

Tamkesi
儀礼のための氏族の祀堂 Sonaf や Ume Leu の東に立つ供犠柱。Hau Monef(直訳すると「男の木」)の3つに枝分かれした先端(1端は他より長い)は3つの神性 ― 天上(太陽)神 Uis Neno、地上(大地)神 Uis Pah、祖先神 Be'i Na'i ― の象徴といわれる。儀礼家屋の神聖な中心柱 ni ainaf(母の柱)とならんで祭祀の対象となる。
* Schulte NORDHOLT [1966] は Uis Pah のかわりに Uis Nenoの二つの属性 Uis Neno Mnanu (高位)と Uis Neno Pala (低位)としている。
**祖先神のかわりに水の神 Uis Oel を言う者もいる。キリスト教の影響か?

Kefamenanu Selatan

Maslete

Kefamenanu Selatan
NI AINAF

Nimasi のUme Leu
Ni Ainaf(直訳すると「母の柱」)は氏族の儀礼家屋 Ume Leu の中心にある神聖な1本柱。支配層である Raja (王)や Fetor (土侯)階層の氏族ではより規模の大きな儀礼家屋 Sonaf (「王宮」と訳されることもある)を建てることがある。建物は円形ではなく長円形の平面となり、中心柱の構造をとれずに2本の棟持柱が屋根を支える。この場合は、奥の棟持柱が Ni Ainaf になる。柱の足元は丸い石積みの祭壇で覆われ、様々な祖先伝来の神器がかけられている。 毎年の農耕儀礼ではトウモロコシやイネの初穂をくくりつける。かつて部族間の争いが頻繁に起きていた時代には、戦闘にむかう男たちは、この柱のまえで霊的な力を身につける儀式にのぞんだという。屋外にある三つ叉の供犠柱 Hau Monef とならんで祭祀活動の中心。祖霊を象徴する柱とも考えられている。

Oenenu

Kefamenanu Selatan

Haufoo
中北部ティモール
Timor Tengah Utara (TTU)オランダ統治時代には Biboki、Miomaffo、Insana の3王侯国 Swapraja、王侯国の下には Fetor の治める土侯国 Kefetoran があった。
TAMKESI
Biboki Selatan 1987

この建物は他の土地の Sonaf と違い、低い板床が張られている。氏族の故地とされる Belu 地方(一般に高床家屋をもつ)の影響かもしれない。残念ながら、1980年代に無残な改修を受けすでに見る影もない状態だった。

村の中心建物 Sonaf は長円形の平面をしている


長円の一端は土間で炉がある。他端にはケセールの居室がある

2本の棟持柱のうち左手が本来の供犠柱 ni ainaf。儀礼後のトウモロコシとニワトリの羽が見える

穀倉 Lopo の床下は集会場を兼ねた

供犠したブタの顎骨を飾る

MASLETE
Kefamenanu 1987

一月の収穫祭 Natama Maus (「収穫を納める」) では Senak 大氏族傘下の22の氏族が各地からイネやトウモロコシの収穫物を持ちよる。いったん Sonaf に納めた収穫物はつぎの種籾として逞しく育つという。三月にはトウモロコシの初実を持ちよって共食する儀式 Tahfeo がおこなわれる。

Sonaf は2本の棟持柱と4本柱の軸組構造をもつ特異な形式

前室では女たちが収穫祭 Natama Maus にそなえた準備におわれる

屋根裏に吊り下がるトウモロコシ

穀倉の Lopo と家屋 Ume

村の寄り合いはいまも Lopo の下でおこなわれる
KEFAMENANU SELATAN
Kefamenanu 1987


中心の母柱 ni ainafには、剣 suni、シリピナン入れ aluk、竹を八つ又にした sepe とその上に聖具を納めた箱 kopa、トウモロコシの初穂がつけられている

小屋裏に設けた棚 Tetu は神聖な器物を置く禁忌空間

左手のベッド hala nono は、トウモロコシの初実を食べる儀式 Tahfeo に際して、聖水のはいった水甕を置き、二人の女が火の番をする場所、右手の hala は通常の起居に使用する
NIMASI
Miomaffo Timur 1987
(現在の Bikomi Tengah)


核家族の住む一般家屋の Ume

Ume

儀礼家屋 Ume Leu。外観だけでは Ume と区別がつかない

蝶番を使わず、横板をすべりおとす戸口

軒垂木の先端にはニワトリの頭の彫刻がされる

縦板壁の納り

中心の母柱 ni ainaf のほかに4本柱の軸組構造をもつ。Senak 氏族の住む Maslete と Nimasi だけに見られる独特の構法

ni ainaf にはトウモロコシの初穂 usa pena、竹の sepe のほか、剣 suni、ゴング sene などの祖先伝来の品々をむすびつけ、足元の石壇には聖水をいれた水甕を置く

ni ainaf の先端は二股にわかれて短い棟木をささえる
OENENU
Miomaffo Timur 1987
(現在の Bikomi Tengah)


1本柱の建物は近年の改築。建物細部は Nimasi の儀礼家屋とよく似る


OELOLOK
Insana 1987

Raja Taolin in front of his Sonaf
HAUFOO
Nunmafo, Insana 1987



軒先を支える柱、当初材

Insana の建物は屋根に棟をもつ

棟木を支えるための仕口

中心柱の ni ainaf にとりつく祖先伝来の器物には、竹の供物台 sepe、ゴング sene、槍 auni、剣 suni、シリピナン容器 kabi(女用)、aluk(男用)、巾着 kohe、戦闘のさいに巻く赤い頭巾 toli mtasaなど

戸口の対面に主人の寝所 Kean、右手に男のベッド Hala Atoni、左手に女のベッド Hala Bife

箱のような主人の寝所 Kean

播種用のトウモロコシを保管
穀倉 Lopo が王権の象徴でもあった TTS とは異なり、TTU では個人の住宅ごとに小規模な Lopo を付設することが多い。とくに Insana ではジャワ家屋の Pendopo 風に各家の前庭に Lopo が建ちならんでいる。Insana の豊かさを示すものだ。






中南部ティモール
Timor Tengah Selatan (TTS)Mollo、Amanuban、Amanatun の3王国領からなる。
TTU では屋根に短い棟木を設けるのが一般的だが、TTS では棟木を使わず円錐屋根をつくる。
TOBU
Mollo Utara 1987

Mollo の王家である Oematan 氏族の Sonaf がある。昔、Miomaffo の王が Mollo の王を訪れる時にはこの土地の Sonaf で一泊する習慣だったという。1910年(?)頃の建設。長径12m、高さ6mの楕円形平面、本来は中心の1本柱で棟木を支えていたが、棟が不安定で屋根が傾きやすいという理由から、1971年の屋根葺き替えに際して2本の棟持柱をもつ形式に改められた。









左にみえる板状の柱は屋根を支える4本柱のひとつ

石積みで囲われた棟持柱のひとつが本来の ni ainaf


4本柱の上にのる屋根裏には、蛇や竜巻に変身する老婆の伝説がある

Ume





AJAOBAKI
Mollo Utara 1987




KAPAN
Mollo Utara 1987




NIKI-NIKI
Amanuban Tengah, 1987




OELEU
Amanuban Tengah, 1987
現在の Kolbano

Lopo は1942年の建設。鼠返し、大梁、床上への入口であるスライド式の扉にはワニ、トカゲなどの図像が描かれ、6本の彫刻された垂木が所有者の地位(usif だった)を物語る。屋根の頂部に人物像を飾っていたが、1968年、プロテスタント布教の影響で撤去。雨漏りのせいで建物全体に傷み激しく倒壊寸前。
この地域では米がとれない。トウモロコシは炉の煙でいぶす必要があり、Ume の屋根裏に保管する。よって、Lopo は家宝の保管場所になっていた。










円錐形の地床家屋 Ume。大きさは千差万別、それでも、内部に Lopo とおなじ4本柱の軸組構造をもつ点は共通している。Amanuban の特徴は、棟木をまったくもうけない円錐形の屋根にある。




王の威信をあらわす Lopo に対して、一般家屋 Ume に併設される Lopo もある。1942年建設の Lopo(写真手前)と Ume。





↑ Ume の屋根裏
↓ Lopo の屋根裏




SUPUL
Amanuban Barat, 1987
(現在の Kuatnana)







The name "Atoni" means "man, person" and is short for "Atoin Pah Meto" (People of the Dry Land) or "Atoin Meto" (Dry People) ("Atoin" being "Atoni" in metathesis). Europeans called them "Timorese," and Indonesians of Kupang may refer to them as "Orang Timor Asli" (Native Timorese) in contrast to immigrant Rotinese, Savunese, and other settlers around Kupang who come from nearby islands.
 World Culture Encyclopedia
World Culture Encyclopedia
The Atoni (also known as the Atoin Meto or the Dawan) are an ethnic group on Timor, in Indonesian West Timor and the East Timorese enclave of Oecussi-Ambeno. They number around 600,000.
 Wikipedia
Wikipedia
Uab Meto : 586,000. Western Timor Island. Alternate names: Atoni, Meto, Uab Atoni Pah Meto, Uab Pah Meto, Timor, Timorese, Timol, Timoreesch, Timoreezen, "Dawan", "Timor Dawan", "Rawan", Orang Gunung. Dialects: Amfoan-Fatule'u-Amabi (Amfoan, Amfuang, Fatule'u, Amabi), Amanuban-Amanatun (Amanuban, Amanubang, Amanatun), Mollo-Miomafo (Mollo, Miomafo), Biboki-Insana (Biboki, Insanao), Kusa-Manlea (Kusa, Manlea). Much dialect variation. Ethnological and linguistic differences in nearly every valley. Close to Amarasi.
 Ethnologue
Ethnologue
Dawan is an Austronesian language spoken by about 600,000 people mainly in the western part of Timor Island including the enclave of Oecusse (Oekusi), which is part of East Timor....The language is sometimes called Meto, Uab Atoni Pah Meto, Uab Pah Meto, Timor, Timorese, Timol, Timoreesch, Timoreezen, Dawan, Timor Dawan, or Rawan. The dialect spoken in Oecusse is called Baikenu although the local people simply call it Uab Meto.
 Omniglot
Omniglot
Dictionary of the Uab Meto language.
 Glossword
Glossword
Kamus Ringkas Indonesia-Inggris-Dawan
 Scribd
Scribd
The first Europeans in Timor were the Portuguese, perhaps as early as 1509. Portuguese trading ships regularly visited the north coast in search of sandalwood. It wasn't until 1568 that Dutch traders first arrived in Timor.....
 Facts About Timor
Facts About Timor
Setelah tahun 1900 maka kerajaan kolonial Belanda mulai melakukan pasifikasi semua daerah di Nusantara.Hal ini mencapai puncaknya pada tahun 1942, dan khususnya di pulau Timor terdapat empat raja dan lima kaisar : Empat raja di Timor ini adalah raja Nahak T Seran di Malaka Wehali,raja Josef Carmento Taolin di Insana, raja Noni Nope di Amanuban, raja Nisnoni di Kupang, sedangka lima orang kaisaer di Timor yakni kaiser Wehali Nai Bria Nahak sonaf Liurai, wafat 1924 dan dimakamkan baru pada tahun 1933, Kaiser Amanatun Banunaek di Nunkolo, Kaiser Tamkese-Biboki, Kaiser Hanmeni Bai Lake, kaiser Oematan di Kapan. id.Wikipedia
id.Wikipedia
Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942)
Swapraja
10 berada di Pulau Timor ( Kupang, Amarasi, Fatuleu, Amfoang, Molo, Amanuban, Amanatun, Mio mafo, Biboki, Insana) satu di pulau Rote, satu di pulau Sabu,
15 di pulau Sumba ( Kanatang, Lewa-Kanbera, Takundung, Melolo, Rendi Mangili, Wei jelu, Masukaren, Laura, Waijewa, Kodi-Laula, Membora, Umbu Ratunggay, Ana Kalang, Wanokaka, Lambaja), sembilan di pulau Flores (Ende, Lio, Larantuka, Adonara, Sikka, Angada, Riung, Nage Keo, Manggarai), tujuh di pulau Alor-Pantar (Alor, Baranusa, Pantar, Matahari Naik, Kolana, Batu lolang, Purema).Swapraja-swapraja tersebut terbagi lagi menjadi bagian-bagian yang wilayahnya lebih kecil. Wilayah-wilayah kecil itu disebut Kafetoran-kafetoran.
 Profil Daerah
Profil Daerah

Timor 島 Kemak (Ema) の家屋

manbani : 蔓植物の一種。チガヤのパネルをタルキに固定するのに利用する。グバンヤシの葉柄で代用。[??????]

tune: グバン gebang / gewangヤシ(タラバヤシ)。掌状葉の先端はロンタルヤシより細長くのび、しなやかでマットや屋根葺きに利用する。幹に蓄えるサゴ澱粉は食用になるかわり、樹幹を建材として利用することはあまりない。若葉の葉脈を編んだ紐 taen-tune は屋根のチガヤをタルキに固定するのに利用。葉柄 pepe-tune はならべて壁面にする。[Corypha utan]

meni : 白檀。インドネシア語の cendana 。ティモール島と西のスンバ島に自生、この地域の歴史に大きな影響をあたえた香木。[Santalum album L.]

matani : マメ科シタン属の広葉樹インドカリン。インドネシア名は angsana、通称 kayu merah (赤い木)。赤く重い木で主柱にはおもにこの木が利用される。[ Pterocarpus indicus ]
 ロティ | Roti
ロティ | Roti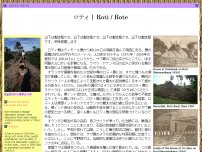

aijao / ijaob : インドネシアで一般に cemara の名で知られる。インドネシアの松とも呼ばれるが、マツ科ではなくモクマオウ科の樹木。タルキやモヤなど小屋組や鼠返しに使用。アトニの建築は matani とこの aijao を使うことが多い。[Casuarina eqnisetifolia]

ampupu : フトモモ科ユーカリ属。一般に kayu putih (白い木)の名で知られる。主柱に使用。[Eucalyptus urophylla]
2012KojiSato.gif)
Oeleu, Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT (1986)
2017KojiSato.gif)
Oeleu, Kec. Amanuban Tengah, Kab. TTS, NTT (1987)
2012KojiSato.gif)
Nimasi, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU, NTT (1987)
2017KojiSato.gif)
Kefamenanu Selatan, Kec. Miomaffo Timur, Kab. TTU, NTT (1987)
- REINWARDT, C. G. C. "REIS NAAR HET OOSTELIJK GEDEELTE VAN DEN INDISCHEN ARCHIPEL,IN HET JAAR 1821", 646P, 1858
- MÜLLER, Salomon 'Bijdragen tot de kennis van Timor en eenige andere naburige eilanden' in C.J.TEMMINK (ed.) "VERHANDELINGEN OVER DE NATUURLIJKE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE OVERZEESCHE BEZETTINGEN", pp.131-446, 1844
- NIEUWENKAMP, W. O. J. 'Een Vooraadschuur en Een Offerhuisje op Timor', Nederlandsch-Indie Oud en Nieuw 8-7, pp.197-203, 1923
- CUNNINGHAM, Clark E. 'Order in the Atoni House', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 120, pp.34-68, 1964
- NORDHOLT, H. G. Schulte "THE POLITICAL SYSTEM OF THE ATONI OF TIMOR", Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-,Land- en Volkenkunde 60, 511P, 1966
- 佐藤浩司 「西チモールの住居」『民俗建築』87, pp.53-71, 1985
- 佐藤浩司 「チモール島の住まい」『季刊民族学』43, pp.24-35, 1988
- PURBADI, Yohanes Djarot "TATA SUKU DAN TATA SPASIAL PADA ARSITEKTUR PERMUKIMAN SUKU DAWAN DI DESA KAENBAUN DI PULAU TIMOR", Disertasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010
 pdf file
pdf file - Dima, Thomas Kurniawan & Antariksa, Antariksa & Nugroho, Agung Murti "Konsep Ruang Ume Kbubu Desa Kaenbaun, Kabupaten Timor Tengah Utara", Jurnal RUAS 11-1, pp.28-36, Universitas Brawijaya, 2013
 pdf file
pdf file - Dima, Thomas Kurniawan & Antariksa, Antariksa & Nugroho, Agung Murti "Struktur Ume Kbubu di Desa Kaenbaun, Kabupaten Timor Tengah Utara", arsitektur e-Journal 6-1, 12p, 2013
 pdf file
pdf file




 フィールドノート
フィールドノート


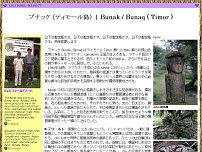



 本ページ中に間違いを発見された方はどうかご連絡ください。誤った情報は改めていきます
本ページ中に間違いを発見された方はどうかご連絡ください。誤った情報は改めていきます