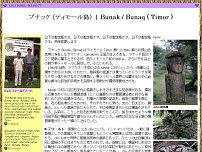サヴ | Savu / Sabu
still test version
島へ帰ること、村へ帰ること、家へ帰ることがすべて「舟に帰る」ことを意味する島。この島では死とは霊魂がアマ・ピガ・ラガという舟に乗りくみ、この世から西方にある祖先の霊魂のいる世界へと航海することであり、葬式は地上の人間がその航海のための準備を整えてやることを意味している。
この島、サブ島は面積約六〇〇平方キロメートル(日本の淡路島程度)、雨が少なく、土地はやせ、やしの木以外には木影もまばらな島内に約5万人(一九七一年の統計)の人口がいる。
東インド会社がサブ島の五王国を正式に認め条約を締結したのは一七五六年だったが、それ以前から、サブ人は勇敢な傭兵としてオランダのために働いていた。しかし、肝心のティモール戦略にとってロテ島ほど重要な価値をもたなかったために、オランダはサブの統治(教育と布教)にはあまり熱心でなかったらしい。サブ人の性格が攻撃的で、他の島で活躍する者が多いといわれるのは、こうした自然環境や歴史に負うところが大きい。
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
サブ島の中心セバの町の郊外にナマタという村がある。この村は1983~84年にかけて、インドネシアの教育文化省により集落の建物や施設の修復を受けている。当時、サブ島やロテ島のある東ヌサトゥンガラ州には、地域の伝統文化の保存のために集落全体の修復・修景を計画実施された村が三か所あった。フローレス島ンガダ族の村ベナ、スンバ島西部のアナカランとならんで、ここナマタがその対象とされていた。観光目的の修復作業はたいてい外見上の美しさに最大の関心を払っているから、修復を機会に建物を新しく(外観を維持しながら)建て替えてしまうことが多い。博物館ではないからこれはある程度やむを得ないけれども、周囲にたくさん残っている伝統村よりずっとモダンな村が出現することになる。アナカランで調査を続けていたある人類学者は、村長が突然オートバイを買えたりするのはどうしてだと思う? と言って笑っていた。
そのナマタは海の見える小高い丘の上にある。むかし、ラエ・コーワ<舟の村>といわれるサブ島の伝統的村落は山の頂にあるのが普通だった。村は周囲を珊瑚岩などの石垣で囲われ、巨石記念物や根元を石積みで覆われた聖木(菩提樹など)のある広場を中心にして舟を伏せた形の家屋が建ち並んでいた。これらの家屋の中心は、アム・ケプエ<根元の家>という村の成立の起源となった家屋で、ラエ・ケプエ<根元の村>の場合には、これは同時にウドゥ(父系クラン)やケロゴ(リネージ)の中核家屋でもあった。
こうした村は同じウドゥの成員からなり、バング・ウドゥ(クランの全権を委ねられた首長)という船長を中心に組織された舟共同体を構成していた。新しい村が作られるとしたら、いまなら少しでも交通の便のよい平野部に立地するし、村から離れた畑地の出作り小屋をそのまま家屋に利用することも多い。さすがの舟共同体も社会的な統制力はすでに弱まりつつあるというべきだろう。けれども、どの家も必ずどこかのラエ・ケプエとつながりを保っていて、いざ儀礼という時には、いまでも村に駆けつけるのである。
ナマタには、敷石を並べた環状広場の東に鍋を伏せたような巨石群や村の聖木のある一画がある。さらにその東には棟を西に向けた3棟の儀礼家屋が南北に建ち並んでいる。
バニ・デオ<女神>、マヌ・タダ<鶏の合図>、ヘオ・カニ<九本の(舟の)竜骨>という屋号をもったこれらの儀礼家屋には、それぞれ慣習上の役務を担った人物が住んでいる。それは、慣習儀礼一般を司る首長デオ・ライ<地の神>(本来は雨期の儀礼の中心)とその補佐プロド<太陽の祖先>(乾期の儀礼の中心)、そして戦争を司るマウキアであるという。
サブ島は東西に長く、その景観は西部地方が山がち(といっても海抜二五〇メートルにみたない)なのに対して東部は比較的平坦である。そのために島は西に船首を向けた舟にたとえられている。村落の配置も家屋の配置もこの舟の方向に逆らうことのないように主軸はつねに東西方向にある。

Savu の家屋 Ammu Ru Koko の平面
屋根の妻先が突き出して、裏返しになった舟に喩えられるアム・ル・ココ(アムはイエ、ルは葉や毛、ココはのど、つまり「喉毛のある家」)もまた妻先の方向は東西をさしている。
この舟の家の側舷には、南北どちらかの側にベランダがある。畑地へ出なくてもいいような暇な時、縁側にあたるこの空間では男たちがロンタルの葉を編んだり、女たちが布を織ったりしている。これを家屋の正面とすると、サブ島の舟家は正面からみてつねに右側が船首ドゥル Düru、左側が船尾ウイ Wui と見做されている。
ドゥルとウイは、象徴的には男と女に結びつく。ベランダから屋内に入る扉は、船首側が男用の入口、船尾側が女用の入口であるし、屋内には船首側の男の空間と船尾側の女の空間がある。女の空間の上にはダムという屋根裏空間があり、ここには家の主婦だけがのぼることができる。
女の空間はさらに中程の間仕切りで二つに別れ、もっとも船尾の部屋には炉がある。つまり、屋内の空間は、船首(男)、中間(女)、船尾(女)に三分割されていることがわかる。
雨期の終わり(四月から五月にかけて)に、サブ島のあらゆる農耕儀礼のフィナーレを飾るホレといわれる収穫儀礼がある。この儀礼は、各家々や村々がその年に収穫されたモロコシと緑豆で一種の粽をつくり、これを儀礼舟にのせて、サブ島西方のライジュア島(サブ島はライジュア島の土から作ったという神話がある)に向け舟出させるのである。この儀礼の過程で、儀礼に使われるモロコシと緑豆の一部は、ココヤシの殻に入れ、主婦の手で屋根裏にある女の柱ガラ・バニの下におかれる。西方にある祖先の島に穀物を流すことと、ガラ・バニに穀物を捧げることが同一視されているのである。
主婦の専有空間の屋根裏ダムには、棟木を支えるために二本の棟束、ガラ・モネ<男のマスト>とガラ・バニ<女のマスト>がある。サブ島の家屋における女性価値の重要さはここにも示されているわけである。
RAELORO
Sabu Barat 1987
NAMATA







Chiefs house in the island of Savu [A Collection of Drawings made in the Countries visited by Captain Cook in his First Voyage. 1768-1771]
 captcook-ne.co.uk
captcook-ne.co.uk






LIMAGGU
Sabu Timur 1987
DOKAIKI

UNUMOLA











メモ

 フィールドノート
フィールドノートThe islands are split into five traditional domains, the largest is Rai Djua (Djua/Jua Island) follwed by Heb'a (Seba) as the second largest on the northwest coast. Society is divided into clans named after their male founders. The Savunese are also divided into their Big and Small hubis, which are determined by the mother's lineage. The big hubi is called hubi ae (big spadix) and the small hubi is called hubi iki (small spadix). Their secular tradition is known as Jingi tii Eu (Jingitiu)
 Savu Islands
Savu Islands
110,000 (1997). Population includes 15,000 to 25,000 outside of Sabu. Islands of Sawu and Raijua south of Flores and west of Timor, and in Sumba (especially in Waingapu and Melolo), in Ende on Flores, and the Kupang area of Timor. Alternate names: Hawu, Havunese, Savu, Sawu, Sawunese, Savunese. Dialects: Seba (Heba), Timu (Dimu), Liae, Mesara (Mehara), Raijua (Raidjua). Related to Dhao.
 Ethnologue
Ethnologue
 Melayu Online : Rumah Adat Temukung
Melayu Online : Rumah Adat Temukung

due: lontar(パルミラヤシ/オウギヤシ)はサヴ島やロティ島の生活にかかせない。 [Borassus flabellifer L.]
 ロティ | Roti / Rote
ロティ | Roti / Rote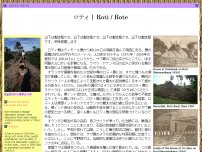
 Tapping the Lontar Palm
Tapping the Lontar Palm

1日2回、叩いた花序から滴る樹液を採取する。この樹液がヤシ酒や砂糖の原料になる

島民はlontarの生み出すヤシ砂糖を栄養に育つといわれる










sasando ロティ島の楽器

ti'ilangga ロティ島の帽子

lontar 日本では貝葉の名で知られるロンタル文書
2014KojiSato.gif)
Desa Limaggu, Kec. Savu Timur, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia (1987)
- KANA, N.L. 'The Order and Significance of the Savunese House', in J.J.Fox (ed.) "The Flow of Life", Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts & London, pp.221-230, 1980
- 佐藤浩司「舟型住居の原型を追う:サヴ島とロテ島の住まい」『季刊民族学』46, pp.92-103, 1988