フィールドノート 1987 fieldnote 1986.10.20 -1987.3.6
10月20日(月) 晴のち曇 Mataram
バリ島での調査を終え、ロンボック島へ向かう。
Padangbai発午前9時。快晴。マルクでの航海とくらべると、このフェリーは格段に大きく、たかをくくって本を読んでいると、揺れがひどいために酔ってしまった。軽い吐き気。読書を中止するとこれもやむ。
バリからのフェリーは針路を北東にとり、途中で南東に針路をかえる。大きく北を迂回。ロンボック島のLembar着は午後1時(東部時間の午後2時)。Lembarはいかにもロンボック島をおもわせる朴訥な風情の港。フェリーの操縦がヘタクソなためか、接岸までにずいぶん時間がかかり、その間、客室を降りた乗客たちはバスやトラックの隙間に荷物をならべて待つ。
LembarからMataramまでは送迎コルトがある。赤児を連れた初老の(どうみても)婦人は、車掌の制止をきかず、荷物を客席にはこびこみ、挙げ句、子どもは途中で嘔吐し泣きはじめる。傍若無人のこの婦人と嘔吐物の悪臭。
Mataramに近づくにつれて雲、雨が降りはじめる。スラバヤで会ったことのあるイワン・タナヤ氏の店にころがりこむ。あの時、彼と同行した刺青の弟氏は、つい数日前に、スンバワ島のDompuで刺し殺されたという。犯人4人がつかまり、うちひとりをのこしてすでに放免された。この家から学校へ通うSMP(中学生)の男の子は、子どものくせにやけに人扱いにたけている。一緒に食事をしながら、「少ししか食べないんですね、もっと召し上がってください。」などと言う。この子はイワンの店にすわって一人前に金勘定から商いまでする。さすがは中国人。

ロンボック島へ向かうフェリーはバリ島東岸のPadangbai から出港する
10月21日(火) 晴 Mataram
朝から役所まわり。それもかなり曲折した。

役所の屋根は穀倉を模したもの
10月22日(水) 晴 Pengeleng
午前中、Polisi(警察)、Bappeda(地方開発計画局)、PdK(教育文化省)をまわる。PdKでは前日約束の時間に行ったにもかかわらず、Musjarah(博物館歴史部)の部長ワチャナ氏がいず、所員の某氏と押し問答。激しいやりとりのあと、結局ワチャナがあらわれ、めでたく必要な本を頂戴することができた。帰りにそのことを謝ると、まあそんなもんですよ、という答え。memang begitu。ここで時間を費やしたため、Mataram を出発したのは12時過ぎ。中部ロンボックの県庁 Praya 到着は1時をまわっていた。Mataram の Bappeda からは、この書類を県知事に持って行くように言われていたが、どうせ相手にされないだろうとはじめから機転をきかして Sospol(社会政治局)の建物に行く。ここで所員に書類をわたすと、半ば面白半分に所員たちの質問攻めにあう。これで書類が受理されるのか思えばそうでなくて、200mほど行った Bappeda に行けという。最初からわかっているなら時間の無駄で質問など無用の沙汰。急遽 Bappeda にむかう。役所の閉まるまでいくらも時間がないが、所長の好意で市長宛の書類をつくってくれた。宿泊所が Praya にはないのだからしょうがない。Praya からコルトで30分ほど行ったところに Sengkol の村があり、これが Pujut市の中心。すでに3時過ぎ、役所があいているはずもなく、市長の自宅を訪ねる。昼寝中のところを起こし、書類だけをわたして明日来るつもりでいたら、親切にも所員のひとりを呼び、村長宛の書類をつくってくれた。
Sengkol村は20の分村Dusunをもつ。村長のラル・クスマナタは猜疑心に満ちた目で僕をねめつけ、市長からの手紙をなかなか開こうとしない。ところが、建物や村の話を訊ねはじめると、やけに親切になって事細かに教えてくれる。昨年訪れたJunge村はこの1年間にずいぶん現代建築が建ったという彼の助言で Junge よりさらに道をすすんだ Pengeleng という村で調査することになった。
この分村長はアブドゥル・ハキムといい、すでにハジの称号を得ている。家もコンクリート造の大きなもので、どうもこの金持ちの家に僕を泊めようという魂胆から、村長はこの村を選んだものと思われる。村長の前でこの分村長はやけに恭順で純朴な男を演じていたのに、村長が帰宅するや急に雄弁になったのには驚いた。彼の自慢は350万RPかけてハジをもらいに行ってきたサウジアラビアのこと。スラバヤからバンコクまで4時間、バンコクからサウジまで8時間飛行機に乗ったと言い、日本まで8時間で、距離は同じくらい遠いと説明する。ところが、サウジとインドネシアの時差が8時間で、日本とインドネシア・スラバヤの時差は2時間という話になると、日本はずいぶん近いんだということになってしまう。世界地理というものはここではまったく通用しない。子どもたちは学校で地理を習うらしい。「地図をみると日本はいつも赤く塗ってあるけどどうしてか?」とくる。
中部ロンボック県では99.46%がイスラムである。おそらくヒンドゥー・バリ人に対抗する手段として、ササック族は急速にイスラム化したのかもしれない。この分村にハジは4人いる。たまたまこの日の夕刻同席した村の男はやはりハジで、彼の場合は船で26日かかってメッカまで行ってきた。

分村長の自慢は350万RPかけてハジをもらいに行ってきたサウジアラビアのこと

10月23日(木) 晴一時曇 Pengeleng
朝のトイレとマンディが一苦労。200mほど行った畑のなかに泉があり水浴びできるし、その水浴場の近くに小川があるからそこで用をたせばよい、との話で、子ども二人につきそわれて出向く。水の干上がった田んぼの中のあぜ道を歩き、藪の中にわけいったところに泉がある。正確に言うと、直径2mくらいの池の面影を残した沼。周囲の木々の落とす葉、何人もの人間の水浴のカス、これら堆積物によってヘドロ化した地盤、硫黄臭を発するメタンガス、微動だにしない沈殿した水。かつての小川の跡には点々と水を残した水溜り、水辺に近づこうものならサンダルごと足を取られてしまう泥沼。群がる蚊。このなかで、ともかく用を済ませ、硫黄臭い水を浴び、村まで歩いて戻るうちに、ふたたび身体は汗にまみれる。
午前中、村中を歩き、適当な家を物色、綺麗に並んだ Bale(家屋)と Alang(穀倉)の列が印象的だ。が、家屋の方は平面上の変更をこうむっているものが多く、調査家屋の選定に苦労する。Junge まで足をのばして前回調査分の確認。Junge は山の斜面が急で、家屋の基壇もずっと高い。山頂にはモスクがあるという。古い家屋は3棟のこる。状態は多分 Pengeleng よりも良し。Pengeleng は集落配置にすぐれる。一長一短あって、結局 Pengeleng の Bale Ama Kecet の採寸。
Junge は hebat だ。もう電気がはいろうとしている。と、Pengeleng の若者の賞賛にみちた発現。

朝のトイレとマンディは一苦労
10月24日(金) 小雨のち曇 Rembitan
マンディ場の見聞。村はずれの井戸は水はキレイだが見晴らしがよすぎてトイレに困る。しかも、多くの衆人環視の中。それで仕方なくもうひとつの湧水場へ。トゲトゲのパンダヌスに覆われた粘土質の土地。サンダルと足の間がすべって、サンダルがすぐに脱げそうになるため足元危うく、排便も容易でなく必死の態。湧水の穴は田のすぐ脇にあり、結局この田んぼを通しただけの水か。どういうわけか、ここの水も硫黄臭があり、水浴後の水がすぐ逆流して泉におさまる仕組み。火山性の土質のためか、積年のヘドロのためか。このマンディ行に1時間以上も費やす。帰宅後朝食。疲れる。
調査をはじめようとすると、筆入れから日本製の4色ボールペンと0.3mmシャープが紛失しているのに気付き、にわかに意欲を喪失した。家にもどり荷物をまとめる。村を出る。村長はじめ数人が家にあつまり捜索をはじめる。犯人の見当はついている。昨夜、子どもたちがこのペンで遊んでいたから彼らのひとりにちがいないが、大人がタバコを盗ることを平気でするのを見ていれば、彼らがボールペンのひとつふたつちょろまかしても決して怒れないのだ。しかし、このペンは日本から持ってきた最後の1本で、調査にはどうしても必要。この国に代用品がないのだから。これをとくとくと話してきかせた。
金曜日、モスクで礼拝のあと、村長たちが戻ってくると、ひとりの子どもがペンを見つけたと言って持ってきた。このおかげで彼はペンを見つけるのが上手く、朝マンディ場に案内してくれた子(昼すぎに学校へ出かけた)が犯人ということになってしまった。本当は、ペンを見つけてくれた子が昨夜ペンで遊んでいたのだけど。
午後2時、Rembitan へ向かう。徒歩約30分。田んぼを突っ切って歩く。Rembitan はあたらしい村長が軍人あがりで盗人はいないという噂だったが、確かに明朗な村長。いちおうトイレ場らしきものが村にあるのがいい。そのかわり、寝るのは穀倉を改造した高床の建物で、床にゴザを敷いただけ。しかも、数人と雑魚寝でこれは蚊が多くて閉口だ。夕方、モスクの図面採り。夕食、緑豆の葉(アクがある)のスープと卵焼き、山盛りのご飯。

このマンディ行に1時間以上も費やす


実測図:Pengeleng家屋 Bale 平面
調査途中…にわかに意欲を喪失した
10月25日(土) 朝雨のち晴 Rembitan
Sade分村、Rembitan より徒歩20分。昨年まったくの荒野と化した畑のなかにたたずむ Sade を見て不毛な村という印象を得ていただけに、今年は薄らハゲ程度に緑があって厳しさを欠くかな。
昨年帽子をねだられたクルダップ君と再会。帽子と古着をお土産にわたし、旧交をあたためる。彼の魂胆はともかくとして、いろいろと親切に手助けしてくれるので助かる。
昨年調査済の Bale の再調査。M先生の図面ではアイソメが描けないため。この家の家主の金をねだるのにはまいる。タバコ2箱進呈すると、これで1000RPするとクルダップが説得している。金に換算したうえで納得されるのも困る。ロンボックの住民は二言目には金という。けれど物価はとても安く、地方のくせにジャワのカンポンなみだ。伝統的なインディゴ色の布(糸を手でつむぎ、色も自然の材料)を1万RP(言い値)で買った。この村の基準からいうと、ずいぶん高く売りつけたようだけれども。
Pengeleng の村長は手の皮膚の感覚がなくなっているので何か薬はないかと言っていた。いま考えると、これは何か鉱物質の中毒ではないか。水のせい?

帽子をねだったクルダップ君もいまは(2017年)村長兼校長先生

実測図:Sade家屋 Bale 平面
10月26日(日) 曇 Rembitan
Sade の調査続き。Bale、Alang、Berugakの図面採り。昨日来の熱心な(?)図面採りのせいか、村の人たちの共感をようやく得たらしい。
村での調査心得
①食事も休憩もとらない気迫をみせること
②服が汚れるにまかせること。すくなくとも村人にキタナイと言われるように。屋根裏にのぼれば簡単
③時にわざとらしくともパフォーマンスを演ずること。たとえば、どんな小さなものでも逃さないといった心意気で図面を採り測ってみせる。丁寧に樹の葉の写真を撮ってみせる、等々
berjibaku(自爆する):勇敢に死ぬことを berindonesiakan した日本語で言う。berjibaku untuk merdeka (独立のために死んだ)とヒューヒュー笛のような息で話す老人が言う。

実測図:Sade家屋 Bale 梁行断面

実測図:家屋 Bale 桁行断面

実測図:家屋 Bale 詳細図

実測図:大工道具

実測図:穀倉 Alang 断面
10月27日(月) 曇 Rembitan
毎夜のように雨。日中も雲多く、写真を撮るのに苦労する。
Sade に着くと、たまたま屋根葺き替えに出くわす。片面のみの葺き替えで、朝6時から12時まで、約20人くらいの作業。老人4人が竹から結縛の紐をつくり、他の人員で葺き替える。棟には一時的にチガヤを葺くが、稲の刈り入れ後、稻束をならべて押さえる。
午後より木の撮影。観光客がバスでやってきて20分ほど村を歩き回り、keton(お金)と群がる老人子ども、kain(布)を売ろうとする女どもに送られて Kuta へ向かう。村長はダブダブのズボンをもらい嬉々としてはいていた。

実測図:集会場 Berugak
10月28日(火) 晴 Rembitan
朝、珍しく快晴。Sade の写真、木の撮影。これを済ませる頃には雲がひろがり、いつもの天気にもどった。村長の子どもを連れて Kuta ビーチへ海水浴。将来ここにホテルが建設される予定という。昨日、Sade の近くの森の中で会ったイギリス人とトラックの荷台で同道。彼は cari tanah(土地捜し)とインドネシア人の案内役が語っていたが、山師? まん丸サングラス、金髪パーマ、耳に揺れるイヤリングといった風体で、どうみてもまっとうではない。けれども、まじめな建築学者がイヤリングをして調査というのも人当たりが良くて悪くはない。
Kuta で帰りのバスを待つこと1時間、しびれを切らし、子どもたちをなかなか出発しないコルトに残し、歩きはじめる。約20分、海岸までおりてくると、さすがに天気もよく暑い。この炎天下を歩く。山道にさしかかったところでコルト追いつき、汗だくの体で乗り込む。子どもたちは1ヶ25RPのビニール入りのアイスキャンデーをおいしそうに食べている。けれど、ちょっとこわくて食べられない。もっとも、むかし東京にだってキャンデー売りがいた。1本5円の割り箸にさした長いキャンデーだった。他所から来れば、これだってこわいに違いない。
結局、午後2時すぎ Rembitan 帰着。昼食を済ませ、Sade での調査再開は午後3時。集落配置図はあきらめ、布の撮影と家屋調査の補足。家屋は丘陵の傾斜面に山を背にするように連なる。穀倉の余地のない家屋も多いが、原則は家屋と穀倉のセット。

村長の子どもとKutaビーチへ海水浴

Kutaの海岸は定期市の会場
10月29日(水) 晴 Mataram
朝、例によって記念撮影を済ませ、Rembitan を出る。
Teruwai村の Tempit に古い大家屋が残る、という情報を Pengeleng で得ていたため、帰路この見学を済ませておこうと思い、市役所へ立ち寄る。選挙のため、役人はみなこのところ会議で、市長は Puraya 出張中で不在。事情を話すと、所長という立場の物わかりのよい男がすぐに書類を整えてくれた。これを手に馬車で Teruwai へ向かう。
おかしいのは、Teruwai の村役場でこの書類を差し出すと、折からひとりの男が飛び込んできて言うには、県庁からの書類をよく見ると、僕の調査地は Rembitan と Sengkol の二箇所になっている。Teruwai は含まれていないから先刻の書類は無効にしてくれという。ただそれだけのために、この男はオートバイを走らせて僕を追いかけて来たわけだ。しかし、せっかく来たものを引き返す道理はない。別にここで泊まろうというわけじゃなし、観光客としてでよいから見るだけ見せてくれと頼む。
この村役場の担当は、はじめからこの追跡してきた男の言うことを相手にもせず、私が連れて行ってあげようという話になったので助かった。ここらへん、村の役場ひと筋で長年働いてきたこうした人間は、出世を気にしながら腰掛け的に各地の役場の所長を遍歴してあるく者たちと違って融通がきく。村に愛情をもって、それを知ってもらおうとしているのがわかる。マルクの警察官ツァヘウスのようだ。
ところが、肝心の Tempit の家屋というのが2年前にすでに改造されてしまったという、その村の人間による新情報。そのため、この役場の男の案内で Tego という分村の別な家を見に出かける。この家屋は、いままでに見た中部ロンボックの家屋のなかではもっともよくまとまり、ディテールもしっかりしていた。柱割りも太い立派なものだ。Sade の家屋よりはひとまわり大きい。家主は60歳代の頭の良い矍鑠とした老人で、家屋のことも詳しい。時間がなく平面のみ採ったが、再調査したい家。


例によって村長家の記念撮影

実測図:Tego家屋 Bale 平面
時間がなく、再調査したい家

10月30日(木) 快晴 Mataram
昨日、午後より天気きわめてよく暑い。一日中買い物。中国人の商店主で自宅に美術館なみの秘蔵民芸品コレクションをしているのがいる。彼のもとで木彫を買ったけれどずいぶんぼられてしまった。観光客相手の中国商人の海千山千の厚顔ぶりにはうんざりさせられる。金を稼ぐということに節度がない。それにくらべてロンボック人の土産物屋の店主のなんと人情味のあったこと。
プールに行く予定でいると、イワンが一緒に行くから3時まで待てという。ところが彼は忙しくて家には現れず、結局プールも行けず。それならそうはじめから言えばひとりで行っていたのに。ここらへん八方美人ですこしこまる。
この彼の家の慎ましい食事にちょっと食傷。昼食は外で3500RPの Udang Goreng(海老フライ)。車海老のようなのが11匹も山盛ででてきた。マタラムの物価は安い。
10月31日(金) 晴 Pancor
午後マタラム発。イワンの妻の従兄弟の子が50RPを飲み込み、これが喉に引っかかった。どうしても取り出せず、子どもの方もぐったりしているというので、昨日来ルクマンは忙しいらしい。昼にその子の手術(喉に器具を突っ込んで取り出す)があり、その後、彼も Pancor まで同行するから待て、と言われおとなしく待つ。
中国人の経営する土産物屋へ行って毒づいてくる。「他所で2000RPで売っている物を3500RPで売ろうとはどういう了見か?」「ならうちで買わなくていいわよ」「なんだその言いぐさは」……ということで、「まけろ!」「まけない!」「中国人は金を稼ぐことしか考えない!」「あら、人間はみんなそうよ」てなもんで、後で考えると我ながらあほらしい。もっとも、いま思い出しても腹が立つからこれは確信犯。
Pancor のハジ・ルクマンはイワンの妻の兄らしい。とにかくマタラム中の中国人は何らかの血縁関係にあると思われるほどだ。彼らはジャワの中国人とくらべてよく純血をまもっている。で、このルクマン氏は7人の子持ちでこれが全部女。男の子がひとりいたが、17の時に死んだ。家はこの地方としては大きく、僕はあまり歓迎されていないのか、そのお手伝いの部屋に寝かされることになった。ともかく荷物を預かってくれるだけで助かる。電池、土産、手帳、フィルム、野帳、筆記具、衣類と、すべて余裕をみて持ってきているから、荷物の量はマルクの時とくらべて格段に多い。
ロンボックの木彫はみな愛嬌のある顔をしている。ワヤン・ゴレッに登場するボケ役のキャラクターだ。首が長く肩が落ち、間の抜けた顔でとぼけたことを言い、周囲を笑わす。と、思ってベモに乗って周囲の人びとを見ると、この木彫にそっくりな顔が多いことに気付く。目と目の間が極端に離れ、顔の輪郭にしまりがない。これがロンボックに独特の木訥、明るい農村的雰囲気を醸し出しているのかも知れない。
夕食後、ここの家の次女とその恋人とともに映画を見に行く。600RP。場内は小さな町とは思えぬほどの盛況。白人と混血のインディアンがインディアン呼ばわりされながらも騎兵隊員たちを指導し、烏合の衆、白人を殺すことしか能のないアパッチの本拠を奇襲して彼らを全滅させる。しかし、基地にもどった彼を生き残った仲間の騎兵隊員は残忍と非難する。彼はひとりさびしく基地を後にする。インディアンの敵はインディアンというわけだ。後から土地に侵略してきた白人たちが正義で、原住民のインディアンを虫けらのように退治する。アメリカは今でもこんなワンパターン映画をつくっているのだろうか。戦争映画の敵は殺されるために存在する。
11月 1日(土) 晴のち曇 Pancor
本日出発の予定がルクマンのすすめで明日になる。きょうは調査許可証をとるのに役所をまわり、午後から周辺の見学に連れて行ってあげるというまことに親切な申し出であった。
はじめ彼所有のポンコツ外車に乗り、役所 Bappeda → Bupati → Sospol と案内してくれる。この車は走りながら地下鉄銀座線を思わせる騒音と震動を発する。やがて彼の奥さんの妹の結婚先の店に案内され、ここでもう少しマシな車を借り受ける。これからが問題だ。
車には彼の末子の女の子と友人の新聞記者(ルクマンもそうだ)が同乗してきた。まず行ったのがガソリンスタンドで、ここでガソリンを満タン。「お金あるかい?」と、親指と中指を擦りあわせながらルクマン。つぎが Aikmel の市役所で、これは明日からの調査の報告をして手紙を用意してもらうため。明日、役所からの一行が Sembalun を訪れるということで、僕はこれに合流すればよく手続き終了。
この後、ルクマンとその友人はたまたま通りかかった消防車の後を追って火事の取材。20棟以上が燃えた現場は炎天下のうえ残り火が燻っていて熱い。この地方都市の火事に時間のない僕がつきあわされる羽目になる。その後、彼は湧水に案内。ここで子どもたちが素っ裸で泳いでいるのをしばし見物し、Tetebatu に伝統家屋の見学。道は悪く、彼の運転はヘタクソで、途中で買った Bantal というバナナのはいった餅米のお菓子は何度も床に落ちた。これを買うとき、彼は小銭を捜しながら500RPあるか? で、ここでも僕が払う。
Tetebatu は高原の避暑地。美しい自然のなかに湧水を利用したプール、小川のほとりに伝統的穀倉を改造したロッジのある日本的佇まい。残念ながら調査の参考になるような建物はない。ここにルクマンの親戚の経営する Wisma があって、池から獲ったばかりの魚を料理すると彼は自慢。もっとも、唐辛子と臭いタレに覆われて出てきた料理では新鮮もへったくれもない。そして、この4人分の食事代8500RPも僕の財布から出た。ここでも彼はわれわれをそっちのけで店主(DPR=国会議員らしい)と延々と話し込み、要するに今日一日、彼のために僕はつきあわされ、経済的負担を背負い込んでやった格好。何かとっても疲れる。帰宅後、ほとんど寝てすごす。

たまたま通りかかった消防車の後を追って火事の取材。20棟以上が燃えた現場はまだ熱い

子どもたちが素っ裸で泳いでいるのをしばし見物

伝統的穀倉を改造したロッジがある
11月 2日(日) 晴 Sembalun Lawang
昨日より体調悪い。身体だるく熱っぽい。疲れて眠い。
昨日とはうってかわって親切なルクマンさん一家に送られ、村で食べるようにと塩漬け卵、スルメイカなどを頂戴して出発。
ところが、市役所の隣家で車をUターンさせようとしたところで、道路脇の水路にかかっていた橋は落ちていてすでになく、ルクマン氏運転の Chevlolet はみごとに前輪をこの溝にはめ込んでしまった。10人ほどの応援をうけてようやくの思いで車を戻す。結局、市長一行は出発せず、ルクマンは僕をトラックの出発するターミナルへ。トラックが満杯とみるや、そのまま僕を乗せて Sembalun へ向かう。東海岸沿いに北上、Aikmel から Obelobel まで2時間半。道は舗装されて快適。Obelobel から道悪く、岩石と土埃の急な道。ルクマンの普通自動車ではこれをパスできず、彼が送ってくれたのもここまで。後から来たトラックに乗る。
トラックの荷台には山のような荷物と30人ちかい人で、道が悪いから荷台は時々大きく傾き倒れそうになる。この荷台の上に場所を確保するのが大変で、クルプックの袋、タバコの葉、野菜、セメント、米、鍋、バナナ、椰子の実、ベニヤ板、波板鉄板などのなかから手頃な物の上に体重をのせねばならない。この積載荷重をはるかに超えたトラックは急斜面をのぼりきれず、時々、乗客たちはすべて降ろされて坂道を歩かされる。昨日来、体調悪いため、これで頭痛と眩暈。ルクマン家からもらってきた卵はほとんど割れ、途中で捨てる。捨てたものを他の乗客が拾っていた。この Obelobel から Sembalun まで4時間を費やした。
ロンボック島でジャワのベチャ(輪タク)に代わって重要な交通手段はチドモ Cidomo という名の馬車である。牛車 Cikar の車台を馬 Dokar が曳き、これに車 Mobil のタイヤをはかせる。さらに、車のホーンとサイドミラー、アンテナ風の飾りをつければ完璧だ。チドモがシャンシャンと鈴の音を鳴り響かせてやってくると、どんな高貴な方々のお通りかと思わせる。けれど、案に反して、王侯貴族の代わりに乗っているのはパッサール(市場)へ行くオバチャンたちで、大きな野菜の束やアルミ鍋、籠などを山のようにのせて100RP程度の運賃で利用しているのが普通だ。


トラックの荷台には山のような荷物と30人ちかい人

王侯貴族の代わりに乗っているのは市場へ行くオバチャンたち
11月 3日(月) 快晴 Sembalun Lawang
Sembalun は周囲を山々に囲まれた豊かな高原地帯に開けた村だ。村というより町にちかい賑わいで市場のほか Bakso屋、飲み物屋などの屋台が道をのし歩く。人びとは Gudang Garam やら Jarum やらという箱入りのタバコをふつうに吸う。これだけでもずいぶん消費経済の発達した村だとわかる。
この時期、ニンニクの収穫期で近隣から労働者が集まるという。田から収穫したニンニクを大きな束ふたつに束ねて、これに棒を通して担いだ男たちがひっきりなしに往来している。家々の軒先といい、庭といい、所狭しとこのニンニク束が吊り下げられていて、村中ニンニクの香りに満ちている。東ロンボックの海岸地帯の干からびた不毛な土地から、艱難をこえてこの村に至ると、無何有郷を思わせる。豊かな自然と田畑の緑、清らかにあふれる水。
ここの村長は魚屋のお兄ちゃんのように愛想がよいが、口ばかりでとらえどころがない。何か訊ねると、打てば響くように答えが返る。親切でもある。けれども真心が感じられない。まるで観光客を扱うガイドのように。そつなく人をあしらうことに慣れたせいか、住居をみたいという僕の要求に、村はずれに伝統的な住居を移築した Mini Sembalun があるといって案内させた。これは Bule村と呼ばれ、数年前にこの土地の伝統住居がうしなわれるのを惜しんだ知事の肝いりで改築予定の古い家の移転をしたもの。現在、Bale が7棟、穀倉が5棟、Berugak が1棟建つ。住居は村のものと同様にすべて北面、正面に穀倉をもつ。建物は全体に粗雑な印象をあたえる。集落も死んだ町のようで、人が生活しているのに生活臭がない。なにより、住んでいる人間が建物の由来について何も知らないというのはどういうことか?
朝、いまだ体調悪く、なかなかベッドから起き上がれず。8時頃より Sembalun Bumbung の見物に出かける。Bumbung と Lawang はおなじ盆地の両端に位置し、ふたつの村のあいだに水田がひろがり、乾季のあいだ、ここでニンニクの栽培をする。この田園風景のなかを約20分歩く。空気が冷涼で、日本の高原の夏を思わせる。Bumbung も中心部は火事のため焼失し、多くの伝統家屋は近年の建設。Ama Raisam という自称92歳の大工の家を見る。戦前の建築で、よく整った住宅。土間先の柱にバリのものとおなじ彫刻があり、これは Masbage という村の大工が彫ったという。
午後より Lawang 内の古い建物12棟を見る。採図するにはどれも欠点あり。おもしろいのは、1961年の大火の後、古式に則って建設された伝統住居がいくつかあり、Ina Dawingi の家(1967)、Ama Satriadi の家(1962)など、現代風にくずれることなく、古式の範囲でかなりの完成度を示している。こうして完成された後で、この村の伝統住居はもはや建てられることがなかった。
夜、村長があらわれる。いろいろ質問があり、これに答えてくれるかと思いきや、村の仲間らとともにビリヤードとおはじきを併せたようなゲームに熱中しはじめる。こちらの質問にもうわの空、古い家を見つけたいと言っても、案内人をつけてくれるわけでもなく、何の助言もなし。

村というより町にちかい賑わい

ニンニクの収穫期には近隣から労働者が集まる


家々の軒先といい、庭といい、所狭しとニンニク束が吊り下げられている

伝統住居がうしなわれるのを惜しんだ知事の肝いりで出来たBule村
11月 4日(火) 晴 Sembalun Lawang
朝食前、村はずれの山に登る。焼き畑のせいか(?)木もなく、柴と灌木だけの山をよじ登る。村の全景がよくわかる。家並みはすべて北面し、奇麗に整っているのに、村の中心にあるモスクが北面しておらず、村の軸線と約45度ずれている。登るはよいが、降りるのは一苦労。道もなく、下を見ていると思わず足がすくむ。
山から見て古い家並みの奇麗に整った所が二箇所あり、ひとつは昨日家を見た一画、残ったもう一箇所で調査をはじめる。アマ・サエン(サエンの父)の家は、1920年代の建設。まとまりはよいが、細部で多少不明な点あり。架構に無理があるのか、家屋は東と南にいくらか傾いている。

村の中心にあるモスクだけが村の軸線とずれている
11月 5日(水) 快晴、一時雨 Sembalun Lawang
この村で一番頭にくるのは、夜、自分たちが遊ぶときだけはあかるいランプを灯すくせに、僕が仕事をしようとしても、ほのかに暗い石油ランプだけがたよりということだ。
朝、再度山に登る。村の全景撮影。雲なく、リンジャニ山快晴で全容をあらわし、村の背後にひかえる。帰宅後、アマ・サエン家の調査。ここの家主、家族はよく物をねだる。先日は下痢で熱があるといいながら腹痛のカプセルはないかときた。クロマイを4錠あたえると、今度は僕の使用していた三色ボールペンをためつすがめつ、私のこのペン(黒のボールペン)と交換しよう、と半分冗談半分本気。かと思うと調査用のメジャーを記念にくれ。Sesando(前面テラス)に寝転がっていた男は洋服をくれないか。これは聞こえぬふりをして通すと、今度は家主の息子がヘッドランプを売ってくれ(値段を知ったらそうは言うまい)。調査に必要だからと断ると、今度はきのう着ていたカメラ用のジャケットはどうした? タバコを2箱だけおいて帰る。
断腸料理。東ロンボックの食事は辛い。ルクマン家の食事も十分辛かったから多分一般的なことだろう。Sembalun に来て最初の食事はカレー汁のようなやたらに辛い煮込みと、それに唐辛子、トマト、ニンニク、玉葱をまぜたサンバル。この極辛料理もたまには乙なものだから全部たいらげる。辛い辛いカレーの口休めは唐辛子のはいったサンバルで、嫌がうえにもご飯の食がすすむ。しかし、1日3度、こうして胃のちぎれるような食事が毎日続くとなれば話は別だ。唐辛子のサンバルに漬かった茹で卵、唐辛子と煮込んだナス、唐辛子で炒めた小魚、唐辛子をまぶしたカリカリのうずら豆ご飯等々。こうして日に3度の食事の後には1日3度の下痢。これを待ってからでないと仕事がはじめられない。

雲なく、リンジャニ山快晴で全容をあらわし、村の背後にひかえる

実測図:家屋 Bale 平面
11月 6日(木) 晴 Sembalun Lawang
Permintaan (つづき)
きょうも例の調査家屋へ行く。下痢の薬はどうした?と元気のよい主人。俺はまだ下痢で気分がすぐれない。薬を持ってきたかというのだ。部材の名前を訊いていると、見たことのない男が現れて、いつのまにか主人にかわって熱心に説明してくれる。これはありがたい、と彼に質問してゆくうちに、突然この男の言うのに「私はタバコを買わねばならない」。タバコなら僕に言わずとも店へ行けばよいではないか、とは言わずに、後であげるから、と僕。この聞きとりが終わると、家の主人「もう済んだのか?私と妻の写真を撮ってくれないか?」
一日中、この家の周囲で図面採り。母屋、穀倉と配置図。

私と妻の写真を撮ってくれないか?
11月 7日(金) 晴のち曇 Sembalun Lawang
midan 夜這いの風習
結婚前の男は毎夜 midan に出かける。midan を夜這いと訳すのはちょっと語弊があって、女と語らいに行く。昔は、未婚女子は Bale 内の米を置くための小空間 Bale Dalam に寝床をもっていた。そこで、男は恋人の家を訪れると、家の外からこのベッドの位置に近づく。建物の壁は竹を編んだ網代で出来ていて、その一画に小さな穴が開いている。この穴を介して彼らは夜の更けるまで話をする。女の方は寝床にくるまっているからよいが、男は家の外に立っていなくてはならない。毎夜、夜中の1時2時までこうして語り合って帰るのは、男にとってはなかなかきつい。ここは標高1200mで夜は冷える。この midan によって女の心を射止めるまで、男はあちこちの家に midan を仕掛ける。かくて、相思相愛の相手を得たあかつきには互いの kain(布)を交換する。ところで、現在 Bale Dalam にこの midan のための寝床をもつ家屋は残っていない。Sembalun Bumbung では、昔からこうした寝床を Bale Dalam 内につくる慣習はなかったという。であるから、現在の midan も様変わりして、男は女の家の玄関(はないが)から正式に訪問する。そして、まことに行儀よく彼女の両親の面前でふたりは語りあかすことになる。アマ・サエンの息子の語るところによると、彼は恋人の家ではカマドの北側のベッド tinduan atas で横になり、彼女はこのベッドの下に寝るという。けれども、すべての男が彼のように女の家で泊まるのか、あるいは夜半におとなしく帰宅するかはわからない。そのアマ・サエンの息子君は、今夜は Sembalun Bumbung の女の所へ行くから一緒に来ないか、とさそってくれたけれども断った。
朝一番、この女の寝床をもつ家を探して二軒まわるが無し。Sembalun Bumbung まで出向くが、結局、ここではそういう風習はなかったということで問題にならず、すごすごと引き返す。村に戻ると(すでに2時)、ちょうどふたりの男が電信柱にのぼり電気の配線をしているところであった。こんな交通不便の村にも、あとひと月で電気がはいる。今後、観光地として開発される見通しという。来年には道路の建設も完了する。
昼食後、アマ・サエンの道楽息子をともなって森へ木の撮影。帰宅、集落配置図の仕上げ。夕刻、アマ・サエンの Bale の正面に穀倉をもつ ハジ・アサリに聞きとり。氏の家への道すがら、小さな男の子が案内を買って出る、というより、後をついてくる、と言った方がよい。聞きとりはわずか30分ほど。氏は父から相続したこの穀倉をふくめ3棟の穀倉(うち1棟は娘に与えた)とあたらしい家屋をもつ。さらに、息子の結婚後、彼本人が移住するための家屋を建てる準備をすすめている。穀倉のうち1棟は彼が6年前に購入したもので、当時ニンニク50kgを支払った。50,000RPという。また、のちに私の居候先の主人アマ・エリに訊いたところ、氏も自分たち夫婦の隠居用に土地1アールを250,000RPで今年購入したばかりだ。彼によると、建物家作だけの値段は穀倉が1棟5万RP、伝統形式の Bale が1棟2万5千RP程度(これは、いまどきこうした住居の買い手がいないためらしい)だという。土地は1アールで道沿いなら50万RP、道から離れていれば25万RP。
また、アマ・サエンは穀倉を所有しておらず、息子の結婚後(結婚後1~3ヶ月のあいだは老夫婦とともに暮らすのが普通)、彼の家の前の穀倉(ハジ・アサリが所有)の下に暮らす予定という。彼には自分たちの家を建てるだけの甲斐性がない。
この聞きとりのあいだ件の少年は私を待ち構えていたらしくて、暗闇から突然あらわれ、私の先導をして勝手に歩き出す。本通りまで出たところで彼にいちおう礼を述べると、少年の言うのに「マス、タバコありますか?」 先刻森へ案内してくれた道楽息子氏とその友人に残った3箱はあげてしまっていた。
夜は夜で居候先の主人があらわれ(彼は僕が道楽息子にタバコをやるのを伝え聞いたらしいのだが)「日本人はタバコを吸わないのか?私はタバコが好きだ」
ボク「吸う人は多いけれど僕は吸わないのです」
主人「キタムラ(キタムラタダシという人類学の先生が6年ほど前に約3ヶ月この村で調査をしたらしい。また彼の名は中部ロンボックの Rembitan でも話に出て、昨年2ヶ月間 Rembitan と Sade で調査をして帰ったという)はタバコを吸わなかったが、日本のタバコを持ってきた。だけど、あれはここではあわなかった」(→→喜多村正先生)
(沈黙)
何を言いたいかはわかるが、僕が黙って暗いランプの手元でノートをつけていると(なんとこの間、外では明るい石油ランプを灯して例のビリヤードに興じているのだ)、部屋に戻っていった。
Sembalun Bumbung の村長の父親(前村長)の話。
村の家屋はすべてLau(北)の方向を向く。インドネシア語に訳すと Lau は南で Daya は北だが、Sembalun ではこれが逆になる(何のことか不明。あるいは低地Sasak ではそうなのか?)。川の水はみんな Lau の方へ流れるし、死人の頭は Lau に向けて寝かせる。Lau は海の方向、祖先の方向のことか?
Sembalun Lawang の東の小山の上にマジャパイトの王族の墓というのがある。村の歴史によると、紀元14世紀頃、マジャパイトの王族があらわれ、村を支配したという。ロンボック北岸の Bayan では100%ジャワ・マジャパイトの出身者だというが、ここへはその一部が渡ってきたらしい。

実測図:家屋 Bale 梁行断面

実測図:家屋 Bale 桁行断面

実測図:家屋 Bale 詳細図

実測図:穀倉 Geleang

実測図:集落配置図

実測図:Sumbalum Bumbung

道楽息子をともなって森へ木の撮影

11月 8日(土) 晴 Pancor
Sembalun Lawangの村長の話
低地Sasak族の一般言語では Daya は北をさし、Lau が南をさす。ところが、Bayan, Sajang, Sembalun などのロンボック島北岸の村々ではこれが逆になる。要するに、Daya というのは山の方向で、Lau はそれに対して海の方向ということらしい。Sembalun では家屋は正面を海 Lau の方向へ、背面を山 Daya に向ける。いっぽう、死体の頭を北へ向けるというのはイスラムの風習で、頭を北にして寝かせ、顔を西へねじる。これはロンボック島の北でも南でも「北」で一致している。 Sasak
Sasak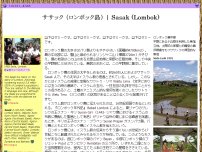
地縁的共同体 Gebuk と血縁的共同体 Waris (?) について
村はいくつかの地縁組織グブック Gebuk にわかれている。Gebuk は100戸程度の集合体で、相互扶助の基本的組織となる。これに対して、血縁的な組織 Waris は5つの主要な首長がいる。これは婚姻にかかわる。女は結婚によって元の Waris を離れ、男の Waris に移る。離別した場合をのぞいて、女は一生このあたらしい Waris のメンバーとなる。子供も当然、男の Waris に属する。また同一 Waris 内での結婚はより望ましいとされるが、多くは相異なる Waris で結婚するという。Waris にかんする詳しいことは不明。
結婚には婚資がいる。これは現在15,000RP(たかが知れた金額、忘れた)と決められていて負担は軽い。けれども、婚礼のため牛をすくなくとも3頭(1頭20万RP)供犠せねばならないから、この儀礼のための負担が重い。結婚前、男は女を家族のもとから盗み、彼の兄弟(友人)宅に隠す。3~7日ほど、女の両親は娘を捜しまわる。かくて、彼女が男と結婚したい意がわかると、Tobat(婚礼)となり、女は男の家で住む。Tobat では新郎新婦が椅子に腰掛けたまま、4人ずつの男によって担がれ、新婦を先にして道を練り歩く。その後、新婦(左)、新郎(右)に座り、水をかけられる。この時は、ニワトリ、山羊などを供犠する。この Tobat から数ヶ月~1年ほどして、祝祭が盛大に執り行われる。牛を殺し、Tobat の時と同様に担がれ、約2時間ほども道を練り歩く。
この Waris とくらべると、Gebuk の共同体的規制はいっそう強いものである。葬式を執り仕切るのは同一 Gebuk のメンバーである。死人がでると、Gebuk の成員による会議がもたれ、香典や儀式の援助いっさいを Gebuk がおこなう。死んだ者の家族は何もしなくてよい。また、屋根葺替の扶助をするのも Gebuk であって、肉親縁者といえども、他Gebuk に属す場合は扶助に参加する義務はない。これに対し、同じ Gebuk の構成員はたとえ自分の家がすでに鉄板葺きに変えられ、他の人びとの扶助が不要な場合でも、かならず参加せねばならない。材料のチガヤは Desa Sajan(Sembalunの北方、山の下の村)から買う。これは馬一頭分(4抱えで1pondonと呼ぶ)2500RPでふつうの家では15pondonが用意される。Gebukの成員は家根替の前夜、件の家へあつまり、ここで竹 penggapit でチガヤを縛る作業をおこなう。これにはコーヒー、タバコなどを供するだけでよい。屋根葺替の当日は食事がふるまわれる。他の Gebuk に属する穀倉を所有している場合、この穀倉の屋根を替えるのは当主の所属する Gebuk の人員で、彼らを引き連れて他の Gebuk の土地で屋根替作業をおこなうわけである。
Pancor へ帰る道すがらの物語。
町へ降りるトラックが朝8時に出るというので、荷支度をすっかり整えて僕はテラスに腰をおろしていた。8時、まだ早いから多少遅れるのだろう。9時、そろそろかな。10時、まだ来ない。11時、ようやくあらわれたトラックは Sembalun Bumbung へ向かってしまった。12時、Bumbung から引き返してきたトラックは多少の荷物と若干の乗員を荷台に載せていた。運転席には派手なピンクの洋服、小さな皮のハンドバッグ、ゴム草履という、およそこの村に似つかわしくないいでたちの女性と若い男がすでに乗っている。荷台にまわって座をしめる。と、みるみるうち横の市場から大きな米俵ほどのニンニク袋をかかえた男たちがあらわれて、、、

町へ降りるトラックの荷台。山のように積まれたニンニクの袋の上に雲霞のように群がる乗客。悪路の山道をくだり4度のパンク。しまいにはスペアタイヤも底をつき、通りかかるトラックをひたすら待ちわびる一日

11月10日(月) 快快晴 Alas
食事前、5時半に時間厳守でベモが迎えに来たのには驚く。しかも、このベモが道すがら鉄片を踏んづけてパンクしたのにはなおさら驚く。よほど悪運。
ロンボック港でまた一悶着。おとなしくチケット売り場にならんでいる我々の横を5枚、10枚とまとめ買いするバスの車掌(バスのチケットと一緒に買うようにとの知事通達があったと聞く)が割り込み、個人客は立ちつくしているのみ。これはどうしたことだと文句を言うと、この立ちならぶ乗客のなかから「サントリはここに並ぶしかないよ」と自嘲的な答えが返ってきた。それでなおも並んでいると、やがてそのまま切符が売り切れてしまった。これで発火した。係員に食ってかかる。「私は知らないよ。無い物はないし、上からのお達しだから」と軽くあしらわれ、仕方なく警察に頼み込む。こういうところ、外人(日本人)というと効果覿面で、不可能が可能になるから不思議だ。警官氏は、私がなんとかしようということになって、書類をつくり、これに署長のサインをもらうだけで、この書類が水戸黄門の印籠に早変わりしてしまう。改札はフリーパス。警官氏に値段を聞くと、2000RPというので、彼の懐におさまるであろう料金を支払った。正規の運賃は2500RP。
約3時間、ロンボック海峡とくらべ、いたっておだやかな航海でスンバワ島の Alas 着。暑い。とにかく暑い。以前のアンボンを思わせる暑さで、アンボンではこうした暑さが続いたあと雨期にはいったから要注意。
ここから飲まず食わずで忙しい。港から馬車で市役所へ。市長に面会し、荷物を預けたあと、バスで Sumbawa Besar へ。約1.5時間。Bappeda に報告して書類を書いてもらうかたわら、PdK を訪れ ITS の Alas調査資料を見せてもらうように頼む。出てきた PdK の所長はアイスキャンデーを食べながら、担当のムスタキムに訊かねばわからないと。ここでも段取り官僚主義の御託を教条的に繰り返すばかりで、腹をたてて事務所を後にする。ムスタキムの家を訪れ、何故か痩せこけた氏と再会していくつか情報を得たのち、とんぼ返りで Alas へ。市長自宅を訪れ、書類の約束をし、Losmen Anda に宿をとる。
そのままちかくの村の見学。あたらしい建物の混在するなかに、よく見ると穀倉が混在。しかし、期待したほどのことはないか。ここの市長さんは親切でよい。
夜、ロスメンで同宿のマタラム在住の東ジャワ人、片目のスブロトという得体の知れない男と村唯一の映画を見に行く。400RP払ってはいると、ビニール張りの簡易椅子がずらりと並び、結構盛況だ。テレビはないし、毎日出し物が変わるから、テレビを見る気分でちょっとやってくる若者が多いのだろう。天井で大きな扇風機が懐かしげに回転している。洋画で、アフリカか中東の海岸でたわいなく遊んでいた白人の男女たちが、いつのまにか戦略的に重要な事情のなかに巻き込まれ、残虐なだけの軍隊にとらえられ、意味もなく監禁されていたが、最後はこの軍隊を全滅させて脱出に成功するというもの。字幕のインドネシア語が見えず、音がよどんで英語の発音が聞こえないというのもさることながら、意味もなく人を殺し、白人に暴行をくわえる有色人の兵士、どこか旧植民地の都市で豪壮な邸宅住まいをしているこれら白人たちの家族、こんな設定で彼らがまんまと兵隊たちを皆殺しにして脱出しても感動も共感もわかない。理不尽なだけの話だ。片目氏はいい映画だと感心しておったが。

Sumbawa Besarにある Dalam Roka 宮殿

新宮殿
11月11日(火) 快晴、夕立 Alas
午前中 Desa Mapinrea へ行く。小一時間ほどの距離をベモで走り、着いた村はふつうの農村で古い穀倉はない。早々に Alas に引き返す。
朝、市役所で会った男(Marenteの出身)の話で、Desa Marente に三種の穀倉がある。Alang Be 壁をもたない古い形式、Alang Lumbung、Alang Kandawali と言うことで、Alas に戻るや馬車をチャーターして Marente へ。とにかく暑い。Marente から川を挟んだ隣の Dusun Besa Beru に Alang Be が幾棟も建つ。ただし、軸組より上みなあたらしく、出来が悪い。
とりあえず一棟を選んで図面採り、聞きとり。折から激しい夕立で、ノートとシャープペンを手にしたまま転び、泥まみれとなる。夕方帰ろうとすると、先刻の雨で川が増水、腿まで水につかり、激しい水流にあやうく押し流されそうになりながら、死ぬ思いで渡り終えた。ここ数日、悪運続き。

川を挟んだ隣村に屋根倉 Alang Be が幾棟も建つ

実測図:Desa Marente 穀倉 Alang Be
11月12日(水) 晴、夕立 Alas
Desa Dalam、Desa Kalimago、Desa Julanalas をまわる。建物探すが残りすくない。Alas をえらんだのがまずかった。ITS(アイルランガ大学?)の調査したという穀倉、Desa Julanalas の貴族L.M.Tahir 所有とわかり会いに行くが、2年前すでに取り壊したということで今はない。残っている柱はチークで径30cmもあるものばかり。彼の住宅は床下高さ5m、間口9m×27mという巨大なものだったが、彼の代に柱を切ってしまって今は床下50cm程度。入口部分はジャワのクラトン風に石敷に改造。屋根は鉄板。
こうやって右へ左へと人に会っているうちにまた一日が終わってしまった。Desa Kalimago で大工道具の図面採り。あすは Desa Dalam の穀倉 Kandawali形式と Desa Kalimago の穀倉 Be形式、および住居 Bale の図面採り。日中暑くて、図面を採っているとつぎからつぎへと汗が吹き出す。イライラして図面に集中できず、気を抜いてしまう。この暑さでは調査意欲も減退。

床下の高さ5mもあった建物は柱を切ってしまって今は床下50cm程度

Kalimagoでは割礼式に遭遇

・・・・(;_;)

実測図:Desa Kalimago 大工道具

実測図:Desa Kalimago 大工道具
11月13日(木) 晴、夕立 Alas
Desa Dalam と Desa Kalimago の穀倉の図面を採る。軸組はどちらもしっかりしているのに小屋裏がひどい。手抜きの改造。他の穀倉を比較して復原を試みる必要ある。朝食抜きで2時過ぎまではたらき、途中、先日 Tahir氏と約束の模型を見にPdKへ行く。模型はデコラ板に窓を刳り抜くといった作りのお粗末な Istana のコピー。とりあえず写真におさめる。食事後、Kalimago の穀倉図面採り。これも小屋裏の改造激しく、途中で目が回って仕方なかった。屋根裏はサウナ風呂のように蒸し暑い。何もない小屋裏の図面を描くのにずいぶん時間をくう。
この地域で壁のある穀倉 Alang Kandawali が造られはじめるのは戦後のことらしい。1980年以降になると、米の品種改良のため、穀倉に穂刈りした米を仕舞うことができなくなって、穀倉は空のまま使われなくなる。
イネの品種
1980年以前のイネは収穫までに5ヶ月かかった。穂刈りして穀倉に納めることで4~5年は保存可能
mayan dene … 短粒。粒は丸め
dendak … 長粒
anak loas … 赤米
lege bokar … 糯米
lege mandi … 糯米。籾は黒い
lege pisak … 糯の黒米
1980年以降は新品種のIR36に変わる。長粒種で3ヶ月で収穫可能。収穫後すぐに脱穀して米袋(土のう袋のようなポリプロピレン紐を編んだ袋)にいれ、家屋の床下で保管する。1年程度はもつ

小壁のある穀倉 Alang Kandawali


実測図:Desa Dalam 穀倉 Alang Kandawali 梁行断面

実測図:Desa Dalam 穀倉 Alang Kandawali 桁行断面

Alas にあったという貴族住宅の模型

壁のない穀倉 Alang Be

実測図:Desa Kalimago 穀倉 Alang Be
11月14日(金) 晴、夕立 Alas
わざわざ早起きして手紙を書いたのに、今日は祝日で郵便局はやすみ。昨日知り合ったモハマッド A という親切なおじさんの穀倉の図面を採る。Alang Be、ようやく満足のゆく穀倉に出会った。昼に仕事のキリがついたため珍しく昼食を食べ、昼休みまでとる。午後2時半より再開。Kalimago の村長を訪れ、Kalimago にのこる成り上がり平民のやたらと高い高床住居の図面採り。屋根は瓦に変更、小屋裏は見るに忍びなく、軸組のみの図面。未亡人がひとりで住んでいるため室内の機能も不明。ほとんど空き家同然。この家も長くない。写真、図面、聞きとり3時間で切りあげる。
村長に Jambu とオレンジをもらった。この村長はかつて日本に行ったことがあり、たいへん律儀に親切に面倒を見てくれる。

ようやく満足のゆく穀倉に出会う

実測図:Desa Juranalas 穀倉 Alang Be

成り上がり平民?の立派な高床住居

実測図:Desa Kalimago 家屋 Bale 平面・梁行断面

実測図:Desa Kalimago 家屋 Bale 桁行断面
11月15日(土) 晴 Sumbawa Besar
午前中に Marente で木の採集。モハマッド A 氏の紹介で村の小学校校長が手助けしてくれる。村人ひとりに案内され、山林のなかをかれこれ4時間ちかく歩く。朝食抜きで(軽い気持ちで)出てきたために非常に疲れる。件の村長氏は手ぶらで鼻歌まじりなのに、こっちは重いカメラバックと三脚をかかえて息も荒い。彼は木の場所を知っているわけではなくて、森の中を歩きながら道沿いの木を物色する。彼が見つけると、僕が葉っぱを取り、これを写真におさめ、野帳に貼り付けるという案配だ。まるで昆虫採集の要領。
午後1時 Marente にもどり、そのまま馬車で Alas へ帰る。荷物をまとめ挨拶を済ませて出発。Kalimago の村長の案内でバスターミナルで待つも、午後3時をまわっているとあってバスがなく、トラックを探す。村長さんは、腹を突き出し律儀にも最後のバスがあらわれ、これに僕が乗り込むまで待っていてくれた。
Sumbawa Besar 到着はすでに暗くなってから。宿をとり、ムスタキムと会う。そのまま中華料理屋で満腹するまで食べる。ビールのせいで頭痛と眩暈。そのまま眠る。
11月16日(日) 晴・曇 Semongkat
7時半スタンバイ。8時にはターミナルで Batulante 行きのベモを待つ。ベモがターミナルを出発したのは10時。長時間待ったおかげでVIP用の助手席に座らせてくれたのはよいけれど、背もたれは完全に中身だけになっており、鉄の金具がベモの振動のたびに背中にあたって痛い。スンバワ島の車はどの島のベモより内装の傷みがひどい。惨憺たるありさま。
Semongkat は山あいの小さな町。古い家ありそうもなく、Batuduran というベモの終点まで行く。ところが、この村は戦後もとの場所から移動してきたといい、古い村に特有のあのニオイがない。古い様式をふんだ家もなく、要は粗末な家が多い。時間を無駄にするのも惜しく、木の採集をしただけで Batuduran を後にする。1日1回のベモは先刻乗ってきたばかりだから他に車はない。約20kgの荷物をかかえて歩く。Semongkat まで約1時間40分。Semongkat にあった古い家は数年前に焼失して今はない。帰りのベモもない。ここで足止めになった。
Dusun Batuduran の 村長はかつて兵補だった。日本人の兵隊のほかに彼のように現地人で兵補になった者があちこちから来ていた。日本軍は大きなトラック何台もの荷物をこの村に運びこんだ。日本兵は衣服、時計などと食料、タバコを交換した。彼はよくタバコの葉を持って遊びに行った。ところが、ある日、日本兵は跡形もなく姿を消した。何台ものトラックで運びこんだ物資もろとも忽然と消えた。彼は仲間の兵補たちと相談した。仲間たちもどうしてよいかわからない。それで思い思いに自分の村へ帰ったという。

VIP用の助手席に座らせてくれた

ベモの終点まで行くが古い村に特有のあのニオイがない
11月17日(月) 晴・曇・雨 Sumbawa Besar
7時47分、Semongkat に運よくあらわれたベモに乗る。Sembawa Besar 到着後、その足で PdK のムスタキム氏宅訪れ、荷物を預け、役所まで氏を追いかける。Batulante の状況を報告し、家屋の図面が採れなかった旨話すと、そのままこの日一日、彼は僕のために家を探し、採図のあいだ待ち、家に泊めてくれたうえ、大工を家に招いて聞きとりのできるように手配までしてくれた。感謝感激。
旧スルタンの補佐をした首相の家。1804年の建設で、品のよい未亡人と子どもが住む。建物は Istana に非常によく似るが棟はひとつ。入口に向かって右側に傾斜した階段がつく。床高は約5m、全体の傾向として、ふるい豪壮な家屋は高い床高と太い柱によって象徴される。現在の傾向として、この高い床高を嫌い、柱を切る例がある。この建物の写真撮影中に天井裏を突き破り、あわや落下というところで助かった。材は表面的には堅牢に見えて、内部の腐っているものが多い。この文化財に大きな穴を残して暇を乞う。建物大きく、妻部の変更が激しいため、ひとりで数時間では採寸できない。ITS が調査済ときく。
この後、町中をオートバイで走り回り、一軒の粗末な竹葺き家屋を見つけて採図。建物規模小さく、材の仕上げも悪い。けれども軒先を支える棟肘木があり、妻側の変更もない。構造としてはよくまとまっている。約3時間。
この日の圧巻は、夜マスタキムの家でおこなわれた大工アハマッド(56歳)への聞きとりで、建物建設について念入り丁寧な説明を受けた。6時半より10時半まで。
大工 Akhamad 氏の話
Ⅰ 木材の伐採から村への運搬まで

山で木をさがすには、最低7人ほどの人間が、一週間近く山に泊まりながら木を切り、荒仕上げをおこなう。木の伐採を開始する日の前日、棟梁と sanro(いわゆる dukun 祈祷師、一般に精神的な病について悪魔払いの方法、吉日吉時や方角の選び方、儀礼の方法などを心得た者をいう。家屋の建設にあたって、多くの場合、大工の棟梁は自らこれを学び sanro を兼ねるが、別人のこともある)は tiang-guru(男柱 salaki と女柱 sawai の2本ある。貴族は jati チークを使った。一般人なら kesami、jeliti などがすぐれる)となるべき木のまわりに黄飯をまく。一夜明けた翌日、吉時を選び、この木を倒す。続いて他の木を切りはじめ、約一週間ですべての材の荒仕上げが終わると、水牛で牽引して、これらの材を村まで運ぶ。
Alas のモハマッドA氏によれば、村の入口で tiang-guru に黄飯をまく。
Ⅱ 材の加工から仮組まで
村に運んだ木材は2,3日後、形を整え、Nata Ramai (Pahat Ramai 日本の釿始め) を迎える。Nata Ramai のおこなわれる日には近隣から多くの大工が呼ばれる。

① 朝、まず sanro が吉時を選び棟梁の手で tiang-guru-salaki に bongkang (枘穴) をあける。この時、pat (鑿) には枝のない鉄部だけのものを使う。これを皮切りに、他の大工たちもそれぞれに受け持った柱に bongkang をあける。続けて柱に payompong (枘) をつくる。
② tiang (柱) に続き、pangkarat (梁 lanong がすぐれる) に柱頭枘のための枘穴をあける。pangkarat-guru の枘穴は棟梁が受けもつ。

③ penisi (軒桁) は長材の場合柱の上で継ぐ。この場合、6本とも(桁行3間あり軒桁は2列ある) suki (込栓) 用の穴2箇所づつをあける。penisi の接合は木の元口が入口側に来るように配し、末口が元口の上にのる。
④ panumuk (桁先の受材) : penisi と tolang bangkang (背骨の意、棟束下の桁) を受けるために枘穴3箇所。

⑤ rangke (貫):rangke-pene (梁行の短い貫) 4本、rangke-belo (桁行の長い貫) は長さ2間程度で柱の中で接合する。手前側が左になるように。
⑥ 小屋組:tunyang (棟束) 4本、pajolo (合掌) 8本(桁上では仕口をつくらず)、bungis (棟木) 、以上の材はすべて lanong がすぐれる。tolang-bangkang は2、3本を継ぐことが多い。丸い枘穴をあけて棟束を受ける。apit-saka (外壁の支え、柱の外周をまわる構造材) 長材がなければ2-3本を継ぐ。ima (竹の斜材) は叩いてつぶし、折り曲げる。以上、家屋が大きな場合や経済的理由で一度に組み立てられない場合、Senyata Bola といって小屋組を地上で一時的に仮組みしておくことがおこなわれる。
Ⅲ 建て方
① 石の上に pangkarat (梁) を置き、柱を pangkarat の上にならべる。
② 棟梁が「ろ」列(正面から2列目)の柱を pangkarat の枘穴に通す。2→3→1→4列の順。
③ 棟梁が rengke (貫) の先端を押さえながらそろそろと柱に通す。
④ baji (楔) をいれて rangke を締める。2→3→1→4列の順。

⑤ こうして「ろ」列が終わると、これにならって「は」「い」「に」の順に他に取りかかる。
⑥ 軸組を引き起こす。まず baret (水牛の皮を編んだ紐) を pangkarat 中央に巻く。polas (air、tereng から作った竹紐) を pangkarat 両端にめぐらし、この紐の先端に持ち手として竹筒を括り付ける。竹筒を回転させて紐を捩りしっかりと固定。
⑦ 以上のロープ(polas を括り付けた竹筒と barat)の先端を各1人が押さえ(全部で6人)、さらに柱1本につき2~3人づつかかって軸組全体を持ち上げる。
⑧ 同様にして、「は」「い」「に」の順に立て起こし、桁行き方向にも rangke をいれる。2→3→1→4列の順。

⑨ tolang bangkang (中央の桁) と前後の penisi (軒桁) を順に置いて suki (込栓) で締める。
⑩ panumuk (桁先を受ける横木) を前後の順で固定。
⑪ 以上の工程が終わると、棟梁が全体のバランスをみる。
⑫ 柱の下に礎石をいれる。2→3→1→4列、「ろ」「は」「い」「に」の順。このとき、rengke に竹筒をあてがい、碓 nisung などを地上に置いて、梃子の要領で柱を持ち上げ石を置く。

⑬ 小屋組を載せる。tunyang (棟束) → bungis (棟木) → pajolo (合掌) → の順。部材の結縛に昔は semongkat を使った。いまは uwe ロタン。
⑭ 屋根瓦 santek の作成は、約100本の竹を節の真上で切断し、それぞれ4等分する。
tiang-guru に対する儀礼柱頭を約1m角の白布でくるみ糸で縛る。さらに、檳榔樹の花果 mayang 一房、ココ椰子の実、バナナ一房を結びつける。柱の下には okong (kamukat を編んでつくった皿状の籠) を置き、その上に白布でくるんだ金を kain cindai (絹の色布) で包んで置く。tiang-guru はこの上に乗る。
Ⅳ 入居式
① Ntek Bale (入居) :新築家屋の試し居住。sanro に先導され家族の者たちが猫、米壺、水甕 namo、シリー・ピナンの箱、パンダナスのマット、枕をもって家屋を訪れる。まず、建物の周囲を左回りに3回まわる。階段下で女から順に水甕の水で足を洗い、家屋にはいって中の間に座る。tiang-guru から順に柱に水甕の水をかける。10~20分ほど座って話をし、持ち運んだ物は tiang-guru の傍に置いて帰る。
② Rapina (転居) :3、4日後、吉日を選んで移住する。
Ⅴ 完成祝
Sikir Bale (家屋の安全祈願):当日もしくは1週間のあいだに客を呼び山羊を屠殺してふるまう。
Alas のモハマッドA氏によると、完成後40日して Teras Bale というすべての楔を打ち直す儀式がおこなわれる。

1804年建設の貴族住宅 Bala Datu Ranga

写真撮影中に文化財の天井裏を突き破りあわや落下

一軒の粗末な竹葺き家屋を見つけて採図

実測図:Sumbawa Besar 家屋 Bale

柱 tiang - 梁 pangkarat - 軒桁 penisi - 合掌 pajolo

柱外周をめぐる apit-saka

小屋組

棟木 bungis と合掌 pajolo

竹瓦 santek

実測図:Desa Kalimago 家屋 Bale 平面・梁行断面
11月18日(火) 晴 Dompu
6時半、ムスタキム氏宅発。氏の奥さんはバタック人、氏とはティモール島で出会い結婚したという。無口で無愛想、暗闇の中から人を観察しているような気配がある。その彼女が早起きしてわざわざお弁当を用意してくれたので驚いた。Bima行きのバスは7時発という予定通りに出発。これも例のないこと。ムスタキム氏によると、彼の役所は全員7時半に出勤する。これもインドネシアでは異例のことで、スンバワ人の自主性と自由の気風か。ふるくからスルタンを中心に栄えた文化伝統ゆえか。ジャワに色目を使うことがない。
道はすでに全面舗装され快調。途中で多くの乗客が乗り、結局通路は荷物と人の山になってしまったけれど。中央線のラッシュを考えると、だからインドネシアが非人道的な国家で、日本がそうでないとは言えない。
Dompu 着はかれこれ1時半。マタラムのヨン(イワン・タナヤ)の兄の店へ居候。Toko Taufik は Dompu では最大規模の店。ヨンの兄弟4人が Dompu で店を構える。中国人の団結は強い。兄弟12人(うち2人死亡)のほとんどが各地で店をもつ。核分裂のように経済力で繁殖する。彼らの父は福建省の人。Dompu の Huu という村で農民をしていた。戦争中、日本軍に協力して、米、酒、お菓子などを供出したという。あるとき、米を提供するように言われ、400(キロ?)あった米を200供出したところ、アラブ人の商人がこれを憲兵隊に密告した。父は Dompu の憲兵隊に出頭するよう言われた。彼は Dompu へ直接行かず、途中、知り合いの隊長を訪ね、事を告げた。アラブ人は逆に憲兵隊に逮捕された。3日間、頭だけ出して土に埋められた。このアラブ人はまだ現存して、Dompu で店を開いている。Toko Taufik では今も米から酒を自家製造している。日本時代の遺産でバリのブレムに似た味。
Dompu 到着後、すぐ PdK へ。民家の情報を得に文化担当の マカラウ という男を訪ねたところ、彼はさっそく自分の一存ではいかぬと所長に引き合わされ、この所長は surat (手紙)はあるか?と官僚主義丸出しだ。知識をもとめるのに surat は必要か?PdKは知識を司る官庁で、知識は自由であるべきものである。私は情報を得るためにわざわざここを訪れたのであり、もし許可証がなければ情報はいただけないのか……としばらくゴネる。所長はそんなことはない、と口では言いながら、僕が仕方なしに書類を見せるとみるからに安心した態で許可をあたえてくれた。マカラウ氏の推薦で Huu(ヨンの父親の出身地)の調査をすることになる。
午後、所在なくすごす。夜、末弟で腕に出来の悪い女の顔の刺青をしたイカレポンチのアンちゃん風、陳循強と連れだって映画館へ。「山東から来た男」という題の香港映画。字幕のインドネシア語はもちろん見えないし、台詞はなんと中国語のままだから細かいことはわからない。要するにカンフーに秀でた男が町の大ボス相手に頭角をあらわし、最後はこの大ボス一味の陰謀にかかって大団円。群がる男どもをバッタバッタと叩き殺し、自らも深手を負ってあわや絶命、というところでボスを倒し、自らも死ぬ。ふるき時代の日本映画そのものの目鼻立ちをした配役たち。物言いや場末の雰囲気まで、フランキー堺や宝田明、モスラなどが出てきても不思議じゃない。
11月19日(水) 晴 Huu
Dompu でバスの切符を買い、荷物を屋根の荷台に載せたのが10時。このバスが Dompu を発したのはなんと12時過ぎ。Rasa Bou の Huu市長を訪ねる。この市長は、後で知ったことだが、若干33歳。伝統から何を学ぶかという議論を繰り広げる。結局、村人たちがふるい家を捨て、あたらしい石の家に住むのは、ほかに現代住宅の例がないからだということになる。ここでは、木造=ふるい家、石造=あたらしい現代住宅。したがって、近代化のすすんだ日本では当然石の家ということになり、木造の高床住居であるということは信じがたいわけだ。それで、村人たちのうちで建物を改築するだけの経済力をもった者は、この市長の家にならって、コンクリート造、瓦屋根またはセン(波板鉄板)葺きの家を建てる。彼らは自分たちの家文化を自分たちの能力で変えていこうというだけのエネルギーをうしなっている。
Desa Huu は旧村落から二度にわたって移転してつくられた村だ。建物は、だからこの二度目の移転に際してすべてアレンジしなおされ、ふるい伝統を残すものではない。建築そのものは当初のままのふるいものであるけれども。
建物は柱6本、9本、12本のいずれかで、ここでは妻を東西に向け、階段はやや北よりにつくようにすべて配置される。かつて家屋平側にあった付属屋は後方に移され、これにともなって扉、窓が全面的に配置換えされた。構造形式はドンゴのものに似る。穀倉は壁のある形式。
夕食はモヤシの唐辛子和え小皿ひとつとご飯だけ。海がちかいくせに住人は怠け者というのは本当。

Huuの村落

建物はみな村の移転に際して再構成されている

実測図:大工道具

海がちかいくせに住人は怠け者??
11月20日(木) 晴 Huu
朝のトイレは海のなか。海に浮かんだ排泄物は波間をただよい、波で押し流されては、また押し返されてくる。これをうまくかわしながら座り続けるにはなかなか要領がいる。朝食は煎り小魚の小皿1とご飯。
家屋は原型をとどめるものなく、集落移転後の形式のなかから屋根妻面の破風飾りの残ったものをえらんで採寸。これとて屋根はすでに瓦に変わっているから、どこまで復原できるかはわからない。1986年の典型的な家屋ということ。
イスラムの式典があるらしく、昼には市長ほか要人あらわれ、魚のスープとご飯。疲労激しく、調査は夕方までかかってこの一棟が終わらずもちこし。夜は小海老、小魚など海で漁ったものの煮こみ小皿1で、これはいける。多量に食べてすぐに寝る。例の式典は夜遅くまでかまびすしく続いていた。

実測図:家屋 Uma 平面

実測図:家屋 Uma 梁行断面
11月21日(金) 晴 Dompu
夜半より右脇腹の激痛。右肩まで痛みがはしり、肝臓障害だとしたら、もうバリへもどるしかないと考えながら寝返りをうちつづけた。
朝、ともかく採図の残りだけは終わらせておこうと苦痛をおさえて出発。脂汗が吹き出し、くしゃみをするのも痛くておもわず息をのむ。作業をはじめるとやや痛みがおさまり、午前中で終了。そのまま古い形式の穀倉をさがして、これは2時間ちかくで片付ける。
建物部材名称の聞き取りができず、体調はわるいし、村長は逃げてばかりでアテにならない。というわけで、村長の家族に当たり散らし、荷物をまとめて帰り支度をし、バスを待てどもバスは来ず。たまたま通りかかった男をつかまえて、部材名の聞き取りをしているところへようやく村長氏もあらわれ、調査を終える。
夕刻、ベンフル(馬車)をつかまえ、隣村の Daha へ。Daha からならたくさんベモがある、という話は嘘で、ここでも待てど暮らせどベモは来ず、日は暮れる。運良くあらわれたトラックに乗って、Dompu へと帰る。トラックのボスはこんな地方にしてはやたらと最新の政治問題にくわしい中国人で、Huu から木材を積み、Dompu の学校を建設する仕事を請け負っているという話。
帰宅後、タン・スンミン(陳循明)家で長々と話し、体調が悪いのになかなか床にはいれず。しんどい。
日本の薬(正露丸)の大瓶を戦後日本人が家に残していった。家族の者はこれを Obat Jepang(日本の薬)と呼んで、つい10年ほど前まで愛用していたという。この薬はちょうど tai kambing(ヤギの糞)だというが、まったく瓜二つといってよい。大きさはちがうが。

実測図:家屋 Uma 桁行断面

実測図:家屋 Uma 詳細

実測図:穀倉 Jompa
11月22日(土) 晴のち曇 Bima
タンの案内でビマ Bima着。Bappeda(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 州開発計画局)に書類を出しに行く。市長あての書類を書いてもらうよう頼むと、このタイプを請け負った男はどうやら書式もわからずにタイプを打ちはじめたらしい。他県の書類を見せても耳をかさず。30分以上待った挙げ句、出来上がった書類は所長の目にかなわず作り直しとなった。
そこで警察へ報告に行くと、ここでもご丁寧に書類にハンコを押してくれてありがた迷惑なこと。Bappeda にもどる。
待ち構えていたのは調査担当の係官で、彼は自分で作ったという Donggo と Bima の歴史にかんするタイプ本(約50ページ)を1万RPで買わないか。これは実証的な歴史の話ではなく、彼自身の民間伝承の聞き取りと一般的な史実を綴ったもので、それなりに役に立つ本ではある。けれども言い値が高すぎる。この本を断ると、今度は administration 料を僕の書類をタイプした阿呆男に払えというのだ。administration とは何だと訊ねると、わずか1000RPだからとなだめるように言う。
馬鹿野郎、ジョーダン言っちゃいけねえぜ。おまえらは公務員であって、いまは公務の時間であって、これは国の仕事じゃねえか。いままであっちこっちまわってきたけれど、金を要求されたのはここがはじめてだぜ(じつはCianjurの役所で一度)、と、このような調子で吐き捨てるように言い、渡された書類をひったくって帰ってきた。そのままホテルで横になる。右脇腹のほかに左の脇腹までが痛い。といって、どこも具合悪いわけではなし、痛みのおさまってくれるのを大人しく寝て待つばかり。
夕食を食べていると、イリアン人のような黒い肌の肩幅の広い巨大な女性と、中国系のインテリ風の眼鏡ヤサ男の二人連れに声をかけられた。彼らはジャカルタで広告代理店の仕事をしている。女性はそのオーガナイザー、男の方はカメラマンで Merpatiエアラインの仕事を請け負い、ロンボック、スンバワと土地の文化の広告のため取材をしてきた。あすコモド島へドラゴンの取材に行くけれども、われわれはふたりだけで、すでに船はチャーターしたし、島のロッジも予約してある。であるから、あなたは何も払う必要がないからヒマだったら一緒に行かないか?という申し出なのである。
体調はわるいけれども、こういうチャンスを逃す手はない。即座に同意した。

アユはチャーターしたのが大型快速クルーザーだと思っていたらしく、こんなことを知ったらジャカルタの両親はけっして私を旅行に出さないだろう。。。
11月23日(日) 晴のち曇 Komodo
6時、チャーターした車でホテル発。ここらへん面倒なことをいっさい気にしなくてよいのはありがたい。スンバワ東端の港Sapeまで約1時間半。Sapeよりモーター付き帆船に乗る。
ジャカルタの金持ちの娘アユはチャーターしたのが大型快速クルーザーだと思っていたらしく(そんなものがこの東インドネシアにあるわけはない)、船に乗り込むや、座るべき場所もないことに気落ちして貨物室の屋根に腰をおろし、「こんなことを知ったらジャカルタの両親はけっして私を旅行に出さないだろう」と、いかつい体格に似合わないことをおっしゃっている。この船には船室というものがなく、船室の形跡はあるのだが床をはっていない。われわれはこの船室の屋根上に干魚のようになってころがっていた。
約6時間でコモド島着。マルク州の時とちがって、モーター船だから風はなくとも時間内に着く。途中で釣り上げたカツオを新鮮な刺身にして食べるかとおもったら、夕食に出てきたのは、これ以上不可能なほどカリカリに揚げた切り身で喉もとおらず、新鮮もへちまもない。

新鮮な刺身にして食べるかとおもったら、これ以上不可能なほどカリカリに揚げた切り身で喉もとおらず
11月24日(月) 晴 Bima
コモドに食べられるはずの健気な生け贄の子ヤギは、先発したわれわれを嬉々とした足取りで追い抜いていった。10分後には喉元を一突きされ、40分後には骨もなにも跡形もなく食べられてしまうとも知らず。コモドの動きは緩慢なうすのろバカだ、とおもうと、時々すばらしい足取りで逃げる。休日のつもりで来たけれどやけに疲れた。
帰りの船ではほとんどひっくり返って寝ていた。Sangean島の火山は煙をあげている。海上を雨前線がはしり、雨雲の連なりが遠くにつづく。この雨雲はやがて雨を降りつくしたらしく、あとに虹がかがやいていた。
ガイドの男は帰りの船でも巨大なバラクーダを釣り上げた。写真家のルーカスは日に焼けた真っ赤な顔をしてせわしなく動き回っている。アユは煮炊き場の床で航海中ずっと伏せっていた。

生け贄の子ヤギは骨もなにも跡形もなく食べられてしまう

コモドの動きは緩慢なうすのろバカだ、とおもうと、時々すばらしい足取りで逃げる
11月25日(火) 晴のち激しいスコール、のち曇 Bima
ルーカスは少女チックにコモド島の海岸でひろった小石に日付と3人の名前を書いておいていった。彼らのつぎの目的地はスンバ島。ジャカルタで立ち寄るところができたのはありがたい。
僕のほうは体調おもわしくなく、ようすをみるため近くの村 Wawo へ。穀倉群が村から離れた小高い丘の斜面にならぶのをコモドツアーの路上確認していた。村が焼けても米は残るよう別の土地にまとめたという。新種米IR36の普及で多くの村で穀倉は姿を消しつつあるが、ここでは米を karung(米俵、当時は一般にPP紐を編んだガラ袋様なものを利用)につめて穀倉内に保存している。穀倉の需要はまだある。
市役所までベモで約45分。来意を告げ、Desa Sambori の調査をしたい旨伝える。この時には Sambori は車ですぐ近くと思っていた。ここで Sambori のセクレタリスを紹介される。日本語をまだ覚えているこの初老の男は役場を出るや
「アナタ(日本語)、kuat jalan(健脚)か?ここから Sambori まで歩くと着くのは7時になる」
この時まだ12時前。Sambori はすぐ近くで、今日は日帰りのつもりでいる僕はこれを聞いても半信半疑。
「バスで Tente まで行き、そこから歩けば近いよ。だけど我々はお金をもっていない。アナタ(日本語)責任をもてるか?」
と言って、仲間と料金を計算して
「アナタをいれて我々4人で5000RPだ」
役場の仕事で車に乗って帰るつもりなら金を持ってきているはずだし、歩いて帰るつもりなら僕もそれに従うまでだ。しかし、会って早々客から金をせびるとは気分が悪い。折から激しいスコールで、Wawo 役場近くに居を構える Sambori人の家へ駆け込み昼食。一緒に食べるようにすすめられたが、相手をする気にならず、床にひっくり返っていた。
雨後、彼らと別れ、すぐ近くの Desa Maria で穀倉の図面採り。Maria の村長はつきっきりで世話をしてくれた。Sambori の男とはえらい違いだ。
Wawo市にはふたつの言語圏がある。ひとつは、この Maria を含む東部、西部Wawo で低地の一般ビマ語を話す。これに対して、中南部Wawoは Sambori をふくめて別な方言圏を形成している。ブギスのゴア王国影響がおよぶ以前の土着の文化らしい。
Maria の穀倉のうち、伝統的なものは壁のない形式(Alas で見たような)である。壁のある新形式は1930年代にブギスの大工によって伝えられたという話を村長から聞いた。この穀倉群は遠くから見ると壮観だが、残念ながら架構の精度を欠く。熟した文化から生まれたものではなくて、外来のものを取り入れ、形式を真似ただけの雑なもの。材の仕上げ悪く、ディテールもまちまちで情報源に乏しい。
夕方6時過ぎ、満員のマイクロバスの扉口につかまり Bima 帰着。

カメラマンのルーカス。この数年後に、彼が死んだという手紙をアユからもらった

穀倉群が小高い丘の斜面にならぶのをコモドツアーの路上確認していた

伝統的な穀倉は壁がない。壁のある新形式は1930年代にブギスの大工が伝えた

実測図:Desa Maria 穀倉 Lengge
11月26日(水) 晴 Mbawa
いよいよ昨年の遺恨試合。Donggoの調査。
かつて知ったる道だからさしたる苦労もなく Mbawa 到着。途中で折良くトラックに乗ることができて、9時には Mbawa に着いていた。このトラックに会わなければ12時過ぎのバスまで待たねばならず、昨年の二の舞だった。
Mbawa の牧師ヤコブの元へお土産のビスケットを届け、さっそく家屋の写真撮影。昨年、ヤコブ(アロール島の出身)を介して聞きとりした部材名はほとんど誤っていた。ビマ語には特異吸音(息を呑みながら発音する)があって、タルキ 'boko は普通にボコと呼ぶとオチンチンのこと。ボ(吸)コと発音してはじめてタルキの意になる。これがアロール島出身のヤコブによると mboko となってしまって、これでは正確を欠く。土地の人間は、boko、'boko、mboko を全部区別する。
ドンゴ人はもともとフローレス島の Manggarai から売られてきた奴隷だったらしい。彼らはビマ人の手を逃れ、山中に暮らした。その子孫たちだという。ドンゴ人の教育程度はひくい。インドネシア語を話せない人間がたくさんいる。Mbawa の村長もあやしい。彼はお土産が何かということしか興味がなく、僕が持参したタバコ1カートンをそそくさと家の奥にしまいこんだ。Donngo の市長には土曜日に Bima の自宅で会って、親切な手紙を受け取ってきていたから、これを見せる。癖のある筆記体で書かれたこの手紙を彼は読めなかったらしい。このために後で苦労を背負いこんだ。
日中は隣村の Mbawa と Sanggari の間を往復して、Mbawa にのこる Ncuhi の家(空き家。いちおう修復されているが中身がなく小屋組もいいかげんなもの。参考にならないが)と Sanggari の調査家屋の写真撮影、昨年図面のチェック。この村での聞きとりはヒステリックになる。住民たちと僕自身の言葉の不足もさることながら、村人に聡明な人間がいない。愚鈍な連中ばかりで話にならず、彼らの関心はタバコか金をせびることだけ。
夜、村長たちに村の状態を聞きとりしている最中、3色ボールペンが紛失した。先刻まで村長が使っていたから、彼が持っているはずなのだが、誰か持ち帰ったに違いない、躾が悪い、などと一座の連中。
「誰か持ち帰るって、あれは僕の持ち物なのだから、これは盗みではないか?」
と、語気荒く言うと、彼らのほうでも吃驚したらしく、あちこち探してくれた。そうしてややあって、村長氏、床からやおら拾い上げる素振りで、落ちていたよ。

Bimaから渡し船で対岸のBajoへ

お世話になった牧師の元へお土産のビスケットを届ける

夜は村長たちに聞きとり

実測図:家屋 Uma 梁行断面
(宮本長二郎先生採図)
11月27日(木) 快晴 Bima
午前中、図面チェック。ここでの食事は毎食ご飯にメザシ2、3匹。仕事を終えて家にもどると村長氏の奥方、何か果実をガツガツ頬張りながら、何を訊いても、村長は呼び出しがあって村を下りたと繰り返すばかり。昼食の用意などはもちろんなし。困った。この村から Padende村まで案内役をつけるように頼んでおいたのに(市長の手紙にもそう頼んであった)これでは埒があかない。
小村長を呼び、手紙を見せる。しかし、今さらいくらごねても、案内をするような人間はすべて畑に出てしまっていない。誰も案内してくれないのなら一人で行く、とばかり道を訊き、重い荷物をひとりで担いで村を出る。
Padende までは山越え4時間ときく。怒り心頭に発す、という具合で出発したものの、藪だらけの山道は人通りもなく枝分かれしていて道を確認すべくもないのだ。太陽はギラギラと照りつける。約40分でギブアップ。道ばたの切り株にしばし腰をおろし、バカヤローと大声を出したつもりがたいした声にはならず、山あいにかき消えてしまう。こうして村へふたたびもどり、といっても村長宅を訪ねるなどというバカなことはせず、そのまま村を素通りしてバスの発着場へ向かう。背負子とカメラバッグとでこの道中は完全にグロッキーになった。M(妻の名)、ボクは帰って来たぞ、などと呟きながら半死の態。バス停までの道は来たときとちがって軽い登り。長く果てしなく感じられた。バスの発着場で道ばたのワルンに腰をおろし、水を乞い(コップ5杯も)、かれこれ2時間、日本の物価の高さを話し(1円10RPだからこのまま換算すれば日本の物価は異常だ)、待てど暮らせど1日3回あるという3回目のバスはやってこない。
「客がいなけりゃ日に二度しか来ないよ」
この時までは会う人ごとに1日3回のバスがありますと公式見解を聞かされてきたわけだから。それでワルンの主人がこの日本人を不憫に思ったのか、学校の先生に頼み、彼のオートバイの後ろに便乗して Bajo まで送ってもらった。
この鬱積する欲求不満が昂じたのか、ホテルのフロントの人を食ったオネ-チャンといざこざをおこす。
「あなたには親切心というものがないのか!!」

重い荷物を担いでひとり村を出たものの

実測図:家屋 Uma 桁行断面

実測図:家屋 Uma 詳細

実測図:家屋 Uma 詳細
11月28日(金) 晴 Sambori
昨日の今日だ。朝6時にホテル発。目的地はこれまた遺恨の Sambori で、だいたいの道は確認してある。山の麓までが約1時間、ここから約3時間の山行きで、10時には村に着く。3時まで仕事をして帰れば日暮れ前に山を降りることができる。という胸算用。
6時18分ホテル発、6時22分バスターミナル着。Tente 発のベモを見つけ、6時半にはターミナル発。これは最高にうまく乗り継いだわけだ。Tente 着7時6分。ここから benhoel(馬車)に乗り、7時44分 Roka という山の懐の村についた。ここまでは予定通り。
さほど急でない山道を歩く。体力がない。やたらと喉がかわく。カメラバッグと三脚だけの荷物が重く感じられる。半分諦めて帰ろうという気持ちがあるから道はすすまない。10分歩いては道ばたに腰をおろす。約4時間で Sambori 着。
誰もいない村役場の床に座りこみ、しばし放心状態。とにかく昨日、今日となぜこんな困難にあわねばならぬのか、誰からも強要された仕事ではないから文句も言えないが、恨めしい。
村長は呼び出しがあって Bima へ下りた。例のセクレタリスは頼る気がせず、小学校の校長先生に案内を請い、Sambori の旧村へ。新村のほうにもいくつか伝統的な三角屋根の住居(ドンゴのような)があるが、これは旧村から移築されたもので、やはり旧村を訪れねばならない。
約30分。山の斜面にへばりつくような形でいくつも伝統住居がのこる。ドンゴのものとの大きな相違は、入口が屋根妻面にはなくて屋根天井裏にあることと、この天井下の空間を居住空間として利用している点。規模もドンゴのものより大きい。こうした生活形態は西スンバのものと似る。屋根内居住から屋根下居住への過渡的形態をしめすもの。この家屋を見ては興奮せざるを得ない。10棟をこえる伝統住居が残るのだ。写真を撮り、図面を採っているうちに山あいの村に夕闇が訪れる。
昼食はこの家で用意してくれたご飯と塩。校長先生は食事をつくりたいが鶏を買うお金がない。キミは……とこれまた。僕もそのつもりでいたけれど、結局、僕は新村に戻ることなく、校長先生はひとりで帰って行った。彼の食事には悪い事をした。夕食はケロールの葉のスープとご飯。布を二枚借り、近くの新型住居の床上にパンダヌスのマットを敷いた寝床で寝た。

山の斜面にへばりつくような形でいくつも伝統住居がのこる



実測図:Desa Sambori 家屋 Uma Lengge 梁行断面
11月29日(土) 快晴 Bima
11時まで図面取り他雑事。聞き取りをしようにも老人はみな逃げてしまった。タバコをくれるなら話してやるよ。しかし、タバコは昨日全部この家にあげてしまってない。第一、こういう要求に応じるほど僕は善良でなく、かえってコッチがヘソをまげる。この家の若者たちが見つけてきてくれた(?)老人というのが誠意のない(でなければバカな男で)、
「部屋のなかのどこに寝るか?」
「どこでもいいさ」
「どうやって寝るか?」
「好き勝手だよ」
「この建物の材料は何の木だ?」
「そこらへんにある木さ。強けりゃ何でもいい」
方位名称を訊くと、これまたメチャクチャ。土地の方位名称がインドネシア語と相違するのかと思ってよくよく訊くと、太陽ののぼる方向がすでに現実とちがう。一瞬、ここは南半球で、南半球では磁針が南を指すのかと錯覚した。この男はこれでも大工という。こういう男があらわれると、他の人間は沈黙してしまうから、何を訊ねても答えの信憑性ははなはだ乏しい。すでに肉体的にまいっている。精神力も限界で、道具をしまい山をおりた。
11時下山。村人に教えられた近道を行く。途中で道を誤り、段々畑のなかを突き進む。段々畑といっても石垣は高く、藪が生いしげり、所々に柵をめぐらしてある。このなかを眼下に見える町めざして歩く。山の地形はコチラの思惑通りに出来上がっているわけでないから、直行のつもりが蛇行の繰り返しだ。約1時間半で下山。山の麓から、これまた水の干上がった田んぼの中をかなたの町めざして歩く。木も草もない。山のほか視界をさえぎる物なく、太陽は容赦なく照りつけ、あたかも砂漠を行くかのような疲労を感じた。
昨日通った Roka とは多分方向ちがいのこの町 Ncera から約1.5時間ベンフル(馬車)に激しく揺られて Tente にたどり着いた。道は石と穴だらけ。馬車はクッションがないから飛び上がるたびに低い木の天井に頭をぶつける。手を離せば確実にふり落とされる。これを耐えるにはある種の精神集中を強いられる。
午後3時半、ホテル着。ほとんど生ける屍のような状態であった。
この夜、日本人のタナカという男とホテルで会った。彼は日本政府の援助によって通信用の鉄塔を建てる作業の土地視察に来た。第三世界に住む 金 日本人は腐っているという。彼は立派に札ビラをばらまいて歩く。彼の奢りでビールを飲み、食事を食べた。残念ながらいつものような食欲がない。料金を払い、持ってきたお釣りのなかからバラバラとたくさんあった小銭をこの給仕に全部あたえた。男は一瞬驚いて僕の顔を見、それから嬉しそうにそれをしまった。
東大を出た人間がこんなところにいるとはもったいないとしきりに残念がる。うちの会社にとは言わないけれども、こうした会社にはいれば月50万の現地費がもらえる。予算は自分で好きなように使える。自分は別に悪いことをしているわけじゃなし、どんなところでも最高のホテルに泊まる。それがダメだというなら、他の人間をよこせばよいのである。自分はあちこちに40人くらい女がいる。酒と女にほとんど金をつかう。と嘯く彼は32歳、まだ独身。口髭をたくわえ、サウジで仕事をしていた時には現地人でとおったというが、ここでも顔つきは立派なトッペン面。

実測図:Desa Sambori 家屋 Uma Lengge 桁行断面

実測図:Desa Sambori 家屋 Uma Lengge 詳細

実測図:Desa Sambori 家屋 Uma Lengge 床伏


11月30日(日) 晴 Bima
午前中ひたすら休養。M宛の手紙を書く。
午後2時より7時まで Desa Maria にて調査の補足。先日天候悪く、写真撮影と部材名の聞き取りがのこる。Donggo や Sambori の人間とちがって、ここの人間は調査に理解あるのでたすかる。
タナカさんの一行は、本日バリ経由でウジュンパンダンへ向かうはずで、飛行場まで出向いた。チケットはすでに予約してあったのに、突然すべてキャンセルを強いられたのだと言って憤慨して(しかし大人しく)戻ってきた。なんでもSapeのフェリーの船長の奥さんが刺され(タナカ情報では警察署長の奥さん)、そのために遺族(?)一行が大挙して飛行機に乗り込むためだという。本当のことはわからない。日本だったら事情の説明くあるだろうに、飛行場ではほとんど知らされることがなかったらしい。
12月 1日(月) 晴 Ruteng
昨日出発できず、涙をのんだタナカさん一行に便乗して飛行場へ。ひさしぶりのTwin Otterで快適にフローレス島の Ruteng 着。スンバワ島東部の整備されたライステラスの景観と、フローレス島にはいってからの山また山、木に覆われたフローレス島は好対照だ。これがスンバだと山はすべてボタ山で木という木がなかった。
Manggarai の首都 Ruteng は山あいにひらけた清楚な町。町の中心には意外や中国商店が軒をならべてにぎわい、ひろびろとのどかに配備された役所、教会が四囲の山々に映えてうつくしい。冷涼な空気とよく整備された並木。道を歩くと通りすがる人びとが好奇の目であとを追う。連れも尋ねるべき知り合いもなく、ひさしぶりにまったくの異境にきたときに感じる緊張感。数ヶ月前、Ambon や Kei に着いたときの緊張、昨年はじめてスンバに降り立ったときの緊張に似る。
”Manggarai 人はフローレス島のなかでもパプア的形質のつよい縮毛、色黒、精悍にして文化的に劣る”という予備知識によって想像していた荒々しいところはなく(形質的にはロンボック島のSasakなどと大差ないだろう。パプア的風貌もいればマレー的なのもいる。縮毛はたしかに多く、色黒かな)、総じて慇懃、誠実で親切。
到着早々に荷物をかついで県庁をおとずれ、調査許可の申請。どこに行けば伝統住居をみれるか、というこちらの質問にたいして、Sospol も PdK も非常に親身になって捜してくれた。ただし、この Manggarai 人の誠実勤勉ぶりが仇になってか、数年前までまだあちこちで見られたという伝統住居は見る影もなく放棄された。日本人が竪穴住居を捨てたように、彼らも伝統を捨てつつある。社会や文化がたがいに無数の見えない糸で連合しあい、緊密な関係を織りなし得た極(クライマックス)にいわゆる伝統住居が位置づけられるとすれば、この安定関係がくずれ、社会も文化も関係を変化させつつある現在、住居が変化を余儀なくされるのは仕方のないことだ。住居のシンボルとしての意味が変わりつつあるのだ。空洞化したシンボルは早晩放棄されねばならない。意味をあたえること。空洞に内容を注入すること。宗教が意味される実体なく存在意義を勝ち得ているように。伝統の意味充填はたぶん宗教活動に似る。文化や歴史についての評価、啓蒙は喧しいほうがよい。太鼓をたたき、銅鑼をならす。
夕刻、町の郊外にある Kampung (Lama) Ruteng の見学に行く。徒歩40分。村中央の石壇、これを楕円形に囲む石敷きの広場と、そのまわりにめぐる家屋、山を背にした村への入口。階段をのぼると、広場の反対正面に巨大な2棟の円錐形慣習家屋が建ち、ここから平行しておなじく円錐形の一般家屋が広場石敷きの下にならぶ。村を訪れた者は、広場の奥にある馬降り石で馬を降り、環状石敷きに一定間隔で立てられた立石に馬をむすぶ。家々にはいるには、この石敷きより階段で1mほど下り、直接高床上にアプローチする。慣習家屋 Mbaru、Tunbong には儀礼のための楽器が吊り下げられ、村中の suku(クラン)から各1家族がここに住まう。屋根上には水牛の角をかたどった木彫がかざられる……こうした景観は石敷きをのぞいて今はなく、あたらしい慣習家屋を建設中であると誇らしげに村人は言うけれども、この建物の構造はまったく合理的なだけの木造で(合理的なはずの架構がところどころで破綻しているのはご愛敬というもの)、僕にとっては価値がない。価値は相対的だ。

Ruteng は山あいにひらけた清楚な町。教会が四囲の山々に映えてうつくしい

夕刻、町の郊外にある Kampung (Lama) Ruteng の見学に行く

あたらしい慣習家屋を建設中
12月 2日(火) 晴 Iteng
昨日県庁で得た情報によると、伝統家屋ののこるのは Waerebo という山あいの小村だけであり、ここに行くためには Ruteng で一日一度のバスをつかまえ、2時間ほどで Iteng という南海岸の村へ行き(ここは Kec. Satar Mese の中心)、ここからモーター船で2時間で Dintor という村(Desa Satar Lenda の中心)に着く。ここから木の根をつかむような急な道をのぼって、約4時間で Waerebo に到着するというもの。アンドレアス・アマンというここの県庁に勤める男の妻がこの村の出身だというので、彼から村人への紹介状をもらった。
朝8時にターミナルにて Iteng 行バスを待つ。あらわれたのはトラックで、この荷台にベンチをならべ、ビニール屋根を張り、客席としている。こういうトラックは何台も Ruteng の町中をはしりまわっていたから、ごく一般的な乗合バスということになる。ロンボック島のトラックよりは人間らしい扱いだ。
8時半、このトラックに乗り込む。客席は半分ほど客で埋まり、このままトラックはターミナルを後にした。快調。しかし、町外れまで疾走してUターンする。ふたたび町中をぐるぐるとまわり、やがて到着したのは出発したとおもったターミナルで、ここでまた客をつかまえ、町を縦横にはしり、客をひろってはターミナルにもどる。こうしてベンチに横一列5人の乗客が腰掛け、トラックの荷台が荷物と乗客でいっぱいになるとようやく町を出た。10時。山を越え、日本人が今年補修したという道を下って Iteng 着は12時50分。
親切な副市長の家で昼食を食べ、船を捜すも船はなく、Iteng 発は翌日となる。この夜は、旧知事の大邸宅(現在、彼はDPRになってジャカルタ在住)で寝た。
ウジュンパンダンからはこんだという石タイルを床に貼り、コンクリートの壁、ガラスの窓、波形トタンをはった屋根、各部屋についたマンディ場の洋式トイレと、こうした僻地に似つかわしくない豪壮なつくりの建物が、計画者本人がいなくなったためにこの土地相応に順応して、水の出ないトイレ(水は井戸からポンプで引き上げていた)、ところどころ板の剥がれた天井、電気のつかない電灯、閉まらないドア、等々。蚊の多い部屋のなかで、それでも蚊帳をはったベッドで快適に寝た。
村の建設
村の建設は農地をあたらしく切り開く手順と似る。村ははじめから新地に建設されるわけではなく、すでにある畑地のなかから相応しい土地が選ばれる。したがって、はじめ自然の土地を選び、Ringko (Rokhani) 儀礼をおさめて農地 Uma とし、さらに農地に建てた出作り小屋が支障なく、村の建設に好ましい場合に儀礼をおこない、あたらしい村 Beo をつくりはじめる。この際の儀礼は
① Cece-Cocok (切る-切り株) 水牛を殺し土地を浄める
② Mbaru-Niang (儀礼家屋) の建設
③ Kaeng (長く住む) 農地を開く際の儀礼と似る。

マンガライ社会では、家屋 Mbaru、農地 Uma、水場 Wae-Tek の3つをとくに重要なものと考える。

Iteng にあるカトリック教会。マンガライ風のデザイン
12月 3日(水) 晴 Waerebo
朝7時、チャーターしたモーター船(15000RP)に客一人乗り、Iteng 発。波なく、おだやか。奇怪島 Pulau Ram めざして船はすすむ。目的の Dintor はこの海に突出した山の対岸にある。
約2時間で Dintor 着。ここで Desa Satar Lende の村長に挨拶。彼はこの村唯一の貴族階級の家柄で一般の村人に似ず、頭の回転がはやい。うわずった長嶋調のイントネーションで、こちらがなにか言いかけると、それに応じてたちどころに十倍くらいの話をはじめる。
Dintor に住むアンドレアス・アマンの義父エリトリウス・バオという初老の男と、Denge という途中の村にある小学校の先生、および村長の息子、ほか村人一人の計5人でにぎやかな道中。おまけに僕の荷物は一部この村人たちが肩代わりしてくれて、スンバワ島での孤軍奮闘をおもうと隔世の感。

Kampung Waerebo は Todo の王権の下にあった。かつて山間の僻村であった Waerebo は1967年、政令によって Kombo という海岸よりの新村へ移転をはじめる。1969年、それまで独立のDesaであったのを、Desa Satar Lende に併合。村人の多くは Kombo に住むが、農地が Waerebo にある関係で Waerebo の村にも家屋をもち、この2村を往復してくらす。
Kombo で村人に挨拶。ここから村まで3人の村人が案内をしてくれた。Denge の小学校まで、道はゆるやかな登りながら、小川のせせらぎを聞き、民家のあいだを歩く快適な道中。ところが、Denge をすぎる頃から道はまったくの藪の中で、Waerebo までの2時間半、村なく、激しい登りを繰り返す。カメラバッグだけを持っているのにとうとうギブアップで、このバッグも肩代わりしてもらった。
スンバワ島以来、連日の山行きで体がまいっている。すこし歩くと息がきれる。自虐的な気分でこの山歩きを繰り返す。とにかく、そこに山があるのだからしょうがない。

波なく、おだやか。奇怪島 Pulau Ram めざして船はすすむ

山間の僻村 Waerebo は1967年に海岸近くの新村 Kombo へ移転。村人の多くは新村に住む

実測図:Mbaru 平面

実測図:Mbaru 平面
12月 4日(木) 晴のち曇 Waerebo
Waerebo には本来ひとつのスク=クラン(uku)uku modo しかない。しかし、村内で便宜上このスクはふたつの panga(半族)にわかれている。この半族がたがいに結婚相手の交換をしている。同一 panga 内での結婚は禁じられる。伝統的な居住形態は父系の共同住宅生活(拡大家族とはいえない)で、ひとつの家屋内にいくつかの家族がそれぞれの部屋と炉石をもつ。この家屋には半族のそれぞれが雑居可能で、調査家屋では同一家屋内(異なる panga 同士)での結婚例があった。この村での話によれば、家屋は共同生活ということのほかに、とくに畑仕事や相互扶助といった社会的な共同関係を果たすものではないらしい。アパートのようなものだけれども、居住者が共同でこの家屋を建設するという点ではよほど主体的なものだ。
調査家屋では、兄弟二人が同一家屋に部屋をもつが、この家の建設当時、未婚だった弟の一人は、のちに別の家屋建設のグループにくわわって、別の家屋にも部屋をもつ。
村には4棟の伝統的家屋がのこる。うち1棟が他の3棟に先行し、のこりの3棟は1938年に相前後して建設された。ほかに比較すべき家屋例がないから何とも言えないが、これら住居の入口回りは改変を受けていて(扉の開閉に蝶番を利用)本来の形を知るよしもない。写真撮影と家屋実測に丸一日ついやす。

実測図:Mbaru 断面

実測図:Mbaru 断面
12月 5日(金) 曇 Dintor
12時半まで実測と聞き取り。写真。13時15分、Waerebo 発。Kombo から来た連中はシナモンの出荷のため二人が早朝に山を下りていて、残るは一人。彼にカメラバッグを託し、僕は背負子をかつぐ。帰りは道を知っているから気が楽だ。約2時間で Dange の学校着。先日昼食をごちそうになった礼を言い、即出発。Kombo 着15時30分。約1時間休んだ後、Dintor に下りた。
村の連中は裏がなく純真だ。Donggo や Sambori での精神的消耗がないから気が楽。
Dintor に下りた途端、海辺で待ち構えていた男にボートの有無を訊ねる。シナモンをはこぶために夜ボートが出るという話だったからだが、この男の回答は予想に反した。
いくら?
2万5千RPで目的地まで案内するよ。
コノヤロー!
この夜は村長の家の大きなベッドの暑苦しい蚊帳のなかで、なんと4人の男と雑魚寝。ベッドを横に使って。暑いのに寝袋にもぐりこむ。

村にのこる4棟の伝統的家屋はいずれも1930年代の建設

シナモンの出荷にそなえる
12月 6日(土) 晴のち雨 Ruteng
5時半、Dintor 発。Iteng でのパッサールに行く船に便乗。ところが、この船が Iteng に着くと、村長から言われたと1万5千RPを請求される。あの村長は何を考えているのやら。これはチャーターではないはずだとわけを話し、一般乗客と500RPをはらう。
Iteng 着は7時30分。市役所に挨拶をし、市中のKTP(Kartu Tanda Penduduk 住民証)をあつめて手際悪く数えはじめた彼らを尻目に9時半トラックに乗る。
12時 Ruteng 着。暗雲激しく雨。体だるく分解するような疲労をおぼえた。
食後、雨の中を Kam. Ruteng の見学。先日の話では Rumah Adat の棟飾りを木曜日に取り付け、儀礼をおこなうとのことだった。その成果を見に行くが、建物の小屋組は、扠首を中央に向けて整然と配した体育館のような構造で、形を復元するための最小材料、合理的な構造にすぎず調査の意味がない。村の実測も一人では巨大にすぎ(10m単位の測量だ)、疲れて気力もなく、おまけに雨。すごすごとホテルへもどる。
体熱く、下痢。過労。

パッサールに行く船に便乗

Rumah Adat の小屋組は、扠首を中央に向けて整然と配した体育館のような構造で調査の意味がない
12月 7日(日) 晴 Bajawa
移動日。8時10分、Ruteng 発。Ngada 県の首都 Bajawa 着14時。
バスに案内されたまま無愛想で貧しいロスメンのベッドで手紙を書いてすごす。ひたすら食べて体力を回復しようにも、Bajawa には満足な食堂がない。Ruteng の豊かにひらけた田園風景とくらべると、Bajawa はいかにも貧しい。
12月 8日(月) 晴のち曇 Bena
午前中に Sospol と PdK をまわり情報収集。PdKの所長はマンガライ人で大変に親切。誠意をもって面倒をみてくれる。彼のつけてくれた案内者をともなって、午後からKam. Bena という PdK による保存村落へ出発。
Bajawa からベモで約1時間、Walikeo という村へ。ここからさらに車道を徒歩約1時間でめざす Bena 到着。ここには3ヶ月6万RPという雀の涙ほどの支給をPdKからうける管理人がいて、村の維持を司っている。
村は中央に細長い広場をもち、その両側に建物を平行に配している。広場にはドルメン、メンヒルのほか、各スクの所有する Ngadhu という二又状木に屋根をかぶせた傘のお化け状建築と Bhaga という小型の家屋状建築がある。
家屋のほうは、竪板壁構造の箱形架構物に屋根をかけ、束柱で持ち上げた主屋部分に二重の前室がついた形式。前室部分の屋根は竹を交互に重ねたもので、構造も一定せず改変激しい。主屋の架構だけみると、Nias や Tanimbar Kei 島との類似が目につく。これらの保存修復された家屋群は、しかし、前室の庇をあげるために棟木の位置を前方にずらしたものが大部分で(したがって、主屋架構の対称性をやぶる)、本来の屋根形態をのこすものはわずか5棟しかない。5棟中2棟は、中央桁行の梁上に束をもち、1棟は中央梁上の左右に追扨首状2本の真束。他の2棟はこれら真束の類をいっさい持たない形式。村本来の形式は、bhaga の構造をみるかぎり、真束をもたないものであるらしい。ただし、他部分の状態のよい追扨首型家屋を実測することに決める。
すでに夕暮れ。ドルメン、メンヒル、先の尖った立柱石などのならぶ中央広場のそこここに十字架をつけたコンクリート造の墓が横たわっていて、全体の緊張を損なう。土着のアニミズムや巨石信仰がよくて、現在の状況下でもこれを維持せねばならないなどというつもりはない。しかし、多くの人間たちが手に塩をかけてつくりあげてきた歴史環境を現代の安易簡便なキッチュ製品によって破壊してゆく無神経さに苛立つのである。タバコの空き箱をそこかしこに投げ捨てる無神経さでもって文化を投げ出しているのだ。

破れ傘。こわれた Ngadhu

実測図:Ngadhu

実測図:Bhaga
12月 9日(火) 曇 Bena
トア・メオ(トアは本人の名、メオは母の名)の家屋実測。Bajawa 文化の他のフローレス文化との大きな相違は母系であるということだ。人物の呼称も子どもの名前で親を呼ぶのとちがって、母親名を冠する。
このンガダ Ngada 県には VOC のあらわれた今世紀はじめ以来、4つの治政権(うちふたつはのちに合併して今日3つ)がある。Ngada、Riung、Nage、Keo(のち合併して Nagekeo)で、それぞれが異なるアダット法により維持される。
家屋の茅葺きは、他のインドネシアのパネル式ではなくて、横桟を垂木に固定しておいて、これにチガヤを折り込んでゆくだけの形式。折り返されたチガヤの先が屋内で毛羽立って、スス、ホコリを付着し、小屋組の実測はこの毛羽だった茅先をかきわけ、ススとホコリを浴びながらおこなう。それでも詳細までは見えない。見えないところは Bhaga の構造から類推する。
夕方、近くの温泉でマンディ。川の渓流の一部に湯が湧き出て、小さいけれども久しぶりに湯につかった。人っ子ひとりいない文字通りのジャングル風呂は、太陽もささず、薄気味悪い。夜は蛇がでるという。

実測図:Sa'o 平面

実測図:Sa'o 梁行断面
12月10日(水) 曇、雨 Bajawa
昼食抜き。昼過ぎまで実測をつづける。Ngadhu、Bhaga と家屋 Sa'o。
家屋 Sa'o には格があり、はじめから上等の家屋を建てることはゆるされない。
はじめ、Sa'o Keka という竹の粗末な家を建てる。つぎに再築するとき、Aze Paba という板壁の家屋。つぎに Wati Segere という彫刻のすこしあるもの。最後に、Weti Masa という全体に彫刻をゆるされた家屋で、これは Sa'o Meze(大きな家)と呼ばれる。
Sa'o Meze には一般人の住む Sa'o Kaka と、クランの首長クラスの住む Saka Puu / Lobo がある。棟の上に人物像を載せた Saka Lobo(Lobo は先端の意。男の始祖をあらわす)と小型家屋を載せた Saka Puu(Puu は元の意。女の始祖をあらわす)がある。
夕方5時半、運よく通りかかったトラックに乗り、Bajawa へ。約1時間40分。

実測図:Sa'o 桁行断面
12月11日(木) 激しいスコール Boawae
午前中PdKへ行き、調査打合せ。Riung の王家に属するWangka での調査は So'a でパッサールのある日曜日(車の往来が多くある)となる。それまで Boawae の調査。PdKのスタッフのひとりに Boawae の出身者がおり、彼を案内役につけてくれた。Boawae には王の家と一般の民家がまだのこるという彼の言を信じて。
Bajawa 発14:40分。16:03 Boawae 着。Ende ― Bajawa を往復する小型バスでこれは快適。
到着早々 Boawae の王家というのを見に行く。カンポンの中央に二叉状柱 Peo が立ち、奥手に王の家。セン(波板トタン)葺のほか変更はないということだったが、架構はすべて近年のもので、木造の骨組をみると味もそっけもない。大規模だから体育館のような印象を受ける。伝統的な建物は現代のものの2~3倍も木材がかかるというのは本当だろう。したがって、写真も撮らず、親切な王家の人たちに聞き取りだけして帰宅。
Pdkスタッフの家で手厚いもてなしをうける。鶏肉のスープとご飯、おかずが野菜だけでないのはひさしぶり。

カンポンの中央に二叉状柱 Peo が立ち、奥手に王の家。セン葺のほか変更はないということだったが、
12月12日(金) 曇のち晴 Tutubhada
文句なく過激な一日。
Boawae の王家で失望したので、近くの Wolowea という村まで伝統的住居をしらべに行くという比較的軽い気持ちで家を後にした。
Wolowea は Bajawa から Ende へ向かう道の途中にある。したがって、この路線をはしるバスをつかまえればよいわけだが、これを待つと9時になる。われわれは(Pdkのスタッフと僕)6時40分にトラックをつかまえ、Rega という地点で降り、ここから Wolowea まで約1時間を歩いた。
同行のPdK氏は家のちかくということもあって、コウモリ傘ひとつという軽装。Wolowea の村長宅を訪れ、Rumah Adat の有無を訊ねるとすでに壊したということで、われわれはそのまま街道をそれ、Weaau に向かう。
軽いハイキングコースだけれども、荷物をひとりでかついでいるからかなりの重労働だ。
約1時間で Weaau 着。村の入口にブリンギンの大木があり、これが柵でかこってあって、木の下にマリアの像を祀ってあるのが可笑しい。キリスト教のアニミズム化だ。
しかし、伝統住居のほうは柱をのこすのみで跡形もなく、案内してくれたPdK氏は、自分がここで先生をしていたときには Rumah Adat があったのに(何だ、そんなことか)とぼやいている。すくなくとも、この村はみるからに古い村を移転してできた新村で、たとえ古い家があったにせよ、変更が多くて実測は難しいだろう。せっかく来た記念に、穀倉の写真だけおさめてもとの道を引き返す。
Wolowea まで1時間。ここまでできょうはもう3時間歩いたことになる。
Wolowea の小学校で情報を得る。それによれば、Danga から約3時間歩いた山中の Kam. Tutubhada というところに、4軒の Rumah Adat がいまもたしかにのこっている。これは足繁く村にかよう先生の言だから間違いはないだろう。
このときに Danga がどこにあるのか僕は知らなかったのだ。迂闊にも(先ほど苦労の甲斐なく目的の家屋が見つからなかったのにすこし腹立っていたから)、デハ Tutubhada へユキマショウ、と言ってしまった。Danga がどこにあるか確認しておれば、こんな愚挙はせずに大人しく Bajawa に引き返していたろうに。
悪運はついているもので、ほどなく Danga 行きのトラックが来てしまった。であるから、いっそう軽い気分だったのだ。
Wolowea 発は11時10分。トラックは野をこえ山をこえ、ひた走る。はじめ空席だらけだった荷台のベンチも、そのうち「一列5人だよ、つめてね」といった調子でいっぱいになってしまった。
大きな石と穴だらけの道を右に左に激しく揺られながら、いつしかわれわれはフローレス島中部(南部にちかい)山地から北海岸まで降りてしまった。
Danga 着は13時45分。Wolowea から2時間半だ。ここに住むPdK氏の親戚宅で休憩。
Danga には、戦争中、日本軍の基地があった。Surabaya Dua (第二のスラバヤ)と命名し、日本軍は、各地からあつめたインドネシア人を強制労働に使って、ここに飛行場を建設、無数の死者を出したという。
No.9(ノモル・スンビラン)といって、彼ら現地人を震え上がらせたのは9号(?)の棒で、これを使っていうことをきかない者をひっぱたく。叩かれた者は気絶する。気絶すると水をかけ、起き上がるとまた叩いた。とくに悪辣だったのは韓国人だった(日本のために戦争に引きずりだされているのだからしようがない)。
あるとき、先生をしていた父(この話をしてくれた人物の)のもとへ韓国人の兵隊が来て、そっと耳打ちした。
あした、子どもを連れて丘の上へ逃げろ。町が爆撃されるニュースをラジオで聞いた。このことは誰にも言うな。
翌日、父が家族を連れて避難すると、飛行機が大挙してあらわれ、町を爆撃した。
その後のこと、ケンペイ隊がやってきてこの韓国人をとらえた。スパイだというので、彼は例のNo.9で打ちのめされた。骨砕け、肉切れ、彼は死んだ。
また、あるとき日本軍のブンケン(?)が馬に乗り、したたかに酔って家にやってきた。
オンナはいるか?
彼の母親は部屋の隅に逃げた。男は母親を見つけ、胸ぐらをつかんで引きずりだした。子どもの彼はどうしていいかわからない。おろおろしていると、、、(意味不明)、、、バカヤローと叫び、(別の)男は手にした銃を発砲した。彼は目の前で人が死ぬところをはじめて見た。ケンペイ隊が来て死体を片付け、これを燃やして灰を壺におさめ、どこかへ送った。
例によって、この Surabaya Dua のちかくに日本軍は洞窟を掘っていて、なかは迷路のように枝分かれし、一定の者しかはいることができなかった。用件のある村人たちは、この洞窟の途中まではいることを許されたが、そこでいつも引き返した。穴を掘った者たちは殺されたという。
この洞窟にいまも日本軍ののこした多くの武器、弾薬などがあると考えられているけれども、村人たちは恐れて近寄らない。道に迷い、あるいは蛇にあうことを恐れている。

村の入口にブリンギンの大木があり、木の下にマリアの像を祀ってある
この Danga を出発したのが16時すぎ。同行者はPdK氏のほかに、この Danga の Pemilik Kebudayaan 氏をいれて計3名。荷物の半分を彼らが肩代わりしてくれたので幾分楽。というものの、きょうは歩くことにすでに飽きている。
3度も川を渡り(降雨で増水すると、水のおさまるまでお手上げという。越すに越されぬ大井川だ)、峠の麓の村 Malawona 到着はすでに夕闇せまる18時半。
小学校の教室(ふつうの高床の部屋にベンチと机が8個ならんでいるだけ)でしばし休憩ののち、月明かりの照る断崖絶壁の岩山を這うようにのぼる。見おろせば右も左も断崖で、遠くを見ると目がまわるから懐中電灯に照らされた足元だけを見て歩く。
約1.5時間、3人とも息絶え絶えになって山上の Tutubhada に着いた。この日、合計7時間歩いた。
村長をたたき起こし、ありついた食事はお馴染みのケロールの葉のスープとご飯。とにかく疲れて、寝袋にくるまり早々に寝た。
昨日のスコール、昨晩の激しい雨、日中の曇りがちな天候、とうとう雨期につかまったらしい。そういえば、Bena からの帰りに見た美しい夕焼けは雨期直前に見せる最後の燐光。

Tutubhada は首長の家を中心に22棟の家が平行にならぶ
12月13日(土) 曇のち雨 Bajawa
Tutubhada では伝統が生きている。
Rumah Adat のひとつはいましも屋根を葺き終えたばかりだし、他のひとつは小舞を固定し終わった屋根の骨組みが茅葺きを待つばかりになっている。伝統が生きているという事態は、反対から言うと、慣習家屋が何棟かあっても本当に古いものはないということだ。
細長く家の並列する村の一端に位置した棟の高い首長の家は1980年代の建設。炉まわりなどの一部に古材を再利用しているものの、筋交いを多用した現代の骨組みで、ディテールが悪い。1973年に台風があり、このとき多くの家屋が倒壊したらしい。それ以来、構造の補強に斜材を利用するようになったという。台風以前の家屋(手直しをうけていない)は一棟あり、1960年代の建設。これとて実測するにはあたらしすぎる。ここでの実測調査は見合わせ。
家屋は棟上に船型の茅積をもつ。この茅積のなかに立ちあがる2本のチョンマゲは棟持柱の延長で、この柱の先端をチガヤの葉先を上にして包み、ijuk の紐を巻きつけたもの。船は茅束を7段に積み上げてつくる。
この船型は、この村では bele jata (鷹の翼)、鷹の羽をひろげた形と考えられている。また、この部分を mango dadho (勇気ある男、腰掛ける)と呼び、この村の伝承とむすびついている。
そのむかし、この村の属する suku rendu と隣の suku rawa との戦いの際、rendu はスラウェシ島の Goa 王国に援軍をたのんだ。このとき、Goa から来た男はハトを従えてきて、その足に火をむすびつけ、相手の村に飛ばした。ハトは家々の棟にとまり、家はすべて燃えた。その後から村を襲撃して勝利をおさめた。
家屋の入口(縁側)に男女の姿を彫った木彫(祖先像)がおかれる。以前これは全裸であったが、イエスの教えに相応しくないというので現在では着衣像に置きかえられている。
家屋は主要な3つの空間からなる。簡単な接客と日常の腰掛け空間 Padha、男の空間 Teda、女の起居空間 Tolo である。Tolo には入口右に炉があり、この炉柱 duke の脚部には Lipi とよばれる段状の小空間があって、ここに儀礼のあるつど、ご飯、肉、ロンタール酒、シリー・ピナンなどを祖先にささげる。祖先霊は柱の上部にいて、彼らが食事を Lipi に捧げ、祖先をよぶと、柱をつたわっておりてくるものと考えられている。
家屋をささえる2本の棟木は Teda と Tolo の境の壁梁上に立てられている。この2本の棟持柱 madu には、家屋の建設時にロンタールの葉をまるめた器 sorelobe のなかにご飯、豚や水牛などの肉、ロンタール酒をいれて括り付ける。
家屋床をささえる9本の束柱のうち、中央右よりの柱は聖柱 poso puu である。これら束柱には nara の木、壁板は wuwu、他の小屋組はすべてロンタールの幹を使用する。屋根はチガヤの葉先を外側に向けて折り返しただけのもので、20年ちかくもつ。
Peo (二叉柱)の建設は、儀礼をおこない、好ましい形の hebu の木を見つけるところからはじまる。これが首尾よく見つかると、木を掘り起こし、根を3本(4本?)のこして切る。切ったのこりの根、木などは、その場で燃やす。万一、燃え残しがあると、そこから災いをおこすと考えられている。柱のほうは柔らかい布でくるみ、根先を先頭にして、先端と後尾に一人ずつの男が見張りとして腰掛け、一緒に担ぎあげて村まで急ぎはこぶ。
朝食は白米にトウガラシ。10時まで写真を撮り下山。
Danga まで昨日とちがう道をとおり2.5時間。昨日出発前に訪れた家でふたたび休憩。
Danga でパッサール帰りのトラックをつかまえ、13時40分、Danga 発。約3時間で Bajawa 着と目算していたら大違いで、Boawae 到着は4時間後ですでに17時30分。
ここからが僕の運命の尋常ならざるところで、おりからのはげしい雨。トラックには、市場帰りの客がブタ、ヤギ、ニワトリから野菜、米俵などなどを積み込んでいる。これらの積み荷をはこぶため、Boawae からトラックは突然脇道へそれ、Boawae の市場へ向かう本通りからはるかにはずれたところで、手ぐすねをひいていたかのようにパンクの修理をはじめる。
こんなことは本通りでしてくれれば別の車を探せるものを、いくらか人通りのないところへ運んでおいておこなうのがここのやり口だ。クソ。
約30分、ようやく道をもどりはじめた途端、坂道でスリップし、あわや側溝にはまるところでまた停車。タイヤの交換をはじめる。
このままでは Bajawa 着はいつになるかわからぬ。夕食にもありつけない恐れがある。オカズ抜きのメシを食ってきた後だから、おいしい食事を食べられぬのはこまる。今後の戦意にかかわる。乗客無視のあてどないトラック修理にはロンボック島で泣かされている。だから、人情はもうない。
あっさりこのトラックを捨て、本道を目指して歩く。雨。すでに夜。荷物を背負ったまま、この沿道に立って、来るか来ないかわからない車を待つこと約15分で、バスがあらわれたときには、おもわずはげしい感激にうちふるえた。積荷をあちこちでおろしてゆく必要はない。これで夕食にありつける。
20時半、Bajawa 到着。3日間をほとんど無駄に引きずり回されただけで終わった。疲労だけが重くのこった。

家屋は棟上に船型の茅積をもつ。この茅積のなかに立ちあがる2本のチョンマゲは棟持柱の延長で、船は茅束を7段に積み上げてつくる


炉柱の脚部には Lipi とよばれる段状の小空間があって、食事を Lipi に捧げ、祖先をよぶと、柱をつたわっておりてくる

ロンタールの葉をまるめた器のなかにご飯、豚や水牛などの肉、ロンタール酒をいれて棟持柱に括りつける

トラックには市場帰りの客がブタ、ヤギ、ニワトリから野菜、米俵などを積み込んでいる
12月14日(日) 晴 Wangka
この数日をどう表現したらよいかわからない。これを書いているのはじつは12月17日、Bajawa のロスメンでだから、この日の朝、食事に出かけようとしているところで部屋の戸がノックされ、悪魔が微笑んであらわれた、という情況がまさに当を得ている。
Boawae 出発前の PdK 所長との打合せでは、日曜日に So'a でパッサールがあり、Wangka 途上へ向かうトラックがある。したがって、土曜の午後、So'a へ向かえるように、それまで Boawae 周辺でかるく調査してこようというものだった。Boawae でのかるい調査の顛末はすでに記したとおりであるから、土曜の午後に Bajawa へ戻れなかった以上、Wangka 行きはもうなくなり、きょうはひとりで So'a へ出かけるつもりであった。So'a まではトラックの便がある。
この朝、ドアをノックした悪魔の主は PdK の所長に紹介された案内役のアドリアヌス・アリ、Riung の男。Wangka までの同行を買って出た初老の先生だった。彼の言うには、昨日はずっと僕を捜した。きょう Wangka 方面へ向かうトラックがあるから、これから Wangka へ行くだろう?と。
Wangaka 行きをすでに切り捨てていた僕は、いったん躊躇した。トラックを降りてからまだ16kmあるという話にうんざりした。しかし、相手の方に熱心にされて、引き下がってはおれない。いつのまにか荷物をまとめ、彼とふたりで出発する手はずとなってしまった。悪魔に魅入られたわけだ。
彼は順を追って、つぎつぎと約束を反故してゆく。いまからおもうと、老獪な手口に引っかかったと言うべきだ。所長との打合せでは、この男は Wangka へ同行したあと、いったん So'a へ引き返し、僕を So'a のしかるべき人物に引き渡す。トラックを降りる Poma から Wangka までは荷物を運ぶ者を捜そう。Wangka からの帰路はトラックがないから(So'a でパッサールのある日曜と翌月曜のみだ)、Wangka の村長にたのんで、われわれは馬に乗って帰ろう。というような具合であったわけだ。
雨期にはいると、5ヶ月間 Riung、Wangka は Bajawa との交通を断たれる。先日来の雨で、雨期入りと思っていたのに、きょうは晴れてしまった。悪いことはかさなる。
Bajawa 発10時。トラックは So'a の市場まで約2時間。市場には竹の仮設的建物が並んでいて、ここに売り手は露天をかまえる。
まだ閑散とした市場で降りる。村で食べるように干魚を買っていこうか、という僕の申し出を、彼はそんなもの重くなるだけだからおよしなさい、とたしなめる。しかし、タバコを2カートン買っていこうと言ったのには驚いた。約1万RPする。村への土産には高価すぎる。1カートン買う。
So'a から Poma まではイネ科植物(カヤ、ススキの類)の大群生のなかをトラックで40分。午後1時40分、Poma の市場(といっても何もない)でトラックを降り、歩きはじめる。
So'a から同行してきた Wangka の村人ひとりをつかまえ、アドリアヌスはどでかい自分のスーツケースを持たせている。僕の方は、自分の荷物を自分ではこぶしかない。
峠をのぼり、ここから緩傾斜の山道を約1時間。さらに野をこえ山をこえ、果てしなく長い道のりを歩く。これで Boawae の二の舞だったらタダじゃおかない、と呪いの言葉をはきながら。
イネ科植物の群生は焼畑耕作の痕だろう。いまは牧草地として水牛や馬の飼育につかっているらしい。十種類ちかくにのぼる相似した草のなかから、屋根葺きには Alang-alang(チガヤ)だけを選んで使う。
Wangka の村長宅にたどりついたのはすでに暗い7時ちかくで、結局20kgからの荷物をひとりで背負い、5時間歩かされたことになる。
村長宅でモッケイ(tuak)を飲もうというので、Ya と答えると、2壜買うと400RPだと金の負担を強いられた。
Rumah Adat は3棟のこるというので、まずは安心して寝た。身体中痛い。

So'a の市場には竹の仮設的建物が並んでいて、ここに売り手は露天をかまえる
12月15日(月) 曇 Wangka
村 Desa に3棟(手近に2棟)Rumah Adat がのこるというので、Kam. Waezea というところにあるものから見学に行く。これは出作り小屋程度の大きさしかなく、しかも、あたらしい材料はすべて竹。勇壮な家屋形式を想像していた僕は、村長の言う Rumah Adat という言葉をにわかには信じられなかった。
もう一棟のKam. Panrowan にあるものはもっと大きい。しかし、これとてもインドネシアの建築形式のどのプロトタイプでもない。多分、この村だけの形式であって、このために5時間の難行を経たのかとおもうと腹立たしい。造作も雑。しかし、儀礼や木の組み方、住まい方などは伝統的な形式が確立しているらしくて、なかなか細かい。約5時間かかって写真、実測、聞き取りを終える。
落胆し、憤慨しているこちらの心中を知らず、PdK のアリ氏と村長は、聞き取りのためにあす長老を呼んで酒盛りをしようと打ち合わせている。酒盛りは勝手だ。聞き取りといったって、もう聞くべきこともない。あすはいち早く帰るまでだ、と僕は僕で考えていたのだけれど、この宴会の費用を当然のことのように僕にもとめる彼らの伝統とは何なのか。
ニワトリ2羽4500RP、米4kg1200RP、モッケイ2壜400RP。夜の食事にこのニワトリのスープが出た。内臓ばかりで肉はない。
Riung の王家の領域は相異なる8つの言語圏にわけられる。この8つは文化的にもそれぞれ独自のもので、Wangka の住居形式は Wangka だけのものである。Wangka で多数をしめる Nbare Pau というクランは後インドに発し、スラウェシ島のウジュンパンダン経由でこの地にやって来たと伝える。

実測図:Lewo 平面

実測図:Lewo 梁行断面

実測図:Lewo 桁行断面
12月16日(火) 晴 So'a
長老たちを呼ぶというので待っていると、あらわれたのは昨日の調査家屋の家主ひとり。建築儀礼の聞き取りは、結局、村長ひとりが答える。この村長は頭の回転がはやい(すぎる)のか、ひとりで喋り続ける。しかも、彼の話しは混乱をきわめ、理解不能になる。空虚な言葉の洪水。
村長が手配してくれたのは馬ではなく、たまたま村にいた教会のジープ。ただし、彼の話しとちがうのは、このジープは Molu という峠の上の村までしか行かなくて、Bajawa 行きは夜になるという。PdK のアリは所長との約束を反故にして、So'a までつきそうことなく Wangka から直接 Riung に帰る。Wangka に残って、僕の金で買ったモッケイを飲んでいた。無責任男。
Molu から先、案内してくれたのは、たまたまジープに乗り合わせた中学生の女の子で、彼女がいなければ So'a 到着は覚束なかった。こっちとしては本来一人旅だから文句は言えないが、こうまでして Wangka へ行き、金と時間を無駄に使うことはなかった。
Molu から徒歩1時間で Poma の市場着。市場といっても、市場のない日には竹屋根のガランドウ建物が一棟あるきりで閑散としている。ここで約1.5時間、待てどもトラックはあらわれず、それどころか人間すらもとおらない。さらに約1.5時間歩いて、So'a に新設中の飛行場へ運ぶ岩石を河原から運搬するトラックに便乗して無事 So'a へ着いた。
So'a の副市長は誠意にとぼしい遊び人で、僕をしたがえ、村長宅に情報を聞きに行く称して家を出たまま、この家でブリッジをはじめる。要するに、これが目的だったらしい。僕の方は、早々に帰って(情報もかんばしいものではなかったから)寝た。
12月17日(水) 晴 Bajawa
So'a の中心は山のなかにある4つの古村からなる。しかし、このどれにもまともな慣習家屋はなく、聞き取りのほうも気力がうせて満足に出来なかった。
家屋の基本構造は Bena のものとまったく同じ。外壁の彫刻に赤い粘土を使った着色をしていることが目立った特色。この着色のために特別な儀礼があると聞いた。家屋はとくにその内部で傷みがはげしく、殺伐とした印象をあたえる。
午後、Bajawa 行きのトラックに乗り、早々に帰る。
ところが、何事もおとなしく済まないのが運命らしく、このトラックは約1時間ほど走った山中で異音を発して止まり、修理をはじめる始末。これをおとなしく待って、いままでどれだけの時間を無駄にしてきたか。運よく通りかかったトラックをつかまえ、あっさり乗り換えた。情に棹させば流される。

供犠柱 Peo にも近代化はおよんでいる
12月18日(木) 晴 Koli
Nagekeo 型の家屋をもとめ、Mauponggo へ。
朝、PdK を訪れる。所長のニコ氏は Ende 出張で不在。こうなると所員の実質的な協力は得られない。所員たちはいつものように協力的、ただし、これは口だけの話で、具体的な方策となるともう彼らの責任の外にある。儀礼的な挨拶だけして早々に PdK を後にし、県庁へ向かう。PdK の協力がダメとなると、頼りになるのは自分だけで、そうなると書類上の手続きだけは完璧に済ませておかねばならない。Sospol からあたらしく書類を発行してもらう。
午後1時、Bajawa 発。約3時間で Mauponggo 着。軽い気持ちでここまで出かけてきたけれども、市長の話を聞くと、ここでも古い家はダメらしい。
Desa Ululoga の家はすでに半分石造にあらためられた。Udiworowatu のものは昨年焼失した。Kam. Witu というところにヤシの葉葺きの丈高い慣習家屋が残るらしい。20日(土曜日)に市場へ行くモーター船があるからこれに乗ればよい、という話だが、それまで待ってはいられない。
悪運だけは強く、ここに市長宅のまえを Desa Witu Romba Ua の者が通りかかり、彼をつかまえ、海岸沿いを徒歩で行くという手筈になってしまった。すでに夕方5時、西方に暗雲ひろがり、昼食も食べていないというのに、また歩かされるのだ。村までは約4時間、道は平坦という話し(ダケ)。
実際には、急な峠をこえ、川をわたり、さらにしばらく歩いたところで(約2時間)大雨の直撃をうける。暗闇の中をずぶ濡れになりながら近くの小学校に駆け込む。寝袋も何もかも濡れた。気持ち悪いのを我慢し、この寝袋におさまって夜をあかした。
12月19日(金) 晴 Witu Romba Ua
約2時間、さらに峠をこえ、海岸の断崖をあやうくわたり、岩だらけの海岸線を歩く。昨夜、懐中電灯の光だけをたよりに、満潮時のこの難路をどうやって切り抜けることができただろう。雨がなければあやういところ。
Desa の村長宅に荷物を置き、約30分、山の中腹の村 Kam. Witu 着。斜面に沿って、Peo、Madhu がならび、一棟の丈高い家屋がある。Peo、Madhu 上には、人間の思考を象徴するという鳥の彫刻がささる。
Kepala Adat (アダット長)の所有するこの家屋は、Lio 族のものと似て、残念ながら Nagekeo 型ではなかった。Kepala Adat はアダットのことをよく話してくれるけれども、どこまでがアダットでどこまでが彼自身の創作かわからぬ。誇大妄想的なところあり。この家は、村でもっとも早く建てられたもので、すでに300年たつという彼の説明をかしこまって聞く。
小屋組に辻褄のあわないところ多く、何度か改修を受けているだろう。棟木は最近変えた。部材を勝手に切り張りして改造をくわえているので大雑把な印象をうける。礎石建ての柱は戦後の大工の仕事で、以前は掘立だったという。すべての柱を礎石建てにすることはゆるされず、いまも1本のみ掘立柱がのこる。しかし、こういう決まりがアダットのはずはなく、彼の創作だろう。束柱は床下までで、礎石建てのうえ、縦横に貫を通したもの。
半日で図面を採り終えることができず、最後は give up したかたち。中途半端な調査だった。家屋が本来のものでないので、気乗りもしなかった。
疲労と真っ黒になったタオルがのこった。悪夢の1週間。無宗教(インドネシア流に言えば共産主義)の僕もキリスト様の慈悲にすがるよりない。アーメン。

鳥の彫刻は人間の思考を象徴するという
12月20日(土) 晴のち曇のち晴 Ende
Witu 発10時45分、約4時間の航海で Ende 着。Pulau Ende(エンデ島)をすぎる頃から一陣の寒気おしよせ、風強く、波高く、暗雲広がり、おだやかな航海は一転して砕ける波をかぶりながらのただならぬ航海になった。この暗雲も Ende 入港時には去り、ふたたび強烈な太陽に照らされる。
ここ数週間というもの疲弊し、消耗していたため、すこしでもよい宿をさがして歩く。
Ende は Ruteng、Bajawa とちがって、都市が郊外にスプロールしており、歩き回るには広すぎる。通過する道の名を掲げたベモが縦横に走り回り、客の注文を聞いて道をアレンジする。この仕事が車掌の役割で、バンドンのベモとくらべて車掌の役割はずっと重い。いわば乗合タクシーで、小都市だけにどんな場所でもくまなく送り届ける。料金は100RPでどこの都市とも変わらず。

12月21日(日) 晴 Ende
完全休養日。手紙を書き、エアコンのきいた部屋でベッドに寝転がってすごす。果物と冷水の飲み過ぎで下痢。食欲もなし。

日曜礼拝にあつまるエンデ市民
12月22日(月) 晴 Ende
10時、PdKへ情報あつめ。PdKも所長の人柄によっていろいろだ。Ngada では書類の提示ももとめず、非常に歓待された。ここではまず、私たちの情報がどういうかたちで発表されるかをあきらかにしてもらいたい、と開口一番。いろいろ説明しても猜疑心が解けぬらしく、LIPI の書類を見せるとようやく安堵したかのようだ。
ここ Lio では東大のNさんと都立大のSさんがそれぞれ3~2年ずつ調査をしているけれど、彼らふたりはPdKに顔を出さなかったらしい。いらぬ官僚主義に巻き込まれるのはゴメンということか。僕の場合、短期間の調査だから官僚主義もいいことがある。
PdK のあと、Sospol で書類をもらい、いざ出発と勢い込んでバス停に行き、八方手を尽くしてバスを捜したけれども、とうとうつかまらなかった。しだいに体力の減退を感じ、ふたたび Wisma にもどって一日休養。あす早朝に出発できるよう、手配だけした。
詰め込めるだけ詰めるバスというのは人権無視のようだけれど、定員だからあすまで待てと言われるよりはまし。
夕方嘔吐。コーヒーの飲みすぎか。夕食は食べられず。

Christo Regi Katedral

Flores Theatre
12月23日(火) 晴のち曇 Moni
Wolowaru 行きのバスは7時前に定員となり出発してしまった。クリスマス休暇で帰省客多く、どのバスも満員だ。仕方なく Maumere 行きのバスに乗る。料金は Wolowaru まで1100RPのところ3000RPとられる。このバスは7時20分にターミナルを出発、途中バスオーナーの事務所へ寄り、定員のチェック。太った大柄の中国人は乗客名簿を見て、座席の番号と乗客名が一致しないデタラメさを車掌のフローレス人に向かってなじる。小学校の混乱が支配した(事実、小学校も出ていない人間だって多いのだから)現地人相手の、しかもバス停の混乱のなかで、小学校の班長さんに飛行機のような乗客名簿をこの中国人は期待しているのだ。車掌は先生の前に出たバカな小学生のように萎縮し、何一つ答えることができない。中国人はこれにますます腹をたて、とうとう手を振り上げ彼の頭を叩く。オマエ、名簿というのは何のためにあるんだ。この間、他の乗客たちはまったく無視されたままだ。オーナーは乗客を降ろし、座席を入れ替え、誤って乗った乗客3人を別のバスに移し替え、2人分の空席に乗るべき乗客をターミナルから捜してきて座らせる。約30分がこうして過ぎ、バスは定員の乗客を乗せて事務所を出発する。ところが、町はずれまで出たところで、待っていた客2名をさっそく拾う。まさにキツネとタヌキの化かしあいで、これらの客については彼らの懐に金がはいるという仕組みなのだ。
Wolowaru まで約3時間。役所で書類を書いてもらうのに2時間もかかり、さらに Kam.Koanara というPdK(教育文化省)によるお墨付きをもらっている村のある Moni に戻るのにトラックを待ち、Koanara 到着は4時。しかし、Koanara にあるのは古い家一棟。たしかに出来はよいが、疲弊したように建ち並ぶセン葺きの小さな地床家屋群のなかで余命を送るといったありさまだ。

車掌の仕事は乗客の管理だけじゃない
12月24日(水) 曇のち夕方スコール Moni
Koanara に残る唯一の伝統家屋の実測。家屋内の豊かなレリーフ。完成された構成。儀礼のための種々の装置。屋根の最上層にのぼるパフォーマンスで家主の理解を得る。こうした大屋根の Sao Ria(大きな家)に住むのはスク長(mosalaki と称する)の家族で、長男が代々血統を維持する。
家屋内に置かれた数々の石片のひとつひとつに儀礼の際には食事を供える。供えるべき石の多いこと。家屋の奥二隅、mangu と称する棟持柱の下、lena という1階張り出しの棚部分の隅、tenda-teo という棟近くのもやから吊られた供物用カゴの中の石(この石を watu wula leja 月と太陽の石の意味、wula-leja は日月神)。どこから入手したのか巨大な象牙が4本、家の隅に家宝として置かれている。
家主は旧村長で、現在はPdK公認の文化財管理者。村長宅を早朝に出たため朝食にありつけなかったが、この家で昼食を出してくれた。
夜、巨石文化名残りの石積み石柱群のなかで、セメントでかためた十字架型の近代風墓に蝋燭をともしていた。あすはクリスマス。
12月25日(木) 晴 Moni
村長宅は朝から教会に出かける。きょうは朝食にありついて体調十分。家屋実測の続き。まる一日家にこもりきりでクリスマスは終わる。東京の喧噪を思い出してハラリ。

クリスマスのおめかし
12月26日(金) 快晴 Moni
調査家屋3日目。村長のいる Kam.Watugana にはかつて Sao Ria があったというが、これは現在、柱のみ残る。この柱は香木で、100年経っても実用に耐える。Watugana の Bhaku は非常に多くのレリーフをもつ。ところが、このレリーフは白、赤、青とペンキを塗り、屋根はセンに代えられている。
12月27日(土) Jopu
午前中、Bhaku という納骨のための建物と Kebo 穀倉の実測。穀倉の屋根はすでにセン葺きで、約3時間ですべての作業を終える。就任7ヶ月目の元気で親切な新村長に送られ、12時すぎ、トラックでWolowaru着。市長宅で荷物の補充後、徒歩 Jopu へ。約1時間。道よし。ハロー・ミステールという子供の大群。ツーリス、ツーリスと呼ばれるたびに腹が立つ。
Jopu の村長も新任7ヶ月で、新任村長は概して親切。村長の案内で Desa Jopu 内の4つの Kampung をまわる。
Kam.Jopu には2棟の Sao Hubu Bewa(棟のあがった家)がある。形式は Moni のものと同じで造作は Moni より劣る。しかし、Moni ではゴミ溜めの真珠だったアダット家は Jopu では石積み、Bhaku、Kebo、他の古い家屋群のなかにあってマズマズの環境。
Kam.Nuapaji には同形式でやや小ぶりの Sao。
Jopu の起源地である Kam.Rangase には3棟の Sao Hubu Bewa。2棟はやや小ぶりで仕上げ劣る。残る1棟は Moni 形式とは入口部に変化があり、正面 Tenda の中央がわかれて、ここに階段(3段)がつき、この階段下に翼(船)をかたどった装飾板(扉下に付くのと同様の)がおかれる。
Kam.Wolobheto のものはこの Jopu 型。すでに150年近いという話をPdKで聞いてきた(が、これは信頼できない)巨大な家屋。これを拝見、と思ったところ、中から額に容れた書状をもった子供が出てきて、インドネシア語と英語で書かれたこの内容というのがふるっている。「この家を維持修復するために見学者に寄金を募る」とある。これが修復のために使われる金でないくらいのことはわかる。しかも、観光客相手の商売を僕にもしようというのだ。ということに腹を立てて(黙ってここまで連れてきて何もしない村長にも腹を立て)、結局、中は見なかった。これは相変わらず浅はかで思慮のない行為であった。惜しいことをした。本来なら、こういくべきであった。このような形で観光客から金をあつめる以上、寄金者の名簿はあるであろうか、とただし、また、県知事や市長はすでにこのことを知っているのであろうね、と念を押し、さらに畳みかけるように、私は市長からの書類を持っているが、それでもこういう形で金を払う必要があるだろうか、と言う。一軒で金を払うということは、他の家を見るたびに同様の金を要求されるということで、家屋調査は成立しない。が、これは後の祭りで、結局この家を見学することはできなかった。後で知ったことだが、この家主は現村長選挙の際に立候補して破れた、いわばこの新村長(彼はインドネシア人らしからぬ清廉潔白な金の使い方をし、また旧村長の汚職についてさんざん聞かせてくれた)とは犬猿の仲であるからして、村長が見ているだけだったのもわかる。そうとはじめから知っていれば、強引にねじ込んだものを。逃がした魚は大きいという喩えあり。
しかし、Jopu 独自の家屋形式は、この Lio 一般型の Sao Ria ではなくして、Sao Banga という。この住民たちによってプラフ型の屋根の家屋と考えられている蒲鉾屋根の家屋だ。かつて、一般住民のほとんどは Sao Banga だったというが、いまは Kam.Jopu と Kam.Rangase に各1棟残るのみ。Kebo という穀倉もかつてはこの蒲鉾屋根を載せていたらしい。が、いまはやはり2棟残るだけで、他は寄棟。これに対して、Bhaku(納骨堂)は Sao Ria 型の長大屋根を架したもので、いまでも多く残る。Moni の Bhaku との違いは、Peti(木箱の棺)の置き場所が Jopu では上から吊られていること。もっとも、Moni の Bhaku、Kebo はどこまで原形を残しているか不明だが。
洗骨再葬風習:死体はいったん埋葬された後、数年経って儀礼とともにこれを取り出し(儀礼の費用が大きいため、特定の者しかこれを成就しない)、洗った後、布でつつみ、木箱に移して Bhaku に置く。あるいは、死体をアレン(サトウヤシ)の幹でつくった棺桶に容れ、ブリンギンの木(榕樹/ガジュマル)に吊して風化させた後、木箱に移す、という者もあり。

就任7ヶ月目の元気で親切な Watugana の新村長一家と記念撮影

Jopu 地方本来の家屋は船形屋根といわれる Sao Banga

実測図:Lepa Benga 平面

実測図:Lepa Benga 梁行断面

実測図:Lepa Benga 桁行断面

遺体は埋葬された後、掘りだして洗骨後、木箱に移して Bhaku や家のベランダに飾る
12月28日(日) 晴のち曇 Jopu
Kam.Rangase の Sao Benga 実測。実測にのこのこ出かけたところ、昨日入れてくれた家の主である女性が内から閂をかけ、許可しないと駄々をこねる。言うには、昨日主人の許可なく家に立ち入り写真を撮った。で、彼女はヘソを曲げ、金を出せだの、入れないだの。2時間、外で作業ののち、家主は裏口から出て畑へ逃げたというし、集まってきた村人たちと口論のあと、裏口から押し入る。実測をはじめてしまえば、誰が文句を言おうと知ったことじゃない。鬼よりこわい調査許可証がある。
のちに得た情報によれば、彼女は未婚で、正当な家屋相続者となり得ず、親族のあいだで田畑、家屋をめぐるいざこざがあり、Suku長のあずかり、という形になっているとか。彼女がヘソを曲げたのも当然といえば当然で可哀想。
例によって昼食抜きで夕方まで作業し、引き上げる。

蒲鉾屋根のSao Banga 駄々をこねた翌日はご機嫌麗し
12月29日(月) 晴のち曇 Jopu
昨日の続き。きょうはご機嫌麗しく、昼食(キャッサバとご飯のお粥)を出してくれた。そのかわり、村長宅で朝食はバナナ1本と茶。昼抜きでも、朝ちゃんと食べねば作業はできぬ。すっかり肉体労働者の身体になった。
午後より Rangase の スク長(mosalaki)の Sao Ria(Lepa Hubu Bewa 棟の高い家)実測はじめる。
村を歩いていておもしろいのは、こんな辺鄙な土地なのに、よく世界一周ですか?と訊かれることだ。気宇壮大というか、井の中の蛙というのか、世界の広さと自分たちの置かれた位置を知らない。

実測図:Lepa Hubu Bewa 平面
12月30日(火) 晴のちスコール Jopu
Sao Ria 調査。当主家族は午前と午後にココアとクッキー、昼食には鶏を殺しふるまってくれた。いたれりつくせりの気持ちよい調査。こちらの質問には律儀に、正直に答えてくれる。今年10月の屋根葺き替えに際して、豚9、馬4、羊1、犬4、鶏30羽を殺したというだけあって、かなり裕福な家柄。
夕方より激しいスコールで、ぬかるみのなかを Jopu の村長宅へ戻る。

実測図:Lepa Hubu Bewa 梁行断面

実測図:Lepa Hubu Bewa 桁行断面
12月31日(水) 晴のち曇 Jopu
午前中、Sao Ria の調査。この日も鶏を殺し、昼食をご馳走になった。午後、穀倉2時間の実測。Jopu に戻り、夜8時まで Bhaku の実測。
大晦日。あすは新年。本来なら今頃 Timor の Kupang のはず。近隣のガキども多く村長宅にあつまり、画面の見えない声だけのテレビを見つめる。9時過ぎ、疲れたならどうぞお休みください、と言われて寝袋にこもる。やがて、カセットを弄っていた村長は外部スピーカーとの接続を終えたらしく、騒々しい歌謡曲が明け方まで村中を騒がせた。かぎられたテープを繰り返しかけるので、どうにか眠りについても、目が覚めると同じ曲が執拗に鳴る。明け方5時にようやくこの喧噪がおさまり、ここではじめて、これは新年を迎えるための新しい儀式なのだと気が付いた。
現在、1円は約10RPだから、日本での物価を説明すると桁外れに高くなってお話にならない。1kg350RPという米の値段は、日本では2500RPになってしまう。ところが困ったことに、村人の多くは換算レートがその貨幣のもつ価値だと認識しているから、例えば1円は10RPである。だから、日本人はインドネシア人より10倍豊かである。これはまあよいとしよう。1ドルは1600RPもする。だから、米国人はインドネシア人の1600倍も豊かである。このドルには日本の円もかたなしで、1ドル160円ちかいから、米国は日本よりまだ160倍豊かである云々。彼らの頭はカタイから、そう思いこんでいる人間にいくら説明してやったところで、本当の理解には至らない。
また、こういうのもある。村にはいって、世話になっている家で済まなそうにご飯を出す。パンはありませんけど、こんな粗末な食事でよければどうぞ。日本人は(先進国は)パンとチーズを食べるものだと思っているのだ。同じように、ここでは木造の高床家屋は貧しい未開人の住まいであって、セメントの地床家屋が発展した、つまり先進国の住居であるという了解があるから、当然、日本の家屋は地床のセメント(石)造家屋のはずであると彼らは思っている。それで、日本人は高床の木造住居ですよ、と説明するのだけれども、彼らの現在の粗末な木造以外に木造家屋というものの概念のない彼らにとって、いくら説明をくわえたところで理解には及ばないだろう。
こうして、この一年は終えてしまった。

実測図:Lepa Hubu Bewa 詳細

おかげさまで、Rangase ではいつも気持ちよく調査ができました

実測図:Kebo 穀倉

実測図:Bhaku
1月 1日(木) 快晴 Nggela
おせち料理のかわりは山盛の油炒めご飯と豚の内臓のソト。この内臓は管ばかりで食べる気がしないから、ご飯に汁だけをかけて胃に流しこむ。この気候では雑煮を食べたいとは思わないけれども、日本の正月の寒々と人気のない広場や通りを思い出す。人生60年として60回正月経験がある。そのうち半分はもうす過ぎてしまったし、3回は(フィリピンの時をいれて)パスしてしまった。20分の1だから結構大きい。
起床5時。もっとも3時頃から音楽にうなされていた。早朝、畑まで木の葉の採集に行く。たった1枚の葉のために村をはずれ約30分も歩く。帰宅後、昨夜実測の Bhaku のチェック。9時半、Jopu の村長に別れを告げ、本通りまで村を降りてバスを待つ。約1.5時間待ってバスは来ず、荷物を担いで歩く。Nggela までは途中バスの終点 Wolojita まで約1時間、Wolojita より畑(つまり山)のなかを1.5時間。これはもう近いうちだろう。
Nggela の村長は新任4ヶ月で親切な老人だ。けれども話に聞いていた古い家屋ばかりの家並みというのはなくて、Suku内のまとまりが得られず、朽ちるにまかせた Sao Ria が一棟あるばかり。なかにはいると、筋交いの補強があり、炉以外の設備のないまったくのガランドウにちかい外観だけの建築。一般に海にちかい村はココヤシやロンタルヤシを多用するため加工は粗雑で洗練を欠く。ココヤシ、ロンタルは堅く繊維が荒いから彫刻もない。
Nggela にはヨーロッパの観光客が多い。ドイツのテレビ局が布作りの取材に2度訪れたというから、そのせいだろうか。布以外には訪ねるべき価値がない。1日苦労して無駄についやした。

元日の記念写真。Jopuの若き村長(背後)は数年前に死亡。毒殺の噂も、、

Nggela に行くものの朽ちるにまかせた Sao Ria が一棟あるばかり
1月 2日(金) 晴のち雨、豪雨 Maumere
早朝 Nggela 発。約2時間で Wolojita 着。すでにバスは出発した後でアテのない2台目を待つ気もせず、Wolojita を出る。Wolojita でケンカの挙げ句、腕を槍で刺された老人を Wolowaru に運ぶ一行の後を追う。椅子を担架にくくりつけ、怪我人はこの椅子に腰をおろし、これを6人の男が担いで運ぶ。黄門様のお通り、、、呆けたような老人の顔。
Wolowaru の市長邸へ行くも家主一家は正月休暇で Ende へ行ったということで、こうなるとこの家からのあらゆる親切は期待できない。家を預かる夫婦は汗だくで現れたボクを黙って見守るばかり。
荷物を預け、近くの村 Lisedetu へ向かう。ここは街道沿いの村で、バスの車中から棟の高くあがった Sao Ria とその前面広場を囲む4棟のやや小型の同形家屋が印象的だった村。しかし、家屋のほうは紛い物にちかく、実測するまでもない。気力も失せていたので助かった。
中心家屋は Jopu 型の入口階段。床高、軒高、天井高、扉高、すべて大きく大ぶり。前室空間は本来の Bilek というよりも、天井高く奥行きのあるためにホールにちかい。屋根が風圧で倒壊するのを防ぐため、妻側に筋交いをいれて補強。厚生省の指導の成果あって、側壁には明かり取りの窓が設けられた。建物自体よりも Watu Wula Leja (月と太陽の石:祖霊の象徴)にかんする聞き取りのほうが興味深かった。
夜9時のバスで Maumere へ。12時半着。バス酔いか、吐き気と眠気と戦う。プラフで夜を明かしたときのような。

Lisedetu は街道沿いの村で、バスの車中から棟の高くあがった Sao Ria とその前面広場を囲む4棟のやや小型の同形家屋が印象的だった
1月 3日(土) 曇・雨 Maumere
Maumere は海岸に開けた町。Ende のように傾斜地にスプロールした閑静な佇まいはないけれど、町中心の店の多さは Ende並。インドネシアの地方店はどこでもそうだけれど、店のほとんどがいわゆるよろず屋で何でも取りそろえているかわり、どの店へはいっても並んでいる物は同じだ。Ende や Ruteng に感じられる文化の香はなくて、商業都市。フローレス島に着いて以来、人びとが誠実であることに(外国人相手でも)感心してきたのに、Maumere に着いた途端に、夜行バスでは正価より高い料金を請求されるし、町で乗ったベモは2倍以上の言い値で、ジャワを思わせる姑息さ。こちらの姑息さはそれ以上だから彼らに負けてはいない。
朝より役所めぐり。Sospol で書類を請求する傍ら、Bappeda、PdK で情報収集。Sikka には伝統住居といえるものはすでにないらしい。PdK の文化担当の案内で Maumere より約6km離れた丘上の博物館 Leda Lero(高いところにある太陽の意)に行く。キリスト教大学に付属の施設で、玉石混淆、宝石あり、貝あり、化石あり、骨あり、布あり、彫刻あり、で学術的に整理する博物館員はいない。収蔵品は多い。Polisi に報告。午後より約8km離れた Kewapante市の副市長宅へ明日予定の Hewokloan 訪問のための報告。ここで、すぐ近くの村に茅葺きの伝統家屋がひとつ残るというので行ってみると、これはコンクリートの束柱に木造をのせ、セン屋根の疑似モダン建築。1931年建設の当時カピタンの邸宅。これを伝統家屋と呼ぶようでは Sikka 文化もない。

1931年建設のカピタンの邸宅、らしい
1月 4日(日) 曇 蒸暑い Sikka
8時半、ロスメン発。ベモ約45分でHewokloang への近道入口で(強制的に)下車。Hewokloang は谷を挟んだ向かいで、いったん川まで山を降り、再び登る。約40分の徒歩。これは便利な場所に属するだろう。しかし、村は蚊が多いほか取り立てていうほどの香りなく、PdK の情報も(あるいは Sikka の状況故)アテにならない。慣習家屋はあるという話でその家を見に行くと、高床セン葺きの(古いだけの)非文化住宅で、全体の寸法をとり、適当に聞き取りを済ませて村をあとにした。
Maumere に戻り、その足で Sikka へ向かう。王の家はすでに壊れ、その骨組みだけが残るという話だったから、この地域で伝統住居に巡り会う希望ははじめから持っていない。首都の Lela と Sikka にポルトガル時代の教会(フローレスでもっとも古い時期の)が現存する。Lela まで Maumere より約45分。ここで昼寝中の市長を強引に起こし、手紙をもらう。旅行中の感触では一般に日本の評判はよく、インドネシアのよき協力者、日本人は勤勉で熱心という相場になっているから、こういう時、仕事熱心のあまり日曜日に休養中の市長を起こすということも、なるほど日本人ならば、となって大目に見られる。どころか、非常に協力的であった。
Lela の教会 St. Maria Imakulata は1896年ポルトガル時代にスペイン系の教団(イエズス会)によって建てられた。例の如くセン葺き。センが高級な建物に用いられるのはこういうところに起源するのか。教会の構造を見る目がないから記念の写真だけ。教会の横に牧師館があり、これが高床で四周にテラスをもうけた洋館。こんなものまで慣習家屋(古い家)の範疇にはいってしまう。
Sikka まで約3km、海辺の村。王の家(?)とやらはロンタルヤシの丸太を使った高床妻入の建築だったらしい。コンクリートの入口階段と柱、貫が倒れた状態のまま無造作に残る。話をまとめると、ボルネオの Dayak族のロングハウスと構成が似る。建築はスンバワ島の宮殿などと同様の通し柱、礎石建ての通し柱を貫で固め、一気に建て起こしたようだ。現存したとしても、さして目を見張る状態ではなく、仕上げの粗い合理の建築であったに違いない。
教会 Ignasius Loiola の状態はよい。1895年12月24日と記銘の石が入口左の壁面に据えられている。屋根は当初セン、海岸のためこれはすぐに腐食し、現在はオランダ時代(?)のセメント瓦。現場製作のもの。内壁には、近年の改修だろうけれど、Sikka の腰巻きのモチーフが描かれ、よく維持されている。Lela のものより軸組も上等。ステンドグラスはアールデコ。
Sikka でエドムンドゥス・パレイラという日本語をよく話すインテリ老人の家に泊まる。彼は元教師、教会のオルガン弾き。日本の歌をいくつも覚え、日本時代の思い出という本を自費出版している。伝説では Sikka族の起原地はどこですか?というボクの質問に、インドシナ半島に起源するマレー族移民のひとつの集団、という学術的お答えでまいった。山の上から、天からという神話と、教科書にあるこのあたらしい神話との相違は何だろう?
関係のなかったふたつの物を結びつけるところから問題は生じる。インドシナとフローレスを結びつけ、天上界と地上を結びつけ、神話と教科書を結びつける。個々の物をバラバラのカテゴリーにおさめておくかぎり問題の余地はない。分類し、結びつけるところから今度は歴史がはじまる。ヒトはサルとおなじ霊長類に属する。霊長類は魚や鳥ではなく哺乳類である。これは分類であると同時に、歴史/起源を暗示している。歴史とは分類する作業である。

Hewokloang に残る慣習家屋


Sikka王家のロングハウスもすでに廃墟

Ignasius Loiola教会, Sikka


Edmundus Pareira 夫妻
1月 5日(月) 晴のち曇 Kupang
蚊はいないというパレイラ老人の話だったが、夜のあいだ中、蚊に悩まされる。村の水道が壊れて昨晩はマンディもできなかったから身体中むず痒い。
Lela でバスをいったん降り、教会の再撮影のあとマウメレへ。ロスメン・ボゴールの息子にカメラを売るようにせがまれる。しかも安く。
午後2時半離陸。フローレス島は厚い雲におおわれすでに完全な雨期。空路クパン入り。クパンでもっとも高級なササンド・ホテルへ投宿。AC、湯付きの部屋でやっと正月になった気分。痴呆のようにすごす。
Adat(慣習)と伝統は本当はちがう。「伝統」は新しいものに対して古いもの、死んだもの、あるいは実用をはなれて生きるものの意だ。こう考えると、伝統の維持というのははじめから逆説でしかない。伝統はいつの時代にあっても過去に失われたものとしてありつづけた。これに対して、アダットは外の世界(同じ仲間たちの住む空間の外にある世界)の習慣に対して土着の習慣として時代のなかで生きていた。これは仲間であることをしめすアイデンティティの表明でもある。だから、アダットは形を変えても現在でも生きている可能性がある。マンガライの Ruteng 村で見た、形のみふるい形式に則ったまったくあたらしい構造の家屋をアダット家(慣習家屋)と呼ぶのがそうだ。アダットに則った儀礼をおこない、村人たちの社会の存在証明としてこの家屋は建てられている。古いものと新しいものとの区別がまだあまりなかった時代、これは慣習ではあっても伝統ではない、と考えていいのか? 伝統はつたえ、受け継がれてあるものの意で、現在でも受け継がれるべくある。これが死んだものを意味すると考えるのはたんに受け継ぐべき方法に問題があるからではないか? 伝統はいつの時代にあっても、過去から受け継がれるべきものとしてありつづける。

1896年建設のSt. Maria Imakulata教会, Lela

1月 6日(火) 晴 Kupang
11時までホテルの浴槽で何度も湯につかりながらすごす。手紙を書き、日記をつけ、他にすることもなし。キラキラと光り輝く海をエアコンの効いた清潔な部屋からながめる。たかがホテルに感動してしまう。
11時より行動開始。PU(公共事業省)へ行きラムリ君と再会。荷物を彼の家へ運ぶ手はずをととのえ、県庁へ調査許可の申請に行き、書類の出来上がるのを待つかたわら、警察へ報告、さらにPdK(教育文科省)で情報収集、昼食、これだけを終えて県庁にもどる。ベモは町中あちこちと迂回し到着は2時15分。所員は帰宅していない。なんとか室内にはいろうとしていると警備員がやって来る。
「どうしたのだ?」
「書類がほしい」
「もうみんな帰った」
「鍵はどこにある?」
と、すったもんだした挙げ句、諦めて帰ろうとすると、
「ちょっと待ちなさい。いま鍵をもっている人間に電話したところだから」
この役所にもちょっとは話のわかる人間がいる、と感心しながら待つ。ところがどっこい、彼が呼んだのは警察だったのだ。いかついふたりの男が現れる。すでに半分逆上していたため、これを見て100%怒ってしまった。あの物わかりのよいデブの糞オヤジめ! はじめ警官とのやりとりを横からうかがっていたこの男は、僕の剣幕のただならぬのを見てどこかへ消えてしまった。警官は僕を署へ連行しようとする。こちらは動かぬ。
「連行するなら書類を見せろ!」
ここらへんで彼らは僕が外国人であることを察したらしい。態度が急に変わり、こちらの書類を見せろと言う。警察で先刻もらったばかりの判子のある書類を差し出す。
「どこから来た?」
「その書類を見ればわかる」
「目的は?」
「書類を見ろ」
「調査なら警察に報告する義務がある」
「書類を見ればわかるだろう」
とやっているところへ、先ほど判子を押してくれた警察の上役があらわれ、
「どうしましたか?」
事情を話す。
「この人は日本の学生でさっき警察に報告に来たばかりだ。インドネシア語が十分通じないためにお互いに意思の疎通に支障をきたしたのだろう」
と、この警官のおかげで助かった。もっとも、こうした事件を楽しんでいるところもあるが。異邦人は気楽だ。日本だって役所は時間通りに閉まる。温情の欠片もないのは日本の方が上。

11時までホテルの浴槽で何度も湯につかりながらすごす。たかがホテルに感動してしまう
1月 7日(水) 晴、夕方一時雨 Kupang
PUの所長に会い、各支部宛の紹介状をもらう。「君の考えるところでは伝統住居の将来をどうみるか聞かせてほしい」と言われ、こういう難しい議論をインドネシア語で話すのは大変だ。日本語さえ覚束ないというのに。要は、住居はたんに住むための器ではなく生活の反映によって形づくられるものである。これは住居の調査が建築物の調査では成り立たないということと同じ意味で、住居の象徴、機能、儀礼など社会内部での意味がもとめられる。意味を失い(機能をではなくして)形骸化したものはやがて捨てられるだろう。伝統住居とはこうした社会と住居とが安定した関係を打ちたてたいわばクライマックスにおいて生まれたものである。したがって、社会が変化し、この対応関係が崩れつつある現在、住居が変化するのは仕方のないことである。この変化を住居の面だけから留めることはできない。すると、伝統住居にはふたつの可能性が残る。
ひとつは地域を指定した保存の措置であり、これは学術的あるいは観光資源としての価値を目的とするものである。技術的には建築的に正確な保存修復の必要性。もうひとつは、風土に適して発展してきた住様式の評価である。一般的傾向として、この地方では伝統的な木造高床建築は発展の可能性を与えられずに切り捨てられ、ジャワ、ヨーロッパ伝統のセメント(石)造(屋根に波板鉄板を葺いた)、地床住居に代えられつつある。この一般的傾向のひとつの結果が伝統住居の放棄、破壊をもたらしているのであり、木造=非近代的、石造=近代的という図式を覆さぬ限り、伝統住居の放棄はすすむであろう。したがって、政策上の問題として、一般民家に可能な近代的木造(高床)住宅のプロトタイプを提示してやる必要があるだろう。。。というような内容をしゃべった。
伝統住居は現代の生活には適さないということだね、と念をおされたのが不気味に印象的であった。
その後、SosPol(社会政治局)へ因縁の書類を受け取りに行く。所員の誰もが昨日の事件のことを知っているらしくてじろじろと見る。やがて所長が僕を呼び。。。
1月 8日(木) 晴、曇、夜雨 Atambua
クパン発9時、Atambua 着午後4時。街道沿いに同形式、beehive を地上に伏せた建物がいまも多くみられる。方形に現代風家屋の裏にきまってこうした小型円錐家屋が付属している。住居としての機能を果たしていると考えるには現代風家屋とのギャップが大きすぎる。TTU(中北部ティモール県)にはいる頃から街道に沿って円錐屋根、4本柱の穀倉が多くみられるようになる。クパンやTTS(中南部ティモール県)の地床円錐建物が棟木をもたず、一点に屋根頂があつまるのに対して、この穀倉は小さな棟木をもつらしい。棟に木の幹(areng ヤシ?)を伏せて被せてある形式とチガヤを絞り込んでチョンマゲをふたつ棟上にのせている形式がある。街道に沿ってこの円錐形穀倉が整然と並んでいるのはあたらしい伝統か? 建築そのものはすべて比較的最近のものらしい。
Atambua はフローレス島の Bajawa に似る。雑然とした町の中心。しかし、インドネシアの地方のどこの町についても、さしたる違和感なく何年も住んでいる町のように溶け込んでしまえるのは、町の中心を構成する中国商店ゆえか。この中国商店は金太郎飴さながら、どこの町でどこの店に入っても、売っている物はほとんど同じ。石けん、化粧品、日用品、お菓子、薬、食品、衣類、サンダル、タバコ、カセット、その他いろいろ。ティモール島のクパンに来て以来、ここ Atambua でもオヤッと思うのは、店で買い物をすると、新聞紙できれいに包んでくれること。まるで日本のようで、インドネシアの他の地方の人間には真似できない。バンドンのデパートで包装を頼んだときの店員のぎこちない包み方を思うと、ティモールの店員指導は別。
伝統は無意識の行為である。伝統とは何か、伝統をどう継承するか、と意識するようになった時にはすでに硬直化がはじまる。伝統の素直な展開の道は閉ざされ、二進も三進もいかなくなるというわけだ。意識させるようなアナタが悪いのか、それとも意識するワタシがいけないのか。
1月 9日(金) 曇のち雨のち曇 Atambua
朝7時半、PdK。情報収集は学問の領域ではなく政治の領域に属する。LIPIからの書類は必需品。しかし、政治的であれば故、書類さえ整っていればしかるべく面倒をみてくれる。
北部 Belu の Lamaknen, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat には3つの Suku (ここではSukuは民族と置きかえてよい独自の言語をもつ)がある。Buna', Tetung, Kemak であって、彼らの慣習家屋はいずれも巨大な円錐屋根の高床建築であるらしい。これに対して、南部 Belu の Malaka では、住居は楕円形平面の高床家屋である。
PdK に続いて SOSPOL へ。ここの所員の案内で、KODIM と POLRES へ。さすが東ティモールに近いだけあって書類の審査はきびしい。書類のコピー代だけで3000RPもかかった。パスポート、KIMIS、警察、軍、LIPI、州のSOSPOLの全書類。これも中央からの書類さえ揃えばパス。こっちはすでに場数を踏んでいるから、こういうところはぬかりない。SOSPOLの書類発行に時間がかかり、11時までの仕事時間を延長してかれこれ12時ちかくまで所員一同のこってくれた。しかし、Lamaknen に行く車は既にない。出発は明日になった。
この書類を携え、Atambua に住む Tasifeto Barat の市長宅へ。キツネのような顔の、どの人種にも似ている(中国、ジャワ、オランダ、ティモールの混血という)不思議な顔立ちをした市長の義母と市長の帰宅するまでの約1時間無駄話をしてすごす。市長は若い伝統愛に燃えた男で、慣習家屋(本物の)の調査を吾が意を得たりと喜んでくれた。彼のインドネシア語は僕とおなじくらいか。日本人は魚をたくさん食べるのでIQが高い。昔、この地方の先生の多くは Atapupu(Atambuaの近くの港)の出だった。海洋民はみなIQが高い、という彼の説を聞かされた。Lamaknen より戻った後、調査の便をはかってくれることを約して家を出る。
Losmen に戻ると、外国人が泊まっているのに報告に来ないと警察がオカンムリだと女主人が愚痴をこぼす。ここの宿帳をつける以前に僕の方が早く警察に報告してしまったからだ。一般外国人は24時間しか Atambua には滞在できないということだ。
歴史 ― 多かれ少なかれ、世界の秩序を体系化する作業。その体系のなかで、自らの立場を確認する作業。。。という意味では、現在の歴史家(ヒストリアン)の作業は神話の語り手にちかい。ところで、書かれた記録がはじまって以降を有史時代、それ以前を先史時代という定義に従えば、記録(すること)は歴史を意味する。面白いのは「歴史家」は「歴史」に先行してあるということだ。フーコーが記録保存人(アルシヴィスト)を称しながら、なおも分類にこだわり続けたのは何故か?歴史家と歴史を分類するというのも要は同じか?
1月10日(土) 晴、Weluliは雨 Weluli
たかがお菓子とあなどるなかれ。
生津止濁,開胃消食,醒酒提神,化痰止咳,舟車勞神,嘔吐暈浪,常食有益
さすが中国のお菓子はすごい。もっとも肝心なのは、これは薬ではなくお菓子だということで、たくさん売れねばいけない。それで最後の一文がある。
9時、Atambua 発。PdKの紹介になる胡散臭い男が同行。彼は Weluli に住む所員。Weluli までの道は、ここ一週間の雨で所々田んぼのような泥濘。二度橋のない川を渡り、二度粘土質の坂道でトラックは立ち往生した。草を敷き、石を撒き、それでもタイヤは煙を吹き上げながら穴を掘るばかりで、乗客は車を降り、ロープを結びつけて全員で引っ張り上げる。黒い雲のたれこめた Weluli 到着は12時50分。PdKの男は料金5000RPの支払を僕に要求。これを断り、一人分2500RPをこの男にわたす。あとでこの料金は2000RPであったことがわかる。彼は要するに僕には何の役にも立たぬ腹黒いだけの男であった。くそいまいましい。
警察、軍に報告する頃から雨。雨の道はサンダルを吸い付け、泥をはね上げる。おまけに道はすべり、荷物が重いので、歩くのも容易ならざるありさま。雨期突入の村に来た。Kewar まで約8kmで、今日中に歩いて行くつもりであったが、雨で川が増水して駄目だということで、市長宅で一泊することになった。
この村に住む元知事、DPR(国民議会議員)を勤めた Loro(大王)の末裔の Bere Tallo 氏に会い、彼の所有する慣習家屋調査の許可をとり、この土地の文化について話を聞く。彼は4分冊の Lamaknen の歴史に関する本を著した(まだ出版できず)だけあって土地の風習にくわしい。頭の回転早くインテリ。Buna' の文化は婚姻風習(相続をふくめ)による限り、キサール島のOirata のものに近い。言語の上からもおそらく。

粘土質の坂道でトラックは立ち往生した。乗客は車を降り、ロープを結びつけて全員で引っ張り上げる

Kewar にある巨大な慣習家屋 Deu Hoto と石積みの bosok
1月11日(日) 曇 Kewar
市長のセクレタリスに伴われ Weluli 出発。他同行一人でカメラバッグはこの男に託した。途中、川を越え、車の通る緩傾斜の道を約1時間。ずっと登りで大変だと言われて、マンガライのような山道を想像していたから、これはハイキングにちかい。道が粘土質の泥濘でなければ文句ない。途中、峠の上から Kewar の慣習家屋が遠望できる。林のなかに亀の甲羅のような屋根だけが浮き上がってみえる。
Kewar は Lamaknen の中心。巨大な慣習家屋の前面に石積みの bosok (メシバ)、環状に石積みをめぐらした慣習会議(裁判)の場 mot、首狩りの首をかける柱 ai-manu、石の祖先像 aitos など、様々なヒエラルキー施設をもつ空間。
慣習家屋は巨大で中身がなく、体育館のような印象をあたえる。柱、梁、すべて木割が大きく、ディテールは雑。柱のすべてに彫刻が彫られ、壁板は迷宮(線が途切れてはならない)と乳房で埋めつくされている。おなじ巨大家屋でもフローレス島の Lio のものはもっと細やかで空間が豊かだった。この建物は、本来小スケールのものを引き延ばしただけで、中は本当の暗黒。寒々として人間の安心して住める空間ではない。とにかく他にないので実測をはじめる。
この村でやっかいになっている村長は軍人。いまだに村長の給料でなく、軍人の給料の支給を受けている。この親切な(ちょっと癇癪持ちの?あるいはちょっと精神異常気味といったほうがよいのか。Moa 島の村長息子にちょっと感じが似ている)村長の語るところによると、現在、王を標榜している Bere Tallo のいる Suku Loegatal は女のラジャであって、本当の男ラジャは村長の属する Tesgatal であると。それで、その昔 Suku Loegatal の者が王を名乗ったときに、Suku Tesgatal の男がこの王を刺したことがある。私の家族が Bere Tallo の家族を殺したんだ、と村長は誇らしげに語った。
夜、建築儀礼の聞き取り。

実測図:平面

実測図:梁行断面

実測図:桁行断面
1月12日(月) 曇のち雨 Kewar
実測の続き。一日中家にこもる。昼すぎより雨、さすがに寒い。
印度尼西亞日報という中国語とインドネシア語のチャンポンの新聞。

実測図:詳細
1月13日(火) 雨 Nualain
午前中、雨のなかで写真撮影。この体育館は写真を撮ろうにもフラッシュは広すぎて届かず。光の漏れる隙間すらない暗黒。
昨夜から降り続いた雨が昼近くにようやく止み、Kewar を出発。尾根を道は縦走して約1.5時間で Nualain 着。再び雨。
夕方より Nualain 村(旧村は道からはいった丘の上にある)の見学。4棟の人間的スケールの慣習家屋が残る。
| ① | Suku Monesogo | 1964年 | チガヤ、棟持柱、4本柱の変更 |
| ② | Suku Umametan | 1959年 | チガヤ、棟持柱、4本柱の変更 |
| ③ | Suku Belebuas | 1964年 | チガヤ、棟持柱、4本柱の変更 |
| ④ | Suku Leorawan | 1967年 | チガヤ、棟持柱、4本柱の変更 |
②はもっとも大きく、rai(王)の氏族が所有。妻側にアプローチの梯子をもつ点では Kewar の王家と同様だが、裏口はなく、この村の住居全てを通じて側面に第二の扉口がある。炉の(向かって)左手に家宝を置く小部屋が設けられ、現在、この部屋の扉は盗難を恐れてか、釘で閉鎖。①③④はやや小さく、ほぼ同形式同規模。一般住居のプロトタイプと考えられる。炉位置は nulal hoto(火の柱)の真後ろで、Kewar の王家よりもこちらが柱名称にふさわしい。4棟とも軒先は腐朽して落ち、棟は乱れ、トタンで補修。
感じのよい教会の司祭館?で手厚いもてなしを受け宿泊。外人の来ることは滅多にないせいか、どこへ行っても食事にかならず肉が出るのは(このためにニワトリを1羽屠殺するわけだ)客としてもてなされているためだ。外人客から何かせしめることしか考えないロンボック島、スンバワ島などの経験とくらべると雲泥の差。心理的にたすかる。

Kewar の王家。巨大すぎて屋内はまるで暗黒の体育館

丘の上の Nualain 旧村

4棟の人間的スケールの慣習家屋が残る
1月14日(水) 雨、曇、晴、雨 Nualain
昨夜来激しい雨。朝にはこの雨もやみ、一日中天気はめまぐるしく変わった。天空高くうなりをあげる風にのって、雲はすばやく流される。Nualain の村長の案内で約1kmほど離れた Ekin 村へ行く。粘土質の道は完全な泥濘で水田さながら。サンダル・ジャパン(ビーチサンダルをそう呼ぶ)は地面にへばりついて歩けず、裸足で歩く。これでも坂道は滑っておもうにまかせないほど。
Nualain の王家 Nai は Kewar の大王 Lolo とは別の系統である。東ティモールよりはじめに Leowalu に至り、そこから現在地に村を築いた。Dilun(ここにも慣習家屋が残る)はこの Nualain の分派。いっぽう、Ekin は Kewar からの分村だ。
Ekin にも慣習家屋は4棟残る。ただし、Kewar や Nualain のような凝集的な村落構造はなく、道をはさんで4棟が点在する。
| ① | Suku Dasi-gatal | ||
| ② | Suku Asutalin | 1979年 | 屋根 |
| ③ | Suku Monegoncet (Nai) | 1979年 | 屋根替え |
| ④ | Suku Monegoncet-tau-bul | 1979年 | 屋根替え |
このなかで③は王 Nai の氏族所有。他の3棟よりやや大きく仕上げも丁寧。壁面に祖先像を象った浮彫あり。この村つくりの祖先が建設というが、当時のものかどうかは不明。100年まえくらいまでの記憶、伝聞は現在も残り、確認できるが、それ以前のことはすべて神話の世界になってしまう。村つくりの祖先(10代以上前の)の建設と言いながら、扉を彫るだけのために3年かかったともっともらしい説明をしてくれる。この扉板を中国人が200万RPで買うと言ったが、彼らは売らなかった。先祖代々のものだから300万RP要求したのだ、と得意げに語ってくれた。これは先祖代々の文化財だから売れないと言うのならまだよい。文化財だから300万RPとれるという皮算用は悲しい。この私は精神健全、肉体頑強、体力無比、頭脳明晰でありますから3億円で売ります、と看板を下げて歩いているようなものだ。
①②④は材の仕上げも悪く、木組みも雑で、やや劣る。屋根は葺き替えて間もないせいか、すべて軒先まで整い、屋根をくぐるのにほとんど潜り込むような格好。竪穴住居をおもわせる外観。
Monegoncet 氏族の家屋を実測。昼食はマラリアでふせる Ekin 村の村長宅でふたたび鶏肉のご馳走。
夕方より雨がふり、暗闇のなかをスケートリンクのような道を歩いて Nualain へもどる。
この地域の特産はニンニクで、今年は雨のために収穫の多くが駄目になった。それでまだ1月というのに Musim Pelaparan(飢饉の季節)だ。朝から僕の寝泊まりする教会の司祭館にはトーモロコシの配給を受ける村人がならんでいる。司祭館での食事は外人客の僕のために特別豪華なようだ。ご飯(トーモロコシでなく)の他、おかず3種、バナナ、コーヒー。

Monegoncet 氏族の家屋を実測する

実測図:平面

実測図:桁行断面

実測図:梁行断面

調査を終えたのはすでに夜。暗闇のなかをスケートリンクのような道を歩いてもどる
1月15日(木) 雨、曇、雨 Weluli
夜半から例の如く激しい雨。風雨とも激しく雨のおさまった朝9時半まで司祭館にこもる。ここの教会の建物はこの地方でもっとも古いものであるらしい。ポルトガル時代に建設され、はじめこの地にはなく(Atambua?)、いくつかの土地を転々として、ここに移築されるに到ったという。インドネシアの他の教会の例にもれず、木骨セン葺き。
雨の止むのを待ち、丘上の Nualain 旧村(教会はこの小高い丘のちょうど下にある)の写真撮影。住居のならびに平行してある環状石積(慣習法会議の場)の一部は神聖であって、人間の登ることを禁じられている。理由は村人たちも知らず、昔からそうであったと言うにとどまる。こうした聖域自体はいくつもの地方的バリエーションのひとつで、位置がどこかということは問題にならない。目に見えない空間のヒエラルキー設定という行為のほうに問題がある。聖域の設定は俗域を活性化する。
11時、Nualain 発。途中、Ekin に立ち寄り実測の続き。聞き取りをしようにも話のわかる老人がいない。頭の悪い若者がひとりと、老婆と、何を聞いても知らないその娘。僕が彼らの立場だったら、やはり同じようなトンチンカンな答えをするだろう。日本家屋の各部の名称など、僕だって知らない。
「ここは何て言うの?」「居間」「だって、居間は現代の言葉じゃないの?」「あっ、そうか。じゃ、茶の間かな?」「これは何て呼ぶの?」「柱(はしら)」「柱は屋根を支える木で、床を支えるのは束(つか)って言うんじゃないの?」「ふーん」
夕方にはからなず雨がはじまる。雨がはじまると、川は増水し、Weluli には帰れなくなる。山の天候で、黒雲は走るように空を流れ、いつ雨が降ってもおかしくない。聞き取りはあきらめ、調査もそこそこに Ekin を出る。Weluli までは同行してくれる者もなく、荷物は自分で担がねばならない。道も知らない。約3時間という村長の言葉通りなら、Weluli 着はすでに日が落ちてからだ。泥濘の道を走るように歩く(サンダルでなく靴をはいているから)。途中、雨が降り出し、呪いの言葉を吐くと、見事に雨はやんだ。雨は多く、激しく降るけれども、天候運だけはよく、荷物を担いだ道中に雨に降られたことはフローレス島の Mauponggo で一度あるきりだ。約30分歩いたところで Weluli に向かうふたりの子どもに出会い、彼らに同行。休息なしの気違いじみた早足で約70分で Weluli 到着。
昼食を食べていなかったため、食べ物を買いに立ち寄った中国商店(村に2軒あるきり)で、家に泊まるようにすすめられ、そのまま徒食の身となった。まったく運のよいことに、この日、市長一家は Atambua へ行っていておらず、Bere Tallo は Kewar に登ったきりでまだもどっていなかった。この親切な中国人がいなければ、あやうく野宿となるところだった。
一日中垂れ込めていた黒雲から夕方には滝のような雨。これが山道だったら。。。

ポルトガル時代に建てられたという教会


Nualain 村。住居のならびに平行する環状広場 Mot

Ekin 村。首狩りの首をかける柱 ai-manu
1月16日(金) 曇 Atambua
親切な中国商店主は、Atambua へもどるもどる僕に記念品といって Lamaknen の織物をくれた。見ず知らずの人間を泊めてくれたばかりか、高価なお土産までつけてくれた。まるで竜宮城で、日本でどんな現実が待ち受けているのか空恐ろしい。日本の便りを得なくなってすでに3ヶ月以上たった。
ここ数日の雨で道はすっかりぬかるみ、昨日は Weluli まで来るベモはなかった。峠の上から約12kmを村人たちは歩いて戻ったという。ところが、この中国店の好意で、彼の所有するベモが Atambua へ行くことになった。
AKさんによく似た彼の娘婿が運転手で、後部車輪には日本軍にならったという自家製のチェーンが巻かれている。彼ら夫婦の子どもは7ヶ月、6月生まれだから(まだ見ぬ息子の)Aとあまり変わらないはずだ。そのことを話すと、この子の指は一本多いと言って掌を見せてくれた。右手の小指の外に枝分かれした指がある。中国人同士の結婚を繰り返すせいか、妊娠中の薬物のせいか。
妻を4年前に亡くしたという中国店主とその娘、6本指の子どもに見送られ、8時40分、Weluli 発。途中でこのコルトディーゼル100PCは座礁した。左後輪は車軸まで泥にはまり、腹をこすって車は身動きできない。インドネシア人の小間使いが泥たまりに這いつくばり、ジャッキで車輪を持ち上げる。彼は先刻、家の裏手で白いご飯だけの朝食を食べていた。悪路にさしかかると、彼は車を降り、先行して路上の石をどける。川に到れば、車より前に川をわたり、浅瀬を指示する。そして、車が動けなくなれば、この泥濘の路上に這いつくばり、素手で泥を掻き分けている。何かあるたびに罵られ、かしこまって言うことをきくのだ。たった一皿のご飯のために。犬を飼うよりヒトを飼う方が便利にきまっている。
3度、乗客たちは車を降り、ロープで車を引き上げる。2度、橋のない川を渡る。運転席の床から水が噴き上がる。約4時間で Atambua 着。運賃を払おうとすると、これもいらないと言われて、2500RP程度渡しても仕方ないと思い、最後まで親切を受けた。
Atambua の町を歩くと、あちこちから日本人だというヒソヒソ声が聞こえる。外人は滅多に来ない土地だから、一週間もいるとみんなが知っている。
Lamaknen で毎日のように雨にうたれ、寒い夜をすごしたせいか、風邪をひいたらしい。喉痛く、熱っぽい。両足の傷口はいつのまにか化膿してふくれあがっている。右足付け根のリンパ腺が腫れて痛む。泥の中を四六時中歩いていると、足の感覚は麻痺して、傷のことなどかまっていられないのだ。いままで使わずに我慢していた抗生物質(サワシリン)をのむ。この時期に病気などしていられない。時間がない。
クパンの Cipta Karya のバリ人プトゥが仕事で Atambua へ来ていて、ロスメンの隣室同士でばったり顔をあわせる。彼は僕の調査に興味をもっている。自分も民家調査をしたいからカルマン氏に手紙を書くという。この調査の目的や成果について、根掘り葉掘り訊かれる。答えることは何もない。照準もない。そこに山があるからだ。しかも、この山はなくなろうとしている。この変化を止めねばならない、などと大それたことを言うつもりはない。移ろいゆくものを凍結して見せること。
昔、住居建設は一世一代の大イベントであった。村中の人間のエネルギーがそこにつぎ込まれる。現在も慣習家屋の建設は続けられていることがある。しかし、人間の労働(時間)というものが商品化された以上、時間は別のことに向けられる。3年がかりで扉一枚の彫刻を彫るよりも、ラジオやテレビやホンダを買う方がよほど賢いというわけだ。

店先のテレビに集まる子どもたち。日本でヒットした「おしん」はこの頃インドネシア中の子どもの心をとらえていた。いつか自分たちの苦労も報われる。。。

後部車輪には日本軍にならったという自家製のチェーンが巻かれている

3度、乗客たちは車を降り、ロープで車を引き上げる。2度、橋のない川を渡る。運転席の床から水が噴き上がる
1月17日(土) 雨、曇、雨 Atambua
夜半より朝まで雨。昨日、Tasifeto Timur (Tasi は海、Feto は女で北の意、南は Tasi Mane で男の海)の市長宅を訪問、市長は急な呼び出しをうけ、クパンへ行っていておらず、車で案内してくれるという約束は反故になった。Lamaknen でもそうだが、会議で市長がいないとなると、たいていのことは成就しない。しかし、この市長宅に居候する所員が案内してくれることになった。
8時、Nenuk にあるボロ役所へ出向き、副市長に挨拶。各村宛ての書類はすでに一週間前に送付済という驚くべき手際のよさ。Naikasa村にあるふたつの小村(Dusun:日本の「字」にちかい)、Tetun族の住む Halituku と Kemak 族の住む Nufuak の視察をすることになった。
「近くだから行くとよい。この役所はすでに Naikasa村のなかにある」
という副市長の言葉を信じて軽い散歩のつもり。10分ほどで到着、と期待していたところ、10分ほどで橋のない川を渡り、乾期なら車も通るという道を約1時間。さらに脇道へそれ、泥濘のなかを約30分で目指す Halitoku に出た。これはもう山の麓にちかい。
ここには3棟の慣習家屋があるという小村長の話だったが、いずれも近年の改築。このうちの1棟 Wanameta氏族の Uma のみ見る。Lamaknen と同プラン(Belu 家屋の典型)の矮小化された姿。1年かかるはずのものを1ヶ月でつくればこうなるのであろう。部材名、室名のみの聞き取りで引き上げる。家屋正面に、水牛の角を掛けるという叉状柱 kakeu と垣根に囲われた小さな石積み fatu-hada-tuan(batu-susun-lama:古く・積んだ・石)がある。これも Lamaknen のものとくらべると、伊勢神宮と住居内の神棚くらいの差がある。
この Halitoku から約1時間もどったところに Nufuak はある。時折、小雨の降りしきるなか、泥と草のなかを歩き、水量の増した川を下半身水に浸かりながら渡る。
Nufuak 小村には2棟の Uma Luli (Rumah Pemali:神聖な家)があるが、これもごく近年のもの。プランは Bunak や Tetun のものとまったく異なり、4本の主柱が小屋組を支え、6本の束柱が独立に床を支える。縦板壁(壁板はすべて交換され、bebak やひしぎ竹を使用)の穀倉型建築。真束1本の円錐屋根のものと真束2本の棟をもった楕円錐屋根のものがある。家屋正面に小さな円形石積み bogos があり、儀礼の際に殺した家畜を供える。扉板は蝶番を使用、金物の把手をつけ、鍵をかけた超近代的なもので、室内には炉があるだけで特別な施設はない。男ははいって左、女ははいって右の空間分割があるのはスンバのものと同様。基本的な構造理念もスンバと同じか。
簡単な聞き取りで近くの車道からベモに乗る。Nufuak 発すでに15:30。このまま市役所の所員氏をうながし、Fatuketi村の村長宅を訪れ、Tenubot小村宛ての書類を書いてもらう。風邪をひきながら雨中を歩き、泥道と川とで全身濡れた。蚊取り線香は雨ばかり続くせいか、しけってすぐに消えてしまう。泥だらけの衣類も靴もこの天気では乾かない。

家屋正面に、水牛の角を掛けるという叉状柱 kakeu と垣根に囲われた小さな石積み fatu-hada-tuan がある。Halitoku

Lamaknen と同プラン(Belu 家屋の典型)の矮小化された姿。Halitoku

Kemak族の住む Nufuak には真束1本の円錐屋根のものと真束2本の棟をもった楕円錐屋根のものがある


Kemak の家屋は Bunak や Tetun のものと異なり、4本の主柱が小屋組を支え、6本の束柱が独立に床を支える。Tenubot
1月18日(日) 雨 Atambua
Tenubot 小村の調査。一日中雨。靴は昨日来ずぶ濡れでサンダル履き。泥道で一歩ごとに地中にくっつき、泥を跳ね上げる。サワシリンをのんでいるせいか、あるいは風邪のせいか、下痢。おまけに調査家屋(これ自体1982年に改修して、壁、屋根、床、梁、扉など代えたらしい。どこまで本来のものかは不明)の家守は愚鈍で、同じことを聞き返すと別のことを答えるからアテにならず。na'i (王)を名乗る老人は作り話が多くてこれも信用ならない。体調も天候も気分も悪く、不完全な調査をした。ちょっとこの地の Kemak族は1911年東ティモールからの移民組で本来の姿を知りたければ東ティモールへ行くより仕方ない。
雨に濡れながら夕刻ロスメンにもどる。時折、雨は狂ったように激しく降る。雨で涼しいのはよいけれど、何もかも湿って不快。衣類はおろか、鞄、靴、ベッドもシーツもだ。家族の夢をみる。MとH(Aは出てこない)と3人でロケットに乗っている。10、9、8、、、、もう少しで打ち上げ、このまま眼が覚めないかも知れないよ。

実測図:平面

実測図:断面
1月19日(月) 曇のち晴、にわか雨 Betun
Atambua発8時半。昨年、道路の舗装が完成する以前には、雨期のあいだトラックで丸二日かかったという道も、いまでは2時間の快適、確実なドライブ。Kayu Putih(ユーカリ)の原生林の目立つほか、道沿いに Kayu Jati(チーク)がまとまって植林されているのが目につく。ここでは1本5000RPにしかならないという話だが。
南部Belu平原は有名なティモールの穀倉地帯。年間2度のトーモロコシの収穫があるのはティモールではこの地方だけだ。Atambua で久しく見なかった太陽が Atambua を離れると同時に顔を出しはじめる。湿気った身体を精一杯太陽にあてる。これで湿っぽい気分を一新して調査がはじめられると思っていたのはしばらくのあいだで、Betun はジャカルタさながらに湿気の多い暑い土地だ。今度は身体中に噴き出る汗。ぎらつく太陽。自然は容赦ない。
南部Beluにはふたつの住居型があるらしい。ひとつは土着の Tetun 人の住居、もうひとつは東ティモールの Suai より1900年代になってから移住してきた Tetun人の住居。東ティモールよりの移住組は Kamenasa村と Kletek村のふたつの小村にいる。土着組はかつて Belu 全域の王都であった Laran村を中心に Malaka市全域に住む。
午後、Betun より約3km離れた Kamenasa村の見学。伝統住居は新築も含めればすべてが伝統的な高床形式であって、この点は Sumbawa Besar や Dompu に似る。屋根は Gewangヤシの葉を時に1メートルちかい厚さに葺いたもので、この屋根の重量感は日本民家をおもわせる。いわば新村だから集中的な集落形態は見られないが、こうした家屋が村の敷地内に割合整然と建つ。しかし、「古い家」というのは難しい。案内されたのは村で一番古い戦前の家屋。古いだけ整っているかというとそうはいかない。古い、つまり粗末なことのほうが多いのだ。海地性建築の常ですべて納まりの雑な作図のしにくい建築。村に一棟ある下賤な者立ち入り禁止の慣習家屋は生け垣で囲われたひときわ丈高い高床建築。とにかく禁忌だから構造の詳細はわからない。
はじめ村人(女性)たちがインドネシア語を解さないために難儀したけれども、好奇心旺盛な村人たちをぞろぞろ引き連れての調査で聞き取りはやりやすい。親切に案内してくれたのは高卒の(これは立派な肩書きだから、学部卒のIrやDrsと同じに、彼は自分の名前の頭に Bukas SMAと付け加えた)若者。午後、雨が降り、Gewang製の傘を借り受けてロスメンに帰る。この傘は Gewang の若葉を火であぶり、糸で結んだもの。

生け垣で囲われたひときわ丈高い禁忌の家

Gewangヤシの若葉を火であぶり、糸で結んだ傘
1月20日(火) 快晴、夕立 Betun
Umakatahan村、Kletek村とBetun近郊のふたつの村の見学。調査家屋をさがす。
早朝に Umakatahan の村長宅を訪れる。8時にちかいというのに、村長は睡眠中で目をはらして出てきた。昨日の Kamenasa では昼過ぎで村長氏は畑へ出ていていなかった。給料もない村長に時間通りに役所にいろというのも無理だけれど。時間に追われた調査はやりづらい。この不機嫌な村長と午後に会う約束をして、ひとまず約3km先の Kletek村に向かった。ところが、この日ほとんど一日を Kletek で費やしたために、Umakatahan はお茶を濁した程度で終わった。Kletek までは馬の後ろに便乗。
Kletek には3つの小村がある。本来の土着 Belu人は Rainain小村だけで、道を介して並列する Suai と Tolaran は1901年以降、東ティモールよりの移民たちの住む村。Belu の住居二形式、土着の矩形住居と東ティモールの楕円形平面の住居がここでは軒を接して並んでいる。昔、地上近くまで葺き降ろされていた屋根は軒先高く切りそろえられ、しかも葺厚は50-100cmちかいから、一見すると日本民家の復原家屋に似る。
たまたま村長宅の前を通りかかった誠実な小学校の先生の案内。暑くて何か行動を起こそうとするたびに10ずつ数を数えてからはじめるというような気分。図面採りどころではなく、呆然といくつも建ち並ぶ同型同大の家々を振り仰ぐばかり。とにかく、すべてが伝統型住居なのだから、こっちの選定基準が明確でない以上、注文の出しようがない。古い家(かならずしもこれが判断基準ではないが)といって紹介してもらった幾棟かの家屋を見る。両形式とも2本の棟持柱をもったいわゆる Belu 型家屋。土着のものは、この棟持柱が外壁際にあるために寄棟の矩形家屋。この正面妻側に高床のベランダ空間をもうけ、妻の庇を追加してあるので前後で非対称。東ティモール型のものは、北部Belu のものと大同小異のプラン。但し、平入りはなくてすべて妻入り。
Suai にある Yosep Lekitahuk の家 uma は1950年代のもので意匠もおもしろく、採図向きだったけれど、Kletek は Betun より遠いということでひよってしまった。概して古い家のほうが床が高い傾向にある。母系。

間取りの変化
夕方、Betun 近くの Belu の中心、旧王都の Laran 小村の物色。ここの住居と Kletek の土着型との大きな違いは、Kletek で一般的であった入口前付属の高床空間上に室内側から天井裏が設けられていたのに(この形式自体はBelu北部の住居では普通)、Laran では一般にこの天井裏を欠く。そのため、入口前の高床空間は小屋裏までの吹き抜けで間延びした印象をあたえる。
ところが、Laran の村はずれに保存されているかつてBelu全体を支配した王族の「聖なる家」ではこの入口部の高床空間そのものがない。したがって、建築そのものは前後で対称の整合性の高いもの。この家は20世紀初頭の建設らしい。居住者はおらず、建物は傷みひどく倒壊寸前。造作も悪い。
Laran でもっとも古い建物に属する1936年建設の P.Bauk の家では、棟木はこの高床前室まで延びておらず、この空間の扠首は宙に浮いた格好でとりつく。この前室部分は構造的にはまったく切れており、後年の追加か?
Betun に料理屋は3軒しかない。どこも似たようなメニュー、メニューの種類はひとつ。しかも、これが三度三度おなじもので、一日三回食べると三回ともおなじ食事だ。山盛りのご飯、上にのった歯の痛くなるほど堅い味付け肉、おなじ肉の細切れがはいったスープ、500RP也。これが嫌なら、町にたったひとつある屋台のビーフン・バソ 250RP しかない。

移民型の家屋 Dusun Suai

後ろ側の棟持柱は炉の手前にある

土着民の家屋は妻側屋根が切り立ってみえる。Dusun Rainain

棟持柱は炉の背後、外壁に接してある

入口前付属の高床空間に室内側から天井裏を設ける一般型。Dusun Suai

入口前の高床空間に天井がなく小屋裏まで吹き抜け。Dusun Laran

村はずれに保存されていたかつての王族の「聖なる家」。入口部のベランダ空間がないため、建築そのものは前後対称。傷みひどく倒壊寸前。Dusun Laran
1月21日(水) 快晴 Betun
Kamenasa の家屋実測。朝より午後3時まで。暑くてまいった。夕方より Laran の家屋実測をはじめる。

実測図:Kamenasa 家屋平面・詳細

実測図:Kamenasa 家屋桁行断面

実測図:Kamenasa 家屋梁行断面・詳細
1月22日(木) 晴 Kefamenanu
午前中に Laran の家屋調査。午後、TTU(Timor Tengah Utara: 中北部ティモール)県の首都 Kefamenanu へ向けて移動。Kefa の天気は下り坂で雲多し。Kefa 到着後、さっそく警察に報告。

実測図:Laran 家屋平面・梁行断面

実測図:Laran 家屋桁行断面
1月23日(金) 曇、雨 Kefamenanu
SosPolで書類申請。PdKで情報収集。この書類は部長がいないために12時をすぎても出来上がらず、待ちぼうけになった。PdKのエル・バラン氏の案内でKefa近くの村 Maslete へ行く。
TTUにあった旧Swapraja のMiomaffo、Insana、Biboki のうち、Miomaffo王侯領に属する。1月26日に会った Miomaffo Timur の市長氏によれば、この村の祖先である4つの氏族 Ato、Bana、Lake、Sanak(この村自体はSanak)は奴隷商人に臣下の民を売り尽くし、国土と国民をもとめて東方より来たという。この4大氏族は、はじめ Kiskasen(現在の Biboki の土地)に集まり、続いて Subun の Kiskasen へ移動、さらに Maumolo → Musi → Fatuknapa → Nimasi と場所を変え、Nimasi からの移転組。ひとりの Fetor(Swapraja Miomaffo の下に8土侯 Fetor)の下にあるこの4氏族の居住地は、Ato は Oenano、Bana は Tufue、Sanak は Nimasi と Maslete、Lake は Nillat。
Maslete の氏族の家は巨大。2本の棟持柱、4本の天井を支える主柱という組み合わせ。なかに Bi-Kaunan という老婆(bi は女の呼称、kaunan は蛇)が住んでおり、時に応じて蛇になったり人間になったりするという言い伝えあり。二日後にひかえた Natama Maus(maus 収穫、natama 容れる)という、今期の収穫をこの大氏族の下の22の氏族の人間が氏族の家に持ち寄る儀式があり、その準備に女たちが米を搗き立ち働いている。
アダットが強すぎるためか、この家の写真を撮ることも実測をすることも拒否され、為すところなく引き返す。PdKの案内役の説得の仕方が悪いのだ。
帰りに立ち寄った近くの村 Tufue では Michael Bana という名の Fetor(これら4氏族の長)を囲んで多くの村人(氏族長?)たちが会談中。日本時代の話をきかされた。
彼の兄はケンペイ隊に生き埋めにされ、顔を殴られ、あやうく殺されるところだった。歯は折れ、顔は変わったけれど、いまはよい。日本人がいなければインドネシアは独立できなかったであろう。だから、私はここでどうもありがとうと日本人であるあなたに言いたいなどと、ヤシ酒で酔っているのかしつこく言われる。こう礼を言われて、どういたしましてと答えるわけにもいかないし、こまった。彼はオランダ時代に人柄を見こまれて Fetor に任命されただけあって博識。ごく最近の政治問題などを訊かれても、こっちのほうが知らない。
オランダ人は名誉のために死ぬ。中国人は金のために死ぬ。だけど日本人は仕事のために死ぬのだろう?
確かにそうかも知れないな。僕もインドネシアにいて、やたらと日本人っぽくなったことを感じる。戦争中の日本人の風評を聞くたびに、この国での自分の行動と瓜ふたつなことを感じる。日本人はやるといったことをかならずやりとげた。この国ではできないよ、とあまりにあっさり言ってのける。出来ることを出来ないと言われれば意地でもやるさ。
10人で重い荷物を持ち上げさせる。出来ない。すると、日本兵が命ずる。ひとり減らせ。出来ない。また命ずる。ひとり減らせ。とうとうふたりになった。やっぱり持ち上がらない。ひとり減らせ。最後に残った人間で持ち上げることが出来た。
というお話。インドネシア人らしいや。

Maslete の氏族の家は巨大。写真を撮ることも実測をすることも拒否され、為すところなく引き返す

二日後にひかえた収穫祭にそなえて女たちが米を搗き立ち働いている

Tufue 村の穀倉の下では Fetor を囲んで多くの村人たちが会談中
1月24日(土) 晴 Manufui
PdK(教育文化省)情報によれば、Biboki の Tamkesi という山中の部落に旧ラジャ(正しくはケセール Kaisar で、swapraja ではなく tuan tanah であるらしい。道すがらに聞いた村人の話では、このケセールは雨を呼び、風をおこすことができる)の rumah suku (クランの中心家屋)があり、数年前に村人たちの力で修復をおこなったが、構造はまったく古いままで改造はない。
こういう話はたいていダメだな。
ケファ Kefamenanu より一日一度のバスで東の南ビボキ市 Biboki Selatan の首都 Manufui まで約2時間。主要街道をそれると、途端に道は悪くなって凸凹を繰り返す。この地域は、インサナ Insana とならんで家屋前面にかならず円錐の lopo (穀倉)がある。街道沿いにこの lopo が十数棟も建ちならぶとなかなか壮観だ。Manufui の市長に報告。ここで Tamkesi の属す村の村長と会い、村長の紹介してくれたインドネシア語を解さぬ老人(rumah suku の鍵をあずかる juru kunci)と連れだって出発。
歩きはじめるやいなや金を要求する青年があらわれたり、ベルトが切れ、これを直しているうちに今度は手が切れるという不吉な前途であった。
川に沿って(正しくは川のなかを)しばらく歩き、やがて本道(乾期ならばベモもかよう)をすすむ。道は緩勾配ののぼり。同行の老人に先立って村へ向かう若者のグループと歩く。
老人、女性はインドネシア語がダメだ。アトニのような地方語でも、大地域をしめる民族になると閉鎖社会の傾向があり、Dawan 語しか理解せぬ者が多い。日本人が外国語ベタなのとおなじだ。必要のない言葉はおぼえない。
さて、村へ帰るという馬に乗った青年とアタンブア Atambua へ小学校の教科書を取りに行くという3人の学生との道中で、道を急ぎすぎたためか、同行のはずの老人がいない。彼がいなければよそ者は村へははいれない、と青年たちは Tamkesi のアダットの強いことを懸念する。しかし、待てどもこの老人はあらわれず、道中、友人につかまってソピを飲んだくれているという話がつたわり、おそれる子どもたちを説き伏せ、単身 Tamkesi の村へ乗り込んだ。
Tamkesi は切り立って聳える大奇岩を背景にした岩山の村。Kaisar の住むというだけのことはあって、幽鬼ただようロケーションだ。
外国人は靴をぬいで裸足で村へはいらねば慣習家屋 rumah adat のなかを見ることはできないという変なアダットがまかり通っていて、仕方なく靴をぬぐ。裸足で溶岩質のゴリゴリした岩山をよじ登るのは、靴生活に慣れたわれわれの足にはこたえる。
この10メートルちかい小高い岩山の上に、荒々しく突き出た岩々に埋もれるようにして、いくつかの茅葺き建物がかたまる。奇観。
ところが、家屋のほうは、数年前の改造が功を奏して、なかは体育館の殺風景さ。外観は原形をとどめているというものの、これでは調査にならない。2本の棟持柱にささえられた北部ベル型の家屋。ベルのような高床がなく、地表に根太を配したひくい板床と地床の炉が同一屋根下にある。これはアトニの地床生活とベルの高床建築の折衷だろう。
村人にまともなインドネシア語を話す者がおらず、建物規模だけ測り、聞き取りもできず、村で一泊する予定を返上して、その足でManufui へ引き返す。Manufuiの市長宅到着は完全に暗くなってからで、たったひとりの道中。昼食とらず、村でもらったオレンジをかじっただけで往復5時間。家屋の実測中に得体の知れない虫(アリ?ダニ?)に素足をやられ、下半身全体に赤い虫刺され痕がのこった。
妻が出産前というなぜか暗い市長の家で一泊。

村へ帰るという馬に乗った青年と Atambua へ小学校の教科書を取りに行くという3人の学生との道中

Tamkesi 村

Tamkesi は切り立って聳える大奇岩を背景にした岩山の村。Kaisar の住むというだけのことはあって、幽鬼ただようロケーションだ

実測図:Tamkesi 平面 / Haufoo 断面

家屋の実測中に得体の知れない虫(アリ?ダニ?)に素足をやられ、下半身全体に赤い虫刺され痕がのこった
1月25日(日) 晴 Kefamenanu
親切で禿の Insana市長(彼は王の息子のひとりだ)直々の案内。運転手付きの調査ははじめてだ。氏族の家は十数年で取り壊すのが普通(本当?)で、その後、氏族員全員の相互扶助で建て替える。これは一同に会した氏族員の繁栄ぶりを見、互いの協力を確認しあう機会なのだという。それで、氏族の家の本当に古い建物は一棟もない。道沿いにある Nunmafo村の氏族の家を見る。ここで最大の氏族 Naisa'u の所有。1982年、扉前の6本の柱を除いて全面改築。中心の1本柱で棟木を支える構造。この地域の氏族の家にはこの1本柱のものと2本柱のものがあり、各氏族がそれぞれの伝統に則って造る。
簡単な聞き取りと写真撮影のあと、Insana の中心、Oelolok の王家へ向かう。かつて9本柱の華麗な穀倉があったところ。この穀倉は屋根落ち、柱は白蟻のために中が空洞となって、1983年に倒壊した。現市長と現存する老王はこの柱を再利用して穀倉を再建する計画。柱の中にセメントを詰め、、、
この知的な老王は忠実な伝統の再現を望んでいる。Nordholt のアトニ族の本を取り出し、書中にある彼自身の若い頃の写真を誇らしげにみせる。僕の持参した Masalah Bangunan 誌のコピー(なかに Insana の穀倉の昔の写真がある)を何度もながめ、口惜しそうな様子であった。
Nunmafo にもどり、約2時間で氏族の家の図面採り。予定を2日間短縮して、夕方のバスで Kefa にもどった。
足がかゆい。赤く硬化した皮膚のかゆみにひとつずつレスタミンを塗る。両足あわせて約50カ所。

かつてあった9本柱の華麗な穀倉の残骸

実測図:HaufooのUme Leu 断面

実測図:HaufooのUme Leu 平面
1月26日(月) 晴のち一時雨 Nimasi
8時半、Miomaffo Timur の市役所を訪れる。一通の調査許可証をつくるために、ここの所員は3時間かかった。市長との話も途絶え、タイプのキーをひとつずつ打つ物憂げな音を聞きながら、初夏の午後、南海の孤島で船を待つといった雰囲気であった。ようやく打ち上がった書類をもらい、以前 Oenenu村の村長を務め、現在、市役所に移転したばかりという親切な男(このテの顔にはよい男はいないと思っていたのに例外)の案内で Oenenu の旧村へ。3棟の慣習家屋がある。うち1棟は近年の改築。この1棟は中心1本柱の小ぶりな建物。扉は落とし込み板。他の2棟は棟持柱をもつ形式。うち1棟は半倒壊。鍵を預かる男が畑に住み、調査できず。こういうことはよくある。
Oenenu の旧村はほとんどが円錐屋根の家屋と穀倉。Oenenu から約1時間で Nimasi村へ。ここの物臭な新任村長に市長からの手紙を恭しくわたす。慣習家屋は王 Fetor 所有の大きな家が未改修で残る。これをあす見ることができると言われ、期待しつつ、白米に芋の葉っぱだけの食事を食べる。朝食をとっただけで歩き続け、空腹を耐えてきたのだ。アトニ人は思いやりがない。
ところがその夜、1970年に王の家を建て替えた時に、たまたまオランダ人夫婦が居合わせ、彼らも一緒に儀礼に参加したという話になった。よくよく聞けば、王の家はこの時に全部建て替えた新築。古い建物は残っていないよと平然と言う。この嘘つきでケチな村長のもとでの調査はかなわない。寝床に与えられたティカールを敷いただけの板ベッドで空中戦のような激しい蚊の羽音を聞きながら寝袋にくるまって寝た。風邪をひいたらしく身体の節々が痛く熱っぽい。マンディはおろか、顔を洗う水すら与えられなかった。クソ。キサール島の村で、エロ写真を壁一面にはった村長のマヌケた息子の部屋でダニに犯されながら寝たことを思い出す。あそこのベッドも布団がない板床だけだった。

Oenenu には3棟の慣習家屋(氏族の家)がある

1月27日(火) 晴 Soe
朝、旧村へ向かう。村長氏は人をつけてくれず、本人も案内する気配なく、ひとり歩き。道も知らねーのにだぜ。旧村といっても十分広く、屋根はすべて円錐屋根だから、このなかから慣習家屋を見つけ出すのは不可能にちかい。ひとりであちこち彷徨い、いくつか出会った家の写真を撮る。ところが、慣習家屋は家主が畑へ出ていてなかへはいれない。村長の案内を請うために新村へもどる。
僕「村へ行ったけれども家主が畑へ行っていてなかを見れないではないか!」
村長「そりゃ家主がいないのに家へ無断ではいることはできないでしょう」
僕(声を荒げ)「昨日、慣習家屋の調査はできるという約束だったろう?」
村長「しかし、俺は家主じゃないよ」
僕(コノヤロー)「調査できないならこの村にいる必要はないし、家のなかを見れると言うから旧村まで行ってきたんですよ」
村長「昨日、使いの者を出したけんどね。主人はもどってないんだろうね」
僕(こんな話その場しのぎの言い訳に決まっている)「肝心なのは家のなかをみれるかどうかであって、使いを出したかどうかじゃないでしょう。使いを出しても結果がともなわなければ要するに意味がないんで、弁解を聞かされたってしようがないよ」
こんなやりとりをし、気乗り薄の村長を引き立てて旧村へ向かう。紅茶と ubi kayu (キャッサバ)だけの朝食をとり。
一棟の慣習家屋の調査。約5時間をついやし、午後2時半に帰村。ふたたびご飯と葉っぱだけの食事をとり、タバコがまだあったら置いて行ってくれないかという村長に、お礼に渡すつもりでポケット入れていた時計のかわりにタバコ一箱を置いて村を出る。道案内はなし。
近道はひとりで歩くと余計時間がかかる。川に沿って行くという道は所々本当に川のなかを歩く道。川に沿いながら、トーモロコシの畑の中を柵を乗り越え歩き続けると、川は延々と蛇行し、いつのまにか元の所に舞い戻っている。川と思っていたのは、川ではなくて島をめぐる池のような案配だったわけだ。水はほとんど干上がっているので水の流れはない。20分前に道を訊ねたおなじ人に、ぐるっと一周した挙げ句、また出会い道を訊く。結局 Kefa まで2時間。村長は45分と言っていたけれど、これは例の誇大妄想だろう。夜行バスで Soe へ移動。

屋根はすべて円錐屋根だから、このなかから慣習家屋を見つけ出すのは不可能にちかい。Nimasi

中心柱のほかに4本柱の軸組構造をもつ。Maslete と Nimasi だけに見られる独特の構法

実測図:NimasiのUme Leu 平面・断面詳細

実測図:NimasiのUme Leu 断面
1月28日(水) ほぼ雨 Kupang
夜1時、So'e 着。念願の洗濯を終え寝た。しかし、この日は雨で、結局これらは乾かずにクパンへ持ち越した。靴も濡れたまま。
この濡れ靴を素足の上に履き、午前中に役所まわり。Sospol、PdK、警察と終え、すでに午後1時。雨雲いよいよ厚く、この分ではここ数日は Lamaknen の二の舞だろう。ここでの調査を延期して、クパンへもどる。クパンも雨。途中で渡った川はすべて増水して土色の濁流となっていた。
クパンの Permnasははっきり言って居心地悪い住宅。空間がない。水浴場は小さく臭い。借間人が家主と共同ベッド。雨が漏る。蚊が多い。若者の友人たちがしょっちゅう出入りしてプライバシーがない。だから、ちっとも休まらないのだ。はじめに会った時の恩を仇で返すのが悪いからというのと、手紙の受け取りのため、ここに居座っている。この三文長屋のような家に午後5時半着。雨。あすはサヴ島かロティ島へ出発の心算で荷支度をととのえる。Mからの手紙、バンドンのI氏(Nさんの加筆あり)よりの手紙を受け取り、久しぶりに(約4ヶ月)日本の様子を知った。トタン屋根に降りしきる雨音激しく、セメントの床は湿気をおびて気持ち悪い。洗濯した服も靴も乾かないままだ。
1月29日(木) 雨 Busalangga
旅の途中に時間をみつけて日記をつける。好奇心の強いインドネシア人のつねで、周囲の人間こぞってこれをのぞき込む。失礼という感覚はない。どうせ読めないと思うけれども、意識すると筆がとまる。考えてみれば、インドネシア人が物を書いているというところを役所以外では見たことがない。
日本へ行ったことのあるインドネシア人の感想に、電車に乗ってボーっとしている日本人はいない。みんな新聞や雑誌を読んでいる、というのがあった。新聞というのは東京スポーツかもしれないし、雑誌は平凡パンチのようなものであるかもしれないけれど。
インドネシアで調査に退屈したら飛行機に乗るにかぎる。空から地上をながめる。あたらしい土地に行く。これで麻痺した感覚を再活性する。料金はやすい!!
クパンは夜半より早朝まで豪雨が続く。朝6時半、小雨の中をオートバイで飛行場へ向かう。サヴ島行きは雨のため2日間欠航し、きょうもなし。したがって、調査地はロティ島に決まる。雨期の飛行機は流動的だ。
ベモでいったんクパンに戻り、精一杯贅沢な食事をとり、M宛の手紙を出す。小島に渡るといつ帰って来れるかわからない気になる。
ロティ島には山がない。空から見るロティ島は、ほとんど起伏のない土地のそこここが雨のために広範囲に冠水している。水田かとおもうと、幹線道路がこの冠水のまっただ中を横切っているからそれとわかる。ほとんど沼沢地とかわらない。雨を避けてロティ島まで来たのにここも雨。ロティ島はインドネシアの最南端だ。
Baa にある Lobalain 市役所に報告。頼んだことは聞いてくれるけれども、応対はそっけない。あとできくとサヴ島人で、クパンの公共事業省の副所長もやけにそっけなかった。これもサヴ島人。仕事は早いが身をかわすのも早い。
オランダはロティ島の統治に手を焼いた。そこで島民にソピ(ロンタルヤシの焼酎)を飲ませて懐柔し、18の小王国にわけ、互いを争わせて統治した。現在、この小さな島には6つの市 Kecamatan があり、人口 人を数える。将来、県 Kabupaten になるためには最低6つの市が必要。
この市長宅で偶然会った町会長のペンナ氏の親切で、彼の家で食事後、彼の娘婿のモナド人(上辺だけ親切で誠意ない、弁解は上手なくせに、行動は伴わぬ、得体の知れないモナド人)のオートバイに便乗し、南西ロテ市 Kec. Rote Barat Daya の Thie へ向かう。
「トゥアン ガソリンを入れてから行きましょう」
Baa から Thie まで約23km。約半分すぎたあたりで街道沿いにいくつもの伝統形式の住居が見える。Busalangga (北西ロテ市 Kec. Rote Barat Laut の中心)にさしかかった時に、激しい雨にあい、このモナド人はいろいろ理屈をならべて結局 Thie まで行くことはできなかった。彼の理屈はくどくどしく嫌味だ。
雨後、ここの市長宅に世話になることになった。彼はアロール島人。中国人的な顔の、それでも純粋ロティ島人という奥さん。ふたりとも知的で親切。なにも血縁関係がないはずなのに、4人の子供のうちひとりは白子だ。しかし、家庭はあかるい。

ロティ島には山がない。空から見るロティ島は、ほとんど起伏のない土地のそこここが雨のために広範囲に冠水している

旧Baa王家の邸宅

偶然会った町会長のペンナ氏の親切で、彼の家で食事後、彼の娘婿のモナド人のオートバイに便乗
1月30日(金) 雨 Busalangga
北西ロテ市には Boni という閉鎖的な村があり、ここまで行けば古い家屋は多くのこる(だろう)。しかし、約20km、雨期の期間、車の通行は不可能ということで、ここでは断念。かわりに Desa Netenai という約6km離れた村に巨大な(?)未改修の伝統住居がのこるという情報があって、この調査のために役所の所員ひとりと連れだって出発。
途中、Dusun Oetutulu で台風並の豪雨にあい、この村長宅で休憩。ついでに、この村のふたつの古い家屋を見る。ロティ島で、伝統住居そのものはいまでも建設されているから、外観だけでは古いかどうかの識別はできない。あたらしい(?)伝統住居というのは、多くの場合、近代化の影響で従来家畜空間であった床下を壁で囲い、地床生活をできるようにしてある。それで床上はほとんど機能をうしなって倉庫と化す。床上の炉もつかわれずに、床下に炉をもうけ、あるいは別棟の台所で調理する。こうしてみると、高床生活から地床への移行段階にあると考えることもできる。
Desa Netenai 到着は3時頃。先刻の豪雨で道路にも水があふれている。目的の Paulus Mbau の 家屋 ume はたしかに大きい。桁行の通柱2本のところ、ここは3本ある。しかし、棟持柱がなく、かわりに真束。棟木は垂木を貫通させるロティ形式で古い。あたらしいものはこうした棟木の納まりをとらずに、上下2本の棟木で垂木を挟み込む形式にかわっている。あかるい近代生活の普及で、薄暗い高床の建物内はここでもほとんど使用されずに、生活空間はかつて家畜の飼育場であった床下。蚊帳付きのベッドを置き、椅子をならべ、建物の外壁には窓をもうけ、デコレーションに新聞紙、雑誌の写真を隙間なく貼り付ける。それでいて、屋根裏は神聖だからのぼってはいけないなどともっともらしく言うところがおかしい。ともかく真束の伝統住居はないので、調査はあきらめ、簡単な聞き取りで済ます。
午後5時、家を辞す。ソピを飲んで気が大きくなったのか、やたらと雄弁になった案内の役人のかたるところによると、屋根裏にのぼると雷にうたれるといわれ、彼は畏れた。家人たちは金の支払いを要求したけれども、そこは学生だからと説得し、オレのポケットから5000RPを引き抜き、ソピを1本買ってこさせた。飲みつ語りつ、主人は屋根裏にのぼることをゆるしてくれたけれども、もう帰るというのでそれにしたがった。
こんなやりとりはロティの言葉でやっていたわけだから、僕の知るところではない。もっとも確実なのは、この男の酒好きと酒癖のわるさで、たんに酒と仕事をむすびつけたかっただけだろう。帰りが夜遅くになるからと急き立てる僕をそっちのけで、ここはオレの領内だから暗くたって大丈夫、といつまでも居続ける彼をうながし村を出る。
道は一本道といえども、ほとんどがひどい泥濘だから夜道も大丈夫などと言ってはいられない。彼はやたらとしゃべり、ウマの鳴き真似をし、途中の家で喉が渇いたからと茶をいれさせる。これを煽ってまた歩き出す。ロティ島では、腹が空けばどこかの家にはいって要求さえすればよい、と自慢げに言う。
7時半、ようやく市長の家にもどり、調査の報告。あいかわらず雄弁な彼。ふたたび心地よいベッドで寝た。
雨と泥濘のせいで、日本からもってきた靴の底はついに開きはじめた。喉が痛い。
風雨のため街道沿いの大木がたおれ、たまたま通りかかった小学校の生徒8人がこの木の下敷きとなった。車で通りかかった市長は彼らを Baa の病院にはこんだ。ひとりは車中で血を吐いた。ひとりは後頭部がつぶれて死んだ。4人が入院した。

目的の家屋はたしかに大きいが、棟持柱はなく、かわりに真束。調査はあきらめ、簡単な聞き取りで済ます

棟木にあけた穴に垂木を貫通させて固定する。ロティ島やサヴ島に特有の垂木納まり

あかるい近代生活の普及で、薄暗い高床の建物内はここでもほとんど使用されずに、生活空間はかつて家畜の飼育場であった床下
1月31日(土) 雨ときどき曇 Sunsa
市長のつけてくれた所員とオートバイで約13km離れた南西ロテ市の中心 Batutua へ向かう。本来なら当初の目的地だ。13kmはオートバイで1時間半、人間の歩行とさして変わらない。しかし、このオートバイは途中パンクのために走行不可能となり、結局オジェックに頼ることになった。道路の泥濘がひどく、道なき道を走る。市役所到着とほとんど同時にふたたび豪雨。激しい風が吹きあれ、あたかも台風。これだけ連日まとまって雨がふれば、日本だってすぐに浸水や土砂崩れがおこるだろう。雨期に車の通行が不可能なこの島の状態を未開だと言い切れるものではない。
市役所でつけてくれた所員ひとりを従え、Sunsa へ。Sunsa は Batutua と Busalangga のほぼ中間に位置する交通不便な閉鎖的村落。ロティ島のほとんどの村へはとにかく車道が通っているから(雨期のあいだ用をなさないにしても)、車道のない村は例外的な僻村ということになる。
途中の川が増水して渡れず、海岸まで迂回し、河口近くの流れの緩やかなところを選んでわたる。それでも水は股まである。途中立ち寄った古い家の写真を撮り、ここでピーナツとグラ・アイル(ロンタルヤシの樹液からつくる蜂蜜状の砂糖液)の昼食。Sunsa まで約2時間。
ここでも目的とする古い家はすでに修復(改築)後。壁はベニアにペンキで絵を描く。森で木を伐り、不揃いな板をつくるより、市販の一見美しく加工された工場製ベニアのほうが価値があるし、10年ごとに葺き替えねばならないチガヤやグワンヤシの葉よりもトタン屋根のほうが格が上なのだ。
古い建物ということで案内された崩壊寸前の家をそれでも伝統形式がよく整っているので調査することにする。Belu 型の(棟持柱のあるティモール島ベル地方の家屋形式)2本主柱家屋。平入りで平側にデッキをもうけている。他の家屋形式と同様で、この地方のプロトタイプらしい。
市役所から案内してくれた役人が僕のことを大統領の許可をもらった客人と吹聴したので(昨日の村で金を要求されたということがあり、そうならないように市長に念をおしておいた)丁重な扱いをうける。もっとも、水浴にもWCにも誘ってくれないのは、そういう場所のないことが普通の生活観念だ思っているからだろうが、これは困った。
ちょうど村で結婚式――婚資を払い、はれて嫁をもらいうける時があったために、この夜はロティ島の音楽と踊りを見物。ゴングと太鼓を巧みに組み合わせた心地よいミニマル音楽。このミニマルと日本的な激しい太鼓のリズムがかみあう。踊りも秀逸で、さながらディスコ。
僕のためにヤギを一頭殺すが、ご自身でこのヤギに一太刀浴びせますか?それとも若い者にまかせますか?とあらたまって聞かれ当惑。

途中の川が増水して渡れず、海岸まで迂回し、河口近くの流れの緩やかなところを選んでわたる

ゴングと太鼓を巧みに組み合わせた心地よいミニマル音楽

踊りも秀逸で、さながらディスコ
2月 1日(日) 晴、夕刻激しい雨と疾風 Busalangga
トイレをこらえ、必死の図面採取。朝より午後4時まで。久しぶりの快晴。強風に乗って雲は飛ぶように流れる。
調査を終え、村人の案内で北西ロテ市の市長宅へ向かう。道はない。田をこえ、畑をよぎり、川をわたり、沼地をさまよい、雨のために土砂崩れをおこした絶壁を歩く。途中、雨。遠くに雨、とみるまに滝のような雨を浴び、カッパをかぶる間もなくカメラバッグ、背負子もずぶ濡れになった。この雨のために、白い粘土質の泥濘のなかを滑りながら斜面を上り下りするはめになった。
もっとも、ロティ島には山といえるほどの山や森というほどの木の繁みはないので、こうした歩行もさして苦にならない。サバンナの景観は全周360°視界がひらけ、ハイキングの心持ち。
約1.5時間で市長の家に到着。さっそくウンコ。ロティ島到着以来はじめて服を着替え、洗濯。喉痛く熱っぽい。1週間ちかく、喉がキリキリ痛む。変な病気だったらこまる。

実測図:床上平面

実測図:梁行断面

実測図:桁行断面
2月 2日(月) 晴、風強し Lalao
Baaまでは市長の便宜で役所の人間がオートバイで送ってくれた。今までの市長のなかでもっとも面倒見のよい市長。Baaの町会長の家で彼の帰宅を待って時間を潰す。
午後3時40分、オジェで東ロテ Rote Timur 市の Lalao へ向かう。想像以上によい道を約2時間で Lalao の市場着。町会長の紹介してくれた中国人のオジェはしっかり1万RPを巻きあげて去った。ふつう6000RPと聞いていたから好意でもなんでもない。中国人にはかなわない。
大きな伝統住居があるよ、という話はたいていガセネタだ。けれども、ここの王家は本当だった。やっと目指す家に出会い、思わず緊張する。柱太く、各部材は大ぶり、それでいて納まりはきちんと整い、改変の痕跡がない。屋根に穴が空き、修復の費用がかかるために取り壊す話があったという。それで、この家をさんざん褒める。ロティ島にはこうした家はすでに一棟しか残っていないこと、東ヌサトゥンガラ州全体を通しても数少ないことなど説明する。外人、しかも技術先進国の日本人に褒められて、彼らははじめて自分たちの文化財に気づく。こうした場合、一所懸命に調査してやればやるほど、彼らの家屋に対する思い入れもふかまる。
この日はすでに夜で、簡単な聞き取りだけで寝る。

ここの王家は本当だった。柱太く、各部材は大ぶり、それでいて納まりはきちんと整い、改変の痕跡がない
2月 3日(火) 快晴 Lalao
家主の要求で8km先の市役所へ行き、調査の許可をとる。きょうはたまたま週一度の市場のある日で、バスの便があった。けれども、ふつうの日にはバスがない。村よりはるか先の市役所まで出かけ、ふたたび戻ってくるという現実にはほとんど不可能なことが、政治システムの上からは平然と要求されているのだ。こうした官僚主義とつきあってゆけることが、インドネシア調査の最低条件。ご公儀でござる!!
要求通りに書類をもらって(東ロテ市の市長が理解あって、すぐに書類を用意してくれたので助かった)トンボ帰り。ついでに市長の家でトイレを借り……
残りの一日をほとんど写真撮影についやす。夕刻より図面取り。ロンタルヤシを使った大ぶりな梁桁はたいてい心材が腐ってなくなり、お椀状にえぐれている。ヤシ材の基本的な欠点で、丸太や半割材を使う場合には問題ないが、心材のみを使用すると容易に腐朽する。おなじロンタル製の妻飾りも腐って落ち、いまはない。この妻飾りは独立材でなく、棟木の延長なので、棟木を変更する以外に修復する手段がない。Kula を使った柱は十分な強度を維持しているが、ロンタルヤシを使った上屋構造はほとんどが破損を受けていて、見た目には十分整っていても、このままではあと10年くらいしかもつまい。かといって、修復するにも予算の問題以上に、これを管理できる技術者がいない。ラマクネン(ティモール島中部)の王家とおなじ結果になるだろう。結局、いまのところ打つ手はない。
夜、この家の居候氏の誕生日で、この伝統家屋でもささやかなパーティー。おもしろいのは、かつて主要な空間であったであろう高床の室内がまったく使用されず、庇下の土間空間が社交、就寝、調理の場となっていることだ。このパーティーも庇下空間に机、椅子をならべ、ジャワでみるように、受け取った皿にいくつかのおかずをテンコ盛りしてゆく。Sunsa のペスタでもゴングを鳴らし、踊りを踊るのはこのバレ空間だった。このパーティーのために床下の炉で蒸し焼きしたやけにおいしいパンを食べる。
「日本にヤシの木はありますか?」
「木はあるけど、実はならないよ。寒いからかな。」
「じゃ、パンに塗るバターがなくて困るでしょう?」
(あっ、そうか、それでこの国のバターは臭いんだな。ヤシ油から作っていたのか)
「バターは牛乳やトーモロコシから作るさ。」
へえー、というどよめき。そこで今度は僕。
「ねえ、ロティ島っていうけどこの島の名前とパン(Roti)と関係あるの?」
「それはありませんね。むかし、ポルトガル人がこの島を訪れたときに、住民に島の名前を尋ねたら、言葉がわからないでしょう? それで自分の名前を訊かれたと思ってロティと答えたら、それが島の名前になったといいますね。」
こういう話は多いな。ルソン島で「臼」を指さしてこの島の名は?と訊いたものだから、ルソン(臼)となったとか。
夜は更け、12時ちかくまで、このパーティーの主賓である影の薄い老人そっちのけで、日本の話に花が咲いた。
ここの村人たちは純朴であたたかい。
ヨーロッパ人の旅行者が半ズボン、Tシャツ、サングラスで闊歩するのと、あなたはちがう。やはり東洋人ですね。あるとき、オーストラリアの旅行者が水浴をしたいというので泉に連れて行ったところ、彼は素裸になったので村人はみんな驚いて逃げ出した。彼はキチガイだとわれわれはおもった。
インドネシア人は慎み深く恥ずかしがり屋だ。

実測図:床上平面

実測図:床下平面

実測図:桁行断面

実測図:梁行断面

2月 4日(水) 快晴、夕立 Lalao
朝から村人たちと連れだって木の撮影。木の撮影のあとは、伝統衣装をまとった村人たちの記念撮影。気を許すと,私もよ私もよとばかり際限ない。写真を撮るのはいいけれど、あとの処理に金がかかるから大変だ。
日本時代に日本軍はこの家に起居しておったそうだ。日本時代には盗人はいなかった。盗みをはたらくと、クギを無数に突き刺した板切れでもってこの盗人の手をたたく。
「おまえがやったんだな」
バシャッ。
手はみるみるうちに血みどろと化す。いまでも日本ではそうですか?
午後3時までに図面を取り終えてBaaへ帰るつもりが終わらない。聞き取りをしようにも部材名称や空間名、機能を知っている者がいないのだ。50すぎの男が、私は若い世代だからよくわからないと答える。伝統は生きているようで本当はとっくに過去のものなのかもしれない。
ヤシ砂糖の甕だけがおかれたガランドウの床上空間を指さして(炉も使われずに瓦礫の山だった)、ここは誰が使うのか、と訊くのもなるほどバカげている。
驚くべきことは、午後になって、10人ちかい村人が屋根にのぼり、急遽、屋根の破損箇所を修理しはじめたことだ。チガヤを取ってきて棟をふさぐ。
屋根を修理し終えたらまた写真を撮ってくれ。だから帰るのはあすになさいと言われる。僕の調査の効果がこんな風なかたちであらわれるのは嬉しい。思わず図面も細かくなる。
というわけで、結局Baaには戻れず、また一夜をあかす。
ヤシ砂糖を溶かした水をがぶ飲みする。ロティ人はこれだけで食事を済ますけれども、力があって米俵をかつぐ。米を食っているわれわれは力がなくて駄目だ、と北西ロテの市長が言っていた。ヤシ砂糖は蜂蜜に似た風味。これだけ食べ続けても糖尿にはならないという。果糖だからか。澱粉の補給にはなるはず。
ここではヤシ砂糖とパパイヤの葉を食べる。南西ロテ市のThieではピーナツとヤシ砂糖、ご飯にヤシ砂糖だった。ご飯に砂糖水をかけて食べるのはお菓子のようでなかなかオツなものだ。

伝統衣装をまとった村人たちの記念撮影。気を許すと,私もよ私もよとばかり際限ない

10人ちかい村人が屋根にのぼり、破損箇所を修理しはじめた

ヤシ砂糖を溶かした水をがぶ飲みする。ロティ人はこれだけで食事を済ますけれども、力があって米俵をかつぐ
2月 5日(木) 晴のち曇のち雨 Baa
村の若者の駆るオートバイ(半分壊れた)でBaaまで3時間。途中、家の写真、木の採集、コサンビの実(ブドウの口当たりでチェリーの味)を食べながらのたのしい道中。ところが、Baa近くで雨にあい、またズブ濡れになる。
飛行機はいずれも満員で、来週水曜までのチケットはない。さあ大変。この島に幽閉はこまる。ケイ諸島の二の舞。
例の町会長の娘婿のモナド人にたのみ、あす飛行場で直接掛け合うことになった。その後の情報では、破損中のフェリーにかわって、あたらしいフェリーが土曜日に出港するというが、これも諸説あって風評の域を出ない。小さな島のくせに情報は混乱。思い入れと真実の区別はつかない。
久しぶりにロスメンに泊まり洗濯。電気のある個室におさまって1週間分の日記をつける。

村の若者の駆るオートバイでBaaに戻る
2月 6日(金) 晴のち曇 Baa
日本から持ってきてもらった登山靴は、濡れたままで泥濘を歩きつづけた結果、とうとう底があいた。カメラはFA(NIKON)のほうはフローレスの頃からストロボが同調しなくなった。天候のよい日がつづくと同調するようになるから、黴のせいか。FE2は、Lalao の調査時に開放測光用のスプリングが切れ、測光不能になった。分解し、切れたスプリングをとにかく繋ぎ合わせたけれども、これも時間の問題でまた切れる。錆がまわりはじめたのだ。背負子の肩あてのヒモは今にも切れそうで、危ういところでつながっている。これが切れれば荷物の運搬は困難だ。紙幣入れを兼ねたベルトはチャックが壊れ、半ば開いたままだ。そのうえ、金具は力をいれるとはずれる。何度締め直しても、ツメが甘くなっているのですぐにまたはずれる。ヘッドランプはロンボックとティモールで二度ランプが切れた。長時間使いつづけるからランプの寿命か。このランプはここでは売っていない。ロンボック島のルクマン氏所有のヘッドランプ(スラバヤで買ったそうだ)の補助ランプを貰い受けてあったから、現在はそれを使用している。これが切れると、もう調査は大変だ。日本から持参した物のうち、太陽電池・電卓付きの時計はマルク(大Kei島)の調査時に海水につかって壊れた。現在は、ダイバースウォッチの電池を交換して使用している。実測用のメジャーはキサール島で折れた。先端が折れると、全部が中に巻き込まれて使用できない。バンドンで購入したセンチ・インチ共用のものを使用しているが、これもずいぶん変形した。ジーンズのズボン2着のうち1着はヨレヨレにすりきれてスンバワ島を離れるときに捨てた。ジーンズのYシャツはまだ丈夫だけど、ボタン孔が広がってボタンがすぐはずれる。カメラバッグは酷使に耐えてまだ十分使用できる。パンツはすり切れてところどころ穴があいた。シャツは脱ぐ拍子に破れた一着を捨てた。洗面用具入れもボロボロになった。寝袋の袋はやぶれ、丸めてしまうことが困難だ。雑巾のようになったタオルは二度捨てた。サンダルは何度も切れて交換したから十足ぐらいになる。
調査も二年近くになると、消耗するのは肉体ばかりではない。
昨夕以来、何度か激しい雨が降った。日中の天候はまずまず。早くこの島を出発したい。天候のよいうちに。けれども、モナド人との約束はあてにできない。それでも待つしかない。
日記をつけるより時間の潰しようがない。たとえばクパンやケファ(Kefamenanu)なら、店を覗いて歩くということもある。バスは頻繁に往来するから、どこへ行くのも自由だ。しかし、この小島のなかでは、かぎられた店があるだけだし、行くところもない。車に乗って隣の町へ行ったが最後、戻りの車を見つける手だてはない。マルクの時もそうだったけれど、何もできないときに日記はふえる。反対に、いろいろと事件のあったときには書いている余裕もない。
Baaの町は海岸通りに店がならぶ。店の裏はすぐに海だ。この時期の海は荒い。ときに突風が吹き荒れる。道沿いのヤシの木は折れそうなほど反り返り、トタン屋根はめくれ上がる。突風とスコールが過ぎ去ると、ふたたび熱帯の太陽が顔を出し、物憂い海岸通りに人びとはたむろする。
仕事、調査、外界そのものからあまりにも無縁な時間の進行。毎日繰り返されるスコール。週一度のパッサール。年に一度ずつめぐる乾期と雨期。このリズムに乗らないすべてのことは、意味をあたえられることがない。忘却あるのみ。
海水パンツを持ってこなかったのは惜しいことをしたな。ちょっと疲れた。
モナド人はやっぱりあらわれなかった。いまごろ弁解の文句でも考えていることだろう。昼前にすでに突風とスコール。この突風のために、一昨日の飛行機はあやうく墜落するところで、着陸できずにクパンへ引き返したという。
雨の後の町を歩く。フェリーの便を確認に行くと、あす出港するとの確報を得て、切符を買って帰る。クパンまで5時間だ。道ばたでコサンビの果実を買い、立ち寄ったワルンでコーヒーとバター付きパンを食べる。結構優雅な気分。
Sasando という楽器を買い求めに行く途中、町会長に会い同行。
「どうして家に泊まらない」
と訊かれる。昨日彼の家に行ったけれども、家族の感触は冷たかったのだ。
この島にいる猫はすべて日本猫だ。ここでは猫も食べる。猫の肉は鶏肉のような味だという。
日本では犬や猫は食べません、と言うと、けれども日本人は蛇を食べるでしょう、と言われる。戦争中の日本兵はさかんに蛇を捕まえて食べたらしい。トッケイも食べましたね。それから日本人は甘い物が好きで、何にでも砂糖をまぜて食べていたなあ。
インドネシアの甘すぎる紅茶やコーヒーに閉口しているいまの日本人には意外だろう。

Baaの町は海岸通りに店がならぶ。店の裏はすぐに海だ

Baaの市場

Sasando はロンタルヤシの葉からつくる。ロティ島オリジナルの楽器だ

当時インドネシア中にあった二人子政策のロティ島版
2月 7日(土) 晴 Kupang
Baa のロスメンに2晩泊まった。2日目から日本人であることを知られたら料理の質が格段によくなった。
初日の夜食。ご飯、ポークビーンズ風のブタ脂身と豆の煮込み、パパイアの実をこの脂で炒めたもの、ヤキソバ、という村の食事とあまり変わらないメニューだった。朝食のナシゴレンはご飯に卵をおとし、ケチャップで味をつけただけの料理。喉につかえるほどに炒めすぎてボソボソになったナシゴレンは間違いなくインドネシア人の料理だった。
そして2日目。夜食は、ご飯、大きな鶏肉のステーキ、ジャガイモとニンジンと鶏肉のスープ、パパイヤのカレー炒め。朝食のナシゴレンは、卵と豚肉をまぜ、うすい塩味で炒めたうえ、おまけに目玉焼きがのっていた。デザートにバナナ。
こんなことを書きならべるのは暇な証拠か。
戦争中の日本人の印象。Pendek-pendek(低身)、berani(勇気ある)、hebat(強烈)、pukul(殴る)、mati bagus(死ぬのは上等)、Indonesia Joto-nai(インドネシアは上等でない)、Shinto(神道)
午前中をほとんどぶらぶら所在なくすごす。町に出てもすることなく、仕方なしに(?)コーヒーを飲む。
11時15分、おなじみコルトディーゼルのバスでBaa発。12時45分、日本時代に軍港であった Pantai Baru 到着。ここで海岸に腰をおろし、多くの乗客とともに船を待つ。クパンは出たらしいという噂だけが頼りで、あてどのない船を待つ。朝から入港しているという噂もあったくらいだから、この目でたしかめるまでは信用できない。
1時をすぎる。2時もまわった。3時になっても船影はない。フェリーが入港したのはゴム時間の3時半。このフェリーに、北西ロテ市からBaaまでオートバイで案内してくれた男や Lakao の村長などが乗り合わせている。
波おだやか、風雨なし。ロティ島東部の海岸線はマングローブの群生するほとんど起伏のない板状地形だ。
クパン入港は夜10時。Sasando ホテルに入宿のつもりでいたけれども、この時間では食事にありつけない。仕方なくベモでプルムナスに帰る。案内する乗客たちのなかで僕は最後にまわされた。町中を走り回り、乗客を降ろした挙げ句、プルムナスにはいる。住所と名前を言う。
車掌「ほら、ここが家だよ。」
よく見るとちがう。「ここじゃないよ。番地は・・・だから、そこまで案内してくれ。」
車掌は車を降りて聞きに行く。彼の声が聞こえる。「ドイツ人で骨董品をあつめている男だ・・・」(?)
車掌、戻ってきて「この裏の通りだよ。すぐのところだから歩いて行けるよ。」
僕「家の前まで送り届ける約束だろう? いままで引きずり回しておいて、ここで放り出すテはないだろう?」
この押し問答を聞きつけて運転手もあらわれ、「もうガソリンがないからここまでだよ。さあ降りな!」
こっちはますます腹をたてる。「ガソリンのあるなしはお前たちの問題で僕の知ったこっちゃないよ。」
この騒ぎを聞きつけて近所の若者があつまる。「ラムリのうちならあそこを曲がったところだ。一緒に行ってやるよ。」
僕「約束は約束だから家まで送ってくれ!」
運転手はふたたび車に乗り、車掌をせきたてる。「さあ、ターミナルへ帰るぜ。降りたくないならターミナルへ戻るんだな。」
若者たち「ほらトゥアン、ターミナルに逆戻りするよりここで降りた方がいいよ。」
「ばかやろー、そんな脅迫に大人しくしたがっていられるか。」
日本語で悪態をつきながら車を降りる。運転席の窓から運転手の襟首をつかむ。中国人系のヤサ男の彼はヒェーと絶叫して運転席に伏せ、「送ります、送ります。」
この反応にはこっちがビックリしてしまった。さながらヤクザだな俺様は。それにしても、居丈高のくせにやけに度胸のない男だ。度胸がないのはうしなうものが大きすぎるからで、うしなう物のないヤケクソの奴ほど糞度胸がある。
調査旅行も5ヶ月をむかえると、精神的にストレスがたまるのか、こちらの態度が硬化してやたらと軋轢をおこすことが多くなった。さながら日本兵の生き残りだ。

ロティ島の足コルトディーゼルのバス


海岸に腰をおろし、多くの乗客とともに船を待つ
2月 8日(日) 曇 Kapan
昨日以来のストレスの蓄積をふやした。
朝、靴、石けん、Seba(サヴ島)行チケットの購入など済ます。朝にいつもコーヒーとお菓子を用意してくれていたラムリ君は、僕が食事をおごるようになってからこっちの食事のことをちっとも考えてくれない。ロティ島行きの時も Atambua へ行く時もあやうく朝食抜きのところであった。それだけではなくて、投函を頼んだ手紙はおつりを返してくれない。ガソリン代を平然と受け取る。朝食や夕食を用意してくれない代わりに一緒に食べる食事代はこっち持ちだという具合で、お義理の親切でターミナルや空港へ送ってくれるけれども誠意がないのだね。僕があまりにも金持ちすぎるせいだろう。何しろ1本1万RPもするフィルムを10本も買うくらいだからな。
9時20分ターミナル到着と同時にあらわれたバスに乗る。幸運!と思ったのは早合点で、この車は例によって市内を縦横に走るばかりで町を出ない。ひとりひとり乗客を迎えにゆく。この国の人びとはバスが着くとようやく用意をはじめるのだろう。乗客を待たせたうえに悠然とあらわれ、のそりのそりと歩いてくる。これだけで短気な日本人は頭にくる。これを乗客全員つきあっていたら軽く一時間たってしまう。
30分くらいで町を出るからと言う運転手の言葉を信じる方がよほどバカだ。乗客を迎えたうえ、車のオイルを買い、ガソリンをいれる。ここまでつきあって町を出たのは1時間半近くたった10時40分。途中でオイル漏れという事件があって、So'e 到着は2時。
So'e で昼食後、またしても運良くあらわれたベモに乗り込む。2時45分。So'e を出発したのは4時。約束してあった乗客を市場や家まで捜し回るという念のいれよう。この幼稚園さながらのインドネシア社会のことを思うと顔もひきつり乗客どもの顔を見る気もしないほどであった。乗客を迎えにゆくための待ち時間だけできょうは3時間を費やした。20人の乗客ひとりを迎える時間が5分として、はじめに乗った客(これが僕)は100分待つ。乗客全体の無駄にした時間は総計で (0+100)/2x20=1000、約17時間。インドネシア中でこれがおこなわれているわけだから、国の損失は計り知れないぞ。これはゴム時間なのではなくて、単なる甘え社会というだけのことではないか。その親切の恩恵に僕も浴しているわけではあるが。
Mollo Utara市の中心 Kapan 到着は5時15分。霧の町 Kapan。盆地の中腹にあり、日本の温泉町のようなたたずまい。温泉のない。。。
市長は病気中、セクレタリスはあすの議会の準備で役所へ行ったきりもどらず。ここでもほったらかされかしであった。10時までセクレタリスを待ってもあらわれず、与えられたベッドで寝る。

ターミナルで空席の多いバスに乗るのは禁物。Kefamenanuのバスターミナル

霧の町 Kapan。日本の温泉町のようなたたずまい

Kapan にもある伝統家屋のUme
2月 9日(月) 晴れ Tobu
ここのセクレタリスと話していると小学校低学年の子どもを相手にしているような気になる。Hのほうがまだしも明快な答えをするぞ。
ボ「慣習家屋の調査に来ましたが、この地域にまだ慣習家屋はあるでしょうか?」
セ(しきりに身をよじりながらしばしのあいだ、考えているのか、寝惚けているのか、二日酔いか)「要するに慣習家屋というのは丸くて全部のタルキが一点に集まっておるものですな」
ボ「ええ、だからそのような家はどこに行けば見られるんでしょうか?」
セ(ふたたび先生の前に出た生徒のように身をよじり)「要するに、慣習家屋というのはそれぞれの氏族がもっておりまして、どこの村にもあるようですな」
ボ(たたみかけるように)「ですから、僕の調査にとって相応しいのはどこの村でしょうか?」
セ「要するに私はこうした問題にかんしては暗いのでして、要するにわれわれはまず役所に行く必要がありますな」
というような内容のことを、彼はさも思慮深いといわんばかりに途切れ途切れに語った。市役所の仕事がこのペースで動いているとしたら(セクレタリスはふつう名目だけの市長にかわって仕事を取り仕切るのだ)この国の歩みはまさに悠久の流れのなかにある。
役所に行くと、昨日仮病の市長が元気な姿を見せており、Mollo の王の子孫という彼はセクレタリスとちがってやけにテキパキとした応対をする。
Mollo にはかつてひとりの Swapraja のもとに6人の Fetor がいた。このうち、現在の Mollo Utara には3つの(のちオランダ時代末にひとつ追加して4つ)Fetor領がある。それは Netpala、Numbena、Mutis と Paeneno であって、この Fetor領の中心に慣習家屋 Sonaf がある。Kapan 近郊で Sonaf が見られるのは Netpala の中心、Leloboko村(約30km)、Netpala の Fetor 移転後の中心 Ajaobaki(2km)、Paeneno の中心 Tobu(15km)がある。このうち Ajaobaki のものはすでに改築してコンクリートを使用、Leloboko は遠すぎる。Tobu に向かう。
Kapan から Tobu まで、雨で増水した川を渡り、自動車のための石だらけの道路を歩く。日本から持ってきた登山靴が壊れたためにクパン出発前に買った運動靴はもう開きはじめた。9時に Kapan を出たのに紆余曲折あって(随行の役所員は市長からもらった書類をポケットに入れたつもりで道中落とす)、途中会議のためにせっかく上京してきたばかりの Tobu の村長(Fetor の子孫)をつかまえ、道をもどる。村長は寄り道をする。そのたびにシリピナンをふるまわれ、世間話に興じ、道はこちらの思うようにはすすまないのだ。
沿道見かける円錐住居の TTU のものとの大きな相違は、棟のない完全円錐のものが見られることだ。道沿いにある方形家屋にはかならずといってよいほど、その後ろにこの円錐家屋 Ume が付設している。この地域では TTU でのように穀倉 Lopo が目立たないかわりに、この Ume がある。収穫したトーモロコシはこの Ume の天井裏に吊るし、下から炉の火でいぶすことによって虫害をふせぐ。Ume はいわば別棟の台所として現在は機能している。途中、運良く河原から砂を運搬するトラックに便乗。Tobu 到着は1時。
Fetor 所有のこの慣習家屋を見るために長老を集めてアダットをおこなうからしばらく待てと言われ、村の他の家々を見てすごす。TTU のものより総じて巨大。4本柱のうち、入口よりの2本から左右の壁に向けて仕切りを設けている。巨大な慣習家屋に見られる前室構造の初期の様相か。
かれこれ1時間、アダットは無事済んだ。使いが来て慣習家屋へ案内される。本道脇の小高い丘上にある慣習家屋は村中から見える。楕円錐屋根を伏せたような外観、正面入口前の石敷き広場には、その一画に王だけが座ることを許された3つの平石のドルメンがある。建築構成は Maslete のものに似て、4本の主柱と2本の棟持柱をもつ。Maslete との相違は2本の棟持柱のうち、前方のものが Maslete では前室内にあったのに対し、ここでは主室内に2本。ところが、この2本の棟持柱は後年の改修で、本来は1本柱によって棟木を支えていたらしい。
日帰りのつもりで調査用具以外持ってこなかった。仕事をはじめたのはこのアダットの済んだあと午後3時。このアダットで僕を村に受け入れるためにスレンダンを首に掛けてくれた。こんな贈り物を受けたのははじめての経験で、さながら国賓待遇。この時間に Kapan へ帰ることは不可能で、この家のベンチに横になって寝る。毛布一枚借りたけれども、夜気は冷たく、ベンチは痛く、風邪をひいた。

Tobu村

Tobu村にのこる儀礼家屋 Sonaf

実測図:Tobu村の儀礼家屋 Sonaf 平面

実測図:Tobu村の儀礼家屋 Sonaf 桁行断面

実測図:Tobu村の儀礼家屋 Sonaf 梁行断面

この家のベンチに横になって寝る。夜気は冷たく、ベンチは痛く、、、
2月10日(火) 晴 So'e
午後2時まで実測。この家屋の住人たちの叩くゴング、太鼓のなかで賑やかに食事。村によって歓迎の仕方もいろいろだ。2時40分下山開始。昨日トラックに乗った道を1時間半で川までくだる。身体の節々が痛く、煤と埃をかぶったままだから気分は最悪。川を渡ったところで、ここでも運良く中国人の乗るジープに拾われて登りを省略できた。Kapan へもどり、案内役の市役所員ともども市役所で挨拶。最終バス(6時過ぎ)で So'e へもどる。

村によって歓迎の仕方もいろいろだ
2月11日(水) 晴 Oeleu
Niki-Niki の調査。So'e から Niki-Niki まではベモで1時間。Niki-Niki はかつての大王国の中心。Niki-Niki の王の宮殿 Sonaf はオランダ時代建設の2階建てのヴィラ。このヴィラ横に2棟の大型穀倉 Lopo があったが、いまは柱を残すのみで倒壊した。この柱に取り付けられた鼠返しは石製でパウル・クレーばりの絵が描かれている。残念ながらこの絵はすでに剥離をはじめているが。ここでかつての王がゴマスリの村長にかしずかれ、その頭を撫でているという構図の写真を撮らされる。
Niki-Niki から古い穀倉の残る Oeleu までは約30km。オートバイをチャーターし、その後ろに便乗しているものの、山道では降りて歩かねばならない。平均時速10km、約3時間かかって土埃の舞う Oeleu 到着。彫刻付きの古い穀倉は Amanuban(Niki-Niki)の各地に残るが、いずれも遠い。Oeleu はもっとも近い例だ。
むかし大 mosalaki の所有したこの穀倉 Lopo は村のなかのもっとも高い丘上に位置する。Lopo にならんで同年代建設の住居 Ume があり、これもあわせて採図に決定。この地域 Niki-Niki の Ume は入口部構造が突出しているために洞穴のような印象をあたえる。穀倉のほうは屋根傾き、チガヤ欠け、屋根には大きな穴があって、このままでは破損倒壊を待つばかり。
棟の下に巨大な蜂の巣がぶらさがり、残念ながら棟納まりの細部を見ることができない。下から棒をのばして棟高をはかる。高床上は二重の床が張ってあり、この上部の床に登ろうとして止められた。この蜂は非常に悪辣で、そんなことをすれば蜂に刺されて死ぬというわけだ。ところが、おとなしく下の床で図面を採っているあいだに、この邪悪な蜂は人間の気配を感じ取ったらしい。髪の毛のなかに飛び込んできたかとおもうと、振り払ってもタオルで叩いても逃げずに、結局、頭の真上を刺された。蜂の毒が血液にのって流れるのか、頭皮にそって痛みがひろがり、頭痛が続いた。この蜂はたいてい頭を狙って刺すという。風邪のせいか、関節も痛い。夜、村長宅泊。

Niki-Nikiには2棟の大型穀倉Lopoがあったが、いまは柱を残すのみで倒壊した

Oeleuの Lopo は屋根傾き、チガヤ欠け、破損倒壊を待つばかり

実測図:Oeleu村王族の穀倉 Lopo 断面

実測図:Oeleu村王族の穀倉 Lopo 平面・断面

おとなしく図面を採っているあいだに人間の気配を感じ取ったらしい。邪悪な蜂に頭の真上を刺された

Lopoの下で記念撮影
2月12日(木) 晴 Niki-Niki
早朝、村よりやや下った林の中にある小さな穀倉の採図。彫刻はないが、一般採図の穀倉としてはよりまとまって古いもの。昨日ハチに刺された頭痛が続き、そのことを話すと伝統的な治療を施してくれた。この家主の女性のはめた指輪の真鍮を削り、これを水に混ぜて頭をこするのである。自分のはめた指輪を削ってくれるというだけでも相当な親切だから、ありがたくこの治療を受ける。この治療のあと、ふたたび丘上の穀倉と円錐家屋の採図。2時半までみっちり8時間の作業。頭痛、関節痛、喉痛(家屋内の埃を吸うため)で、疲労困憊。
昼食後、Niki-Nikiに向けてふたたび出発。Niki-Niki到着はすでに夕刻で、Kefaへ行くバスを道路沿いで1時間待ったがあらわれず。オートバイで案内してくれた Pene Utara の村長宅にやっかいになる。新品のホンダCBを乗り回しているのでさぞや金持ちと思ったら、家に行ってみるとガランドウの空間に8人の子どもと妻。ここにオートバイだけがやけに神々しく置かれている。出発前ピカピカだったオートバイも石だらけ急坂を上り下りしたためタイヤはすり切れ、埃にまみれ、チェーンはゆるむ。3万RP要求されたのを2万RPに値切ったけれど、これでは割が合わないな、きっと。

村よりやや下った林の中にある小さな穀倉と家屋を採図する

実測図:Oeleu村の穀倉 Lopo

実測図:Oeleu村の家屋 Ume 平面

実測図:Oeleu村の家屋 Ume 断面
2月13日(金) 晴 Kefamenanu
SoeにあるTTSのPdK(教育文科省)で見せられた本のなかに Susulaku 村(Insana)の村落配置の図があった。円形の慣習家屋を中心に同じ円形の住居が環状に配されるというものであった。Kefamenan のTTUのPdKでこの話をすると、所員一同そんな村はないというし、このPdK出版の本もない。文化担当は会議でおらず、彼がこの本をかかえているであろう。が、わからない。こういうケースではまったく事はすすまない。情報が公開の場に置かれるという体制がない。同じPdKの本部が出した本、しかも、この Kefamenanu の管轄する地域の報告というのに、Kefamenanu まで来ると、これにかんする情報がまったくないのだ。
昨日 Kefamenanu まで出ることが出来なかったために、Insana 到着はすでに10時半、頼みの綱の禿頭市長は病気につき自宅療養中で役所におらず、セクレタリスは手紙を用意してはくれたけれども、案内の役人もつかず、単独の調査となった。
Oelolok の Raja を訪問。PdK情報のチェックのため。Raja の話では Susulaku 村には慣習家屋はない。環状集落は Nuntefa という山上の部落の移転計画書であったが、これは実現されてはいない。また、Insana に環状集落があったことはない。したがって、この計画案はあたらしい村落の構想である。。。ということがあきらかになった。政府はヒトの文化を盗むくせに、その維持のためにはちっとも金をよこさない、と不満顔であった。
Raja の記念写真を撮る。「俺はハンサムだろう?」と何度も訊く老いた Raja の最後の勇姿を写真におさめる。「ハンサムに撮れてなかったら、俺は写真を破り捨てるよ!」
結局、Susulaku 村には行かなかった。市長宅に預けた荷物を取りに行くと、病気中の市長が姿をみせる。右足の臀部に腫れ物ができ、ここ一ヶ月足が痛い。高熱が続く。医者ははじめマラリアの薬をくれた。現在は、注射をうった際の消毒が不十分、そのために細菌がはいったという診断で、抗生物質をうちつづけているらしい。そんなバカげた診断はない。
市長のつけてくれた所員の同行を得て、街道沿いにある前回の調査村の穀倉の図面採り。穀倉の数は多いけれど、すでに造作は雑で、とにかく資料として一棟の図面を採り、夕方 Kefamenanu に帰る。
33歳になった。まだ自立できない。仕事のあてもない。いまの作業は重要には違いないけれど、生活の足しになるわけではない。見通しもない。方法論もない。毎日、自分に与えた仕事を消化しているだけなのではないか、と思うと情けなくなる。だからといって、何をすればよいのだ。街角に立つ娼婦のように仕事の来るのを待つことしかできないのか。無闇に不安になり、それでも疲れているからすぐに眠った。

Insana王国のTaolin王さま、ハンサムに撮れているでしょうか?

街道沿いにある穀倉を選んで図面採り

実測図:Haufoo 村の穀倉 Lopo
2月14日(土) 晴 Kefamenanu
前回調査拒否にあった Maslete の慣習家屋の調査をするために一日中役所をまわり、人に会った挙げ句、結局無駄に一日を費やす。
Miomaffo Timur の市役所を訪れ、市長より直々の手紙をもらう。この手紙を持って Kefa の Kopeta(Koordinator Pemerintah Kota)へ行き、Maslete の Kelurahan(区)長宛の手紙をつくってもらう。Kopeta はおらず代理人。
この手紙を持って 区長の自宅へ。無愛想な家人は区長は「Kopeta へ出かけた」と言う。「Kopeta から来たばかりだ」と話すと、「じゃ、Kantor だろ」と言うので、区の役場へ行く。彼はここにもおらず、不親切な所員は、「Koramil(Komando Rayon Militer:町区軍管区)だよ」のひと言。仕方なく Koramil まで歩く。今度は、「いまさっきまでいたけれど帰った、きっと家だろう」と言われ、家へ戻る。やはり家にもおらず、彼の戻ってきた午後1時ちかくまでおとなしく待つ。
区長はかつて Fetor だった男で頭はよいらしい。Maslete の家屋の調査のためにもらってきた書類をみせる。
「勿論デキルヨ。写真も撮れる。天井裏にものぼれる」
そう保証され、とりあえずちかくの村の一本柱の慣習家屋の見学。見学ついでに図面をとり、先に村へ向かう彼とは村で会う約束をして別れる。
ところが図面を採り終えると、
「この家屋の中心柱にのぼるなど禁忌であって、どういう許可をとってした?ニワトリを一羽殺さねばアナタも我々もただでは済まない」
ひとりの若者に食ってかかられる。区長にはちゃんとこの話をして許可をとっていたのでこれは意外。区長に訊いてからということにしてここは逃げる。
Maslete隣村の Tufue で結婚式があり、区長は氏族長だからこの結婚式に出席のため Tufue にいる。先刻の約束では、彼は Tufue に行く前に Maslete に立ち寄り、調査の話をしておいてくれることになっていた。Tufue 着はすでに夕方にちかく、きょう中に調査の打診だけをしておくつもりであった。酔っ払った区長に招かれるままに、この Tufue の慣習家屋にはいり、ここで祝宴の食事のふるまいをうける。こっちは日が暮れるから気が気でない。食事後、ようやく彼をつかまえる。
「調査?できるとも。俺が許可したと言えば彼らはみせてくれるさ」
と話すのも言葉だけ。実際にひとつも調査に向けての協力をしてくれない。Maslete にも立ち寄ってこなかったのだ。人をつけてくれと言ってもダメ。手紙を書いてくれと頼んでもダメ。酔ったまま
「4つの氏族はひとつのものだ。俺は ABRI(軍人)だ」
のらりくらりと埒のあかない話を繰り返す。
「もう日が暮れるからあすにしよう」
冗談じゃない。日が暮れるような無駄話を繰り返すのはこの男のほうであって、さっさと手紙を書くなり、人をつけるなり、自分が案内するなりすればよいのだ。無理矢理腕をとり、さあ行こうとうながす。
「私はまだ用事があるからダメだ」
酔っ払った相手とまともに議論をするほどバカなことはない。かなり激昂したやりとりがあって、ついに得るところはなかった。
俺はABRIだ、というのは自分は強い、みな言うことをきく(はずだ)という意味だろう。この時には気付かなかったけれども、彼もやはりアダットをおそれている。アダットと政府の役人としての役割のあいだで彼自身の立場は微妙だ。一見合理的にみえる彼の思考も深層でアダットに縛られている。このことに気付かなかったのが失敗だった。彼は役人の権威を借りて遠くから事を操作しようとしているだけなのだ。

ちかくの村の一本柱の慣習家屋の見学。見学ついでに図面をとる

実測図:南Kefamenanu村の儀礼家屋 Ume Leu 平面

実測図:南Kefamenanu村の儀礼家屋 Ume Leu 断面

家屋の中心柱にのぼるなど禁忌であって、ニワトリを一羽殺さねばただでは済まないと食ってかかる
2月15日(日) 晴のち曇 Kupang
調査への気力が減退している。So'e で泊まり、月曜に市役所で調査許可を申請しておくつもりが、So'e まで着いてそのままクパンに戻り、Sasandoホテルにおさまってしまった。
Kefa から So'e の道中、Supul 村に立ち寄り、近年改築の大Lopo の見学。彫刻のかわりにペンキで描かれた人面のある梁、整ってはいるけれど雑なつくり。省エネはゆきとどいている。

Supul 村に立ち寄り、近年改築の大Lopo の見学
2月16日(月) 晴 Kupang
銀行で日本人の大学生と会う。半ズボンの男。オーストラリアへもっとも安く行くため、マレーシアから船でスマトラ入り、スマトラをバスで縦断、フェリーでクパン入りした。日本円がここでは7RPにしかならないので急に貧乏になった気分。あすサヴ島に行く予定と言うと、へえーやるじゃない!
銀行員と英語で話しているので(相手は??)、何をしたいかと尋ねると、だからいま言ってんじゃない!
なれなれしいというのではない。礼儀知らずと言うつもりもない。のびやかと言って言えなくもない。けれど、なにか押さえのきかない環境のなかでアッケラカンとふくらみすぎたカルメ焼のようなとらえどころのなさ。私も歳です。久しぶりで日本人に会ってすこし興奮したのかね。これがおなじ国の人間なのかとおもうと妙になさけなかった。
クパンを離れるためのいくつかの準備を済ませ、ラムリ家でサヴ島調査のための物の交換と補充。快適なホテルに泊まってゆっくり休んで元気百倍とおもっていたところが、気がゆるむためか、かえって疲労感ばかりのこる。クパンは異常な暑さ。噴き出す汗、焼け付く太陽。
2月17日(火) 晴・曇 Seba
午後1時出発、12時チェックインとあるので、ロティ島の時のこともあるから、10時半に飛行場に着きおとなしく待っていた。ところが、Seba行きの飛行機が出発したのは2時半で、とくに遅れたことを詫びるわけでもなく落ち着いたものであった。インドネシア人の常で遅れてくることを見越して出発時間を早く知らせてあるとしかおもえない。国中がこうしたキツネとタヌキの化かしあいで時間を無駄にしている。バカな話だ。
サヴ島の Seba まで約40分。サヴ島上空をちょうど雨雲が走り去るところで、この黒い雲の流れを迂回して石ころだらけの滑走路に着陸。サヴ島は暑い。じっとしているだけで体力を消耗してゆくようだ。人類学の鍵谷明子さんと織物の研究をしているタカダ(?)という女性が泊まったという7500RPもするくせにサービスの悪いロスメンにはいる。
Seba にある王宮、コロネードを前面にとった古典様式のオランダ建築、このコロネードの庇部分の屋根はトタン、本体は瓦。女ラジャ(か、王の未亡人か)がひとりで住む。写真を(無断で)撮っていると若者があらわれ、「何のために写真を撮る、ラジャは写真を撮られたくないと言っている」(彼女は昼寝中)。
市長宅で近くのPdK保存村 Namata の村長宛の手紙を書いてもらい、やたらとアグレッシブな先生のオートバイで村まで案内してもらった。サヴ人は仕事ははやいが逃げ足もはやい。ここでは親切は金勘定のうえに成り立つという印象をふかめた。合理的(?)といえば合理的。元気で傍若無人。大阪人に似ている。サヴ島での調査に人情は期待できない。
Namata は小高い丘の斜面に東西に棟をならべた伝統住居が建つ。PdK の保存修復作業の結果、この丘の途中から山上まで意味不明の屈折を繰り返すアスファルト遊歩道がつくられ、まったくあたらしい伝統住居風建物が建ち(博物館のためというが機能せず)、巨石文化名残の環状石敷のうえからコンクリートでかためる。村の一画に大鍋を伏せたような巨石記念物がいくつかあり、案内してくれた若い村長にこの意味を訊くと、「私はよく知らない」。彼は何を訊いても伝統のことについては「よく知らない」、で、さすがにアダットの強いサヴ島も若い世代はまったくまったくアダットに無関心だ。
慣習家屋は3棟。同一形態の一般住居とのちがいは正面(西)側に開放されたデッキをもつこと。一般住居ではこれがすべて壁で囲われてしまう。3棟のうち2棟は80年代の改築で、梁の一部をのぞきすべてあたらしい。扉には金属の蝶番をもつ。PdKの保存は外観、集落保存が多く、建築内部にまではおよばない。

Seba にある王宮はコロネードを前面にとったオランダ建築


巨石文化名残の石敷き環状広場。保存作業の結果、コンクリートでかためられる

村の一画に大鍋を伏せたような巨石記念物がいくつか
2月18日(水)晴 Bolou
市役所へ行き、村長宛の書類を用意してもらう。これがフローレスやロティ、ティモールだったら、村まで案内の所員をつけてくれる。ところがサヴ人でこういう気の利く人間に会ったためしがない。人間的に成長しているのか、合理的なのか、それとも単に不親切なだけか。書類をつくるのに時間がかかるだろうとおもい、そのあいだ警察に報告に行く。警察から帰ってくると、書類は市長の机の上だという。それではサインを待つだけだろうと考えたらとんでもない。下書きのチェックを待っているという。結局、タイプを打ち終わるまで待たされた。
この書類を持って Namata へ。古い一棟、アダット長の家屋を見るための交渉をするが、家主が畑におり、結局許可をもらえない。このまま Seba にいても時間を無駄にするばかりだ。
Seba に戻ると、一日一回の東部行きのベモがまだ客間待ち中だ。これをつかまえ一気に東サブ市へ向かった。東サブ市の市長もサヴ人。簡単に用件をきくと村宛の書類をつくる手配をし(こういう事務処理ははやいのだ)、それでは、と引き下がる。かつて fetor だったという所員がひとり、僕をプギナパン(宿)へ連れて行く。村まで案内することを頼まれていたこの男はそのまま逃げてしまった。役所に帰って待っているのかとおもい、書類を受け取りに役所へ行く。1時半なのに役所はすでにもぬけの殻。サヴ人の逃げ足ははやい。用件を他人におっかぶせ、自分はさっさと逃げるというのはこれまであったサヴ人すべてに共通する。
かつてサヴ島東部のアダットの中心 Dokaiki は慣習家屋2棟をのこすのみで面影はない。現在は Desa Kujiratu という5kmほど北の村に多くの慣習家屋が残るというが、ここには行く機会がなかった。Dokaiki の近くの Unumola (Limaggu村)にある家屋の調査に決まる。一般に家屋の天井裏は禁忌空間で登れない。Unumola の住人はプロテスタントに改宗しており、この禁忌がないから調査はやりやすい。
サヴ島の家屋はプラフ(舟)を転覆させた形と表現される。棟木をささえる柱は船のマストとおなじ名称。家屋の東(南入口の場合。北入口の場合は西)は男の空間であり、舟の舳先、あるいは人体の頭とかんがえられ、西は女の空間(炉がある)、船の艫、人体の尻とかんがえられている。Namata の儀礼家屋では東西に分離されていたこの男女の空間は、ここでは一連の壁で囲われている。高床の床高も戦争の際に敵が床下にひそんでくるのを恐れて Namata のものよりかなり低い。床下の土が盛り上げてある。東と西にそれぞれ男の入口、女の入口があり、死体は男女それぞれの扉の近くの空間に埋められる(屈葬)。この地域では、家屋の造りは一般に悪い。ある一定の形式に則って造られているのだが、良材が得られないためか、柱は曲がり、ロンタルヤシの梁は無骨で細部の納まりは非常に悪い。棟木とタルキの仕口はロティ島のものと同様、棟木に穴をあけて枘差しするのが本来のものらしい。

サヴ島東部のアダットの中心 Dokaiki は慣習家屋2棟をのこすのみ

Unumolaの住人はプロテスタントに改宗しているから天井裏も実測できる

棟木に穴をあけておきタルキを穴に通して固定
2月19日(木) 晴、一時雨 Bolou
Unumola の家屋調査。親切に昼食をあたえてくれた。出されたコップ一杯のなみなみとつがれた水を飲み干す。飲みながらコップの底を見ると微妙に動くものがある。よくよく見ればボウフラでおもわず喉が止まった。生水ではないか! すでに胃に収まってしまったものは仕方がない。親切にもさらに出してくれた gula air(砂糖水。ロンタルヤシからつくる水飴を水でうすめたもの)をままよとばかりコップ2杯飲む。サヴ人の主食はこの gula air だ。けれど、これもボウフラ入りだろう。色があって見えないけれども。思い込みすぎるためか、その後、妙に腹具合が悪い気がした。
とにかく暑い。クパンで Sasando ホテルに泊まって以来、身体がだるい。実測中もおもわず横になりたいほどボーッとしてしまう。夕方まで、かろうじて作業を終え帰宿。宿の近くの公衆水浴場、男女混浴といっても、男も女も衣服を着たままで水浴をする。この湧水プールでかたや頭を洗い、かたや洗濯をする。いくら水が湧いていても、多くの人間がいつも使用しているから衛生的ではないだろう。日本の公衆浴場は素裸だからインドネシア人から見ればよほど異様な世界にちがいない。

実測図:Ammu平面

実測図:Ammu梁行断面

実測図:Ammu桁行断面
2月20日(金) 晴のち曇、夜豪雨 Seba
朝のベモで西サブの Seba に戻る。その足でPdKを訪れ文化担当のパジカナ氏を引率して Namata 再訪。Deorai の家主にどう頼んでもダメ。とくにモロコシの苗を植えるこの期間、この儀礼家屋に立ち入ることは禁忌とのことで座礁。仕方なく1980年再建の Heokanni の調査。パジカナ氏はサヴ人らしく、12時すぎにそそくさと帰って行った。時間は金であるという観念がすでに定着しているからだろうか。マイホーム主義が発達しているからか、好奇心がないためか、日本でだったらあたりまえの行動も、このインドネシアで起こると不思議だ。誰もいない室内で勝手気ままに調査できた。昨日東サヴで実測して以来、体調元に戻り、調査そのものは楽。暑さもさほど気にならず、6時すぎまで村にいた。厚く黒々と垂れこめる雨雲のなかを帰宿。夜よりついに雨。

実測図:平面

実測図:桁行断面

実測図:梁行断面

実測図:梁行断面
2月21日(土) 曇 Seba
一日厚い雲におおわれる。おかげで適当に涼しくかえってよい。PdKのパジカナ氏をさそってふたたび Namata へ。Heokanni の実測続き。12時をすぎパジカナ氏が帰ると、途端に騒動がもちあがる。
Heokanni のあと実測予定だった一般形式の住居の老婆はシリー・ピナンを買うお金をくれ。これを断ると住居は見せない。Heokanni も許可しない。こんな駄々をこねられているあいだに今度はアダット長を名乗る男が立腹。ちょっと顔を貸せというので彼の家へ。彼は戦争を司るアダット長と名乗り、
「誰の許可で Heokanni の実測をしたか?」
アダットを司る人間の数は多い。居場所もさだかでないこんな輩といちいち掛け合っていては調査はすすめられない。といって、話をこじらすといっそうヤバイ。村長とアダット長、キリスト教と伝統的な Jinggitiu。アダットが政府組織より強く、土着宗教(原始ヒンドゥー)が文化宗教より強い場合、市役所からの調査許可証に実質的な意味はない。アダットがヘソを曲げるのがオチ。分裂状態にあるこのふたつの組織のあいだで良い迷惑をこうむるのはたいてい第三者なのだ。
村長にはすでに会って報告したこと。Heokanni の家主である戦争を司るアダット長(本当の!)からは許可をとった。Deorai の家主である村のアダット長には昨日会って、Deorai の調査許可がとれなかったかわりに Heokanni の許可をとった。こちらとしては最善の策を講じてきたのであって、これ以上村内の問題には関知できないと説明する。
彼の言い分は(この説明でずいぶん矛先をおさめたかにみえる)、大統領(アダット長)の許可をとったかもしれないが、大統領から大臣に対して何の連絡もなかった。市役所との約束では、すべての入村者は事前に村のアダット宛書類にて報告し、アダット会議の許可をとることと決められている、というものである。
村人がかならず村にいるわけでもないのに、数日しか時間のない観光客がこのアダット会議を待つなどという現実離れした取り決めに従えるはずがない。もちろん、こんな取り決めは市役所側が PdK の修復観光化策をのませるためにしたカラ手形だろう。ともかく、非は連絡をおこたった市役所と村長と大統領にあるというすり替え策が功を奏して、彼の(戦争を司るアダット長から将軍になっていた)怒りもおさまり、この家でめでたく昼食をご馳走になった。
食事後、隣りにある一般形式の伝統住居の実測。柱下に礎石、貫を使用した近代的(?)構法で、柱位置も整理されている。礎石、貫の利用は東サブの住居と西サブとの相違として何人もの村人が指摘した。
6時過ぎまで作業して Seba に帰る。あすの Peddero 行きのオートバイを手配。

一般形式の伝統住居の実測。柱下に礎石、貫を使用した近代的構法

実測図:平面

実測図:梁行断面

実測図:桁行断面

家屋前面のベランダ。船尾側は女性の仕事場
2月22日(日) 曇 Seba
7時15分、約束の時間より15分早く市役所の所員があらわれる。戸口に立ち、聞こえないような声でボソボソと話しはじめる。と思ったら、賃上げの要求だ。昨夜約束した金額ではガソリン代にしかならない……一度決めた料金(この土地では正当な金額)を一晩眠っただけで気変わりする商売人の相手をする気にはならない。市場の駆け引きじゃない。Peddero 行きは挫折。サヴ人相手にこれ以上仕事をする気力がない。
ふたたび Namata の調査。昨日の家屋でまた昼食をご馳走になった。Seba で泊まっているロスメンの食事よりよっぽどよい。村人は親切だな。Seba のロスメンは本当に民宿だ。他に逃げ場がないことを知っているから、この胡散臭い民宿が法外に高料金。二食付き一泊7500RP、サービスは悪い、のではなくて、ない。使用人用のトイレと水浴場、蚊の多いカーテンもない部屋、干し魚とスーパーミー(インスタントラーメン)の食事、残ったおかずは翌日ふたたび登場する。金を払って出される食事ではない。飛行機が空港に降り立った瞬間、とんでもないところへ迷い込んでしまったと気付かねばならない。1週間はどんなに短くてもこの牢獄から逃れるすべはないのだ。

昨日来、2度も食事をご馳走になりました。親切な村人に感謝!
2月23日(月) 晴 Seba
午前中、海水浴。波荒く、風強い。人っ子一人いない奇麗な海。調査のことなど忘れてくつろごうとするけれども、本当の自然のまえでは身構えてかえって緊張する。午後、することもなく Namata へ行き、ボンヤリたたずむ。調査をしようにも役所のバックアップが得られないから住民の理解がない。家は見せないと言われりゃとりつく島もない。
サヴ島のアダットは強い。内部の結束が強いということは外部が希薄だということだ。サヴ島の住人にとって、日本がどこで、オーストラリアがどこで、ジャカルタがどこかですら理解されていない。戦争中、日本人がたくさん来た。だから日本はクパンの先の島ぐらいに思っているのだろう。井の中の蛙の結束は強い。世界観も単純で明確。へんに知識が増えればそれだけ自信がゆらぐ。自分の世界は他人の世界とくらべてそんなに強固じゃないことに気付くというわけだ。
時間の逼迫したこの時期に何もすることのない島で2日間の休日。2日早くバンドンに帰ったほうがよほど休養になったろうに。自分の写真を撮ってすごす。
日本がどこにあるかも知らぬ Namata の老人(115歳だという年齢はあてにならないが、彼の孫もすでに40歳以上)に、日本の家はみんなセン(波板鉄板)の屋根でしょう?石の壁でしょう?と訊かれる。近代住宅のイメージはセメント壁、地床、セン葺きということでほぼ一致している。
サヴ島の住居には家の後端に炉がある。けれども、たいていの家でこの炉は形骸だけ、あるいは、まったく姿を消している。調理は別棟の台所か、もしくは庇下にもうけた地上の炉。こういう点はだいたい東部インドネシアのどこの地方でも一致していて、家の中の炉は儀礼用の調理、出産、病気の時などにかぎって用いられる。火事を恐れた結果とも言うけれども、あかるい床下や別棟のほうが調理しやすいに決まっている。絶えず戦闘状態にあったとすれば話は別だが。
サヴ島の言葉はロティ島西方の Ndao島言葉と似ているという。吸音がある点でスンバワ島の Bima やフローレス島の Lio などとおなじだ。建築的にはどうか? ロティ島とは義兄弟、ティモール島の Belu とは親子、Lio の Jopu地方の Sao Banga型住居とは親戚、いずれも船の建築だ。
サヴ語で南は Ubä Louw(Ubä は口、Louw は海?)、北は Ubä Däe(Däe は陸、得る)という。本来北岸の村なので海は北にある。
家屋はロティ島とおなじで棟を東西に向けるから棟持柱にこの方位名称はつかない。ところが、ティモール島の Belu に行くと、テトゥン語で家屋前方の棟持柱は lor(テトゥン語で lor には意味がない。ただし、北部Beluの Bunak では海を意味する)、後方の棟持柱は rae(rae は大地)と呼ばれている。
däe (インドネシア語の dapat=得る) / däi (sampai=まで) / rai (bumu=大地) / dahi (laut=海) / ai (api=火) / ei (air=水)

人っ子一人いない奇麗な海に緊張

何もすることのない島で2日間の休日


2月24日(火) 快晴 So'e
Seba の飛行場の滑走路は最後のほんの10メートルくらいが舗装されているだけだ。その他の部分は芝生と小石だらけの道で、ふだんは山羊がこの草を食べている。飛行機が着陸すると、小石の滑走路をダダダとはね、最後でようやく舗装部分に乗り上げて止まる。けれど、出発の時はもっとすさまじい。はじめ滑るように走り出した飛行機は突然地響きをたて振動をはじめる。これはまずいことになったとおもう頃、運良くタイヤは滑走路を離れるという寸法だ。それで、飛行機が Seba に着陸するとなると、近所から子どもたちがあつまってきて、到着した飛行機にむらがる。まるで遊園地のようだ。おもしろいのはパイロットもパイロットで、着陸し、出発までの荷物の積み下ろしを待つあいだ、コクピットの椅子にふんぞり返って新聞を広げている。この姿はバンドンのI家にいるTさながらで、パイロットというよりはお抱え運転手にふさわしいではないか。
こうしてエデンの園の一週間を終えて、ふたたび西日輝くクパンにもどった。昨日の日焼けのためにバッグをさげる肩が痛い。食事ののち So'e に向かう。Kapan にある Mollo の住居の図面を採るために。結果として、この So'e 行きはみごとに失敗であったけれども。

近所から子どもたちがあつまってきて、到着した飛行機にむらがる
2月25日(水) 晴 Kupang
一日に3回長距離ベモに乗る。このためにベモの客拾いにつきあった時間だけで3時間以上になった。この間、何も考えず、何も成果なく、脳の活動は停止している。ただ日本語で悪態をついているだけだ。
「何考えてんだこいつら…」
「いーかげんにせーよ」
「ばかやろう」
So'e からクパンにもどるバスにはとうとう生きた鯉が乗り込み、乗客、運転手一同、この鯉を生きたままクパンに運ぶために議論百出。車を止めて水を代える。その間、おとなしく待っている20人ちかくの乗客はいったい何を考えているのだろう。
バスが街道を走ると、道ばたで座り込んでいる村人たちがいる。運転手は車を止めて訊く。しばしやり取りがあった後、彼らは重い腰をあげバスに乗り込む。バスに乗りたいのであれば、はじめから手を上げ意思表示をすればよい。彼らは特別礼儀正しいのかこれをしない。わざわざ走っている車を止め、意志をたずね、荷物を持って車に運んでやらねば一生ここに座っているとでも言わんばかりだ。
また、こんなこともある。市役所の所員と連れだって旧王族やら県知事やらの家を訪れる。威儀を正し、扉をノックする。コツコツコツ。指先で扉をはじくくらいの小さな音。大きな家だったらこんな物音を聞きとめてくれるはずはない。しばらく待つ。応答はない。ふたたび威儀を正しノック。コツンコツンコツン。やっぱり聞こえない。またノック……。来意を知らせたいのであれば、それ相応の大音量を出さねばならない。しかし、彼らはそれをしない。きわめて礼儀正しく、寝ている赤ん坊を起こさないようにコツコツ。相手が気付かねば一日中こうして周期運動を繰り返す覚悟ででもあるかのようだ。
Kapan 近くの Ajaobaki という村に行く。ここの旧Fetor に会う。例によって日本時代の話。
日本時代にTTSの人間は飢えを知らなかった。道沿いの畑という畑はすべて野菜で満ちていた。朝6時半、畑に出て待機。日本人の監督が丘に立って見張っている。全員6時半にキチンと集まっていればジョートーと言われた。すこしでも遅れると殴られた。シリー・ピナンを噛む時間も決められていた。このベルが鳴るまで休憩は許されない。畑作業の労働力はサヴ島、ロティ島、ベル地方などから集められたという。あと数年日本の統治が続けば、ゴム時間もバスの客拾いもなかったであろうに。数年前までこの地方の特産であったリンゴは害虫のために全滅した。これも日本時代の遺産だ。
Mollo のこの地方には二種類の円錐住居がある。棟をもつものと完全円錐のものとだ。こうした形式の違いは各氏族伝来のもので勝手に変更はできない。棟木をもつものでは、棟束が1本のもの、2本のもの、1本で上方に二股部分をもつものがある。棟木を持たない円錐形の住居は Nis-Metan(黒い歯)の子孫、土着民の住居であり、棟木をもつものは Nis-Muti(白い歯)の子孫、マラッカ(Belu県の Malaka はマラッカに由来)に起源する征服民族の子孫といわれる。
Mollo や Miomaffo の住居と Amanuban のものとの相違は主柱上の梁の方向である。はじめ梁を桁行方向に配する Mollo型に対して、Amanuban型は梁行方向にのる。
住居の建設は主柱→梁・小梁→外周柱→もや→真束→4本の垂木(垂木同士を結ぶ)→他のもや→他の垂木→屋根の小舞(チガヤを受ける横桟)の順におこなわれ、建設後に中央の真束を取り除くものがあるという。
以上の聞き取りをしただけで実際の建物調査は出来ずに Kapan を引き上げる。荷物をとりに立ち寄った So'e のロスメンで犬に噛まれ、コーヒーの粉をすり込む。クパン到着後、晩飯を食べているあいだにベモがなくなり、ラムリ家まで街道脇から歩く。呪われた一日。

棟をもたない円錐形の住居は先住民 Nis-Metan(黒い歯)の子孫。Kapan

棟をもつ住居は征服民 Nis-Muti(白い歯)の子孫。Ajaobaki

Molloでは大梁は桁行方向にのる。Ajaobaki

Amanubanでは大梁は梁行方向にのる。Oeleu
2月26日(木) 朝雨のち晴 Kupang
Amarasiで軽く調査の予定だったが、AmarasiのBaun村は市役所とまったく逆方向で遠い。朝の豪雨で気力をそがれ、文書資料の収集にクパンをまわっただけで終わる。
調査で金を使わなかったのに土産物を買い漁り、いっぺんに貧乏になった。金銭感覚が麻痺がしている。10万RP ? 高いなあ…日本円で1万円か、それほどでもないかな…本当は、日本で1万円の買物はやはり考えものだ。
ラムリ家の居候たちをさそって最後の晩餐。
2月27日(金) 朝雨 (Kupang) 曇 Waingapu
飛行機の話。早朝、クパンのEl Tari空港に行くと、Merpati気鋭のTwin Otterが機首をならべて待っている。これがこの朝一番のフライトに向けて立て続けに出発する。Dilli、Ruteng、Bima、Bajawa、Waingapu、Tambolaka、Ende、乗客も慌ただしく、次々と違う目的地の呼び出しがあるから、自分の乗るべき飛行機をみつけて右往左往ということになる。それで目的の飛行機に乗り込んでみると、これは違う、あっちだとか、一人足りないぞとかいう事態がおこる。このさまはベモのターミナルとなんら変わらない。飛行機も経由する路線を書いた看板や数の違うランプをつけておいたほうがインドネシア向きだろうに。
朝、昨日に続いてスコール。雨のあがった7時24分クパン発、まったくの雲の中を飛び続ける。パイロットが銜えタバコに新聞に目を落としている様だけが乗客からみえる。梅雨のように重苦しいワインガプ着8時55分。丘の上に移転した新県庁舎まで出向いて報告。雑談ばかりで書類の作成をあすまで引き延ばそうとする所員を説き伏せて、なんとか書類を受け取ることに成功。
あす、インドネシアのボクシング世界チャンピオン、Elliの試合のことでここの社会全体が動いている。彼らがこの試合を見るための予定にあわせて、こちらの予定を組まねばならないのだ。PauというMeloloの王の末裔の住む村に行く書類をもらった。ところが、この村の村長(旧王の弟)はあすの試合のテレビを見るためにワインガプに出てきてしまう。調査の打診をするならきょうのうちだ。村中の人間もたいていワインガプに来るために村は空になる。調査しようにも聞き取りはできない。Melolo行きのバスは夕方まである。しかし、いま行くと帰れないかもしれない。どうしよう。。。と考えながら荷物を預けたホテルまでもどり、食事をしているところでMという日本人の中年女性と会って、結局、本日のMelolo行きは流れてしまった。
このMという人、埼玉の美術館に勤める40過ぎの(多分独身)女性。よく得体はわからない。インドネシア語話せず、こんな所までひとりで来るというのはただの観光客ともおもわれない。布のことが知りたいというけれど、研究者というわけでもない。話を訊くと、バリで小池さん(都立大の人類学、日本で面識あり)に会ってスンバを紹介されたとのこと。当の小池氏は東スンバで調査中(すでに1年半)、休暇でバリで遊んでいる由。この女性が布の見学にMeloloへ行くのを助けるため、Melolo行きはあすに延期。
ワインガプのホテルは布を売り歩く商人であいかわらずかまびすしい。ひとりをつかまえ、布の品定めをする。気がつくと、こうした商人が周囲にずらりと居並ぶ。
「30万RPだよトゥアン」
「そんなお金ないよ」
「じゃ、いくらなら買うかいトゥアン」
「高すぎて話にならないよ」
「いいから言ってごらんよ。俺もトゥアンのためなら安くするからさ」
「じゃ、2万RPかな」
「7万!」
「3万?」
「4万だ!」
こうしたスンバの布は多くは1万RP程度で仕入れてくるという。差額が彼らの収入になる。時には言い値通りに買ってゆく観光客もいるから、彼らを責めるわけにもいかないけれど。
2月28日(土) 快晴 Waingapu
ワインガプでは、ベモは客拾いをしない。外人観光客が多いせいか。バス停発がすでに定着している。だから7時にバスに乗って10時に町を出るなんてことはない。これはNTT(東ヌサトゥンガラ州)では例外中の例外。クパンでだって客拾いあるからな。
7時かっきり、ワインガプのバス停発。Mさん同行。こっちは村で泊まる覚悟で、重装備でホテルを出る。「どうしてボクシングの試合を見ないの? 戻ってきた方がいいんじゃないの?」と、ホテルの主人。他に楽しみがないからか、このインドネシア人とタイ人の世界マッチが全世界の注目の的だ、と彼らは当然のことのように思っている。
8時40分、Melolo着。市役所で報告。村長宛の書類をもらう。虚ろで物憂いこの役場で所在なく待ち、Pauまで同行の所員とともに出発。Pauは役場から4キロほどの距離にある。しかし、現在風に改造された慣習家屋ばかりで調査の対象にならない。旧王が死ぬ前に遺言したという伝統に則った慣習家屋が丘の上に建てられているというが、村長はすでにワインガプへ発ったあとで見学する機会はなかった。結局、炎天下を布の見学に歩いただけで、午後すごすごとワインガプへもどる。つぎつぎとワインガプへ繰り出す村の若者たちで、特別多いベモもこの日はすべて満員。道すがら追いこす村人たち、ある者は自転車に乗り、ある者はオートバイに乗り、すべてがワインガプへ向かう。
夜、バリ帰りの小池氏とコパリヒ氏がホテルにあらわれる。頭のうすくなった小池氏(僕より年下)は、Wungaというスンバの祖先が最初に築いた村で過酷な調査をしているらしい。5日に一度、往復2時間の水浴、トラックの起点から3時間の徒歩。重要な村ながらヨーロッパの人類学者には耐えられないような過酷な条件のため、いまだに長期の滞在者はいない。コパリヒは要するに日本人相手の小判鮫だ。一昨年すでに会っているけれどもあまりかかわりたくない御仁。もっとも、こちらの好むと好まざるとにかかわらず、食事時になるとかならずあらわれる。
Ellyは負けた。村人たちは金をかけての試合だから異常に熱心。西スンバでEllyが負けた瞬間に死んだ者がいるという後日談。
3月 1日(日) 晴 Waingapu
昨日Rindi Umaluluの市役所でRindiのRatu、Tamburi村の村長と会った。Rindiの慣習家屋はすべて彼の村人が実際の仕事をした。この村にも数棟の古い慣習家屋が残るという彼の話。しかもRatuの紹介だから屋根裏に登ることも支障ない。この村長もボクシングの見物のためワインガプに出るということで、あす(本日)村で会う約束をしてわかれた。
小池氏も同行、Rindiの橋でバスを降り、道に迷いながら村に行く。本当は簡単な道。慣習家屋を見ると、近年の改築で、昨日は古い未改修の建物があると約束したのにまったくの嘘。役場の人間にあるだろうと訊かれたから、私はあると答えた、と彼は言う。村人に、……だろうね?と確認すれば何でもハイと答える。バカ正直にこれを信じた方がどうかしていたと言うべきだろう。こうして小池氏まで巻き添えにしたあげく、また一日無駄にしてしまった。2日で東スンバを終える予定がすでに3日たって、まだ調査家屋すら見つけられない。
夕方、PrailiuのKaburu村にある唯一の慣習家屋、戦前のものらしいが傷みもヒドイ、の見学。家主がおらず、調査の許可は得られない。いまの時期、多くの村人は野良仕事で畑に出ている。
3月 2日(月) 晴 Waingapu
振り出しに戻る。朝PdKで情報収集。現在、東スンバで伝統家屋の生きている地点は、北海岸のWunga、Napと中部のLewaのLailaraという村、Lewaの住居はすでに西スンバ型だから、小池氏の調査村Wungaへ行くしかない。このための書類申請に市役所(Pandawai)を訪れる。会議中で所員がすべておらず、この会議が終わるのを待ち、書類を頼み、このタイプを打ち終わるまで、かれこれ3時間をついやした。
役所近くの(とはいえ約8km)村、Kambatatanaの見学。総数4つのカンポンを見てまわるが、未改修の建物は見つからなかった。村自体をすべて山上から移転した新村にちかい。親切に案内してくれた村人は別れぎわに金を要求。スンバ人の親切もバリ人の親切と変わらないくらいに観光化されたわけだ。
ワインガプを歩く。市場へ行く。「日本人だ」とすぐ見破られる。他の地域だと「ジャワ人?」「バリ人?」と訊かれても、ここは日本人の観光客が結構多いらしい。顔を見ただけで(姿格好かな?)「日本人だね」と言われるからインドネシアへの同化度もいまいちか。もっとも、ハデハデデザインの洋服に着替えてのらりくらり歩けば土地の中国人と変わりはしない。
ホテルに戻ると、小池、M、コパリヒと3人そろって待ち構えていてともに食事。小池氏とあすのWunga行きの打合せ。
3月 3日(火) 晴 Wunga
スンバでは荷物を背負って山歩きをすることはもうあるまい、と考えていたのにまた歩く。クパンで買った12,000RPの靴は底が半分剥げてヒタヒタ音をたてる。これをボンドでくっつけ、バンドンまでもってください、と念じながら再び歩く。
スンバで車に乗って引き回されることはもうない。7時に乗ったトラックは荷台がガラガラにもかかわらず町を出た。快調。大きな川を2度渡り、Kadahang 到着は9時15分。村長とラジャに報告。長期滞在中の小池氏が同行だから面倒なことはいっさいない。村は飢饉で食物なく、村人は山芋をさがして食べているという。ラジャの家で食事をふるまわれているうちに午後2時になり、供の者を一人従え、村へむけて出発。道は、太陽の直射をさえぎる木もないということを除けば、比較的平坦で楽。約3時間半かかってWungaに到着し、シリ・ピナンのふるまいなどを受けているうちに夕暮れとなり、実測をはじめることができなかった。
東スンバの人口密度は極端に低い。Kadahang から Wunga まで、村といえる程度のものはない。雑草のおいしげる珊瑚岩だらけの土地で、水が少ないために農作物の収量は低い。雨のかげんでトーモロコシの収穫がおくれると、途端に飢餓の季節に突入する。
Wunga は丘の中腹にある20棟ちかくの慣習家屋からなる村。村の敷地自体、珊瑚岩が荒い地肌をみせていて、村の建設にふさわしい土地とはいえない。西スンバでは壮麗なドルメン群も、ここでは平滑な岩が入手しにくいためか、このゴツゴツの珊瑚岩を切り出したもので、レリーフは不可能だ。いくつかの古い遺物が残るけれども、この土地の気風も同じで仕上げはきわめて粗い。竹以外に建物に適当な木が近くで得られないこともあって、主柱を除いては頻繁に改修を繰り返してきたものとおもわれる。このなかから、Waimolu という一棟を選んで実測に決定。ラジャ所有の Prain 家も古いが、家屋横にバレ(付属屋)のつく特異な形式。あきらかな後年の追加だが、これもアダットで古い形式に従っているだけと言われれば返す言葉はない。アダットもつぎつぎ塗り替えられる。最近は外国人に金を要求するアダットが多い。

川に橋がかかっていても安心はできない

調査最後の勇姿。体重62kg
3月 4日(水) 晴 Wunga
家屋実測、写真撮影に一日費やす。天井裏にのぼった汚い身体も、マンディ場がなく、そのままで寝る。カユイ。クサイ。
3月 5日(木) 晴 Mondu
ワインガプ行きのトラックが来る日で、今日をのがすと土曜日までワインガプへ戻ることができなくなる。5時起床。実測の続き、写真撮影を終え、あわただしく8時に村を出発。作業の不完全な部分はあとで小池氏に訊ねるしか方法がない。Kadahang まで道に迷いながらも休まず歩き通して、2時間半で Kadahang におりる。
しかし、トラックは現れなかった。一度村をおりてしまった以上、なんとしてもワインガプへ戻るしかない。Kadahang で遅い朝食をとり、ラジャの家に残る小池氏と別れ、Kapunduk に向けて歩く。Kapunduk には市役所の支部があり、ここでこの役所長に頼めばなんとかワインガプへ行く車が見つけられるだろう。
Kadahang から Kapunduk まで約6km。休もうにも木陰もなし。水で濡らしたタオルをかぶってひたすら歩く。約2時間かかって Kapunduk 着。役場前の広場は閑散として車一台、人気もない。定期市場になるはずの露台に腰をおろし、しばしボーゼンとする。話しかけてきた男は、この市場横に小さな店を構えるスンバ人で、スプライト、ファンタ飲まないかね。ビスクエもあるよ。これでは水を頼むこともできない。役所長はクパンに行っていていない。セクレタリスもいない。役所はすでに閉まっている。見わたせば、車はおろか、オートバイすら通る気配もない。露台上には数名の村人が無関心に横たわっている。無気力だけがこの場を支配している。
この露台で一夜をあかすか。さりとて、一夜をあかしたところでワインガプ行きの車があす来るという保証はない。それならば歩いてでもワインガプへ近づいたほうがよい。ワインガプまで約50kmだから、歩けば明日中には着くことができる。疲れてはいるがこうなった以上、他に手段がないのだ。隣村の Mondu までは約10km。急げば1時間半、俺は1時間で行ったことがある。などという時計も持たない村人の話を信じる気にはならないけれど、4kmくらいかな、とはかない期待をいだいて再び歩きはじめた。
道は平坦で問題はない。暑い太陽もすでに西に傾いた。背中の荷物もさして苦痛ではない。しかし、底のうすい靴で荷物を背負って石だらけの道を歩き続けた足の裏がすでに腫れあがって歩くたびに痛い。スピードはだせない。Mondu に着いたのは約2時間半後で、この間、家らしい家すら出会わなかった。足はほとんどいうことをきかない。ヒカラビタようになって村にはいり、最初の家で水を所望する。Kadahang で遅い朝食をとっただけだが、水を飲みすぎたので食欲はない。
村長宅まで行くために大きな川を渡る。靴をぬぐと針の山を歩くような案配だ。ここの村長宅の板床の上にティカールを敷き、よく煮え切らない砂利のようなご飯を食べる。Wunga での実測後、マンディもしていない身体でもう一泊する。まるで兵隊だ。蚊がかまびすしく飛び交っている。
Wunga を朝出発してから7時間歩いた。足が火照って熱い。

Wunga村で過酷な調査実施中の小池誠氏

実測図:平面

実測図:断面

実測図:断面
3月 6日(金) 晴 Waingapu
6時50分、コーヒー一杯を飲んで Mondu 発。途中で非常用に持参した牛肉の Abon(田麩)を食べ、道中の喉の渇きを癒すため、コサンビの実をひろって袋につめる。約15km離れた隣村の Hambaplain まで行けば、ワインガプ行きのベモがみつかる。
足の裏の鬱血はひかず、歩きはじめる以前からすでにビッコ。途中、緩傾斜の坂をのぼることができず、何度も休み、それでも歩く。歩かなければ何もおこらない。人っ子ひとりいない。木陰ひとつない。砂漠のような道を、時々泣き声をあげながら歩く。
Hambaplain 着10時。ワインガプ行きのベモはつい先刻村を出た。今日はもうない。水を頼んだ小学校の先生の家で休憩。食事をふるまわれ、どうにかワインガプ行きのオートバイをさがしてもらって、半死半生でワインガプに戻った。
夕方、どこから聞きつけたのか、コパリヒはまたあらわれ、食事を食べて帰って行った。寄生虫のように。

コサンビの実
私の2年間のインドネシア・フィールドノートはここで終わっています。この後、翌3月7日には、東スンバ県の Waingapu から西スンバ県の Waikabubak へ向かうバスに飛びのり(当時5~6時間の行程)、Wanokaka、Anakalang で短期の調査と家屋の実測。3月12日にバスで再び Waingapu へ舞い戻り、翌日にはスンバ島を後にして、滞在拠点にしていたバンドンへと飛び立ちました。インドネシアを離れるのはそれからおよそ1ヶ月後のことです。
追記:2年間のフィールドワークの目的はインドネシアの伝統家屋についてしらべることでした。携行したのは2台の一眼レフカメラNikon FAとNikon FE2、TTL自動調光に対応したカメラ並みの大きさのストロボ、携帯用でも十分重い当時のVelbon三脚、それに実測用の道具やいざというときの医薬品一式がくわわります。荷物は否応なくふくれあがります。2台のカメラは万一壊れた際の予備機であると同時に、ふだんは屋内用と屋外用のASA感度の違うポジフィルム(コダクロームとエクタクローム)をいれて使い分けていました。これらのフィルム代は1本約1,000円、現像代がやはり同額かかります。学生の身には高額で、2年間あわせて持参したフィルムの総数は120本のみ、現像はもちろん日本に戻ってからで、一か八かの暗い屋内の撮影結果は帰国するまでわからず仕舞い、現像まで時間がたったせいか変色したフィルムもあります。デジカメ全盛のいまでは想像できないことですが、建物以外の写真を撮る余裕はほとんどありませんでした。本フィールドノートにはつとめてそうした写真を載せるようにしています。それでも時にもどかしく感じてしまうのはこうした事情のためです。
いまとなって読み返せば、傲岸不遜な物言いに眉を顰めたくなる部分もありますが、過酷な経験の渦中にあった当時の精神状況をそのまま、あえて記録にのこしておくことにします。(2016.9.22)

フルACならぬ恐怖のフルミュージック付き長距離バス

実測図:平面

実測図:断面

実測図:断面
 「民家調査の現在」『建築雑誌』2014-12
「民家調査の現在」『建築雑誌』2014-12
 フィールドワークを学ぶ人のために
フィールドワークを学ぶ人のために
