タネバル=エヴァヴ
東インドネシア調査記
船出
ヤハと私の軌跡が交差してしばらくのあいだ、たがいの力学に相手をとらえはじめるのは、島へむかうプラフ(帆船)の上のことだった。
私たちの乗った舟は小ケイ島のデブットを午後二時に出帆してタネバル=エヴァヴという名の小島をめざしていた。乗員二七名、くもりがちだった空も外洋に出てしばらくすると晴天にかわり、うねりのないおだやかな洋上を帆走した。風はときに凪いでしまい帆は勢いをうしないがちだったが、海がそのスペクタクルによって私たちを退屈させることはなかった。沖合いで銀色にかがやく腹部をあらわしながら巨大なエイが宙返りをうつかとおもうと、イルカの大群があらわれて舟の左右をならんではしった。
この地域に航行するたいていのプラフは長さ一〇メートル内外、巾は三メートル程度の大きさしかない。その船体の中間に低い切妻形の屋根をかけた部分があって舟の舳先と艫をわけている。屋根の下の穴蔵のような小空間には、乗員のなかでも年長の者たちが日中の日差しを避けてたむろしていた。船室の床は、ちょうど彼らの高床住居のように、船倉の上に割竹のすのこを敷いてあるだけだった。そのためにただでさえ息苦しい室内には船倉に積まれた石油や家畜のにおいがいつも充満していた。若者たち、とくに少女たちはそんな屋内にいることを好まなかった。船室の屋根には屋根押さえの丸太がわたしてあり、この丸太を足場にして若者たちはもっぱら屋根の上に腰かけたり、寝そべって時間をつぶしていた。
私は舳先側の甲板にすわりこんで、舟のためにつぎつぎとあたらしい海面が切り裂かれてゆくさまを飽きもせずにながめていた。
「キョウダイ、タバコアルカ?」
船室の戸口に陣取っていた男が、扉越しに甲板の私によびかけてきた。男は六〇歳ちかい年齢だろうか。島の人間にはめずらしく頭髪が少しうすくなりかかっていたが、これがヤハと最初にかわした会話だった。彼は日本語で何度も私のことをキョウダイとよんだ。それが終戦後はじめて再会したにちがいない日本人に対する親近感のためであるのか、それとも、たんにタバコをせびることのできる外国人相手の慇懃無礼に属するのか、私にはわからなかった。
プラフに乗せてもらうには船賃はいらない。ただ船頭たちのためにタバコを持参すればよいときかされていたから、そのために用意してきたタバコの封を切ってわたした。彼は自分のために二本を抜き取り、残りの箱を船室の奥にいる者たちにもまわした。船頭の手にわたるべきタバコのうちの一箱はこうしてたちまちのうちに煙と化してしまった。ヤハはその後もことあるごとに私の持参したタバコを催促したので、舟をおりるころには、一本のタバコも船頭には残されていなかった。
ヤハはこの一帯が日本の統治下にあった時代に日本軍の通訳をしていた。
「モシモシ、モシモシ、ヒコーキオクル。イチ、ニー、サン、シッ・・・・・・。」
ヤハは喜々として、おぼえているかぎりの日本語を私に披露した。それはおよそ四十年の歳月を経てはじめて意味をもって発せられた音声にちがいない。
「オーストラリアノヒコーキ、バクダンボムボム。」
小ケイ島の中心トゥアルは日本軍の海軍基地となっていたために爆撃をうけたのであった。この期間中にトゥアルに建てられていた伝統的な民家は一棟を残してことごとく焼けてしまった。空襲はやはり海軍基地のあったケイ=タニンバル島もおそい、村への入口にかかる高さ十メートルちかい木製の梯子も被弾して一部が破損した。切り立った丘の上にある村までの近道に、海岸道から梯子がかけられていたのである。はしごには見事な浮き彫りのある扉がとりつけられていたが、それも被弾の記憶をとどめるかのように壊れた状態のまま放置されていた。
戦争や日本軍が島の人間たちの上に果たした意味は、善悪の二項対立のなかではとらえきれないものであることをそのときに私は知った。島では生や死さえもが海のむこうから訪れるできごとだった。そのようにして、戦争は彼らの理解のおよばぬところからやってきて彼らの眼前に出現した。暴風雨や荒波への対応が島の生活に不可避であるように島民たちはこの事件にも対処してゆくほかなかった。島に生きる老人たちの多くにとって、日本時代がもっとも生き生きした話題の源泉でありつづけるのは、むろん彼らじしんの輝かしい若さの記念ゆえでもあるが、それと同時に、戦争を通して個人の体験を社会の体験にむすびつけ、個人の口をかりて社会を語る至福を手にいれていたからである。共有する事件の記憶をもつことのない共同体が存在したためしはなかった。
舟の上では食事がはじまっていた。私は食物をもちあるく余裕がなかったので、差し出されるままにエンバルというその煎餅をうけとって食べた。エンバルはキャッサバを粉にしてうすく固めたものを、焼いて乾燥させてつくる。トゥアルの市場では携行食としてのエンバルを何十枚もたばねて売っていた。無味乾燥のざらざらした舌ざわりだけが味覚のすべてだった。空腹にかられて勢いこんで口にほうばったせいで、唾液がうばいさられ、喉につかえてまったく飲みくだすことができなくなった。水と一緒に少しずつ食べるものだ、と島民のひとりが壜入りの水を差しだしてくれた。島に里帰りする女学生たちは、エンバルには見向きもせずに、乗船前に買いこんだビスケットを屋根の上でかじっていた。
30年以上前の『群居』に掲載した文章。当時は自分の体験を知ってもらうために書いたつもりでいたが、将来の自分に向けたメッセージだったのかもしれない。いまの自分にはとても書けない。極私的感慨ゆえに、リフォームのうえ写真を追加して再掲する。将来ふたたびめぐるかもしれない自分自身のために。本文中に登場する人物はすべて実名ですが(存命だとしても)笑って見過ごしてくれることを期待して。2021年元日
 冒険ダン吉 1986.6.11
冒険ダン吉 1986.6.11
 船体の中間に低い切妻形の屋根をかけた部分があって舟の舳先と艫をわけている
船体の中間に低い切妻形の屋根をかけた部分があって舟の舳先と艫をわけている 船室の屋根には屋根押さえの丸太がわたしてあり、この丸太を足場にして若者たちはもっぱら屋根の上に腰かけたり、寝そべって時間をつぶしていた
船室の屋根には屋根押さえの丸太がわたしてあり、この丸太を足場にして若者たちはもっぱら屋根の上に腰かけたり、寝そべって時間をつぶしていた 島に里帰りする女学生たちは、エンバルには見向きもせずに、乗船前に買いこんだビスケットを屋根の上でかじっていた
島に里帰りする女学生たちは、エンバルには見向きもせずに、乗船前に買いこんだビスケットを屋根の上でかじっていた エンバル embal はキャッサバを粉にしてうすく固めたものを、焼いて乾燥させてつくる。いまはこんなオシャレな形で売られていますが当時は違った。写真は2019年テルナテの市場にて
エンバル embal はキャッサバを粉にしてうすく固めたものを、焼いて乾燥させてつくる。いまはこんなオシャレな形で売られていますが当時は違った。写真は2019年テルナテの市場にて順風にのれば五時間ほどで島に上陸できるときかされていたが、結局、島影ひとつみえない海のまっただなかで日没をむかえた。巨大に膨張した太陽がゆらゆらと揺らぎながら圧倒的な量塊で水平線にかかっていた。その光芒によって、空も、海も、舟も、風をはらんだプラフの帆も、舟上にいてこれをながめる島民たちの顔も、ありとあらゆる存在物のすべてがおなじ色に染まっていた。それ以外のものはここに存在していなかったし、それ以外のものとの関係を否応なくおもいださせるさまざまな痕跡、電話や無線機の類でさえもなかった。時間は音をうしなっていた。少なくともこの一瞬には「私」であることにどんな意味があったろう。そのときに私たちはこの光景をかつて経験したことがないほど荘厳なものとかんじていた。だがいっそう驚くべきなのは、実はこうした光景が地球上のあらゆる場所で、毎日、かならず繰りかえされる現象にすぎないということだった。
私たちを乗せたプラフは、波と風のまにまをただようだけで、人間社会のもつ時間や空間の観念による束縛からは隔絶された地点にいた。私は孤立していたが、だからといってひとりではなかった。私は舟にいるほかの人々も同じ感覚をもつことを確信していたし、なによりもこの感覚を人類全体に敷延することによって、私じしんが彼ら全員の孤独を確信した。それなのに、そうおもう私の感情は少しも共有されてはいなかった。見わたすかぎり唯一物もない大海原をただよう一漕のプラフとそれに乗りくむ二七人の運命共同体を映像にとらえて、私の帰属する社会に伝えてくれるべきもう一漕の舟は、どこをさがしても見あたらなかった。
民族学者は長い期間、彼の帰属する集団からひきはなされ、彼が身をさらす変化のはげしさによって、慢性の故郷喪失症におちいるという。彼はどこにいても自分じしんの社会にいるという実感がしなくなるのである。
私はジブ(前帆)を支えるステーにしがみつきながら舟の舳先に突き出したバウ・スプリットの先端まで伝い、波にあわせて大きく上下に振幅する不安定なその位置で、夕日を浴びながら帆走するプラフの全景を写真におさめた。探険談の筋としてはまさに格好な、このカラースライドを見せられることになった聴衆の何人が、その写真のなかに病的な精神の徴候をみとめるだろうか。私はそのようにしてしか私の故郷の社会との接点をみいだせないことに気がついた。
無限に探険を繰りかえすなかから、純粋な探険が結晶するものであるならば、探険を単調な日々の生活の一部としてしまった人々こそ真の探険家たちだった。南洋の孤島の住人にとって、朝の一定時間に、まったく見知らぬ人間同士が満員の電車に乗り、永遠に交差することのない軌道をたもったまま、それぞれまったく別の目的地にむかう、という生活ほど真に探険の名に値する事態はあるまい。しかし、本当のところは、現代の探険は蝕まれた精神の産みだす記録によってはじめてつくられるのである。
夜にはいってうねりが強くなり、舳先は波に洗われてもはや甲板に居続けることができなくなった。若者たちは、傾いた屋根の上で毛布をかぶって横になっていた。私は仕方なく船室にもぐりこんだ。油のにおいと人いきれで船室の空気は重苦しくよどんでいた。そのうえ、波しぶきの侵入を防ぐために、船室の板扉は閉ざされていた。狭隘な室内で乗員たちの多くがすでに寝ていたから、身動きすることもままならなかった。腰をかがめずにたちあがれるほど満足な高さは確保されていなかったし、横になればなったで足が壁につかえた。眠ってしまう以外にこの苦役の感情をのがれるすべはなかった。
舟が大きな波を越すたびに、船体は激しい落下を繰りかえし、体は無理な姿勢のまま右に左に揺れていた。けれども、短時間のうちに次々と直面することになったあたらしい事態のために、私の感覚はとっくに麻痺していた。これが現実だとすれば、それは少しも現実的な様相をおびてはいなかったのだ。ちょうど芝居でも見物するように、私は自分じしんの言動を客観的にながめることができた。つぎになにが起こるかわからないにもかかわらず、すべては予測済みであり、私はさだめられた筋書き通りに私という存在を演じているにすぎなかった。だから首尾よく舞台をおえた役者が、自分の演技をふりかえるように、一日のうちに起こったもろもろの出来事を再確認してゆくときの気持ちは、現実の悔恨や苦難の感情からはほど遠かった。いつもきまってこみあげてくるのは得体の知れない笑いなのである。このときもたぶんそうしたうすら笑いを浮かべながら、何度か浅い眠りにおち、何度か目をさました。
満天の星空をあおぎつつ屋根の上の少女たちの歌いつづける歌声が船室にも流れていた。
その前年のこと、このプラフとまったく同型の帆船が島へむかう途中で沈没した。六四人もの乗組員がいたが、助かったのはわずか一四人にすぎなかった。島で生活していてもほとんどの女たちは泳ぎが不得手だった。それで、舟が転覆すると、女たちは手あたりしだいに男にしがみついた。やがて力つきて男が沈むと、女もあとを追った。こうした海難事故で助かるのは、たいてい女につかまる心配のない泳ぎのうまい少年だった。この事故がおきたとき、海はいたって穏やかであったが、過重な乗員のために帆を繰りそこなったらしい。舟にはたまたま教会の牧師が乗りあわせていたから、邪教の伝導をきらった島の神々が舟を島に寄せつけなかったのだと島の保守的な人間たちは噂した。
少女たちの歌は、舟を災難から守るものと信じられていたが、気がつくと、その歌声もいつしか聞こえなくなり、波の砕ける音とそのたびに船材のきしむ音だけが耳に残った。
島に到着したという知らせが船室内に伝わり、私は起きあがって甲板にはいだした。船室で横になってからずっと眩暈と嘔吐感にさいなまれていたから、息苦しい穴蔵をのがれて新鮮な夜気にあたるだけでも心地よかった。真黒な海のかなたにほのかな島の明かりが見えていた。舟についたカンテラの光をうけて舟べりを流れ去る海のあちこちがキラキラと発光していた。随分時間がたったとおもっていたのに、時計を見るとまだ一〇時をすぎたばかりだった。デブットを出帆してから八時間が経過していた。
幸福の観念は相対的なものでしかない。うす暗い倉庫のような殺風景な一室におかれた、布団もマットもない堅い木枠だけのベッドでさえ、このときの私には十分すぎるほどの幸福の対象だった。五時間の予定が八時間になっても、これでようやく揺れることのない寝床で、手足をのばしてやすらかに眠れるとかんがえるとさすがに胸がときめいた。
けれども、この期待はみごとに裏切られた。舟はタネバル=エヴァヴ島を側舷にながめながら帆を降ろし、そのまま投錨した。入港は明朝、湾内に潮がみちるのを待ってからということになり、ふたたび手を縮め足を屈めて舟の揺れに身をゆだね、苦しく浅い眠りのなかに舞い戻ってゆくしかなかった。(1989- 2-28)
 巨大に膨張した太陽がゆらゆらと揺らぎながら圧倒的な量塊で水平線にかかっていた
巨大に膨張した太陽がゆらゆらと揺らぎながら圧倒的な量塊で水平線にかかっていた 私はステーにしがみつきながら舟の舳先の先端まで伝い、夕日を浴びながら帆走するプラフの全景を写真におさめた
私はステーにしがみつきながら舟の舳先の先端まで伝い、夕日を浴びながら帆走するプラフの全景を写真におさめた前哨戦
タネバル=エヴァヴ島に上陸した私が巻きこまれることになった事件の顛末を物語るまえに、出発前の小ケイ島で起こったさまざまな出来事をしるして、この事件の伏線をあきらかにしておこう。
タネバル=エヴァヴ島はケイ(エヴァヴ)諸島の南西、タニンバル(タネバル)諸島へむかう航路の途上に位置している。インドネシアの行政上は、マルク州南東マルク県小ケイ郡タニンバル=ケイ村というのが人口五〇〇人にみたないこの島唯一の村の正しい名称である。小ケイ島のトゥアルは南東マルク県の県庁所在地にあたり、調査に先立つ諸機関・・とくに、内務省社会政治局、軍、警察・・への報告と事務手続はこの町で済ませておかねばならなかった。
この国で調査に従事する幸運をえた者は、同時に、研究や調査が浮世をはなれた学の世界よりもむしろ政治の領域に属するものであることを、調査地へおもむく以前の諸手続のうちに発見するだろう。顕在的な仕方ではないにせよ、それは私たちの社会でも真実なのである。
事務手続! その実体は恭々しい型通りの報告、つまり、より上位にある機関発行の書類を提出して、より下位の機関あての書類を申請し、この書類をつつがなく手にいれるまでの数時間をたいてい話題のきまった世間話、たとえば彼の遠い友人が日本へ行った体験談だとか、むかし出あったことのある私の知るはずのない日本人の逸話だとかに費やして待つか、あるいは、しかるべき人物のサインが貰えないために、書式のきまったたった一通の書類をうけとるまでの何日とも知れぬ日数をなすすべもなく役所との往復にすごすことになるのか、そして際限のないその繰りかえし。
調査の主要部分はこうした折衝のための一見無意味な作業によってしめられていた。そのようにして、見ず知らずの土地で有効な人間関係を築きあげることができるかどうかに調査という演劇的な行為の成否はかかっていたのである。
こうして立ち寄った公共事業省の県出張所で、私は所員のヤムコとめぐりあうことになった。ヤムコはタネバル=エヴァヴ島の出身者で、村長は自分の兄だから心配はいらないと言い、島へわたりたいという私のために奔走してくれた。
夜になってどこから聞きこんだのかタネバル=エヴァヴ島の住人と名のる男の訪問をうけた。
「ボス、タネバル=エヴァヴ島へわたる舟をさがしているのだったら、あすわれわれは出発できる。」
月の光を背にして戸口に立ちはだかる男の顔は陰をおび、つめたく無表情な目が私を見つめていた。
値段は?「そんなに高くない」
何時間かかる?「五時間くらいだ」
ジョンソン(モーターボート)か?「プラフさ」
モーターつきか?「プラフ・ラヤール(帆船)だ」
私にはこの突然の訪問者の真意がはかりかねた。島の人間だと男が言う以上、邪険にあつかうことはためらわれたが、突然出現した胡散くさい男の言い分をそのまま鵜呑みにはできなかった。ヤムコに会って意見をきくことが男とのあいだに望ましい平衡関係をたもつための最善の手段だった。
トゥアル湾を見おろす小高い丘陵の斜面にそって道は縦走していた。沿道にある家々の窓辺では若者たちがギターにあわせて合唱していた。男は私の横によりそうようにして歩いた。しばらく沈黙があってから、男は重い口をひらいた。
彼には島に残してきた妻子がいた。随分長いこと会う機会がなかったが、あす帰島するにあたって手土産にするためにいくばくかの金銭・・男の指定した額は、外国人が何がしかの便宜を期待するさいに役人にわたす、あるいは役人のほうがそう期待するところの賄賂とかんがえるなら、けっして不相応な高額とはいえなかった・・を恵んでほしいというのだ。
彼の口調はなぜかぞんざいで、私はこの身の上話の真実を直感した。けれども私は彼の申し出をこばんだ。それが私の帰属する社会で同じ事態に直面した時に、当然とるであろう態度だと信じたためであるが、心のなかに生じた波紋は拭いされなかった。私と彼の境遇にどれだけの違いがあるというのだろうか。いまさら舟の話に拘泥する理由はなかったが、私たちはそのまま月あかりの道を歩きつづけた。
ヤムコの家は彼のつとめる出張所の裏手にある官舎だった。コンクリートブロック積みの二戸一棟型の国民住宅の一戸をさらに薄い板壁でしきって、二世帯が共用していた。トゥアルでは午後六時から十時までしか発電機が稼動しなかったから、この訪問はそれより遅かったのか、それとも家に電気器具をそなえていなかったせいか。ともかく、私たちはうす暗いケロシンランプの明かりだけをたよりに舟の相談をはじめた。
プラフは転覆のおそれは少ないが、揺れが激しいために慣れない人間は船酔いにかかる。そのかわり船賃はいらないのがふつうで、タバコをやるとか、それも面倒なら横に寝転がっているだけのことだ、とヤムコは話した。男とのあいだに二言、三言ことばの応酬があったが、男はそれ以上異議をとなえなかった。ヤムコの話がとぎれるたびに板壁のむこう側からもやはり低い押し殺した人声が流れてきた。
当時のこの海域の船舶事情
 カパル Kapal : 国営の船舶会社 Pelni の大・中型金属船で、月に2度アンボン、ケイ、タニンバルをまわる航路と、それ以遠の南東マルクへ行くKapal Perintisがある
カパル Kapal : 国営の船舶会社 Pelni の大・中型金属船で、月に2度アンボン、ケイ、タニンバルをまわる航路と、それ以遠の南東マルクへ行くKapal Perintisがある モートル Motor : 私営の小型金属船。大ケイ島のElatと小ケイ島のTual間に乗員100名程度のモートル船が3隻運航していた。
モートル Motor : 私営の小型金属船。大ケイ島のElatと小ケイ島のTual間に乗員100名程度のモートル船が3隻運航していた。 ジョンソン Johnson : 小型の木造船にモーターをつけたもので各村で所有している。写真は島の沿岸航海用で、小ケイ島、タニンバル=ケイ島間など外洋航海用のボートは船巾が広く揺れに強い
ジョンソン Johnson : 小型の木造船にモーターをつけたもので各村で所有している。写真は島の沿岸航海用で、小ケイ島、タニンバル=ケイ島間など外洋航海用のボートは船巾が広く揺れに強い 木造帆船 Perahu Layar。一人乗りから数十名程度まで大きさは様々。家畜や荷物の搬送にはもっぱら燃料のいらない帆船が利用された。乗客はそのおまけ
木造帆船 Perahu Layar。一人乗りから数十名程度まで大きさは様々。家畜や荷物の搬送にはもっぱら燃料のいらない帆船が利用された。乗客はそのおまけ 小ケイ島の中心トゥアル
小ケイ島の中心トゥアル 立ち寄った公共事業省の県出張所で、私は所員のヤムコとめぐりあった
立ち寄った公共事業省の県出張所で、私は所員のヤムコとめぐりあった
翌日、ヤムコと二人してタネバル=エヴァヴ人の船頭を訪ねたが、昨夜の男の話しにあった舟は影も形もなかった。私だけの特別船をチャーターする余裕もなかったので、いつ出るともさだかでない船便を待つことになった。
ケイ島に到着してからちょうど十日目の朝、私は舟の出航の知らせをきいた。タネバル=エヴァヴ島ではおりしも新築中の慣習家屋があり、小ケイ島在住の島民たちは屋根葺きの儀式にあわせて帰島する手筈になっていた。
私は書類の催促におもむいた県庁で担当の係官をつかまえることができず、仕方なくヤムコの事務所にたちより、そこで、偶然にも舟の情報を耳にしたのである。ヤムコの話では、舟は島の南部にあるデブットという港を午前一〇時に出航の予定だったが、このときすでに時刻は八時をまわっていた。
郡役場から村長宛の書類をうけとることがなによりも先決だった。せっかく調査地まで行きながら書類の不備のために調査を断念することはめずらしくない。徹底した教条主義と、裏腹な放縦が均衡をとりつつこの国を動かしていたが、外国人や調査という概念はあらかに教条主義の範疇だった。
村長以外に時計をもつ者もいない島の人間の口にした一〇時という言葉を吟味する余裕は、そのときの私にはなかった。ヤムコをうながし、あわてて郡役場を訪れたものの、休日あけのために郡長も副郡長も登庁していなかった。三〇分ほど遅れて登庁した副郡長は、部屋の鍵を忘れてきたことに気がついて、扉の外に呆然とたちつくしていたが、すでに用意のととのったタニンバル=ケイ村あての書類はこの男の机の上にならべられていた。
海岸ぞいの市場の一画に、タネバル=エヴァヴ島民たちがトゥアルの町で根城とする家があった。地方の村の者たちは、たいてい主要な町にこうした村の共同家屋を所有している。私はケイ島に着いた最初の日にこの家を訪問して、調査のために入村の予定である旨を伝えていた。住人たちはみな素足にぼろ切れ(とそのときはおもった)をまとい、長老とおもわれる男が理解不能の日本語で私の相手をした。家の戸口にも窓にも女や子供たちの土褐色をした顔が無数にのぞき、好奇にみちた眼差しを私にむけていた。
いまはその家でヤムコの父親が私を待っていた。出航予定時間はとうにすぎていたが、彼は私を市場にさそい、儀礼のために持参すべき品々、トゥンバコ、シリー・ピナン、アングル、キャンデーを悠然と品さだめして私に購入させた。
トゥンバコは袋入りの紙巻タバコで、一般のタバコにくらべてずっと廉価で強力だったから村人たちは好んでこれを吸った。シリー(キンマ)の実(または葉)と、ピナンの実(檳榔子)は石灰とまぜて噛む。東南アジアの多くの民族は渋柿を口にふくむようなこの刺激を日常の習慣にしていた。とくに老人たちは朱色に変色した噛みかすをところかまわず吐きちらしたから、家の周囲や床下にはたいてい無数に赤い斑点がちらばっていた。シリー・ピナンは客を迎えるさいの必需品であったし、儀礼では重要な供物の一部をなしていた。アングルは壜入りのあまい葡萄酒であり、酒が飲めない人々のためにキャンデーがあった。
デブットまでは小型バスで小一時間、島まで案内してくれることになったヤムコの父親ばかりか、トゥアルを発つ島民全員がトゥアルのターミナルで私たちの出発を待ちかまえて私の同伴者となった。舟がデブットを出航したのは、乗客全員の到着後さらに二時間あまりたってからのことだった。
私は、彼らの社会の人間関係が巻き起こすさまざまな軋轢や、政治的、経済的な規制から切りはなされたうぶな大富豪というわけだが、この富豪はといえば、彼の属する社会では、物質的、精神的な無産階級にすぎなかった。そのうえ滑稽なことに、彼はこの土地の文化や社会の内部の人間たらんことを一人夢見ているのだ。
動物や昆虫が本能の命ずるままにそれぞれ固有の形態の巣をつむぎあげるように、ある人間集団は、成員全体がだれの指図によることもなく、緻密にデザインされたとしかおもえない建築形態をいとも容易につくりあげていた。集団全体としてのおどろくべき特異性と、対照的な集団内の個々人の没個性とは、私たちの集団の直面している事態の対極にある。
いわば私は、近代文明をなりたたせる価値観や人間関係とは異なる制度に支えられた可能性を彼らの社会のなかに期待していたことになる。ところが彼らの流儀は、一見したところ、あるがままの現実をうけいれ、自分の頭でかんがえる面倒をはぶき、習慣や制度の命ずるままに行動し、いつも第三者からのほどこしを待つことなのだった。
私の求めていた「建築」は、特殊な階級にある個人が、彼じしんの創造力とやらいう支配欲の充足のために、ほかの人々の創造力を従属させることによって成立する「作品」なのではもちろんなかったし、また、さまざまな商業戦略や理不尽な制度のにおいをかんじとる以前に、そのような形で発揮される自由な人間性の発露に感動するだけの美的感覚を、私はもちあわせていなかった。だが、だからといって商品としての建築生産を確立するだけで、問題が解決できるものでないことを、私の目のまえの現実は物語っていた。商品の論理は、矛盾をはらみつつも私たちがしたがう論理を極点まで推しすすめ、問題そのものを解消することでしかない。
「住むための機械」は流通貨幣となったろうか?
そうコルビュジエは著書の冒頭で記している。質的な差別を量的な差異に還元する貨幣のように、「住むための機械」は住宅にまつわる因習的なヒエラルキーの解体をもくろんでいる。しかし、流通貨幣も住むための機械も、量的な差異まで解体する制度を保証しているわけではない。私たちはしたがうべき規範だけが解きはなたれた社会にようやく到達したところだ。
 トゥアルの市場
トゥアルの市場 儀礼のために持参すべき品々、トゥンバコ、シリー・ピナン、アングル、キャンデーを悠然と品さだめして購入した
儀礼のために持参すべき品々、トゥンバコ、シリー・ピナン、アングル、キャンデーを悠然と品さだめして購入した 舟がデブットを出航したのは、乗客全員の到着後さらに二時間あまりたってからのことだった
舟がデブットを出航したのは、乗客全員の到着後さらに二時間あまりたってからのことだった上陸
熱帯の太陽が生気を取りもどすまでの朝の一瞬、このわずかな時間のあいだに人はあらゆる微細なものに宿る色彩の綾を確認するだろう。昨夜の冷気をのこす大気を震わせて朝日がほとばしる。暗鬱に島全体を縁どっていた海辺のマングローブにほのかな朱がきざし、みるまにあざやかな萌黄色につつまれてゆく。海は刻一刻と透明度をふかめて青緑の輝きをとりもどしはじめる。やがて、この緊張と生命感に漲る一瞬ののち、急速に温度をあげ、容赦ない日射と蒸しかえる湿気のただなかで、ふたたび細部をうしない、物憂く単調な南洋の一日が開始されるのだ。
プラフは、ジブとメンスルに風をはらんで島の入江をめざしていた。島からはゆるい向かい風が吹きよせ、舟体はタッキングをくりかえしながら、ジグザグの航跡を海にえがいた。湾内にはいり、メンスルをおろすと、座礁を避けるために木の竿で水深をはかりながら航行をつづけた。海底ではくろぐろとした海藻がぶきみにゆらいでいた。とうとうこれ以上近づくと危険とおもわれるほど海が浅くなったときにようやく舵をきりプラフは停船した。
島の者たちは水平線にあらわれるどんなに小さな変化でも目ざとく見つけることができる。空と海との均質な空間のなかから、私には見出すことすら困難なその黒い点が、沖合いを巡航する大型船舶であるのか、他島からやってくるプラフか、あるいは、島の釣舟であるのか、彼らは本能的に言いあててみせた。私たちの乗った舟の到着も、こうして村の者たちはとうに予測していたにちがいない。
陸地との橋渡しのために、プラフにはかならず小型のカヌーが備えつけられている。トゥアルのようなよほどの町でもないかぎり、港には桟橋というものがない。投錨と同時に、カヌーを甲板からすべりおとし、若者がひとりで跳びのって島への連絡に漕ぎだしていった。それに呼応するかのように、島影からは迎えのカヌーが姿をみせた。
乗客たちは二漕のカヌーに乗り移り、何回かにわかれて島に上陸した。乗客、とくに女性たちは我勝ちにカヌーに乗りこもうとした。そのため、私はヤムコの父親とともに最期まで船上にとりのこされた。
カヌーは船頭をふくめて三人乗るのが精一杯の大きさだった。船底にたまる水をココヤシの内核でできた椀によって掻い出していたが、吃水線が高いためすぐにまた侵水した。島民たちはせっかくの晴れ着を濡らさないように、膝をついて踵の上に腰をおろすようにしていた。しごく簡単そうなその格好がカヌーの上では予想外の難事であることを私は経験的に知っていた。以前に私の不注意からバランスをくずしカヌーを転覆させたことがある。私は濡れるのもかまわずなるべく低い姿勢で船底にすわりこんだ。
プラフの停船位置から陸地まではまだかなりの距離を残していたが、漕ぎ手は両端に櫂のついたオールをたくみに操り、カヌーは白い泥土のつづく浅瀬をすべるように走った。島全体をおおうジャングルがみるみる眼前にせまり、私たちの乗ったカヌーはマングローブの樹海に吸いこまれるように島の一画に乗りあげて止まった。鳥の叫びをまぢかに聞きながら、突然おそいはじめた熱帯特有の大気のなかで、とめどもなく汗が吹き出してくるのが感じられた。
 暗鬱に島全体を縁どっていた海辺のマングローブにほのかな朱がきざし、みるまにあざやかな萌黄色につつまれてゆく
暗鬱に島全体を縁どっていた海辺のマングローブにほのかな朱がきざし、みるまにあざやかな萌黄色につつまれてゆく
 島の者たちは水平線にあらわれるどんなに小さな変化でも目ざとく見つけることができる
島の者たちは水平線にあらわれるどんなに小さな変化でも目ざとく見つけることができる
私たちが上陸した地点は、村の西のはずれにあたった。あとでわかったことだが、この一画は村の鍛治、大工などの作業場になっていた。木立のなかに建設中のプラフがあり、木漏れ日をうけて、ほとんど完成した船体が白い腹部を見せていた。村の中心までは湾をめぐり、木立のあいだを縫うように小径が通じていた。
村の中心部は通りを介して両側に整然と家々の敷地がならんでいた。柵で囲われた庭のなかに各戸の住居が建つという景観は、現在の南東マルク州のどこの島でも見ることができる。これがキリスト教会の援助を受けて計画された新しい、そして、理想的な村落の姿なのである。道の突端、つまり村の東のはずれにプロテスタント教会と墓地があり、私がこの島で寝起きすることになった村役場の建物は教会の手前に位置していた。
村長のヨセフは無精髭だらけの頬を左右交互に私の顔に押しつけて迎えてくれた。この挨拶は私にはまったく予想外の事態だったので、おもわず顔をそむけることになった。
なぜ文明国からきたはずのこの客人は、文明人流の挨拶をこばむのだろうか?
数年前に、この島にはフランス人の若い女性人類学者がくらしていた。村長はまだ彼の父親がつとめていて、結婚前の青年だったヨセフは彼女の有能な助手として行動をともにした。
ヨセフはそのときの経験をとおして、人類学者の調査手法をまなび、人類学にめざめたらしい。理論がわからないとこぼしながら、彼は村の人間の出自をしらべあげ、克明にノートに記入していた。私がカメラの整備をはじめると、おそらく彼女の置土産だろうカメラをもってあらわれ、フィルムさえあれば私しか見ることのできない儀礼の写真を撮影できると訴えた。
私は彼女と結婚してもよいとおもっていた、とあるときヨセフは私にむかって語ったことがある。その彼女は帰国後、フランスで博物館の館長をつとめる老人類学者と結婚した。私たちがいる役場の建物のがらんどうの空間にはおよそ飾りというものがなかったが、ただ壁の一画に、彼女から送られてきた写真だけが飾ってあった。写真のなかの彼女はすでにふたりの子供に囲まれていた。
ヨセフの妻があらわれ食事の支度ができたことを告げた。
「島にはパンもチーズもないので粗末な食事しかできません。」
人のよいこの細君は本当にすまなそうな顔をして私に村の食事をすすめた。島では米が生産できなかった。島民たちは粟や芋類を主食にしていたが、特別の機会には島外から輸入した米を食べることがあった。この日の食事にはその米の飯が焚かれていた。
人類学者の目的がいかなるものであれ、こうした島で彼(彼女)らにあたえられる役回りは現代消費文明の身近な象徴としてのものなのである。
ヨセフがいまでも熱心におこなっている人類学的な調査と、村長や牧師として彼の立場に期待される近代化という欲望(それは彼自身が欲していることでもある)の対象をヨセフ自身がどう内面化しているのか、私は知らない。この島にパンやチーズがあれば、ヨセフはまっさきに粟や米をすててそれを食べるだろうし、オートバイをもてば、島中の道をオートバイの通行にふさわしく改めようとするだろう。
オートバイ、ラジオ、カメラ、テープレコーダー、腕時計、ライター、石油ランプなどの工業製品は、民族文化を愛する人類学者によって、彼らじしんの社会的地位をたもつためにもちこまれ、島民の近代化に対する欲望を煽りたてているというわけだ。
ヤムコの父親は私をこの建物まで案内し、ヨセフに紹介して以来、ずっと椅子に腰掛けていた。彼は一言も発せず、おだやかな笑いを浮かべながら私たちの会話に耳を傾けていた。島の人間にしては端正な風貌や物腰は、村の知識人という印象を彼にあたえていたが、このときに私のいだいた感情はそれとはまったく異なるものだった。
彼のうすら笑いは私や私のひきおこす問題に対するいっさいの無関心、そういって悪ければ、彼自身の手にはおえない世界のでき事に対する諦念の表明手段だった。私とヨセフのあいだに交わされる会話がどんな内容であろうと、彼はそうやって笑みをたたえながらおとなしく傍らに侍っているにちがいない。食事の用意がととのい、私たちが席をたつのをしおに、彼はそそくさと帰っていった。
私はヤムコの話から、村長とヤムコが実の兄弟だとおもい、ヤムコの父が同時に村長の父親でもあることを疑わなかったが、これは重大な誤りだった。「兄弟」はここでは私たちが字義通りに解釈するよりもはるかに広い人間関係を意味していた。親族関係をあらわす名称が、それじたい人類学の重要な研究対象となることを私は知らなかったわけではない。が、現実にこうした局面に遭遇してみると、彼らが私を誤解しているのと同様に、私自身が言葉を介して理解しているつもりの「彼ら」に対してもあらためて懐疑的にならざるをえなかった。
 カヌーはマングローブの樹海に吸いこまれるように島の一画に乗りあげた
カヌーはマングローブの樹海に吸いこまれるように島の一画に乗りあげた 村の中心部は通りを介して両側に整然と家々の敷地がならんでいた
村の中心部は通りを介して両側に整然と家々の敷地がならんでいた 海岸沿いの家畜小屋
海岸沿いの家畜小屋 村長のヨセフとその家族
村長のヨセフとその家族
食後、ヨセフにつれられて、崖の上の伝統村でおこなわれている家屋の屋根葺きを見物に出かけた。
私がいる海辺の村落は、実はキリスト教に改宗した者たちが居住する新村にすぎない。原始宗教を信じる本来の伝統村は海岸から断丘状に高まった土地の上に位置していた。新村とのあいだは切り立った崖になっていて、十数メートルの高さの梯子が両村をむすんでいた。むかし梯子の最上部には門扉が築かれていたというが、太平洋戦争中に被弾してこわれ、最後の数メートルは岩伝いにのぼることを余儀なくされた。村の女たちは頭の上に水のはいったバケツをのせたまま頻繁にこの梯子を上下していた。
崖の上にはゆるい傾斜地をなした村の領域があって、そこに二十棟ちかい伝統家屋が建ちならんでいた。これらの家屋はすべて固有の名称をもち、この島出身のあらゆる村人は、どれかの家屋に彼自身の出自を有することによって島民としてのアイデンティティーをえていた。そのため、新村が開かれる以前にはしばしば数十人をこえる人間がひとつの家に起居していた。
「伝統家屋」という表現は、あるいは正確さを欠いたかもしれない。家屋は歴史上のある段階で、一定の人間集団に共通した一定の形式を獲得していたとかんがえられている。このような時間的、空間的にかぎられた範囲で成立した居住形態のことを私たちは伝統家屋とよぶ。
かくして、この村でもっとも普遍的な家屋の形式は、棟を海に平行に向け、三つにわかれる内部空間(その左右の空間をたがいに異なるふたつの出自集団が占めている)をもった木造の高床住居である。ところが、それはけっしてこの村で伝統家屋と目されるために不可欠な条件ではない。それどころか、家屋のいくつかはコンクリートやトタンといったずっとあたらしい材料と構造をもちいて建設されていたし、ちょうど建て替え中の「伝統家屋」もまたコンクリートの布基礎の上に製材された規格材の柱が立ちあがっていた。
伝統はある民族の歴史をになうべく文化的に選択された骨董品やそれを産みだす行為のうちにあるのではない。たとえある種の伝統をうしなったとしても、私たちは容易に別な物に仮託してあらたな伝統を創出するだけの話だろう。そうではなくて、私がその時まで伝統についてかんがえていたのは、近代化といった新しい変化の局面に対して、従来の社会関係や個人のアイデンティティーを維持するように意識される多かれ少なかれ保守的な概念のことだった。結局、私たちはそうした概念を具体化できる対象を、私たちの現在を成立させた過去の遺物のなかに追い求めているにすぎない。
ところが、私の目の前でつくりあげられてゆく伝統は、こんな思惑を突き抜けた先でいとも軽やかに存在していた。
ここでは、伝統は近代と対立するどころか、外来の新しい技術は何よりもまず伝統家屋において実現されることが期待されていた。それにもかかわらずこの建物が伝統家屋であり続けるのは、建設にあたって村全体を巻き込む儀式をともない、家屋のなかに伝統家屋に要求される儀礼の施設をもつことによるのである。伝統はここでは公的、共同体的な生活の範疇に属するものであって、近代の対概念というよりは日常的、私的生活の対極にある。
伝統家屋の建設にともなう儀式のなかでもとくに重要な部分をなすのは、祝儀をもって次々と訪れる姻戚関係の一族との儀礼的な交歓であった。
この地方一帯では嫁をむかえるために、婚資としてポルトガルやオランダ時代の大砲が使われている。青銅製の大砲は、東南アジアではヨーロッパ人の到来する以前から中国人やグジャラート人によって鋳造技術が伝えられていたというから、あるいはそれ以前の伝統に帰すべきかもしれない。ともかく、大砲はこの島全体で大小あわせても二〇門ほどしかなく、かぎられた数の大砲がおよそ数ヶ月単位で島のなかを流通しているのである。大砲は富や地位のシンボルであり、財産としての価値をもつものではあるが、けっしてオートバイやラジオの等価物ではない。大砲は交換されることによってはじめて価値を発揮する。
伝統家屋の建設において祝儀の主役をなすのはまさにこの大砲であり、住居を建設する家族に対して娘を嫁がせたことのある一族は、その際に受け取った婚資の返礼に大砲をもってかけつける。こうしてふたつの出自集団の代表がひとつに家に会し、両家の由緒を物語る儀礼的な掛け合いをとおして、歴史上の事件と関係が村人たちの前で再確認されてゆくのである。
当主側はこの日のために米や粟のほか、海亀、豚、山羊、魚などの肉を用意して、祝儀を持参した者たちを饗応する。祝儀にもたらされた品々、大砲のほか、金銭、シリー・ピナン、タバコ、アングル、衣服、サロン、食物など、は大砲と金銭をのぞいて参加した人々にわけあたえてしまう。
屋根葺のあいだ中、建物内に陣取った老人と女たちが歌をうたい、これにあわせて屋根葺役の男たちのいれる合の手が単調な作業を活気あふれるものにしている。
村の一画からはしきりに太鼓の音がきこえている。やがて、この太鼓に誘われるように赤い衣装をまとったふたりの男に先導されて舞踏の列が村中を練り歩きはじめる。
そのとき、ひとりの男が私たちの前にあらわれて、ヨセフに一枚の紙片をわたしていった。ヨセフはすばやくその紙片を握りつぶしたが、私はそのなかに「伝統舞踏 ○万RP」と書かれているのをみた。この舞踏をとりしきるショアル・ヤマン、つまり舟のなかで私のキョウダイであったヤハのさしがねだった。
すくなくとも私は居住者の自発性によって行なわれている文化的活動が金儲けの手段になるということを認める気にはなれなかった。私の顔色をうかがっていたヨセフは、その金額が無理ならば、自分の力でいくらかまけさせてもよいと言った。
問題は金額ではなかった。私は文化を買うつもりはないし、けっして観光地ではないこの島で、私のあとからきた異国人がたまたま行なわれる儀礼のたびごとにすべからく金品を要求されるという事態、おそらく私自身がその被害者であるような前例となることを望まない。いまの私はこの場への執着をすでにうしなっていた。私は船酔いの名残りのような眩惑をかんじた。必要とあれば案内役のヨセフの顔を立てて、指定の金額を残す用意はあるが、早々に退散したいとおもった。
そのような趣旨のことを私は多少興奮しながらヨセフに話した。私はもはやプロのフィールドワーカーではなかった。情報の代償に金銭を支払うことは健全なビジネスである。だが、そうだとすれば、私が私の社会に対して抱いていた不満、私自身をこの民族調査に駆りたてる情熱の源泉はいったいどこにあるというのだろうか・・・おそらくそうなのだろう。これは私個人の問題であって、所詮彼らの関知するところではないのだ。つまらない日用品が高価な値段で売買され、伝統が利鞘の大きい商品になるということに遅まきながら彼らも気づく、というわけだ。
「暑くて頭がどうかしていたにちがいない」
と、ヨセフは言った。彼の目はあふれそうなほどの涙をたたえていた。
「村へもどって水浴びをしてから出直そう。」
私たちはヨセフの提案どおりに、下の村へ引きかえして水を浴び、そのままそこにとどまった。
村役場、正確にいうと、村の集会のための共同家屋には、裏口への通路の脇に壁で囲われた小空間があった。この部屋の片隅に木枠の寝台が置かれていて、そこに横たわると小屋組を通して屋根のトタンがみえた。屋内とは壁の上で筒抜けだったから、効果はあまり期待できなかったが、私は用意してきた蚊取線香に火をつけ、寝袋のなかにもぐりこんだ。どんなに暑かろうと、これがマラリア蚊をはじめとするさまざまな吸血動物から身を守るための最善の手段なのだ。遠く崖の上の伝統村からながれてくる太鼓の響きは深更におよんでも絶えることがなかった。
神様、神様、あれが人生なのでしょうか、静かに、単純に、あそこにあるあれが
むかしおぼえた詩歌の一節が頭にうかんだ。いつしか昨日来のはげしい疲労感が私の思考を暗闇のなかにおしやっていった。(1989- 6- 7)
 新村とのあいだは切り立った崖になっていて、十数メートルの高さの梯子が両村をむすんでいた
新村とのあいだは切り立った崖になっていて、十数メートルの高さの梯子が両村をむすんでいた 梯子の最上部にあった門扉は太平洋戦争中に被弾してこわれた
梯子の最上部にあった門扉は太平洋戦争中に被弾してこわれた 崖の上にはゆるい傾斜地に二十棟ちかい伝統家屋が建ちならんでいた
崖の上にはゆるい傾斜地に二十棟ちかい伝統家屋が建ちならんでいた 建設中の伝統家屋
建設中の伝統家屋 コンクリートの布基礎の上に製材された規格材の柱が立ちあがる
コンクリートの布基礎の上に製材された規格材の柱が立ちあがる タネバル=エヴァヴにはサゴやしが生育しないために、ルンビアは小ケイ島から仕入れる
タネバル=エヴァヴにはサゴやしが生育しないために、ルンビアは小ケイ島から仕入れる 屋根はルンビア(サゴやしの葉)のパネルで葺かれる。これで約5~10年もつ
屋根はルンビア(サゴやしの葉)のパネルで葺かれる。これで約5~10年もつ 儀式のなかでもとくに重要なのは祝儀をもって次々と訪れる一族との儀礼的な交歓である
儀式のなかでもとくに重要なのは祝儀をもって次々と訪れる一族との儀礼的な交歓である 娘を嫁がせた一族は、その際に受け取った婚資の返礼に大砲をもってかけつける
娘を嫁がせた一族は、その際に受け取った婚資の返礼に大砲をもってかけつける 屋根葺きのあいだじゅう、屋根にのぼった男たちと家屋の中にいる女たちの掛け合いが続く
屋根葺きのあいだじゅう、屋根にのぼった男たちと家屋の中にいる女たちの掛け合いが続く やがて太鼓に誘われるように赤い衣装をまとったふたりの男があらわれ
やがて太鼓に誘われるように赤い衣装をまとったふたりの男があらわれ慣習会議
オランダやインドネシア政府の政治機構が地方に浸透する以前から、それぞれの地方には伝統的な儀礼と法をつかさどるための組織が発達していた。こうした慣習(インドネシアで一般にアダットといわれる)にはその守護者としての特殊な人格、村が集団のアイデンティティーをもとめるときにつねに焦点となる人物が存在している。
タネバル=エヴァヴ島では「海の主」、「大地の主」といわれるふたとおりの人格がそれにあたった。ある種の儀礼はこれらの人格を有する神聖な人物しか執行することができないのである。村で生活をはじめようとするなら、彼らに会って許可を得ておくことがどうしても必要だった。
慣習舞踏をめぐるいざこざがあった日の翌日、私はヨセフとヤムコの父親にともなわれてテリ家を訪れた。テリ家は慣習村にある家屋の中でもっともおおきく、村の共同穀倉という特別な機能を担っていた。
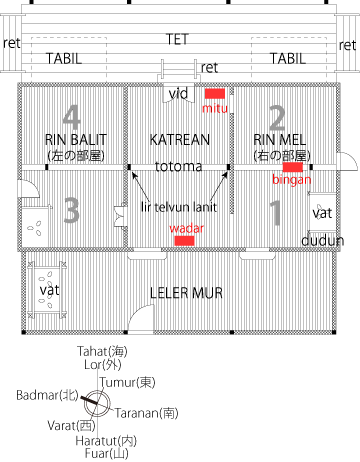
Tanimbar-Kei島の家屋平面 Habad家
タネバル=エヴァヴ島にある慣習にしたがって建設される家屋の空間構造はだいたい一定している。
棟を海岸に平行にむけて建てられた家屋の入口は海側にある。この面には高床の露台があり、この露台を介して中央部の扉から屋内にはいる。中央の部屋は接客と公的な食事にさいして利用される。屋内は三つの空間に区画されていて、扉にむかって右側の部屋を「右の部屋」、反対に左側の部屋を「左の部屋」とよぶ。「右の部屋」と「左の部屋」はそれぞれ家系を異にする親族集団が占有し(おなじ場合もあるが)、右の集団が左の集団の兄貴分にあたるとみなされている。「右の部屋」には炉が据えられているが、農耕儀礼の行なわれる特別の機会をのぞくと、この炉が使われることはない。テリ家では「左の部屋」に住む「大地の主」のカットウヴスが村の農耕儀礼の主宰者で、その時には彼は炉のある「右の部屋」で火の番をしながらすごすのである。日常的な食事の調理は家屋の裏側の下屋空間でおこなわれている。
私たちは家屋中央の空間で「海の主」のワラッブと面会した。屋内は暗く、湿気をおびてつめたい空気が肌に重苦しくまとわりついてきた。床板は厚く、部材は他のどの家よりも大ぶりで、屋根裏はとりわけ高かった。部屋の壁沿いに収穫されたアワの袋がいくつもならべられていた。
テリ家の「右の部屋」の主人であるワラッブは、奥の部屋につうじる戸口からあらわれて私たちの居ならぶ前にあぐらをかいてすわった。「左の部屋」の主人のカットウヴスは不在だったが、このとき「土地の主」のカットウヴスに会っておかなかったことは、あとに禍根をのこす結果となった。
タネバル=エヴァヴ島で、ある個人の社会的な立場を規定するのはそれほど容易なことではない。たとえば、ワラッブはイス・ヤマン(「イスのおとうさん」)と呼ぶのが、すでに彼のような子供のある(つまり社会的な立場のある)人間に対する礼儀正しい尊称である。また相手がキリスト教に改宗していればヨセフのように洗礼名がつかわれるだろう。さらに、ワラッブは村のなかで「海の主」という地位にあるが、同時にヴォヴァンラタンとよばれる大クラン(ヤムという)に属し、ラハクラタッという名のクラン(ウブという)に属し、テリという屋号の家の「右の部屋」に出自するシンゲルウブンという家系の家長であり、かつテリ家の長なのである。トモダチのヤハは正式にはショアル・ヤマンと呼ばねばならないし、ヤムコというのは実はレン家の「右の部屋」に出自する家系の名称である。
この家の実測調査をしたいという私の申し出にたいして、ワラッブは村の慣習会議にはからねば彼の一存では決断しかねるとこたえた。私はこの建物の素性についていくつかたずね、テリ家を辞去した。
慣習の守護者(アダット長)という言葉に対して、私は独裁者のようなイメージを抱いていたがこれは誤りだった。彼は村人の代表として儀礼をおこない、超自然界と交感する。そのことによって彼は村人全員の注意と尊敬をあつめはするがそれ以上のものではない。
慣習会議はその日の夜におこなわれることになった。夕刻までの残された時間を、私はヨセフの案内で村の他の家々をみてあるくことについやした。はやく調査家屋をさだめて、実測を開始することばかりをそのときの私はかんがえていた。

 テリ家は1905年頃に村人の相互扶助で建てられたもっとも大きな家。村の共同穀倉という特別な機能を担っている
テリ家は1905年頃に村人の相互扶助で建てられたもっとも大きな家。村の共同穀倉という特別な機能を担っている レン家は村でもっとも古い建物のひとつ。ヤムコはレン家の「右の部屋」に出自する家系の名称である
レン家は村でもっとも古い建物のひとつ。ヤムコはレン家の「右の部屋」に出自する家系の名称である 成員が多かった昔はベランダにtabilという屋根裏部屋がとりつくことがあった。村で唯一tabilの面影をのこすトキャール家
成員が多かった昔はベランダにtabilという屋根裏部屋がとりつくことがあった。村で唯一tabilの面影をのこすトキャール家 ハバッド家はテリ家と同時期の建設
ハバッド家はテリ家と同時期の建設
ヨセフとともに村役場をでて丘の上の慣習村にむかったのは夜八時をすこしすぎたころだった。島に私をともなってきた者が、会議場にも私を案内する責務をおっていた。慣習会議に物事をはかるには、一定の供物を持参するような慣習ができあがっており、慣習村にあるヤムコの家ではシリー・ピナン、タバコ、アングル、キャンデーをならべて私たちの到着を待ちかまえていた。これらの商品はいうまでもなくトゥアルを出発前に私が購入したものだが、このときまで所在が不明だったのである。昨日の屋根葺儀礼のさいに彼がその一部でも祝儀に持参していたなら、この一連の事件の発端は未然に防げたのかもしれない。村の三大クランにわたるように、シリー・ピナンとタバコをのせた皿が三枚用意され、それぞれに二千RPずつ現金をおくようにいわれた。拒否する理由はなかった。
これらの品々をささげもった女たちに先導されて、ヨセフ、ヤムコ父、私の三人は、慣習会議の行なわれる村の集会場にはいった。集会場はひくい高床の建物で、三〇人ほどの村人がすでに到着して壁ぎわにそって床に腰をおろしていた。こうした会議に参加できるのは、一般に子孫をもつ村の男にかぎられている。供物をのせた三枚の皿はこれら参加者の視線のあつまる部屋の中央にならべておかれた。
「海の主」のワラッブがしずかに何事かをものがたっていた。やがてそれに答えるように私の知らないもう一人の男が話しはじめる。二人の会話に相槌をうつ者たち、雑談のようにきこえる二人の対話によって、会議はいつのまにか開始されていた。
私には彼らの話す島の言葉がまったく理解できなかったから、ただ会話の調子から場の雰囲気をかんじとっていたにすぎない。少なくともはじめのうち会議は比較的おだやかな調子で進んでいた。会の雰囲気が一変したのは「土地の主」カットウヴスにつづいてファルネーという名前の目つきの鋭い精悍な男が発言してからだった。
彼の口調はあきらかに激昂していた。隣にすわるヨセフもすでに議事の成行きに全神経をうばわれていたために、私の面倒臭い質問にいちいち答えてはくれなかった。私は聾桟敷におかれていたが、会議が長老たちをとびこえて、結局のところヨセフとファルネーの言い争いに収斂していることを理解した。ヨセフは興奮した面持ちで、私の所持する調査許可証の文面を読みあげていた。
調査許可証
№2741/S.K./DIT/B.5/1985
インドネシア社会科学院は、本書をもって以下の者がインドネシアで調査を行なう許可を与えられていることを言明する。
名前:
国籍:
生誕地および生年月日:
・
・
・
ただし、その条件は以下のごとし:
1.目的地に到着後ただちにこの調査許可証を当該地域の安全を管轄する部署に提示して到着と調査の目的を報告すること、また、調査地域に出発する以前に地方官庁とインドネシアのスポンサーに対して自ら報告すること。
2.インドネシア国民に対して肯定的に行動し、インドネシア国の法律、特に調査地域の法律に従うこと。
3.秩序、平安、礼儀作法を護り、同時に、口頭であれ、文書/絵画であれ、インドネシアの特定民族の感情を害し、慣習に障り、あるいは、宗教を蔑視するようないかなる表現も慎むこと。
・
・
13.
この調査許可証が必要な用途に役立つように、願わくば関連の公的/私的機関、また個人が、有効な法律に従い、関係者に援助を与えられることを慎んでお願い申し上げる。
会議がはじまってからおよそ一時間半がすぎようとしていた。私は会議の場からしばらく退席することをもとめられ、ひとり集会場をあとにした。
慣習村の広場では屋根葺きにあわせて帰省中の中・高校生たちがダンスパーティの準備を進めていた。あちこちに吊り下げられた石油ランプのために、広場全体が白々とうきあがってみえた。私は広場の片隅にうち捨てられていた丸太に腰をおろし彼らの作業を見まもった。遠くでかすかな海鳴りがきこえていた。
まるで茶番劇だ。島の人間となにひとつ利害関係のない異国から調査にあらわれた学生ごときのために、村のしかるべき地位にある者全員が大真面目で議論をするに値するとかんがえるほど滑稽なことはない。私は慣習会議の結果に高をくくっていたし、そうであるならなおさらのこと、このような会議がまったく無駄なものにおもわれた。
やがて集会場によび戻された私がきいた結論は、会議のなりゆきに楽観的だった私の予想に反したものだった。慣習会議は私が村の一員となること、つまり私が島で調査を行なうことを拒否したのである。私はヨセフとともに会議に参加した人々に形ばかりの礼をのべた。中央の皿にもられた供物の品々はいつのまにかなくなっていた。
彼らがどんな採決をしようと何も心配することはない、とヨセフは言った。家屋のことなら俺がすべて知っているからおしえてやろう。
村が外国人をうけいれるのはこれがはじめてではない。いく人かの人類学者がこの島を訪れたが、入村を拒まれた前例はなかった。私の入村にたいして強硬に反対意見をとなえたのはファルネーと私のトモダチのヤハであったことを会議のあとできかされた。ファルネーがヤハの息子であり、前科者であることも私はそのときにはじめて知った。
最初のキリスト教会が島に建設されたのは十数年前のことである。当時村のなかは、あたらしい宗教を積極的に受けいれようとした進歩派と村の伝統宗教を擁護しようとする保守派に二分されていた。村の伝統にたいする危機感から過激化した保守派の一団は教会に火をはなち、この教会堂は建設後まもなくにして焼失してしまった。このときの焼き討ち事件に連座して警察に捕まった者の中にファルネーがいたのである。
私は慣習会議でどのような内容の会話がなされたのかヨセフから聞きだしたかったが、熱血漢のヨセフは自分に任せておくように繰りかえすばかりだった。
今夜のことは市長をつうじて県知事に報告する。そうすると奴らの立場は極めてまずいものになるだろう、とヨセフは話した。
私はヨセフの政治的立場を支持しているわけでもなければ、ましてやファルネー一派を一網打尽にしようと目論んでいるわけでもなかった。私のささやかな希望はたんにこの島の家屋を調査することだったが、そのために私が経なければならなかった官僚主義的手続、私のたよる中央政府からの書類やその代弁者である村長の威信、そうしたものすべてが島の伝統に生きようとする人間にとっては重大な脅威なのだった。私の目的が無垢であり、私がその目的に忠実であろうとすればするほど、私が彼らの社会にひきおこす波紋は避けがたいほどおおきなものとなった。
会議がおわり、建物からでたヨセフと私は若者たちの代表に乞われて、そのままダンスパーティーの会場の貴賓席にすわらされた。若者たちは慣習会議の終了を待ちあぐねていた。来賓を代表して村長のヨセフは、冒頭につぎのような訓辞をのべた。
他島で勉学にはげんでいる諸君が全員ぶじ島にもどり、ふたたびこうして一堂に会することができたことを神に感謝致します。本日のパーティーを開始するにあたって、ここに私たちは日本から来賓をむかえることができました。今宵君たちの踊るダンスが、われわれの村の伝統にのっとり、異国の客人をむかえて、ともに楽しいひとときをすごせることは村長である私の喜びです。それによって金銭を要求するような真似は、われわれのダンスにはけっしておこらないのであります。
ヨセフは私の方にむきなおりひときわ声高に最後の一節をそうしめくくった。
広々とした村の敷地の一画に踊りの場を囲むように椅子がならべられ、石油ランプのあかりがこの場におよそ不似合なこの工業製品をさむざむと照らしだしていた。昼間ならここから断崖のむこうに水平線がみえるはずだった。
精一杯音量をあげたテープレコーダーの音楽にあわせて村の青年たちはダンスを踊りはじめた。若い男たちが踊りながら椅子に腰掛けた少女たちをエスコートして踊りの輪が広がってゆく。そして踊り手がある一定の人数になったころには音楽もおわり、めいめいの椅子におとなしく戻って腰をおろすのである。
ダンスは曲をかえて何曲もくりかえされた。島の夜はすでにふけていた。彼らの鯱ばった踊りには日常性からの逸脱を期待させるような若々しさよりも、むしろ管理社会の抑圧のほうがつよくかんじられたにしても、これが今日に生きる伝統の姿なのかもしれない。少なくとも異邦人の私を歓迎しようとする彼らの心情に打算の影はなかった。
私の求めてきたものは、私の手の届くところに、私の目の前で鞠躬如として行なわれつつある踊りのなかに、あるのではなかったろうか? 貴賓席の私は若者たちの単調な踊りを呆然とながめながらなんどもあくびを噛みころしていた。
私は、私の調査を支持し、私を村に受け入れようと画策する村長の側にたつ人間として、村内の政治的抗争の場に投げこまれた骰子にすぎなかった。それなのにこの島を訪れることになった私という人間は、私の入村を拒否するファルネーのほうにはるかな共感をおぼえずにはいられないのだ。私の社会で私がもうひとりのファルネーにならなかったという保証はない。(1989-10-28)
 慣習会議のために用意したシリー、ピナン、タバコ、アングル、キャンデーとお金
慣習会議のために用意したシリー、ピナン、タバコ、アングル、キャンデーとお金 精一杯音量をあげたテープレコーダーの音楽にあわせて村の青年たちはダンスを踊りはじめた
精一杯音量をあげたテープレコーダーの音楽にあわせて村の青年たちはダンスを踊りはじめた島の時間
慣習会議で入村を拒否された私は中途半端な状態のまま島にとどまっていた。間断なく繰り返す潮の満ち干のまえに、「個人の運命」が意味をもちえぬような環境のもとでは、予定された将来への信仰はたちまち色褪せてしまう。たとえ村の慣習会議が私の調査を認めなかったにせよ、依然として私は調査の意志をもちながら島での生活を送っていた。村の慣習により村の一員であることを拒否された者が、村の慣習による規制の埓外に存在しうるならば、慣習法にもとづく集団の凝集力はいちじるしく損なわれる。法もまた相対的なものである以上、そのときの私には村の掟にしたがう意志はなかった。
伝統村にたちいることはヨセフから禁じられ、私の日課は浜辺を散歩するか、役場(というのは名ばかりの)の隅におかれた椅子に日がな腰かけて足繁く訪れる村人たちの話相手をすることについやされた。
慣習会議のおこなわれた日の翌日、所在なく役場にとどまっていた私のまえにフェリという名の若者が登場し、島に上陸して以来の私の軌跡は大きく弧を描いて方向転換をはじめた。マラリアの発作で今まで起きあがることができなかった、と言う若者の蓬髪は千々にみだれ、瞳は熱のためにうるんでいた。
「昨夜の会議の結果をきかされ、いたたまれずにいましがた二軒の家に赴いて怒ってきたところだ。調査のことは自分がなんとかしよう。明日になれば熱もひくだろうから。」
結果的に私は村長のヨセフや他の村人たちの誰にも増してこの若者を信用するようになった。他島での長い生活のせいか、体の四分の一をしめる中国人の血のせいか、島の人間には珍しい醒めた雰囲気が私を安心させた。彼のおかげで、あたかもファナティックな人間ばかりの集合であるかのようにこの伝統社会を描きだす不幸から私は免れたのである。
「この国の役人たちは出勤するとまず書類を一枚書く。それが済むとお茶をすすりながら仲間と世間話。首尾よく余計な面倒にも巻きこまれずに昼近くになればそそくさと市場に出かけ、市場から帰ると時間を気にしながら帰り支度をはじめる有り様だ。これがもっと上流階級だと、わざわざ外国まで行って博士や修士のタイトルをとる。ところが、帰国してしかるべき立場におさまると、立派な身なりと貫禄ある物腰にばかり気を使い、私腹をこやすことに専念する。彼らの仕事といえば書類にサインをすることぐらい。からっぽの頭はますますからっぽになる。これでどうしてこの国が発展するだろうか。」
のちに村での私の計画は一時期完全に中断を余儀なくされた。薄暗い役場のなかで、四六時中まとわりつく蚊の大群の相手をするのに閉口して、数日というもの、私は昼間から寝袋にもぐりこみ、寝床の上をはいまわる蟻の行列をながめてすごした。フェリはそんなときに姿をみせては、彼自身の憧れの文明生活をきまってこきおろす私の挑発にひややかに答えた。
「ここではどんなに疲れて帰って来ても家のなかには水も電気もありはしない。我が家にもどってながめるのはせいぜい枕がいいところだ。それでも寝床があれば幸いで、椅子の上や部屋の片隅で地べたに寝なければならないこともある。だから、俺たちの楽しみは金儲け。だけどかんがえてもみろ、この村で一番金をためこんでいる奴だって一〇万ルピアがいいところ、一〇〇万ルピアもあれば大金持ちになれる。けれどもおあいにくさま、どんなに金があったところでこの島では楽しむすべがない。枕を抱いて寝るばかりというわけさ。」
その日、病みあがりの覚束ない足どりのフェリをともなって、私はこの島で利用される樹木の見学にでかけた。
村の領域を一歩ふみだしたときから島のあちこちに露出する石灰岩が執拗に告げるのは、この島の文化が珊瑚礁の上に築かれた束の間の宴にすぎないという事実だった。島民たちの語る高波による冠水の記憶、島の内陸ふかく生い茂るジャングルのなかで見いだされる無数の貝殻のまえに、人間の居住の歴史がこの島に刻みつけた痕跡はあまりにも脆弱でありはしないか?
島民の大部分は一五世紀をすぎてからようやくこの島の上に姿をあらわした移民の子孫にすぎない。だが、歴史が時間的深度のよき代弁者であろうとするかぎり、島民の現在が歴史によるなんらかの規定をうけているとは言いがたい。「永遠」も「破局」もいまだに意味をもって語られたためしはないのだ。ここでは現在とは、終末的な核戦争、食料危機、環境汚染等々の脅威に怯える恒久的存在である以前に、なによりも自然界のあやういバランスの上にはじめてなりたつ彼らの生存の証だからである。
誤解をおそれずに言うなら、くずれさる寸前のガラス細工のような、この島をつつむ自然のあまりにも切羽詰った美しさに私はしばしば言葉をうしなった。しかし、おなじくらい頻繁に、ありとあらゆる工業製品の廃棄物による、徹底的に無頓着で容赦がない彼ら自身の破壊の行状を、私はこの島の上で目撃せねばならなかった。
島の住人はそれぞれの家の祖先がモルッカ海域にある他の島々、さらにスラウェシ島やバリ島からの移住者であることをいまも伝承している。時を経るにつれ、つぎつぎとこの島に移り住んで来た者たちは(ある国家、ある会社、ある組織の成員でないことが今のわれわれに不可能であるように)島の三大クラン(ファアン、ラーハンミトゥ、ヴォヴァンラタン)のいずれかに統合されていった。三大クランに村の儀礼上の役割を分配し、世界を構成すべきこの三要素を島の歴史のなかに編み込んでみせるのは神話という名の、ほんのささやかな手品の種にすぎない。
むかし、この土地にラーハンミトゥとファアンが住んでいたとき、世界にはまだ光がなく暗かった。ラーハンミトゥは祭祀をおこない、ファアンは主食の粟を島にもたらした。レヴマヌット(=ヴォヴァンラタン、現在の支配者層がふくまれる)が羽をひろげ天上から舞いおりてから、この世界は光にみちあふれたのである。
電車やバスの系統にかんする私たちの完璧な知識の体系をおもえば、村人たちが島の樹木にたいしてしめす理解の高さにいまさら驚嘆するのは的外れというものだろう。しかるべき用材にふさわしい樹種、食用になる葉、特殊な病気にたいして効力のある果実、ある色あいをだすために必要な根、樹皮、それらの木々の特長や生育する場所にいたる的確な知識が島民であるための基本的な素養にふくまれる。いつも列をなして私たちのあとにしたがう村の子供たちですら、このような場面では私よりずっと優秀な観察者である。
慣習家屋の建設にさいして、その定められた第一柱にはとりわけ重要な木がつかわれる。ところが、この木はもはや島内で見いだすことができず、村人たちは柱を入手するために、島の北岸にある無人島にわたらねばならない。
フェリが私に語った彼自身の見果てぬ夢は、この無人島を手に入れそこで豚と羊を飼育し、船を繰って商いをすることだった。島にいるかぎり永遠に不可能なことでも、フェリの計算では、数年間日本で仕事をしさえすれば容易に手のとどく現実になるはずだった。
「皿洗いなら言葉も技術も不要。俺はパンをかじっていれば済むし、居場所さえあれば服も寝床もいらない。この島にいたってどのみち同じことなんだから。」
島に到着して以来、私のもとを足繁く訪れる村人はおよそふたとおりのタイプにわけられる。私の居場所にあてられた村役場の机の上には、ヨセフの助言でいつもさりげなくタバコやトゥンバコの包みが置かれていた。やってきた村人たちは、経済的な負担を感じることなく、これらの品々をつぎつぎと空にしながら、いつ果てるともない四方山話の洪水に飲みこまれていった。たしかに、雑談のためにうしなわれた時間の多さを考慮に入れても、ヨセフひとりに依存していたときとくらべて、村にかんする私の情報は飛躍的に増大した。
社会的な権利の行使にかんして従属関係をもち通婚関係にない社会階層、つまりカーストは、キリスト教の布教のもとで表面的に姿を消しながら、マルク地方の広い範囲でいまだに生命を保っている。メル(貴族)、リン(平民)、イリ(奴隷)という三種類の階層のうち、ケイ諸島で発生しつつある新興村の多くでは、メルの比率が極端に少ないために、事実上カーストは機能をうしなっている。万一メルの家柄がひとつしかない村が誕生すれば、村内で血筋を維持してゆくことが不可能だからである。ところが、社会成員の圧倒的多数がメルに属するタネバル=エヴァヴの場合、社会はとりわけ少数の劣者を、社会自体の既得権の維持、「伝統」の保持のために執念ぶかく利用する。
互いに結婚してはならない関係にある男女のあいだのよくある悲しい恋の物語。メル出身の若者がリンの娘に恋をする。この醜聞に家族は猛反対、やがて若者は両親のすすめる女と心に染まぬ結婚へ。しかし、いったん燃えあがった恋の炎は結婚によってもいやしがたい。とうとう若者は妻を捨てて最愛の娘のもとにはしってしまう。彼の下半身はすでにリン、ふたりのあいだにうまれた子供は永遠にリンの運命を背負わねばならない。
はたして事実がどうだったか私は知らない。この若者は総計三人の女と結婚し、実際にうまれた子供の名はヤムコといった。彼はこの島で生を得た瞬間から、もはや島内で結婚することも、社会的な地位を確保することもかなわぬ存在なのだ。低地から高地へ水の流れの向かうことがないように、リンの案内で慣習会議にのぞんだ者がメルの社会に受け入れられる可能性はないというしごく当然な話も、数ある雑談のうちから私の理解しえたものだ。
 病みあがりの覚束ない足どりのフェリをともなって、私はこの島で利用される樹木の見学にでかけた
病みあがりの覚束ない足どりのフェリをともなって、私はこの島で利用される樹木の見学にでかけた 島のあちこちに露出する石灰岩が告げるのは、この島の文化が珊瑚礁の上に築かれた束の間の宴にすぎないという事実だった
島のあちこちに露出する石灰岩が告げるのは、この島の文化が珊瑚礁の上に築かれた束の間の宴にすぎないという事実だった
a fara 太平洋鉄木 kayu besi(写真は幼木)。家屋の第1柱 lir iyaan や、屋内空間を前後に二分する敷居 totoma (床梁、その上で4本の棟持柱を支える)にもちいる。Tanimbar-Kei島にはすでになく、近くの小島から運ぶ [Intsia palembanica]
その日、村はずれの散策から舞いもどった私を待ち構えていたのは、そうしたタバコめあての社交的な連中ではなかった。私の目のまえの椅子におとなしくすわり、しきりに咳払いをしながら沈黙をまもる初老の男の関心が、私の所持する薬品に注がれているらしいことは、村で数日をすごせばいやでも理解できるようになる。風邪、神経痛、発熱、寄生虫、怪我、皮膚病から、さらにもっと重大な病にいたるまで、私の診断を仰ぎにくる村人はあとをたたなかった。私の処方するのがただのビタミン剤だったとしても、彼らの期待と信頼を損ねることにはならなかったろう。子供のときから潮風を吸いながら生活をおくり、強烈なタバコを年中ふかしていれば、なんらかの異常を喉にきたさないほうがむしろ異常なのである。たとえ風邪薬とキャンデーをまんまとせしめたことに、男が心の底から満足の意を表明することはなかったにせよ、まさに、餌付けと個体の識別が調査の常套手段であるのはなにも類人猿相手ばかりとはいえないのである。
ヨセフのほうはこのような事態にたちいたっても最大限の親切を発揮して、私の離島のための舟の手配に奔走していた。帰省中の学生たちがトゥアルへ戻るのにあわせて島から舟が用意されることになり、有り難迷惑なヨセフの義侠心のおかげで私もこの舟で離島の手筈になってしまった。調査に協力すると言ったフェリはあの日以来姿をみせず、私はなんとか滞在を引きのばす口実をさがしていた。おもいがけずヤムコの父親が現われたのは出発を翌日に控えた日の朝であった。不首尾におわった慣習会議以降、彼と会うのはこの時がはじめてだった。
「明日の舟でトゥアルへ発つというのは本当か?」
私はなんらかの事態の進展が知らされるものとばかり期待していた。もし、なすすべもなくこのまま島を離れるとすれば、私は調査の失敗ばかりか私の行動を支えてきた信念の無力なことを否応なく認めねばならない。しかし、私の同意のしるしにたいして、彼は自分も同行したいということだけを確認すると、来たとき同様にそそくさと帰っていった。慣習会議のあとで、会議の結果について村の誰かが私のために裏工作をしているかもしれないという、いまからかんがえればまずありえそうもない空想は見事に打ち砕かれた。結局、この男はたんなる船便の確認に、あえていえばトゥアルまでのバス代をうかすために私のもとへやってきたのだった。
調査の過程でめぐりあう人間同士の綱引、たがいに相手を影響下にとらえ、否応なく軌道の修正をしいるようなエネルギーの放出は、彼と私のあいだにはついにおこらなかった。ヤムコの親父にとって私との出会いは、たまたま目の前を通りかかった乗り合いバスに乗り込む程度の意味しかもちえなかったのであろう。私もまたこのとき以外になんらかの意志力の行使を彼に期待したことはなかった。が、そうであるとしても、彼がいなければ私のこの島での体験はまったく違ったものになっていたのは事実とおもうのである。このときを最後に、彼と顔を合わす機会はふたたび訪れなかった。
島での食事のいっさいを私は村長のヨセフ家の居候として面倒をみてもらっていた。役場の裏手につづくヨセフの家で、ヨセフか、ヨセフがいないときには彼以外の誰かひとりが、きまって私の食事の相伴をした。冷えて団子状にかたまった御飯の上に魚のスープをしたたらせ、流動化しはじめた瞬間の固体をスプーンですくいとっては喉にながしこむ。ほとんど毎食のようにくりかえされたこの献立は、スープの代用にインスタントラーメンが使われるようになっても、この島の標準からして十分満足すべきものだった。そして、いつも朝食のテーブルを飾る、粟をかためたほのかにあまい餅と紅茶。海岸ちかくに掘られた島の井戸からくみあげた水は若干の塩分をふくんでいて、そのためにいつも過度に砂糖を入れた紅茶のあまさはいつまでも舌にのこる。島の日常生活で変異は真にあらゆる意味において似つかわしくないことを私は理解した。
その日の昼食後、ヨセフとの会話はいつのまにか島の観光資源としての価値におよんだ。ふるい建物や風習をのこした村が政府の援助をうけ、観光客をあつめる。一方に地域の自律性を擁護するかにみせながら、その利用をもくろむ国家。そして一方に地域の自律性なぞとっくに放棄しながら、なおも固有の秩序によりかかろうとする共同体。観客の期待するのがこの村を舞台にした近代と前近代との疑似戦争だとしたら、勝負は戦うまえからとっくについている。政府による集落保存の指定をうけたとたん、村長は念願のオートバイを手に入れ、村にのこるふるい家屋はすべてあたらしく建てかえることができた、という村の逸話はけっして例外中の例外なのではない。政治家としてのヨセフが直感的に理解したように、村の近代化と伝統文化の保存という背反命題はすくなくともこの国ではおなじ事象の両側面にすぎないのだ。
遺伝子のレベルではなしえない情報伝達を可能とするために、人類のあみだした制度の総称を文化と呼ぶなら、集団の特異性を前提とする現在の文化はいまだにきわめて不完全なものにとどまる。文化表象としての建築様式を保存せよという議論がこたえねばならない二重の課題は、ある建物をのこすことが、それを成立させる動的回路の維持とはかならずしも結びつかないということ、そして、かりにそのような回路が維持されたにしても、それはきたるべき将来への展望をなにもあきらかにはしてくれないということである。
ともかく、ヨセフは私の言った政府の援助という言葉に心をうごかされたようだ。観光客でにぎわうこの村の将来に私は微塵の現実性もかんじてはいなかったが、政府が村の実体を把握するためには、家屋の調査をして報告書がしかるべき機関に提出される必要がある、と水を向けた。私たちはハバッドという名の比較的ととのった家屋の実測を画策することで合意をし、ヨセフはさっそくハバッドの家主のヒルマに使いをだした。
「これは慣習会議とはなんの関係もない、私とヒルマふたりだけの問題だ。」
かくして私の離島は延期された。ヨセフは子供の中学入学の書類にサインをするために明日の舟でトゥアルへ発たなければならなかった。
そのヨセフのはからいで、おなじ日の夜、村の村長派のおもだった人間をあつめて謀議がもたれた。ヨセフ、ヒルマと副村長、その弟でのちに私のよき協力者となったおしゃべりのタムロー、それにくだんの風邪薬の男と、それに私をあわせて六人が出席した。ヨセフがあえて島の方言をもちいたために、どういう事情が説明され、謀議の参加者たちに了承されたのか私には知るよしもない。
例のごとく、こうした会議のあとには、きまっていつ果てるともない雑談がつづく。それは村をあげての唯一の異文化体験の記憶、いまやこの村では伝説と化した日本時代の話なのだ。
およそ二時間におよぶ昔話しのあとで、あつまった者たちはめいめい伝統村に帰っていった。懐中電燈のよわよわしい光芒だけが、村全体をすっぽりとつつむ黒々とした木立の影のなかに時折みえかくれした。これが現実であるというのは不思議な感覚だった。ヨセフやタムローのような世代の者さえもまきこんで、まるで昨日の出来事のようにいきいきと語られる日本軍の事跡と、私の身体に染みついた現在の日本とを、その両者の現在同士を、破綻なく折りあわせる必要を私はかんじた。しかし、そう試みようとするほどにどちらの世界も私のなかでリアリティーをうしなってゆくのだった。
先刻までの談笑の余韻がのこる室内に私たちはいた。そして、その余韻にとどめをさすかのように、ヨセフは私に向きなおり、彼にたいする私の不信感を極限までつのらせる忠告をした。
「私はまだ彼らに全幅の信頼をよせているわけではない。なにか疑問が生じたならおとなしく私の帰りを待ち、けっして彼らに相談してはならない。彼らとは世間話の関係でいればよろしい。」
ヨセフはあくまで村の政治家であろうとしていた。私のほうは小さな社会にはりめぐらされたあまりにも複雑な人間関係をまえに、このような政治的な駆け引きにはつとめて無頓着でありたいと念ずるばかりだった。
「島にはもう石油を買う予算がないので、あすはモーター船を出すことができない。ランプの明かりもこれでおしまいだ。」
私はすくなからぬ額の金子をとりだしヨセフに手わたした。(1990-01-28/03-13/03-15)


むかし入江には小石を積みならべた境界があり、男女の石像と二股状の木柱が立てられていた
pleyte wzn.,c.m. "ethnographisch atlas van de zuidwester- en zuidooster-eilanden", 39pl, e.j.brill, leiden, 1893

hoton 農耕儀礼の中心に粟がある
出会い
島でしばらく生活してみると、事件はことごとく海から訪れるということが、実感としてわかるようになる。波打ちぎわでは、いつも何かしら事件が私を待ちかまえていて、役場をめぐる村人たちとの単調な生活にあきると、私は気の向くままに、よく入江まで足をはこんだ。都市が人々の欲望や夢を呑みこみ、中世の教会堂が人々の希望の源泉であったように、南洋の小島では、集団の存在のあかしは、海が人々の上に約束するものなのである。
ある朝、海辺で巨大な海亀が解体中だったかとおもうと、翌日には海亀のかわりに鮫が捕獲されていたりした。
海亀は神聖な動物で、儀礼の供犠獣として欠かすことができなかった。だから当面儀式の予定がなければともかく、たいていは儀式の日まで生かしておいてから屠殺される。そのため海亀の調理にだけつかわれる神聖なまな板が用意されて、慣習家屋のしかるべき場所に保管されている。雌の海亀は胎内に一〇〇個ほども卵を持っている。村人たちはピンポン玉くらいの大きさに育ったこの卵をゆでてから、弾力のあるぶよぶよした皮をむいて中身を吸う。この卵を私はハバッド家の調査のさいに御馳走になった。私がこの島にやってきた日に、くだんの慣習家屋の屋根葺儀礼にのぞんで供犠された海亀のものであった。
鮫の方は海岸に引きあげられても、まるで水気を含んだ軽石のようにつめたい皮膚の感触が、生物よりも鉱物を髣髴させる。しかしどんなに残忍なイメージで飾られようと、この動物もここではたんに鰭と肝を採取されるだけの用途しかない。ナマコやコプラとならんで、いまや鮫の鰭はモルッカの島々に現金をもたらす貴重な資源なのである。
フェリとかたらい、ナマコの採集に出かけた折のことである。村の入江は日の高くのぼるころからいつも遠くまで海水が後退して、のこされた白砂の一面にかがやくなかに、小石を積みならべた村の境界が姿をあらわしていた。境界には一ヶ所だけ石積みのとぎれる部分があり、ここにはむかし男女の石像と二股状の木柱が立てられていた。いまは海水の侵食のために朽ち果てたその残骸をとどめるばかりであった。湾の所々にのこる潮だまりが私たちの獲物の場となった。
海辺で生活をいとなむなら、潮だまりにあいた小さな穴の形を見ただけで、その下にひそむ生物ばかりか、その商品価値までも推測できねばならぬのだろう。フェリはそこら中に無数にころがる黒いナマコには目もくれずに、薄緑色をした長大なナマコを掘り出していた。彼によれば、薄緑のナマコは韓国や日本へ輸出され、本当に美味なのはじつは白いナマコだと言うことであった。そう聞かされてみると、私の驚嘆していたことの実体が何であるのか、私にもわからなくなる。
またあるとき、切り取ったばかりの鮫の鰭を物干しに吊りさげながら、白い鰭ならこの黒い鮫の鰭の四倍の高値で取り引きされるのに、と海の男の喋るのを聞いたことがある。
香料貿易のむかしから、交易は一般の島民に、恩恵よりもむしろ使役を課してきたのであるから、乾ナマコやフカヒレの価値が、この島の貧しい食事の内容とあまりにもかけ離れているのは、いまさらあやしむにたりない。それよりも、私には理解をこえたフェリの能力や、海の男が経験せねばならなかったにちがいない生命の危険さえもむなしいものにする、得体の知れない論理の存在におどろくのである。
調査の過程でいつも私を打ちのめし、当惑させるのは、他人とおもってのぞきこんだ鏡のなかに、自分じしんの素顔を発見したときの薄気味の悪さなのだ。
フェリとナマコを採りにいった日の夕刻に、村長のヨセフはトゥアルから島にもどってきた。ところがヨセフが島を離れていた数日のあいだに、フェリとタムローのふたりのはたらきで、村における私の立場はあきらかに大きな変化を遂げていた。つまり私の存在はヨセフひとりの培養器をのがれて、すでに村の多様な人間関係のなかに根をはりめぐらしはじめていたのだ。ヨセフは不快感をあらわにしながらも、最後には私のあたらしい立場を認めざるをえなかった。その結果、とうとう私の入村を決議するために、再度慣習会議がひらかれることになるのだが、その話のまえに、この数日間に私の出会った村人たちと彼らの逸話のいくつかを述べて、村にとって私という存在はいったい何だったのかをあきらかにしておきたい。

 鮫は鰭と肝とを取るためにこの世に存在する。白いフカヒレは1㎏3万RP、400㎏あれば家が建つ
鮫は鰭と肝とを取るためにこの世に存在する。白いフカヒレは1㎏3万RP、400㎏あれば家が建つ 儀礼で屠殺された海亀の頭蓋骨は、慣習家屋に保管される
儀礼で屠殺された海亀の頭蓋骨は、慣習家屋に保管される
 入江の境界にあった石像も海水の侵食で朽ち果ていまは残骸をとどめるばかりだった
入江の境界にあった石像も海水の侵食で朽ち果ていまは残骸をとどめるばかりだった
もし、家屋を実測されるなどという経験をもったことのない住民が、調査の目的や内容を言葉で説明するだけで理解できると期待するのなら、調査の真似ごとをはじめるやいなや、彼らの態度にあらわれる驚愕と憐憫の感情は予想外なものだ。とりわけ調査にたいして最初に強硬な反発をうけたような場合には。そして部材のひとつひとつに片端から、パラノイアのごとくメジャーをあて、あるいは煤と塵埃と汗にまみれ、蜘蛛やダニをはじめとする、ありとあらゆる微小な昆虫類の攻撃をかわしながら、何時間も屋根裏にこもっていたりすると、いつのまにか話しを聞きつたえた村人たちが集まってきて、作業の模様を逐一噂しあい、あるいはこのような作業に従事せねばならない境遇を憐れんでくれることだろう。なぜならこの国では、いやしくも大学で学問を修めたほどの人間が、もちろん強いられたものであるにしても、これほど卑しむべき肉体労働を請け負うべき筋合いはないからである。
そこでこうした教訓を積んでからは、家屋の調査というものはずっと巧妙になる。実測をはじめようと身がまえ、住人たちの視線が私の上に釘づけにされたことを確認すると、私はできるかぎりばか丁寧に、専門家ぶって仕事をこなしてみせる。そうなれば家屋の実測は、さながら調査を成功裏に終わらせるための演技と化すのである。実際いくつもの村で、私はこのようにしておこなわれた興行によって、人々の注目と共感をかちえることに成功した。
ハバッド家の実測がはじまると、タムロー夫妻はそろって調査家屋にやってきて、私のために飲み物や食事の用意をしてくれた。タムローの妻はフェリの妹であった。フェリには姉もいて、ヨセフに嫁いでいた。そこでタムローばかりか、はるかに年長のヨセフもまた、フェリには一目おいていた。ヨセフが島にいないときに、フェリとタムローは毎晩のように私のもとを訪れて、アダットと呼ばれる村の伝統的な支配秩序と、村長のヨセフとのあいだにみられる葛藤についてかたってくれたことがある。
村長の権威は、ジャカルタの中央政府につらなるインドネシアの政治機構の末端として、いわば村の外から保証されている。一方のアダットは村固有の秩序を維持するために、神話や儀礼のなかに権威の基盤をもとめるのである。そこで村長の立場は、あきらかに村の自律性にたいする外部からの侵害でありながら、政府への協力をとおして約束されるであろう、目に見える近代化への欲求にかられて維持されてゆく。つまり村人たちの物欲の象徴として、帆船ではなくモーター船をうごかす権利をもち、ケロシン・ランプではなく発電機を島にもたらす可能性をもつ人物が、それなのである。そのときアダットは既存の制度をまもろうとして、閉鎖的で、村長や政府の論理で言えば、反体制的な性格をおびることになる。このような村長とアダットの緊張関係は、日常生活のなかで姿を消しながら、外国人の訪問といった村外からの刺激にたいして、矛盾をさらけだすのである。
ある社会体制が開放されるべきであるかどうかは、体制がヒエラルキーを前提とした概念である以上、結局、組みこまれる規模の大小を論ずることにしかならない。そのような二項対立の図式にそった議論じたいが、いまの私には、体制を維持する活力そのものなのではないかとさえおもわれてくる。だからといって、何も色を塗らないでおくことが、やはり白という色を意味するにすぎない現実のなかでは、より大きな器をもちだしてくる以外に、その呪縛からのがれえたとかんじる手段を、社会は個人にゆるさないように見える。
村長のヨセフにしてみれば、慣習会議などの意志決定機関が、村長の意向をはなれて存在しうることじたいが、はじめから許容しがたい事実なのである。ましてその会議の場で、私の入村の承認を乞うことの必然性を、もとよりみとめるわけにはいかなかったのだ。たしかに、一介の調査者のために慣習会議で大袈裟な論争が展開されるのを、私が異様な事態とかんじたのは誤りではなかった。慣習会議の場でヨセフは、この不詳事を県知事に報告する、と啖呵をきったのである。
要するに、慣習会議にのぞむヨセフにとって、私の調査の成否などはじめから眼中になかったわけだが、だからといって、私はヨセフを責める気になれない。それより私じしんの入村をめぐって顕在化した事件の推移を、私はしだいに興味ぶかく見まもるようになっていた。
 ハバッドという名の比較的ととのった家屋を実測する
ハバッドという名の比較的ととのった家屋を実測する 中央広間に座る当主のヒルマ
中央広間に座る当主のヒルマ 裏手の炊事場は女性の領域だ
裏手の炊事場は女性の領域だ 家族成員が多かったむかしは屋根裏でも暮らした
家族成員が多かったむかしは屋根裏でも暮らした 調査家屋まで昼食の仕出しにあらわれたタムロー夫妻。ハバッド家のベランダで
調査家屋まで昼食の仕出しにあらわれたタムロー夫妻。ハバッド家のベランダで ハバッド家にあつまった村の面々。左よりおしゃべりのタムロー、調査用のカメラを手にする日本びいきのドミングス、当主のヒルマ
ハバッド家にあつまった村の面々。左よりおしゃべりのタムロー、調査用のカメラを手にする日本びいきのドミングス、当主のヒルマ
ハバッド家の調査を通じて私が知りあった村人のなかには、村はずれで鍛治の工房をいとなむヨハネスや、島の北の岬にある分村のムンに住むドミングスのように、日本軍の事跡を記憶にとどめていて、その回顧にわざわざ調査家屋をたずねてくる者もいた。のちに彼らは二度目の慣習会議の場で、私の入村を支持する論陣をはることになる。
戦争中、ケイ島に置かれた海軍基地の前哨として、タネバル=エヴァヴ島には日本軍の部隊が駐屯していた。このときのカルチャー・ショックは、この小島と、たかだか周囲の数島しか知らない島民に、そして地理的意識のなかでは、日本からとおなじくらい遠くジャカルタからも引きはなされた島民に、いまでも大きな痕跡をのこしていた。
タムローとふたりでヨハネスの工房をたずねたときに、たまたまヨセフの親父が来あわせていた。ヨセフが村長になる以前に村長をつとめていた彼は、戦争中に共産主義の嫌疑をうけて、四度も憲兵隊に連行され、あやういところで斬首をまぬがれた。
もちろん、この島に共産主義なるイデオロギーが、その本来の意味で存在したなどとかんがえないほうがよい。これは村長の立場を貶めるための密告か、さもなくば士気にすぐれぬ住民たちを鼓舞するために、支配階層の者をみせしめに屠る必要があったかの、いずれかの理由だろうから。自分に日本時代の話をさせたら一週間はつづくだろう、と彼は言っていた。
ヨハネスは日本軍にならった技術でいまでもアルミのフライパンを生産している。島の沖合いに撃墜されたアメリカ軍の飛行機の残骸があって、それが彼の自慢のフライパンの原料の入手先なのである。
日本軍がこの島の材料からつくりあげた石鹸、布、皿などの技術がすでにうしなわれたこと、そして、コクミンガッコウというのがあって、青空の下で、棒切れをつかってカタカナの練習をしたけれども、ほとんど忘れてしまったことを、彼はなげいていた。
ヨハネスのもとを辞してから、ドミングスの熱心な招待をうけて、タムローとともに分村まで出かけようとしていたのだが、この計画には横槍がはいってしまった。入村もせぬ者がいろいろと人の家を訪問すると、よからぬ噂をたてる者がある。分村に行くのはヨセフの帰島を待ってからにしろと言うのだ。村長を出しぬいても、村人たちを出しぬいてもいけない。緊張の糸はあいかわらず張りつめたままだった。
「土地の主」のカットウヴスのもとに私を連れていってくれたのもタムローである。カットウヴスはファルネーとともに、慣習会議では私の入村に反対していた。
実測調査の噂は、村の大工である彼の耳にも届いていたとみえる。
「調査の目的はなにか? 結果はどうなる?」
と高飛車だったのもはじめのうちだけで、彼のなかの職人気質が私を放っておけなくなったらしい。結局、ここでも日本軍があと一〇年島にいたら、という話になった。かつて大文明をきずいた民族の末裔が、過去を振りかえりつつ語るときのようなトーンが、彼の言葉にはかんじられた。
ハバッド家の実測を無事終えると、ふたたび私の生活からは意志力を行使するような場面がうしなわれて、村人たちとのあいだにおきる、とりとめない事件のながれに身をまかせるようになった。
ある日の午後、フェリが誘いにあらわれて、私たちはひさしぶりに海岸の散策に出かけた。潮のすっかりひいた湾内には、風のそよぎからも波の音からも見はなされて、船腹をあらわにしたプラフが点々と横たわっていた。
俗世界の解脱をとおして、よりふかい自己認識に達しえたという類の宗教体験談を、私はとても信じる気になれない。現実が私の五感のとどく範囲をこえて、意識のはてに遠のいてしまい、自分じしんの存在感が喪失されるような瞬間を、私は調査の過程で何度も体験したことがある。このとき強烈な陽射しをうけて、あまりにも白々と、静まりかえった海岸をまえに、私はそのような感覚にとらわれていた。
村の人間を巻きこんでまで入村を画策しつづける努力や、この島にわたるために経験したさまざまな苦労、それに、インドネシアで家屋の調査をおこなう計画をたててから、成し遂げる必要のあったプロセスの数々、設計事務所をやめて大学にもどらなければならなくなったある事件の記憶、こうした時間のなかに生きる私個人の歴史がすべて漂白されたあとには、おそらく認識すべき「私」などという存在はないのだ。この浮遊感の理由を私は長期間異国にいるせいだとおもっていたが、日本に帰国してからも、なにかに熱中しようとするときに、この感覚は突然私をおそって、心のなかにぽっかりと空白をのこしてゆくことがある。
そのときに私が正常の感覚を取りもどしたのは、ほとんど完成した一艘のプラフのたもとで、砂地にしゃがみこみ、手斧をふるいながら船底の手いれをしている男に気がついたからである。この男だけが動きの静止したこの画面のなかで、むなしい抵抗を繰りひろげていた。近づいてゆく私たちに気がついて男が顔をあげると、それはファルネーだった。彼と私が会話らしくもない会話をまじえたのは、あとにもさきにもこのときしかない。そしてファルネーは、あの猜疑にみちた眼差しで私たちを一瞥しただけで、作業の手を休めようともせずに、こう言ったのであった。
「なぜ事前にアダットに挨拶にきて、調査の目的をあきらかにしようとはしなかったのか? アダットは、入村が許されないのであれば、それもやむをえないと言うよそ者を、絶対に受け入れるわけにはいかないのだ。」
私には政府の書類が規定する私じしんの立場を、繰りかえし説明するよりしようがなかった。
調査の意図をもつ者は、この国のどこでも村に到着しだい、まず村長に報告することを義務づけられていたし、それ以降の私は、村長のヨセフの指示にしたがって行動してきたにすぎない。島民のあいだにどんな立場上の相違があろうと、調査にあたってこれ以外の手続きを踏むことはありえないのである。しかも私はヨセフの案内で「海の主」のワラッブに会っていたのだから、アダットに挨拶に来なかったと言うのは、かならずしも正しくない。
それに政府の書類がどのような内容のものであっても、書類の強制力を盾にとって入村を果たすつもりなど、私にははじめからなかったのだ。ヨセフがそれをどう利用したかは、私の関知するところではなかった。むしろファルネーたちのわだかまりの真の理由が、慣習舞踏の請求にたいしてとった私の態度にあることはわかっていた。けれども所詮道理などは誰の上にもあるのだから、正論を盾にとろうとするファルネーに、私にも道理があったことさえわからせればそれで十分だった。ファルネーは黙って彼の作業をつづけていた。
ファルネーのもとから帰宅する途中で小さな事件が私たちを待ちかまえていた。
私がこの島へやってきてから、村では三人の赤ん坊が誕生していた。生まれてきた子供の名前に、たまたま島を訪れていた人物の名を借用した前例は多々あって、じっさい三人のうちひとりは、私の名にちなんだ幼名があたえられていた。ところが三人のなかで、私の到着した日に生まれた子供は誕生以来ずっと病気をわずらっていた。私は医者や呪術師ではないものの、近代医学の薬品をいくらか所持しており、村人のなかには私に病気の診断をあおぎにくる者も多くあった。そこでフェリは、私を連れてこの子供の見舞いにゆけば、病気の原因が何であるかを判断できるのではないかとかんがえたのである。子供は食べたものをうまく排出できずに、いままで便通をよくするための薬草をあたえられていた。
数日前に私は偶然にも役場の窓をとおして、不思議な光景を目撃している。そのとき村のある女性が山刀を手にして、役場のまえに植えられていたバナナの太い幹を、飛び跳ねながら必死になって切りたおそうとしていた。それを見て例のごとく周囲にむらがり、囃したてる子供たちを、彼女は激しく叱責した。作業にうちこむ女の真剣さのせいか、怒り方の尋常でなかったせいか、なぜかそれだけのことが妙に私の脳裏には焼きついていた。バナナの幹は病気の子供に飲ます薬を取るための材料であったことを、このとき私はようやく理解した。
病人のいるせまい室内に足を踏みいれると、異様な熱気と空気の悪さのために、たちまちあのプラフの船室にふたたび舞いもどったような錯覚にとらえられた。この息苦しく澱んだ雰囲気は、壁ぎわにそって所在なげに居座る女たちのためばかりでなく、暑い日中にもかかわらず囲炉裏に火を起こしていたことが原因していた。可哀相な乳児は、私ならしばらくいるだけで病気になってしまいそうなこの酸欠状態のなかで、囲炉裏の前に座をしめた母親とおぼしき人物の膝に抱かれ、そのうえ幾重にも毛布にくるまれて病気に耐えていた。
フェリが容態をたずねたのであろう。女は毛布をひらいた。私たちのまえにさらされた子供の腹は膨れあがり、毛布のなかで力なく横たわったままだった。その様子に彼女は以前とちがう異変の兆候をかんじたにちがいない。死んでしまった、とつぶやくと、周囲の女たちも口々に死んだと言い、やがて部屋にはいりきれずに外で待つ女たちのあいだにもそれはつたえられた。
予想されたような狂乱はなかった。静かで自然な幕切れであり、これが舞台であるとすれば、この母親は役者として完全に失格だろうとさえおもわれた。私たちのほうが、周囲に居座る女たちの中央に呆然と立ちつくすばかりで、どう対処してよいやらわからぬ有り様だった。ともかく私は、人の生命を左右するかもしれないような、重大な実験に加担しなくて済んだことに、ひそかな安堵とうしろめたさをかんじていた。
翌朝、役場のなかで朝食の支度を待っているときに、教会や墓地のある一画に通じる役場のまえの道を、葬送の列がとおってゆくのが目撃された。(1990-07-04/05)
 日本軍に習った技術でアルミのフライパンを生産する
日本軍に習った技術でアルミのフライパンを生産する 潮のすっかりひいた湾内には船腹をあらわにしたプラフが点々と横たわっていた
潮のすっかりひいた湾内には船腹をあらわにしたプラフが点々と横たわっていた ほとんど完成した一艘のプラフのたもとで、砂地にしゃがみこみ、手斧をふるいながら船底の手いれをしている男がいた
ほとんど完成した一艘のプラフのたもとで、砂地にしゃがみこみ、手斧をふるいながら船底の手いれをしている男がいた復活戦
息子の入学手続きをおえてトゥアルからヨセフが戻ってきたのは、フェリとナマコを取りに行った日の夕刻のことである。いつもこの時間帯に、昼間のうたたねを終えて水浴びをする者や、水を汲みにあらわれる女たちで、役場のまえの通りはにわかに活気を帯びる。そうした夕刻の活気が乗り移ったせいだか、それとも本島の息吹にふれる機会がヨセフの魂さえも興奮させるものなのか、役場で私の帰りを待ち構えていたヨセフの顔はいくぶん上気していた。私はタムローの案内で「土地の主」のカットウヴスを訪問した経緯を報告した。
「なんのために?」
ヨセフの顔つきは一変した。島に到着して以来そのときまでの私は、ヨセフの立場について重大な勘違いを犯していた。カットウヴスは慣習会議で私の入村に強硬に反対した者のひとりである。私が今後も村での活動をつづけようとするなら、タムローと私がしたように彼を懐柔することの必要性は誰の目にもあきらかだった。だから私の報告にたいして、ヨセフもすなおにその結果を喜んでくれるものだとばかりおもっていた。
「それよりいったいおまえはいつ島を発つ予定なのか? 彼らが受け入れないのならば、もうこんな島にいつまでもいる用はないはずだ。」
ヨセフの手には、島ではほかに吸うもののない外国製のタバコがあった。島に上陸した日に、私の持参したタバコとトゥンバコの山をまえにして、ヨセフは自分の好きなタバコの銘柄について話してくれた。ただ強い刺激をもとめてトゥンバコを吸う村人たちを、ヨセフはひややかに眺めていた。
おなじ日の夜に、ヨセフの出発前にあつまった謀議の面々がふたたび役場に顔を揃えることになった。フェリやタムローの画策していたのは、もう一度慣習会議を開いて、その場で私の入村を正式に認めさせようというものだったが、この計画にヨセフは頑なに抵抗した。自分のいない間に勝手にすすめられた計画を熱血漢のヨセフが拒否するのは当然としても、理由はそれだけではなかった。
この計画を許せば、村の問題にたいして慣習会議が村長以上の決定権をもつことを認めることになる。ヨセフの直面する問題のじつに滑稽なところは、ヨセフを頼って村にやってくる訪問者の目的が、たいていの場合、この村にのこる伝統の価値のためにあるという逆説なのである。村の連中がいかに譲歩しようと、これ以上村長として奴等のまえに頭を下げに行くのは御免だ、とヨセフは言った。しかしそのときには、私の入村はヨセフひとりの問題ではなく、多くの村人の関心をあおる事件にまで発展していたのである。
ヨセフが最後にたっした結論は次のようなものだった。
ヨセフは、慣習会議を開こうと提案するタムローを慣習会議からの使者として受け入れる。そして彼らの譲歩にたいするヨセフの感謝の気持ちを、ふたたびタムローを使者として彼らに伝える。もとよりヨセフは私の入村に同意しているのだから、残された問題は慣習会議の側の意志決定次第ということになる。
そもそも私の入村にかんする支障が、はじめから存在したわけではなかった。今となっては、慣習会議と村長の双方が、たがいの威信をきずつけあうことなく、それを成就する方法だけが問題だったのである。ヨセフはこうした政治的な解決策をおもいついたことに上機嫌で、その夜は謀議のあともいつになく雄弁だった。
慣習会議の復活戦がおこなわれる予定の日に、村の若い男たちは朝から槍を携えて島の奥地へ入りこんでいった。野猪がふえすぎて椰子が被害をこうむりはじめたからである。そのせいで会議は夜半に開催されることになり、私はそれまでの時間をなすべきこともないままに、役場のベッドの上ですごした。
本来、野猪狩りは村にとって特別に重要な儀式とのかかわりをもっている。毎年三月にアワの収穫がはじまるまえの一時期、村を五日間にわたって閉ざす期間がある。このときには、村を訪れることも村から出ることも禁じられて、村の全成員をまきこんだ野猪狩の儀式がおこなわれる。儀式は一定の順番で雄雌あわせて七匹の野猪を捕獲できるまでつづく。捕獲された豚はバナナの葉でくるんで土中で石焼きにされ、その顎骨を村の祭壇に捧げる。そのため集落内には精霊をまつった石の祭壇が六箇所にもうけられている。そして、カットウヴスの住むテリ家だとか、ヒルマのハバッド家といった特定の家が、めいめいこの祭壇を管理する義務と名誉とを保持していた。
さいわいヤムコの父がトゥアルに行っていたために、慣習会議に私を案内する役を今回はタムローがつとめることになった。ヨセフは慣習会議を欠席していた。集会場の入口には、会議に出席する資格のない村人があふれ、私たちの到着を待ち構えていた。アルミのフライパンをつくっている工場長のヨハネスと分村のムンに住む日本びいきのドミングスのふたりの手招きで、私は彼らの間に座をしめることになった。何人かの村人とはすでに顔馴染みで、なかには私にむかって目配せする者もいた。会議はカットウヴスが主導し、意見を述べるのはヨハネスやドミングスをはじめ私のよく知る村人ばかりだったから、ただでさえ退屈な会議のなりゆきに私はすぐに興味をうしなってしまった。フェリとタムローのはからいで、私のために慣習会議の復活戦が決まったときに、私の入村をはばむものはもうなかったのである。
私は会議場にあつまった村人のなかにヤハの姿を捜しもとめた。ヤハもファルネーも会議がはじまって以来、一言も意見を述べてはいなかった。
すくなくとも表面的には、この事件はヤハと私というふたつの焦点を中心に波紋をひろげていったようにみえる。けれども私たちの背後には、あらがいがたい巨大なふたつの力がたえずはたらいていた。慣習会議と中央政府、村の原始宗教とキリスト教、伝統と近代、そしてファルネーとヨセフのふたりに象徴される村人の両極の心性が、果てしない抗争を繰りひろげるなかで、私たちはほんの一瞬間スポットを浴びたにすぎないのである。
ファルネーの姿は会議の場にはなく、ヤハは人垣のうしろにかくれた部屋の片隅で壁を背に腰をおろしていた。私の視線に弱々しく微笑むヤハを目にしたとき、私はヤハが経験したにちがいない挫折感の意味にはじめて気がつくことになった。
ヤハ、きみの口から得意の日本語や日本時代のおもいでが語られる日は二度と訪れることはないだろう。きみの青春の記憶が、ふたたびあの輝く日々のように、光の粒子の舞うなかを躍動することは、残り少ないきみの人生にはもうおこりそうにない。なぜなら、きみとの駆け引きが小さな器のなかで戦わされるゲームに札を投じる程度の意味しかもちえなかったあの日本人によって、きみはきみじしんの過去と同時に、過去の記憶に生きるきみじしんの現在にまで、泥をぬりつけてしまったからだ。
「これでおまえはわれわれとおなじ村の一員であり、今後いつ村にやってくることがあっても、村はおまえをわれわれの仲間としてこころよく受けいれるだろう。」
カットウヴスがインドネシア語にあらたまってそう言うのが聞こえた。
会議がいつのまにか晴れて私の入村を認める決議をしたあとで、ヨハネスとドミングスのふたりにうながされ、私は多少芝居じみているとおもいながらも、会議にあつまった村人全員に握手を求めてまわった。嬉しそうに私の入村を祝福してくれたヤハの手は心なしか冷たかった。私が島の上でヤハを見たのはそのときが最後になった。
ふたりの軌跡は、たがいにおよぼしあった影響力の大きさによって軌道修正をしいられながら、二度と交差することのないたがいの進路を、ふたたびゆっくりとたどりはじめていた。
役場に戻ると、会議の結果をすでに伝え聞いていたヨセフの細君がめずらしく興奮していた。
「それならはじめから入村を認めていればよいのに、彼らは時間に限りがあるということをちっとも理解しようとはしないのよ。」
出発の時がせまっていた。小ケイ島を発つまえに、私は南東マルク県の西の果てに向かう客船を待っていた。中部マルクのアンボンを起点にして、この客船は月に二度のペースで、南東マルクの広大な海域に散らばる島々を巡回している。ところが私が小ケイ島に到着したときに、老朽化した船体の修理に船はドックに入れられたところだった。船がそろそろ修理を終えて、トゥアルへ向けて航海中であるというまことしやかな噂が、頻繁に村人たちの口をついて出るようになっていた。
タムローとともに、祖父の代までこの村に存在したという一本柱の建築について、村の長老のひとりに話をきいたことがある。この建物は中心にある一本柱にのり、傘のようにゆっくりと回転をつづけた。建物のなかには七個の燈心のある椰子油のランプが一日中火を燈され、朝と夕に太陽の光線を避けてランプの位置を移動させたという。この幻想的な建物の痕跡はもはや村のどこにものこされていないし、昔話にともないがちな潤色を免れているかどうかの保証もない。
その話しのついでに、彼らは遠南東と呼ばれる南東マルク県西部へ航海するさいの注意について真剣に語ってくれた。島民たちは椰子の実やパパイヤやバナナをふるまってくれるかもしれないが、けっしてこれらの果物を生で食べてはいけない。もしそうすると寒気で体がふるえ、発熱してマラリアになるだろうと。自分たちの島とくらべて、彼の地はそれほどまでに未開で人間の棲息に困難な土地であるというのである。これと瓜二つの教訓談を、のちに私は遠南東の島でも耳にすることになったけれども。


 集落内には精霊をまつった石の祭壇が六箇所にもうけられている
集落内には精霊をまつった石の祭壇が六箇所にもうけられている離島
いよいよ島を出発するという日にちょっとした事件があった。それは日曜日のことで、島唯一の教会の牧師をつとめるヨセフは、フェリを助手にともなって朝はやくから教会に出かけていた。フェリが村の伝統にも宗教にも辛辣な批判を加えていたことをよく知る私には、島の生活とはおよそ不似合いなほど白く輝くワイシャツを着こみ、聖書を手に、神妙な顔つきでヨセフのあとにしたがうフェリの姿は、悲壮な決意をかんじさせるものだった。
牧師の職業が信仰心に裏打ちされていなければならないなどと言うつもりはないし、ヨセフにそれが欠如していたわけでもない。ただ、神を信じること、あるいは信じていると信じることは、ここではなにより文明化と村の発展とを約束するものであり、村人の欲望に直截にこたえるこうした明快な論理を、教義にもとづくわれわれの宗教はとうに失っていた。
それで、ある村の信仰心あつい村長の息子は、日本人がほとんど宗教を意に介さない国民である、との私の説明に、激しい困惑と拒絶の交錯する表情をうかべていた。彼らの論理では、私こそ文明の彼岸から彼らのまえにあらわれた使いなのだから。
そもそも政府も相手にしないような辺謐な小島で、豪奢とは言えないまでも、トタンやセメントといった工業製品をふんだんに使った教会やモスクをあちこちに建設するのに、いったい誰が資金を投じるだろうか。モルッカの各地で、いまも降って湧いたように出現する小綺麗に整備された集落景観は、村人のたぐいまれな信仰心の記念碑であると同時に、教団の布教の成果をしめす格好の証拠でもあったのである。
政府の官吏や人類学者がモルッカの島々に出没しはじめるずっと以前から、この地域が商人とならんで布教の場をもとめる聖職者の熾烈なフィールドだったことを忘れてはいけない。さして広くもない島が距離をおいて点在するモルッカでは、村がどんな教団とかかわりを深めるかは、政治体制以上に村人にとって重大な意味をもってきた。人口の限られた島のなかで、複数の宗教を共存させるほどの許容力は個々の村にはなかったからである。
たいていの島では、徒歩か馬を利用するくらいしか内陸交通の手段がなく、海岸線に沿って村づたいに島の周囲をボートが巡っていた。海岸までせまりくる山岳地帯を背にした村むらは、わずかな平地をもとめて生いしげる木々のあいだに点々と埋没していた。こうした村にボートが寄航するたびに、それはカトリックの村であったり、プロテスタントの某教団に属していたり、またときには全村あげてイスラム教に改宗したあとであったりした。
こうして村と村の間には、帰依する宗教と信仰の具体的成果をめぐって一種の競争原理がはたらくことになった。不可解にも、利権や利権をめぐるあらそいまでが、信仰の一部であると信じられていたために、ヨセフのような政治家がこの競争の最前線にあって、村の内部では信仰をとおして村人の結束をつよめ、村の外部では信仰のために他村との綱引きを演じていたのである。
ヨセフとフェリが出かけたあと、私は役場に残って出発の用意を整えていた。事件の発端は、例のカゼ薬の男が役場に姿をみせて、役場の隅で黙然と机の上のトゥンバコを吸いはじめたことであった。彼はいつもこうしてトゥンバコを吸い終わると、例によってどこか健康上の支障に有効な薬を所望してゆくこともあったし、そのまま黙って帰ってしまうこともあった。図々しいためなのだか、慎みぶかいためなのだかよくわからない彼のこの習性のために、そのときも私は出発前に最後の薬の催促だろうと予想していたら、そうではなかった。
彼は子供の学資の支払にトゥアルへ行かねばならないと言った。ところが、島の人間には現金をたくわえる習慣というものがなかった。そこでこうした場合に、彼らは必要とされる額に応じて所持する家畜のなかから、水牛だの山羊だの鶏だのを町の市場で売り捌いてその出費にあてるのである。もし島の人間が、すこしでも高い買い主を見つけようと市場で情熱を傾けていたとしたら、それは言い値がこの必要額にみたないからというよりも、むしろ差益でもとめることが可能なアングルだの煙草だのの味のためなのである。
畑で飼っている山羊をつかまえて村へ戻るのに夕方までかかるから、彼は船の出発を明日まで見合わせてほしいと言った。
人間の意志が自然のまえではほんのちっぽけな役割しか果たせない土地で、予定とか将来とかいう言葉に個人的な感慨以上のものをもとめるとしたら、この賭けには大きなリスクが伴うことを覚悟したほうがよい。
乗り合いバスの運転手は、乗客数が十分でないとしたら、車を借りることに要する費用とガソリン代、車掌の取り分、それに彼自身の労働と乗客の数とを斟酌して、その日の商売をやめる誘惑にかられるかもしれない。遅れて到着した飛行機が、半日も待たされていた乗客たちを尻目に、突然あらわれた政府の役人や軍の関係者によってチャーターされてしまわないと誰が言いきれるだろう。小さな船の運行計画など、人間のちょっとした気紛ればかりか、海や天候の状態しだいで簡単にくつがえってしまう。
ここではすでに手に入れてしまったもの、すでに行なわれてしまったことだけが、はじめて予定表に載せうるのである。
その日の出航をのがせば、今度はいつになるかわからない船の便を待ちながら、ふたたび役所のベッドの上で蚊の攻撃をかわしたり、蟻の行列をながめて無為な日々をおくるはめに陥るかもしれないのは、正直言って憂鬱な話だった。予測不能の時間のなかで、その流れにたえず翻弄されていると、人は厳格な時間にたいする一種の脅迫観念にさいなまれるようになる。このような文化的不適応の結果、私は、予定された時間通りに物事を運ぼうとする者が誰一人いないなかで、予定をまさに字義どおりに実行しようとして、かえって時間の名において我を通すという、ほとんど報われることのない悪戦苦闘を、調査のあいだじゅう繰り返していたのである。
彼の要求に逐一こたえるだけの心の余裕があるはずはなかった。私は彼の態度に苛立ちながら、それでも船はチャーターではなく、私はたんに同乗させてもらうだけで、その出航を左右する権限は村長のヨセフにあることを説明してやった。ヨセフには自分から直接話すからと言いのこして、男は何も要求せずに立ち去っていった。
ところが、教会からヨセフが戻って来たときには、事態はまた一変していたのだ。
何日かまえにヨセフは私から数日分の抗生物質をうけとっていた。村のある女が肺炎を患ったという話だったが、この女が昨晩多量の血を吐いたのである。このまま島にいれば死を待つだけの身の上であることは明白だったから、女を小ケイ島の総合病院に護送する手筈になった。ヨセフの裁量で、急遽プラフではなくモーター付きのボートが用意された。私はこのボートに同船して、ふたたび予定通りに島を出発できるはこびになった。先日ヨセフにわたした薬は、結核の治療には所詮十分ではなかったけれども、使われることのないまま、ヨセフのもとめに応じて彼の胸ポケットのなかにおさまってしまった。はじめから病院も薬局もない島の人間に、薬の効能や副作用について話してきかせようとするのは無駄なことだった。


 海岸までせまりくる山岳地帯を背にした村むらは、わずかな平地をもとめて生いしげる木々のあいだに点々と埋没していた。写真は大ケイ島
海岸までせまりくる山岳地帯を背にした村むらは、わずかな平地をもとめて生いしげる木々のあいだに点々と埋没していた。写真は大ケイ島モーターボート用の船着場は浜辺から直接乗船できるように、プラフの停船する湾内の中心よりもずっと東寄りに設けられていた。そこは村の共同井戸のある小さな広場のはずれに位置していて、夕方ともなると、水甕のかわりにカラフルなプラスチックのバケツを携えた女たちが、村中の家からこの井戸をめざして水の補給にあらわれるのだった。この海岸沿いの共同井戸から汲むかすかに塩分を含んだ水が、あの甘すぎる紅茶の原料となる村唯一の生活用水なのである。崖の上の伝統村には井戸がなく、女たちは子供のときから頭上に水をたたえたバケツをのせて、十メートル以上もある梯子をたくみに登っていた。
船着場には早くから大勢の村人が群がりあつまっていた。私はヨセフのうしろからその人垣のあいだを縫って浜辺まですすんだ。船着場といっても桟橋があるわけではなく、喫水線の浅い小型のボートだけが満潮時に海岸まで接近できるようになっていたにすぎない。それで艀のカヌーを使わない分だけ乗下船に手こずらなくなっていたものの、波がくれば足元まで海水に洗われることにかわりはなかった。
「私はおまえが無事に日本へたどりついてくれさえすればあとは何ものぞむことはない。」
ヨセフの言葉をしおに、私は居候のお礼に用意したわずかばかりの金をようやくヨセフに手渡す覚悟ができた。すでに出発の準備を完了していた乗組員の手助けでボートに乗り移ると、ヨセフの指示で波のかからない後部に座をしめた。
モーターボートのことを、この地域一帯でジョンソンとかヤマハとか発動機の名前で呼びならわす習慣があった。それは町なかをはしる乗り合いバスがコルトとかダイハツとか言われていたり、オートバイをホンダと言うようなもので、それらの企業名じたいがすでに一般名詞化されていたのである。
私が乗ったボートには外洋航海に適したように帆の設備があり、そのために長さ六メートルほどしかない小さな船体は、やはり中央を境に前後に分けられていた。横倒しにされた帆柱の下に痩せ細った病気の女が転がされ、体の上から帆に使う青いビニールのシートを無造作に被せられていた。外海に出るとボートはまるで波間を舞う木の葉のように揺れ、時おり前方から不意に打ちつける波が、高い水しぶきをあげて船内をおそった。ビニールシートに直接波がたたきつけるようになっても、女はその格好のまま、船が小ケイ島のデブットに到着するまでのあいだ、まるで死んだように身動きひとつしなかった。この女と私のほかには船をあやつる五人の乗組員が同船していただけだったが、甲板の貼られていない不安定なボートのなかで、航海中に身動きする自由は結局なかった。
何回か始動に失敗したのち、モーターが低い苦しげな喘ぎをもらしはじめたとき、ヨセフはもう私のほうを見てはいなかった。私は役場を振り返ったヨセフの背中に、この人口五〇〇人にみたない小さな島の将来がずっしりとのしかかっていることを理解した。彼自身の生まれ育った南海の楽園は、あえて異国の宗教をのぞんだようにして、遠からずヤマハやホンダやソニーやカシオがなくては維持できぬものにかわるだろう。音もなく忍びよる巨大な力のまえに、いったいひとりぽっちの人間に、ヨセフ以外のどんな対処の仕方が可能だったというのだろうか。
浜辺にはボートを覗き込むような格好で、いくつもの見知った顔があったが、そのなかにカゼ薬の男はとうとう姿をみせなかった。可哀相な男はそんなこととも知らずに、今ごろは村を遠く離れたどこかの畑地で、彼の現金収入の唯一の拠所である山羊をつかまえている最中にちがいなかった。
ボートはすべるように湾内へくりだしていった。浜辺で手を振る村人たちの大写しの顔はやがて入江の点景になり、その入江すらも大洋にうかぶ小島の一部にすぎなくなっていった。この時間と空間のつかのまの変化に、私は完全に不意をつかれて愕然とした。それは記憶の痕跡を逆にたどるかのように、時間の進行をあまりにも早送りに見せつけられたあとの目眩に似ていた。
ほんの一瞬まえまで、私がその上で呼吸をし、その人々の力学をうけ、その将来についてかんがえてきた島は、私の記憶のなかにけっして朽ちることのない根をはりめぐらしているかにみえた。ところが現実に私の目のまえで、タネバル=エヴァヴ島はその存在感を急速に風化させながら、水平線のかなた、遠い忘却の淵にかききえていったのである。(1991-07-04/24)
 女たちは子供のときから頭上に水をたたえたバケツをのせてたくみに梯子を登る
女たちは子供のときから頭上に水をたたえたバケツをのせてたくみに梯子を登る タムロー一家。もしこの島におしゃべりのタムローがいなかったら、私の調査は味もそっけもないものになっていたことでしょう。感謝
タムロー一家。もしこの島におしゃべりのタムローがいなかったら、私の調査は味もそっけもないものになっていたことでしょう。感謝 ヨセフ家をめぐる人びと。あのときはあんなこと書きましたが、居候の分際で何をかいわんや。大変お世話になりました。毎朝食に食べたあまい粟餅の味がなつかしい
ヨセフ家をめぐる人びと。あのときはあんなこと書きましたが、居候の分際で何をかいわんや。大変お世話になりました。毎朝食に食べたあまい粟餅の味がなつかしい- 「船出」「前哨戦」~ 群居 20 (1989.4) pp.83-92
- 「富の概念」「上陸」~ 群居 21 (1989.7) pp.113-123
- 「慣習会議」~ 群居 22 (1989.12) pp.97-103
- 「島の時間」~ 群居 23 (1990.04) pp.105-113
- 「出会い」~ 群居 24 (1990.08.30) pp.112-121
- 「復活戦」「離島」~ 群居 27 (1991.08.30) pp.157-167
 フィールドノート 1986
フィールドノート 1986